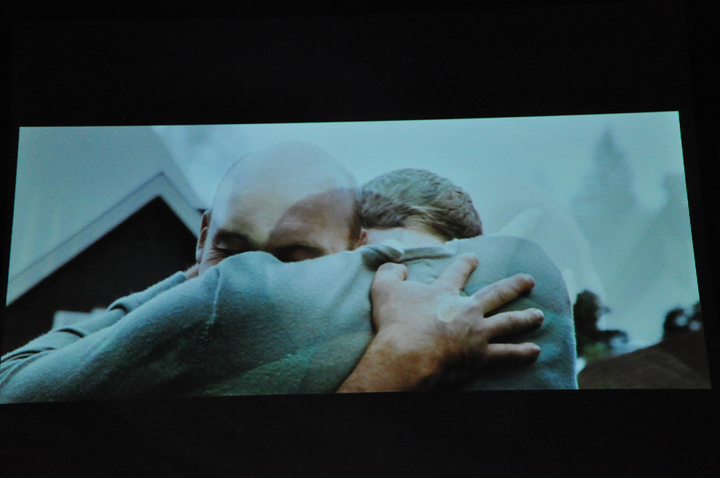毎週火曜に
カローラ・サアヴェドラ 著
アリソン・エントラキン英訳より
日本語訳:だいこくかずえ
「あのね、あたしこの前、あなたにウソついたんだけど」
「ウソ?」 オターヴィオがいつもやるようなわざとらしい、びっくりしたような声で言った。
「そう、映画のこと話したでしょ、覚えてる?」
「ああ」
「特に言うほどのことはなかったって、言ったでしょ。でもあれはウソ」
勇気を奮い起こすための息継ぎみたいに、ワタシはちょっと間をおいた。
「そうか、じゃ教えてよ、ローラ。ウソって何?」と、オターヴィオは理解ありげな口調で言う。
オターヴィオはワタシがウソをついても気にしない。それはウソというのは、真実の別の形だと思っているからだ。数あるウソから選んだ一つのウソというの
は、それ自体充分な告白なんだ、暴露だよ、そう以前に話していた。たとえば、チーズサンドイッチを食べたことでウソをついたとして、ワタシは数ある選択肢の中からどんなウソを言うか考えて、具はトマトだったとかツナだったとか言うことで、ウソの選択をしたことになる。事実を隠すために(この場合はチーズ、あるいはサンドイッチそのもの)、どんなに取り繕っても問題じゃない、そのウソが自分をさらけ出しているのだ。これが結論。逃げ道はない。
そうであっても、ときどきワタシはやってみた。
「ほんとは近くに人がすわってたの。あたしの左側、二つ向こうの席にね。彼が来たとき、もう映画は始まってた。だから顔は見えなかった。でも若そうだった。黒っぽい髪で、たしかジーンズをはいていた。顔は見えなかったけど、手が見えたの、そう右手がね。目の端で見てたわけ。美しくて頑丈そうで、その上繊細な手よ、ピアニストみたいな細い指をしてた。あたし、映画をまともに見てなかった。その男が、その存在が気になったの。まともに映画を見ずに、すわってスクリーンに目を向けたまま、この人はどんな人だろう、どんな感じの人か、生活は? 学生? 働いてる? そんなことばかり考えてた」
「で、どんな結論に達したの?」
「結論ってほどじゃないけど、繊細な人に違いないって思った」
「繊細?」
「そう、見ていた映画のせいだと思う。詩的でロマンチックで、モンテヴィデオに住む作家が娼婦に恋をする話なの。最初女の方は断るんだけど、最後には彼女も彼に恋をしてしまうの」
オターヴィオが興味深げにじっとワタシをみつめた。数秒間、彼は何かノートに走り書きしていた。ノートに何を書いたのか知りたくてたまらない、なんとしても。でも彼は固い守り。そのノートは職業的秘密で、ワタシの夢も恐れも欠点もすべてが報告書となってまとめられ、マル秘情報のように、引き出しに鍵をかけてしっかりと保管される、あるいは常套手段として、たいして重要ではないというように、無造作にテーブルの上にポンと放置される。<彼女はアタカマ砂漠をわたる夢を見た、不明の仲間、集中力をなくしがち>
「ちょっと考えてみて、真っ昼間に一人でその手の映画を見に行く男というのは、繊細な人間ということにならないかしら?」
「まあね」
「でも明らかにそれだけじゃないの、そうじゃなくちゃ隣りにすわったのが誰でもよかったことになる、だってあたしはその男に恋をしたんだから。あのね、
彼は何か違うの、特別だった、彼の存在がかもしだす何か、、、うーん、うまく言えない、オターヴィオ。説明できないわ」
「恋をした、って言ったのかな、ローラ。その男に恋をしたと言ってるのかな」
「恋をしたなんて言った?」
「ああ、言ったけど」
「ええとね、問題はあたしが映画をちゃんと見ていられなかったっていうこと。ずっと隣りの彼がどんな人か想像してて、早く明るくならないかと思ってた。
変なのよね、彼がハンサムだってことはわかってた、どういうわけか、顔を見てなくてもね。それは確かだとわかってた。おかしくない? 足が悪かったり、歯
が抜けてたり、顔じゅうやけどしていることだってあり得た。でもあたしには起こらなかった。明りがついたらどうしようってことで、頭がいっぱいだった。彼
のあとについていって、ラウンジまで追っていくべきか。でもね、わかったの、運命がわたしを導くって」
「運命?」
「そう。思ったの、もし彼があたしを見もしないで、そのまま帰ってしまったら、もう忘れることにする。それが何を意味しているか、受けとめる。でも彼が
帰らないでブックショップに寄るとか、何か飲みにコーヒーショップに行くとかすれば、それがサインだと思うの」
オターヴィオはなんとか偏見をもつまいとしていたが、疑いをもっているのは明らかだった。
「サインって? それが何を意味するのかな?」
「あたしたちの間に何かあるってことよ。これから始まろうとしている物語、彼も知っているはずよ。仮に彼が気づいてなかったとしても、たいした問題では
ないの、だってそこから逃れられないから。運命を信じないの? あたしは信じる。占い師をね、星占いのよ、ほぼ全面的によ。信じるなんてバカみたいだって
わかってる、でも信じないのもバカよ。人生の中で得られるサインってあると思うの。真面目にとった方がいいサインよ。それは何かを伝えようとしてると思う
の」
「まあね、、、」
「まあね」はオターヴィオのよく使う表現の一つ。賛成か反対か決断を下したくないとき、いつもこの「まあね」をもちだす。イライラさせられるけど、無視
するのが一番。
「で、とにかく、あたしは心を決めて、映画が終わるのを待ってすわってた。それで映画が終わると、あたしが立つ前に、彼は立ち上がって出ていったの。あ
たしはじっとすわって、彼に考える時間を与えようとした。すぐに追いかけていったりしたくなかったからね。運命を押しつけたくなかった、わかるわよね。自
然にコトが起きるようにしたかったの。すわって静かにしていた、それから化粧室に行ったの。髪を整えて口紅を入れ直した。鏡の中の自分を見て、それほど悪
くないって思った。実際けっこういけてた。普段自分のことをきれいだなんて思ったりしないんだけどね」
ワタシは下を向いてカラフルなラグを、自分のふくらはぎを、足先を、ハイヒールのサンダルを、最近塗ったペディキュアをちらりと見た。そして続けた。
「でも本当のところ、ちょっと醜いかもと思った、あたしの顔よ。たぶん丸すぎるんじゃないかしら、いつもいやになるの。体重を減らしても関係ないの。顔は丸いまんま。脂肪を取ってみたらどうかって、考えもした。前に読んだんだけど、脂肪がつく前に、女性は両側の臼歯を抜くと顔が細くなって、きれいに見えるって。マレーネ・ディートリッヒがやったって聞いたことがあるの。でも彼女がそれほどきれいだとは思わないけど。彼女の顔って変わってるし、左右が不均等。あらっ、マレーネ・ディートリッヒの顔をとやかく言うなんて、きれいだったためしがないのはあたしよ、少なくとも自分がきれいだと思ったことないし、、、」
そこでワタシは口ごもり、オターヴィオがいやそんなことはない、きみはきれいだよ、自分を醜いと思うのは不安の現れに過ぎない、自信のなさのせいだよ、
と言うのを待った。オターヴィオは何も言わず、いつものように静かに、優雅に、アームチェアにただじっとすわっていた。オターヴィオはハンサムな男だ。そ
れを充分意識してるところがいやになる。オターヴィオが黙っているので、ワタシはしかたなく、こう訊ねた。
「オターヴィオ、あたしって醜い?」
オターヴィオは微笑んだ。賛美にも嘲笑にもなり得るような笑み。
「いや、ローラ、もちろんそんなことはない。キミはとても魅力的な女性だよ」
魅力的。たいしたほめ言葉。オターヴィオが「魅力的」と言うとき、そこには何の意味もない。ここのソファにすわった女性誰にでも、そう言っているはず。
ルイーズ、キミはとても魅力的な女性だ。リタ、キミはとても魅力的な女性だ。ドロレス、キミはとても魅力的な女性だ。顔に笑みを張りつけて、言ってるは
ず。
「魅力があるっていうのは、きれいかどうかとは関係ないでしょ。魅力があって見た目がひどいっていう人もいるはず」
「キミは魅力があって、きれいだ、ローラ。そう思ってるんだろう」
そのとおり、知ってる。なんでワタシがわざわざ訊いたりすると思う? わかってることはもろに出てるはず。挑発するために訊いてきた、そう彼は思って
る、そんな、ローラ、キミはすごい美人だよ、ローラ、たまらないね、ローラ、キミはこのオフィスに足を踏み入れた女性で一番きれいだよ、そう言わせるため
だって。オターヴィオはワタシが彼に恋をしてると思ってるかもしれない。それはあり得ること。オターヴィオみたいな男と恋に落ちない人がいるだろうか?
ワタシはポニーテールにしていた髪をおろした。
「そんなこと知らないわよ。知ってたら訊く必要があるかしら」
「人は時に、はっきりした答えを知りたくて、質問することがある」
ワタシはその言葉を無視して自分の話を続けた。
「とにかく、問題は自分の顔を化粧室の鏡で見て、いけてると思ったってこと。そのときに関して、言うとね。それであたしはブックショップに行った。彼は
そこにいた、外国文学のところにね。背が高くて、少しウェーブがかかった茶色い髪、それほど長くなくて、かと言って短いわけでもない。あたしと同じくらい
の年だと見積もった。あまり近くに行き過ぎないよう、見え透いたことをしたくなかった。あたしはアートブックのところに行って、ポルティナーリについての
本を手にして、パラパラと見ていた。あたしは待っていたの、彼がこっちを見るのをね、あたしに気づくのをね。彼は棚から本を取り出してそれを読んでいた。
没頭してた、家にいるみたいに。三十分たって、まだ彼は本を読んでいた。あたしがそこにいることさえ、気づいてない風だった。まわりの何も、誰にも気づい
てないみたいだった。あたしはあきらめた。自分にあと五分だけ待とうと言い聞かせて、もし彼がこっちを見なかったら、家に帰ろう、って。五分過ぎて、あた
しはポルティナーリの本をとうとう買った、時間稼ぎのために。あたしは店員に大きな声で話しかけた。この本と出会えるなんて、なんて運がいいのかしら、
ずっと探してたの、ポルティナーリを。店員は何か返したけれど、もう忘れた。その間、あの男はそこ立ってて、微動だにせず、あたしなんか存在してないみたいだった。仕方なく代金を払ってそこを出た。そのときには、あたしは彼を憎んでた。でも恋に落ちていた可能性もなくはない、、、」
オターヴィオは興味深そうにしていた。
「へえ、どうして彼と恋に落ちてもおかしくないって思ったのかな?」
「よくはわからないけど、でも確かなの、恋に落ちたかもっていうのは。彼にバカげたことを仕掛けてたかもしれない。見知らぬ人とそんな風に恋に落ちるなんて、おかしくはない?」
「見知らぬ人というのは、映写幕としてよく機能するから」
「映写幕って? オターヴィオ、いま恋について話してるのよ、映画じゃなくて」 ワタシはおちゃくるように言った。オターヴィオは別におかしなこととは
思ってないようだった。彼がユーモアのセンスを見せたためしがない。
「ローラ、ぼくが正しく理解してるとすれば、キミはその男のことを何も知らない。話してさえいない、そうだろ?」
「そうだけど」
「つまり彼はキミの望む誰にでもなり得る。キミのあらゆる欲望を彼に投影し、期待することができる」
オターヴィオはワタシが投影とか防衛とか聞いたこともない薄のろだとでも言うように、教え込むように話した。彼に対してときどき、怒りの気持ちが抑えら
れなくなることがあった。
「あら、それじゃあ、もしそうだとしたら、あたしは通りがかりの誰にでも恋することになるわね。道ばたのポップコーン売りでも、スーパーマーケットの店
員でも、電話の勧誘員の声にさえ、自分の欲望を投影するわけね」
オターヴィオはまだ言ってることが変だとは思ってない風だった。彼はイライラしてきたみたいに見えた。くちびるが見えなくなるまで口を噛み、立ち上がっ
て部屋を出ていこうとしているみたいに見えた。オターヴィオのような人間でも、自分の感情を制御するのには努力を要する。でも彼の場合、努力はいつも報わ
れる。数秒して彼は穏やかさを取り戻し、顔がゆるんで寛大な表情になった。結局のところ、彼のような人種は他人を理解することが求められる。感情に流され
たり、人と対立したり、個人的な意見にこだわることを自分に許したりはしない。彼の解決策はワタシの言ったことを無視すること。
「ローラ、その男に何をしてほしいと思ってるの?」
そうね、いろいろたくさんあったのよ。花束をパッと取り出してくれるとか、フランス語で詩の朗読をしてくれるとか、あいさつをするとき手にキスをしてく
れるとか、家を出るときコートを着るのを手伝ってくれるとか、ワタシが通るところを靴が汚れないように赤いカーペットを敷いてくれるとか、そういうこと。
「何をしてほしいかって、わからないわ。多分なにも」
「なにも?」
オターヴィオは説教口調をまだつづけていたけれど、ワタシは穏便にことを進め彼が望むようにしていようと思った。ほんとうはワタシがしたいこととは全く
違うのだが。
「そうね、多分欲望がお互いのものであってほしいかな。それって誰もが望むことじゃない?」
「まあね」
「とはいえ、どちらにも欲望があるってことはあまりない、ちがう? たとえばあたしの場合ね。ジュリオの奥さんはジュリオが好き。そのジュリオはわたしが好き。あたしは映画館の男がいい。その男は多分誰か近所の人か新聞スタンドの女が好き。わかんないわよね。公平じゃない、ちがう? あたしが完全に間違ってる可能性はあるにしても。ジュリオの妻は夫のことなんか全然気にしてないかもしれないし、個人教授を求めているのかも。ジュリオの方は、そうね、彼が本当に望んでいるのは五階の秘書の人かも。誰にわかる?」
「キミはそのことが気になる?」
オターヴィオの目が光った。彼の目に悪意が見えたと思った。
「何を気にするの?」
「ジュリオがその秘書に気があるってことだよ」
「いえ、ぜんぜん」
オターヴィオが信じてないのは明らかだった。
「この前キミがここに来たときは、それほど会ってないって言ってたね」
「そうなの、最初の頃、会ったばかりの二、三年は毎日のように来てた。来れるときはいつもよ、ときに週末でさえね。奥さんがイタイパーヴァまで車で行くってときに、仕事があるからリオに残るって言ったりして。今はそんなことはない。ときどき顔を見せるだけ。彼の寛大さにはなんの変化もないんだけどね。
今も大学の学費、貸借金、電気代、水道代、ガス代、部屋代、それに必要な小遣いもくれて。非の打ち所がないって言えるくらいの額よ。彼は何も訊かずにそれを払ってくれてる。何の質問も要求もなく、何に使うのか言わせることもない。その上あたしのことを心配してくれてる。すごく心配してて、それでご存知のように、あたしにここに来てあなたと話すよう薦めたの。ここに来るように言ったのは、ジュリオよ。自分からここに来たわけじゃなかった、そうよね。ジュリオは素晴らしい人だわ、そう思わない? 彼みたいな人がいたらと思わない人はいないわよ。思いやりがあって、気遣いしてくれて、あたしが幸せになることだったら何でもやる人。あたしって相当運のいい人間よね、そうじゃない?」
「キミはセックスの回数も減ったって言ってたよね」
「そう、セックスの回数ね」 ワタシは顔をしかめた。
オターヴィオは真剣な顔つきをしている。
「それについてもう少し話してくれないかな」
「それって、どれくらいセックスするかってこと?」
「そう」
ワタシはまた顔をしかめる。
「うーん、それほど言うことはないわ。前に話したように、ほとんどセックスはしてない。最初の頃、会った頃の二、三年はしょっちゅうしてた、普通よね。
で、時間がたつうちにどんどん減っていって、最近なんか最小限しかしない、多くて一月に二回。これって普通だと思う?」
「それはカップルによるんじゃないかな。ある人たちには充分すぎるくらいだし、他の人にとっては足りない」
「よくわからないけど、これって愛人にとっては、ちょっと安心するわよね。だってもし彼が愛人とそんな風なら、妻とはどうなのか想像できるでしょ」
オターヴィオが笑った。ワタシも面白いことだと思った。いっしょに笑うなんて、ワタシたちの間であまり起こらない、オターヴィオとワタシの間では。いい
気分だ。見せかけのものであったとしても、まるで二人がただのいい友だち同士で、いっしょに楽しくおしゃべりして過ごしてるみたいに感じられる。
「そのことが気にかかるかな」
「セックスの回数のこと?」
「そうだ」
ワタシはちょっとの間、答えを考えてみた。ときどきワタシはこうする。
「あるかな、でもないかな。一方ではまったく気にならない。ジュリオとセックスしたいって思わないから。実際のところ、誰であれセックスしたいと思わな
いの。でも一方では、ときどき考えるの。あたしは今二十八歳、女の人のセックスのピークは三十歳だって聞いたことがある。他の人にとってピークが来ようっ
てときに、あたしには何にもないっていうこと。思うの、これがあたしのピークなら、四十になって下り坂が始まったらどうなる?」
「なんで四十歳になったら下り坂が始まるなんて思うの?」
「ねえ、オターヴィオ、そんなこと訊く必要もないこと、わかってるの」
「キミは間違ってるよ。年をとることは坂を下ることじゃない。ましてや四十歳で」
「ごめんなさい、あたしの偏見だった、年をとるのは素晴らしいことよ。あたし白髪が出始めるのが待ちきれないくらい」
「よろしい、ローラ。この話題はあとにまわそう。じゃあその前に話していたことに戻ろう。重要なことに思えたからね。キミはジュリオと、あるいは誰とも
セックスしたいと思わないって言ったよね。あの映画館の男はどうなんだ? 彼とはセックスしたいと思う?」
オターヴィオはいつもこの手の質問をしてくる、彼のマニュアルに書いてあるのだ。ワタシは彼をじっと観察した。ワタシは彼とセックスしたいだろうか?
充分あり得る、そこで彼がそうしたいっていうならば、彼は小さなノートにこう書き込むだろう、彼の報告書にこう書くだろう。愛人間のセックス回数:月に一回、治療上のセックス回数:週に一回。ワタシがそこのソファに裸で寝て。
「そうね、彼とセックスするでしょうね、そこのソファでね、映画館のってことだけど。彼がそうしたいっていうならば」
ワタシは笑みを浮かべて彼をじっと見た。オターヴィオは目をそらした。彼が目をそらすなんて初めてのこと。ワタシの勝ち。スカートのしわを伸ばし、ワタシは微笑んでいた。
小説「Toda terça」(2007年)より
日本語版出版:葉っぱの坑夫
文学カルチェ・ラタン | happano.org
文学カルチェ・ラタン
006区 チリ
カローラ・サアヴェドラ
Carola Saavedra
1973年、チリ生まれ。子供時代にブラジルに移り住む。これまでにフランス、スペイン、ドイツなどに住み、現在はリオデジャネイロに在住。短編集「Do
lad de fora」(2005年)、小説「Toda terça」(2007年)、「Flores
azuis」(2008年)、「Paisagem com dromedario」(2010年、Rachel de
Queiroz若手作家賞受賞)などの出版がある。「毎週火曜に」は「Toda terça」からの抜粋。
スペイン語 → 英語 翻訳者:
アリソン・エントラキン
Alison Entrekin
タイトルフォト
Séptimo Festival Internacional de Cine de la Diversidad Sexual
photo by Movilh Chile (taken on October 17, 2014 /Creative Commons)
STORY
[001区 ブラジル]
リカルド・リジエス
ルイサ・ガイスラー
セルジオ・タバレス
[ 002区 アルゼンチン ]
ファビアン・カサス
ホアン・ディエゴ・インカルドナ
ニコラス・ディ・カンディア
フェデリコ・ファルコ
no.1、2、3
[ウルグアイ 003区]
アンドレス・レッシア・コリノ
オラシオ・キローガ
[コロンビア 004区]
アンドレス・フェリペ・ソラーノ
no.1、2
[ペルー 005区]
ダニエル・アラルコン
フリオ・ラモン・リベイロ
[チリ 006区]
★カローラ・サアヴェドラ
[ベネズエラ 007区]
カロリナ・ロサダ
MUSIC
[001区 ブラジル]
アンドレ・メマーリ
エルネスト・ナザレー
[ 002区 アルゼンチン ]
ロス・モノス・デ・ラ・チナ
ベシナ
ブエノスアイレスのHip Hop
チャンチャ・ヴィア・シルクイート
ART
[ウルグアイ 003区]
ホアキン・トーレス・ガルシア
FILM
[ 002区 アルゼンチン ]
マルティン・ピロ
ヤンスキ
シネマルジェンティノ
アレハンドラ・グリンスプン
ダニエラ・ゴルデス
ジンジャー・ジェンティル
エセキエル・ヤンコ
アリエル・ルディン
[ 004区 コロンビア ]
二人のエスコバル
(ジェフ&マイケル・ジンバリスト)
TOWN
[ 004区 コロンビア ]
ボゴタの新交通網
[番外]
南米の都市のストリートアート