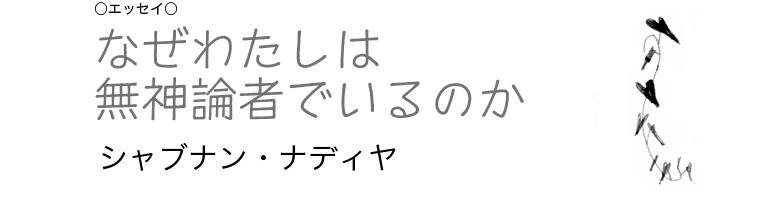
|
わたしはまだ子どもで、宗教は(あるいは神様は)それほど深く考える対象ではなかった。それまでは、わたしにとっての宗教は他の人々と同じように、大きく自分を包むものだった。宗教はただそこにあるものだった。わたしは自分がムスリムであることはわかっていた。ムスリムであることは、アラビア語を習得することだった。コーランやナマーズの言葉はアラビア語で書かれていたから。ナマーズはすべてのムスリムに課せられるお祈りであるが、ほとんどは親類の年配者やわたしの祖父母たち、中でも男たちによって執り行なわれているだけで、週に一度ジュンマでやればいいものだった。ムスリムでいることはまた、イードやシャブ・エ・バラトの祭りをすることを意味した。豪華な食事、両手の平で輝くメンディ、ピカピカの新しい服と下ろしたての靴の鳴る音。もちろんそれ以外にもあれやこれやとあった。学校ではスーラやハディース、予言者の生涯の逸話を通じて、良いことと悪いこと(グナとソワブ、ハラールとハラーム、パクとナパク)を学んだ。その頃のわたしはこんな風だった。わたしにわかっていたのは、わたしは今子どもでいつか大人になること、両親は何でも知っていること。それからアッラーはそこにいて、わたしがいい子で神様に向き合えるようになるまで待っていてくれること。実際にそのときが来てみたら、神様はそこにいなかったのだけれど。 でも、あらゆること(不信心、自信喪失、自分自身との妥協や自分の内部で見せかけの信仰をたもつこと)がやって来たのはもっと後のことだったから、その頃のわたしには、喪失感や孤独感といったものはそれほどなかった。言われていることや与えられているもののすべてを、一も二もなく受け入れ拒否するというわたしの態度は、11歳か12歳のある春の朝に起きたことで始まった。 わたしはそのとき、マクタブ(宗教学校)の生徒だった。わたしの両親は、幅広い教育を考えて、わたしと兄を近くのマクタブに入学させた。わたしと兄はひどく朝早く起きて、自分のカイダ(アラビア語を学ぶ教則本)を手に、マクタブへ重い足を引きずって行くことになった。まだフロックを着ていておかしくない年齢で、わたしはシャルワールとオルナを着て通った。ある朝、わたしは寝坊した。急ぐあまり、母はネグリジェを着たままのわたしをマクタブに送り出したが、オルナを着せるのは忘れなかった。オルナは足先まで届く丈の長いドレス。だから母はシャルワールなしでも大丈夫だと思ったのだ。つまり、わたしのからだは首から足首のところまで、そして頭もしっかり被われていたということ。ネグリジェとオルナがからだを被っていた。マクタブに着くと、フズール(先生)がわたしを呼んで(生徒みんなの前で)問いただした。「トマル・ジャマル・ニチェ・キ?」(ドレスの下には何を着ている?) それからフズールは、大学教師やその子どもたちによって乱された様々な無作法について怒鳴りちらし、わたしは彼のマクタブから追い出され、ちゃんとした服装をしているときだけ来てもいいと言われた。わたしは恥ずかしさと怒りで、耳が燃えるようだった。他の生徒たちがクスクス笑っているのが聞こえ、わたしは家にまっすぐ帰ったことを覚えている。 わたしの感じた恥ずかしさは二重のものだった。ひとつは他の生徒たちの前で恥をかいたという事実。もうひとつは、どうしてなのかは自分でもわからないけれど、フズールにドレスの下に何を着ているかと訊かれたことが、何かいかがわしいことでもされたように、わたしの心をちくちくと刺した。わたしは家に帰って泣きじゃくり、もうあそこへは絶対行かないと母に言い渡した。母はわたしが思っていた以上にわたしの気持ちをわかってくれ、マクタブにまた行かせるようなことはしなかった。 このエピソードについて、二つの理由で述べてみたい。まず、このことはわたしに考えるチャンスを与えてくれた。わたしが何回も自問して得た問題点は、わたしのからだが服で被われていたかどうかということ。それは成されていたはず。ではどうしてフズールはわたしをあんな風に辱めたのか。この質問に納得いく答えができるものはいなかった。そこでわたしはこの問題を乗り越えるために、父に尋ねた。父は学校の先生で、人に質問されることに関しては、長々とした答えを返す術を養ってきた人。それが条件反射のようなものになっていた。 父がわたしに言ったのは、急に起きたことに対処するのは誰にとっても難しいこと。フズールにとっては、わたしは女の子であり、シャルワールを着なければならないということ。フズールはたぶん、何か失礼なことをしてやろうなどと思ってはいなかった。彼はある程度教育を受けたという男にすぎないわけで、あのときに使った言葉は確かに嘆かわしいものだ。彼にとっては、わたしがシャルワールを着ていなかったなら、それは不適切な服装だということ。フズールが突きとめようとしていたのはそのことだけだった。でも足はドレスで被われていたのよ、そうわたしは反論した。わたしはちゃんとした服装だったと言える。理論上はわたしの言っていることは正しい、と父は答えた。でもフズールは論理的に考えていたわけじゃない、多くの人はそうだ。彼にすれば、わたしは女の子で、ある決まった方法で服を着るべきだった。わたしがそうしていないなら、見た目だけそう見えるように何か着ていたとしても、彼にとっては問題じゃない。わたしは依然、不適切な服装だということになる。それはわたしをずっと悩ませてきた様々なことが表面化し、さらに先へと押し進められるような出来事となった。 もしわたしの着ている長いドレスが不適切なら、わたしがフロック(これを着ると足が出ている)を着ているのも不適切になるのだろうか。でもわたしと同年齢の女の子たちはみんなフロックを着ていて、それはまったく問題にならなかった。わたしが男の子のようにパンツを履いていれば、問題になったはず。パンツが足をぜんぶ被っていたとしてもだ。どうやったら納得いく説明になるんだろう。わたしはみんなが従っている宗教上の非合理性に目を向けはじめた。そうはいっても、この段階ではまだ、宗教的実践と宗教そのものの違いに気づくことで、わたしの中にある信仰が行き場を失うことはなかった。 マクタブ事件による第二段階で、わたしはこういう「信仰の先生たち」がいかに取るに足らない人間かということを知り始めた。そのときまでに知っていたフズールといえば、わたしがここで話した人。それ以外にも、奥さんを殴る人(ほかの人には親切な人であっても)、子どもたち(なかでも男の子たち)に罰を与えるのに長けた人。さらに、わたしは女の人を「殴る」やり方がいろいろあるということを知った(バングラディッシュのことわざで、ハテ・ナ・メレ・バテ・マラというように)。それにたぶん、他の男たちがフズールよりいい夫であるとも言えず、弱者をいじめる性癖は宗教の先生だけの領分ではないということ。でもそのときは、こういったフズールによる罪の数々は最低なことに見えた。 こういう人たちをわたしたちは尊敬しなければならないの、とわたしは自問した。神様の言葉を教えてくれるという理由で? 理解能力に限界のあるこの男たち、魂を汚した男たちは、神様に与えられた命の栄光を、理解し難いやみくもな規則や習慣の数々へとおとしめていた。 あのフズールには感謝するべきなんだろうな、とは思う。彼の近視眼的なものの見方と、何を無作法とするかの見極めのお粗末さから(わたしが真っ裸だったとしても彼の言葉はその百倍も無作法だとわたしには思える)、わたしは疑問をもつことを覚えた。それがわたしを14歳という年齢で、不可知論者へと導いた。それでも、宗教の本質のところで、わたしはまだ自分の信仰を心にとどめていた。 そこまでのわたしは、ごくごく細い糸でやっと自分の信仰にしがみついるている状態だった。わたしはイスラムの中の矛盾や野蛮に見える多くのことは、千年も昔からの宗教だという事実に起因している、と結論づけていた(この結論には、三番目のタイプの多くが賛成した)。マホメットの行動や言葉の多く(一夫多妻、子どもの結婚、戦利品として女性を扱うこと)は、あらゆる人間がそうであるように、マホメットもその時代の子に過ぎないという事実で説明がつく。ある日紛れもない矛盾がわたしを打ちのめすまで、そのように自分を信じさせてきた。それはこういうことだ。もしあるイスラムの規律が今日の光の中で野蛮に見えるなら、その意味するところは、イスラムや予言者が人間の歴史のなかのある時代にのみふさわしいということだ。それでもコーランは神から直に授けられた普遍的な、すべての人のための本であると言われていた。そして予言者の生き方は、すべての善良なムスリムの手本であるべきだった。そのことはわたしという人間に根本的な衝撃を与えた。 どうやってわたしは、良いと思っていたこと(皮肉にもそれは宗教からわたしが得てきたものなのだが)と、わたしが宗教の中に見つけたそうではないこととを和解させることができようか。人間においてすべての女性は二番目の地位にいるにすぎない、という言葉を見た後では、どうやって自己意識やわたしは何者かという自尊心を保つことができるのか。もし本に書かれていることを信じつづけたなら、考えをめぐらせる心という広大な場がわたしには持てなくなる、そう思って宗教を拒否した。宗教は、無限の可能性に想いをはせる場を与えてくれるのではなく、わたしの世界を限定し、束縛する。 その本はわたしにこう告げていた。どんなに本を読み、どんなにものごとを知ったとしても問題じゃない、人々への愛や哀れみを胸に抱いていたとしても問題じゃない、わたしに知性や才能や笑いの恵みがあっても問題じゃない、わたしは最低の男たちとさえ並ぶことができない存在なのだ。なぜならばそれはわたしが女だから。わたしは男が種をまくための畑だった。わたしは兵士にとっての奪略の一部だった。わたしは子どもを宿す力があるために、卑しい存在であった。わたしの言葉は男のもののように信じられることはなかった。男たちがわたしを欲するという理由で、わたしは地獄に通じる門となった。 そのような宗教とどうやって暮らしていけるだろう。わたしは信じることをきっぱりとやめた。でもそうしたら、それに代わるものとして何があっただろう。信仰が与えなかったことで、「信じないこと」がわたしに差し出そうとしたものは何だったか。わたしはこう思う。 無神論は人を大人として扱う。宗教はそうではない。無神論は人間にはいい人生を生きる能力があると、いいことをする能力があると信じている。それはいいことをするのがわたしたちの自然だから。そういう人間にとって、永遠なる神から与えられる罰のムチも、いいことを成すための永遠なる神による至福の報酬も必要ない。宗教は人間であることの能力を制限する。宗教は、もし人が地獄で焼かれることを恐れなければ、男は自分の妻や子どもたち、家族や友だちをちゃんと扱えないし、女は恥ずべきことをし、家族を裏切るものだと信じている。 信仰のどんな仕組が、信じないことがわたしに与えてくれる尊厳や尊敬と張り合えるだろうか。わたしが宗教的な人間であったなら、わたしは女として第二級市民に格下げされていた。わたしが宗教的な動物であったなら、わたしは神聖なるものによってつくられ、その栄光を星にむかって讃えるだけの存在であった。そうではなく、わたしは自分が人間であることを選んだ。命の中で最も気高く、限りない可能性をもち、果てしない空と同じような広がりと、太陽の笑いに匹敵するもの。わたしは自分の船の船長なのだ。わたしはいいことをする、悪いことではなく。死んだときに素晴らしい時間が与えられるからではない。いいことはそれをすることがいいことだから、する価値があるのだ。わたしには人間として、すべての生きものの中で、いいことと悪いことを区別する独自の能力があるからなのだ。そしてよいことを選ぼうとする意思があるからなのだ。 短い自分の人生のあいだではあるけれど、わたしは多くの信者たちと信仰の習慣や本質について話してきた。ときにその人たちは、わたしの信仰心のなさに腹を立てているように見えた。多くの人たちがわたしが生きているこの世の暮らしが、いかにはかなく実り少ないものかをわたしに言いつづけた。そこでどんな生きる喜びがわたしに与えられようと問題ではない。その人々が一人残らず理解しなかったのは、どれだけわたしが強く、長いあいだ信仰者であることを渇望していたかということだ。 信仰が意味するのは、わたしを見守る全知全能ですべての愛の根源である父という存在をもつこと。何か悪いことがわたしに起これば、彼がわたしを何らかの方法で助けてくれる。もしこの世でできないなら、来世で。それ以上に心休まるものがあり得ただろうか。悪いことが勝つことはないと、この世の無実な人の苦しみは必ず恨みを晴らされると知ること、つまり「神は天国に、すべての人は神の世の元に」である。すべてを神の手にゆだねることの誘惑は果てしないものだ。 わたしは信仰を守るために多くの時を費やした。でも最後には、無神論という岩だらけの険しい道を歩まなければならなかった。わたしは天から授けられた身を守るための逃げ場をあきらめた。でもわたしは問題意識をもったり、この世にあるものをすみずみまで隈なく探検することができる人生を勝ちとった。宗教に疑問をもち、拒否して、無神論者になった。その理由は宗教の矛盾について自分に対して答えを与えることができなかったからだ。そして宗教は人間としてのわたしに制限を加えたからだ。わたしは無神論者であり続ける。わたしが誰なのか、宗教に教えてもらう必要がないということを発見したからだ。 |
||||
