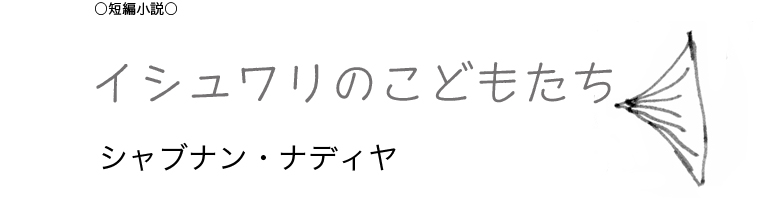
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
ぼくの家族はダッカに住んでいたけれど、ぼくのダダジャンは先祖からの村、ノアパラに暮らしていた。ダダジャンは大きな人で、そのたっぷりしたお腹は、おじいちゃんの財力と地位にふさわしいものだった。笑ったときや何かしようとしてできなかったとき、目のところにしわができた。あごひげは白かったけれど、まだ若さがあるという証拠に少し黒いところが残っていた。おじいちゃんはいつも、洗濯したての真新しい、糊のきいた白い縁なし帽をかぶっていた。帽子は買ったものではなく、どれもおばあちゃんがおじいちゃんのために編んだものだった。 僕の家ではダダジャンを年に二、三回訪ねた。ダダジャンの方はもっとよくぼくの家に来た。年に二度は、ココナッツや生きた魚を入れた土器を運ぶ男をひきつれて現われた。おじいちゃん自身は、お話をしたためてやって来た。お話はいつも変わらず、イシュワリにまつわるものだった。イシュワリが腹の減った狂女みたいになって、草原を飲みこんだ、というような。 「この女神は腹すかしでな」とダダジャンはよく言っていた。「家にいるわたしに喰いつこうとしたんだ」 暴れまわるイシュワリの流れは、巨大な土地を飲みこんでいった。その土地の大部分はおじいちゃんのものだった。イシュワリは家も草原も洗い流していった。村という村がほんの数日で消え去った。でもイシュワリはお返しもしてくれた。「あいつはもぐもぐと噛みくだいたら、パッと吐き出すんだ。どこに新たな土地が現われるかはわからない。でも流される前よりもずっと豊かでいい土地になってる」 とはいえ、川の吐き戻した土地はおじいちゃんの悩みの種だった。イシュワリのお腹から吐き出された緑豊かな土地は、多くの人々の羨望の的だった。正当な権利をもつ者もそうでない者も欲しがった。しばしば調停が必要になった。新しく現われたチャルは誰のものか討議するため、裁判所に出向くこともあった。ダダジャンは、この問題でぼくの父さんと話すため、よく家に来た。父さんはひとり息子だったから、いつの日かすべての土地は間違いなく父さんのものになる。ぼくはダダジャンのひざにすわって、父さんたちがこの土地あの土地の状況を話している間、チャルア(チャル・バンダス=チャル占拠者)の激しさと執拗さについて聞きながら、うとうとしていた。このチャルの人々は、占拠者の権利や土地紛争の法律用語を学んで、新しい土地を獲得しようと奮闘していた。 訪ねて行ったときはいつも、ぼくはダダジャンの仕事の用事についていった。でもチャルを見る機会を得たのはたった一度だけ。それは冬のことで、イシュワリは一年で一番水の枯れた時期だった。ダダジャンは新しく現われたチャルに住む人々に会うために出かけたのだった。ぼくらは途中まで、ダダジャンが自分用に使っている小さなコシャに乗っていった。ほっそりとしたコシャが黒い川底の上を滑っていった。ぼくは雨季の透明な川の流れを懐かしく思った。 ぼくらといっしょに、ダダジャンの二人のカムラ(召使い)が同行した。アブドゥル・チャチャとアラム・チャチャはおじいちゃんのところで働く男たちの中で、いちばん信頼が厚かった。二人は兄弟で、二人の家族もぼくらの家族のために何世代も働いてきた人たちだった。兄のアブドゥル・チャチャは、乾いて固くなった土を掘り起こして、畑にするために働くようになってから、ダダジャンの元で仕事をしていた。アブドゥルはおじいちゃんの行くところどこへでも、黒いかさと必需品を入れた布バッグを肩からさげて付き添った。アラム・チャチャの仕事は、ダダジャンがぼくを自慢の「ひとり息子のひとり息子」として用事に連れていくとき、ぼく(ともう一つの黒いかさ)を、担当することだった。 アラム・チャチャは流れがあるかぎり、一本オールのコシャを漕いでいった。 「ここからは歩かねば、バブよ」 そうダダジャンはガラガラした声でぼくに言った。おじいちゃんは頭が銀の杖を手に、つかつかと道の先を行った。アブドゥル・チャチャがおじいちゃんの頭の上にかさを掲げ、ついて歩いた。ぼくはアラム・チャチャの肩にまたがっていた。アラムはぼくの頭の高さに合わせるため、かさを高く持ち上げていなければならなかった。アラムにとって疲れることだったろう、かなり辛いことだったかもしれない。六歳にもなる男の子のために、しゃれにならない仕事だ。でもアラムは文句を言わないばかりか、腹をたてている様子でもなかった。もしかしたら頭にきていたかもしれないけど、子どものもつ傍若無人さのせいで、ぼくがただ気づかなかっただけかも。 川の両岸の土手は、枯れたカアシュと草が、年老いた人の髪の毛が太陽にさらされて薄くなったみたいに、まばらにポツンポツンと生えていた。たっぷりとした水の流れと青々した川岸は、すっかり消え去っていた。歩くにつれて、まばらな草木も減っていき、川岸は白い砂地の中に溶けて見えなくなった。冬の白い太陽が、そこだけあの熱い夏の輝きを取りもどし無慈悲に照りつけていた。砂と太陽がきらきらと輝き、小さなぼくの目をくらませた。荒涼とした白い風景があたりに広がり、ぼくのまわりのもの全てが光を放っていた。それは見知らぬ世界の風景のようで、ぼくは夢を見ているようだった。まわりの音までもが変化してしまったようだった。イシュワリのゆるぎない水音は去った。家々の、そして村の日々の活気、日常の気配は、遠い夢となった。代わりに、耳に聞こえてくるものといえば、足元の砂が動くときの絶え間ないシューシューいう音と、はるか頭上で輪を描く一羽のタカの耳障りな鳴き声だけ。 これが水がないときのイシュワリ、冬に水を吸いとられたイシュワリの川。年老いて弱ったトカゲが腹を日にさらしているみたいに、川は横たわっていた。おじいちゃんもチャチャたちも、今ぼくらがどこにいるのか、どこに向かっているのか、わかっているのだろうかと思った。いつまでも続くギラギラとした風景の中を重い足を引きずって歩いていると、まるで終わりのない旅をしているようだった。アラム・チャチャの肩で身をまかせているぼくには、一歩また一歩と歩みが重くなるのがまるで自分の足のように感じられた。 突然、目の前に緑が荒々しく広がった。木々と家々があらわれた。近づくと、かなり新しい家に見えたものが、ぼくらの家の牛小屋みたいに建てられたものだとわかった。編んだマットと竹の板をひもでくくりつけた簡単な構造で、壊すのも造り直すものすぐできそうだった。ぼくらの牛小屋はブリキの屋根だけれど、ここの家は茅葺きだった。 掘ったて小屋の前で、子どもたちが遊んでいた。みんなぼろ布をまとっていた。裸の子も少しいて、腰にお守りとタビジを伝来の黒いひもでくくりつけていた。ぼくらを目にすると、その子たちは立ちどまり、じっとこっちを見た。アブドゥル・チャチャが叫んだ。「ちょっと、カムルン・ムンシはどこだ、知ってるか?」 その子たちはみんなじっと立っていた。「言ってるのが聞こえないのか?」 アブドゥルが怒鳴った。「カムルン・ムンシを呼んでくれ。ノアパラのチョウドゥリー・シャヘブが来てると言ってくれ」 子どもたちは、雀の群れが散るように走り去った。 ぼくらは集落を囲むバナナの木の陰に入って、そこで待った。アラム・チャチャがかがんでぼくを地面に降ろした。二、三分して女の人が出てきた。頭と頬をみすぼらしいサリーの端で隠していた。少し向こうで他の女たちが集まって、頭をサリーで隠しながら、首をのばしてこちらを見ようとしていた。ダダジャンのところに女の人がやってきて、自分の額に手をやり挨拶した。「サラアム・アレイクム」 おじいちゃんは頭をさげて愛想よくそれに応えた。 「それで?」 それはまるでアブドゥル・チャチャの声のようなそっけなさで、女の人の足元で砂がたてた風の音かと思った。女の人が聞きとれない声で何か言った。「聞こえない、はっきり言うんだ」 アブドゥル・チャチャが声を上げた。「カムルン・ムンシはどこにいる」 女の人は顔を少しあげて、さっき言ったことを繰り返した。「いま、いません」 少し間をとって、こう付け加えた。「市場に行っています。この時間は男の人たちは、、、」 「それであんたは誰なんだ」 ぼくはびっくりした。アブドゥル・チャチャのしゃべり方はまるで、、、なんでアブドゥルはこの女の人に怒ってるんだ? 「わたしは妻です」 小さな声がかえってきた。 女の人はサリーでおおわれた頭をさげて、もごもごと挨拶のようなものを口にしながら歩き始めた。ぼくらは女の人について庭に入っていった。それを見ていた他の女の人たちがぼくらの後をついてきた。サワサワとしゃべる声が、渦をまく川の流れのようだった。 ムンシの家の庭に着くと、カムルン・ムンシの妻は木のジョルチョウキをダダジャンがすわる用に置いた。背の低いスツールは古くて風雨にさらされていたが、入り組んだ彫刻はそれが造られたときの美しい見映えを想い起こさせた。ムンシの妻がそばにいた女の人に何か言うと、その人はすぐにどこかに消えた。残りの女の人たちは、カムルン・ムンシの妻のすぐ後ろに立っていた。ぼくらは今にも壊れそうなムンシの家を眺め、乾いた牛のふんの塊が隅に置いてあるこざっぱりした庭に目をやり、サトウキビのやわらかくした髄や、燃料にするのか売りに出すものなのかぼろ布の山に目をやった。洗濯ひもが家とバナナの木の間に張られ、そこに赤とグリーンのストライプのサリーが干されていた。今、着ているものと同じくらいボロボロのサリーだった。モシャモシャした鶏が二、三羽、コッコッと鳴きながら走りまわっていた。 「とてもうまくお暮らしのようだな」 スツールに腰をおろしながらダダジャンが地主らしく言った。杖で鶏を指してこう訊いた。「卵はよく産みますか。増やすのに雄鶏も飼っているのかな」 ダダジャンの声には荒いものがあって、その話し方はぼくには、さっき越えてきたギラギラした砂地みたいに見慣れないものだった。おじいちゃんが話していると、さっきいなくなった女の人たちが戻ってきた。一人が小さな木のピリを、残りの人たちが食べものを運んできた。ピリをもってきた人がダダジャンの足元にそれを置き、ぼくに座るよううながした。ブリキのカップ二つが、使い古しのブリキボールに入ったバタシャとココナッツ・ナルといっしょに、おじいちゃんの足元に置かれた。ここの人たちでさえ、お客に水だけ出すのはあり得ないことなのだ。 カムルン・ムンシの奥さんが近くに来て、ぼくのそばに立った。ぼくに手で示しながら小さな声で言った。「お食べ、バブ」 頭からサリーがすべりおちて、ぼくは初めてこの女の人の顔をはっきり見ることができた。日にさらされ色あせた田舎のおばさんたちとはまるで違う、嘘のような美しさをもった人だった。ぼくは薄茶色のバタシャをとってしゃぶった。口の中で砕けて甘みが広がった。ダダジャンはカップをとるとそれをすすった。「これはうまい。バブも飲んでごらん」 ぼくがもうひとつのカップをとって飲む。砂糖水だ。ダダジャンは口を鳴らすと尋ねた。「カムルン・ムンシはいったいどこへ? 若い奥さんをひとり残して。他の男たちもいないのかな」 突然、子どもたちが現われた。女の人たちの後ろから、家の隅のところから幽霊みたいにこちらを覗いていた。子どもたちは母親たちと同じように静かだった。 「男の人たちはこの時間家にはいません。どこの村でもそうです」 ぼくらの前に立ったまま、女の人は視線を落とし、足先で土を掘った。「家だけで?」と訊いた。 「いやいや」 ダダジャンが杖を強く振った。「全部でだ。何人いる?」 「ああ、二、三世帯でしょうか」 女の人はあいまいに答えた。ダダジャンはアラム・チャチャを見て、頭を少し傾けた。アラム・チャチャはすっといなくなって庭を抜けて集落に入っていった。ぼくらのまわりは虫の鳴き声でいっぱいだった。 ダダジャンが微笑んだ。「聞きなさい、ベチ(身分の低い女性への呼びかけ)、あんたたちはここにやって来たところだ。ここで暮らすのは大変だ、わたしは知っている。だが本土の人間たちは、チャルアの暮らしの大変さをよくわかってはいない。でもわたしはアッラーの元で生きる男でな。わたしの領地の中のすべてのものが、意味をもって公平に生きていることを、正義が成されていることを、見定めなければならない」 カムルン・ムンシの奥さんは地面を見ながら、小さな、でもはっきりした声で言った。「わたしたちは働いてます。とても大変です、でもアッラーが許すかぎり働きます」 ダダジャンはうなづいた。「そう、そうだ、そうあるべきなんだ。ただアッラーの世界にもいろんな人はいる。この土地はまだ人が住むことはできないと言う者たちもいるだろう。まだここに住んではいけない、とな。チャルがあらわれてから、誰がそこを所有するかで言い争いがたくさん起きている」 おじいちゃんはあご髭をなでた。「わたしについては、まあ単純な男でな。アッラーの法が、土地の法が、どれがわたしのものか、どれをわたしは所有するべきか示すのに従う。でも他の連中は、おわかりだろう、皆が実直というわけではない。これがカムルン・ムンシに言いたかったことだ」 ダダジャンが話をとめると沈黙が場に広がった。カムルン・ムンシの奥さんは身を半分隠している子どもたちの方を見た。子どもたちは見慣れないぼくらに少し慣れてきて、だんだん近づいてきていた。 「人の家を燃やしたり、実のなる木を引き抜いたり、罪もない村人をいじめたり脅したりすることを何とも思わない連中がいる」 ダダジャンは続けた。「そういうやつらは、自分たちが壊したものは、チャルアのものなんだから何をしてもいいと思ってる。わたしはそれが正しいと言っているのではない。あいつらはそう考えるってことだ。そうであっても、あんたたちみたいにキツい労働に耐えて暮らしている者が、そんな風に痛めつけられるのは過ちだ」 ダダジャンはそこで口をつぐんだ。そして目の前に置かれた椀からナルをとって、茶色のせんべいのようなものをかじった。「誰か来たら、わたしのためにここに住んでると言えばいい」 唐突にそう言った。「そうすれば連中はあんたらのじゃまはしなくなる」 カムルン・ムンシの奥さんはパッと顔をあげると、初めてダダジャンをまっすぐに見た。「でも誰もわたしたちに何かしたことはありません」 「そうかもしれん。でもそのうち来る」 ダダジャンはナルをまるごと口に放りこむと、パリパリと噛みくだいた。「間違いない、連中はやって来る」 そう言って水をすすると、バタシャをとった。 ダダジャンがそれを口にしようとすると、奥さんが言った。「前にもチャルに住んでいました。男たちはどうしたらいいか知ってます」 ダダジャンは笑顔をみせた。「そうだろう、知っているだろう。わたしは、ことをやりやすくするために言ってるんだ。カムルン・ムンシにわたしのところに来て、話をするよう伝えなさい。そうすれば他の連中と話す機会もできる」 ちょっと間を置くと、もうひとくち口に入れるかわりに、ダダジャンはバタシャの半月を手の中でくだいて地面に割れかすを落とした。「あんたの言う魚だが、だんなさんが売りに行ってる魚は、イシュワリの魚だ、誰がとってもいいものではない。川の多くは、そしてこの地域の魚ゲルは、わたしが借り受けている」 ダダジャンは人差し指を奥さんに向けて二、三度振った。「だんなさんはどこで魚をとってる?」 奥さんはくちびるをすぼめた。たくさんの言葉が口から逃げ去ってしまったような顔だった。 「わたしは行政官のところに行くことになってる。ここの人間として、新しくできた土地を見る責任があると思ってる。役人に心配ないと言わねばならん、わたしがちゃんとした人々を、ちゃんとしたチャルアたちをここに住まわせてるとな。向こうがここのことを知ってることは大切なことだ」 鶏がそのへんをうろうろ歩きまわっているのを、ダダジャンは杖で指して言った。「あんたたちは鶏も飼ってるだろう。売るために増やしてるのかな」 奥さんはちょっと間をおいてから、やっとうなずいた。 ダダジャンが「一月に何羽生まれる?」と聞くと、アラム・チャチャが雄鶏を腕のしたにかかえて戻ってきた。アラムはぼくのうしろに立った。 「ボロ・アンマがこれでモラグ・ポラオを作りたいだろうな、わが家の若主人のためにな」 そうダダジャンが言った。 おばあちゃんはいつも、ぼくらがやって来ると、この料理を父さんのために作った。たいてい二、三羽の丸々した雄鶏がぼくらの到着を待っていた。たぶん、今回は忘れていたのだろう。 ダダジャンはゆったりとした笑みを見せ、あご髭をなでた。「わたしの息子が、、、ひとり息子なんだがね、家族を連れて年老いた両親のもとを訪ねて来た。息子はここで育った。だからわたしのとこの男たちはみんな、息子を兄弟みたいに思ってる。ここにいる間はいつも、みんな息子のことを丁重に面倒をみるんだ」 ダダジャンは両手を広げ、手の平を上にむけて、「みんな息子のことが兄弟みたいに好きでな、できることは何だってしようとする」 ダダジャンはアラム・チャチャの方にむいて言った。「足を縛ったらどうだ。運ぶのにその方が楽だろう」 女の人は、ダダジャンが話している間、雄鶏をまばたきもせずにじっと見つめていた。と、突然はっきりとした声でこう言った。「もちろんです。あなたのひとり息子さんであれば、もちろん、これをお持ちになるべきです。わたしたちへの支払いはいりません。贈りものとしてお持ちください。この貧しいチャルアからの贈りものです」 この話にうんざりしたのか、女の人はまた黙りこんだ。この日言うべきことをすべて言い終えたみたいだった。 「では、帰るとするか。カムルン・ムンシにわたしのところに会いに来るよう言ってくれ」 そうダダジャンは言うと、バナナの木立のある小道の方へ、杖を空中で無頓着に振りながら歩いていった。握り手の銀細工が何かの合図のように太陽にきらりと光を放った。そのとき杖がダダジャンの手からすべり落ちて、道の脇に立ってぼくらを見送っていた小さな男の子の顔を直撃した。「おうおう、かわいそうに、だいじょうぶかな?」 半分裸のその子は小さな声で泣きながら、黙って立っている女たちの元へふらふらと寄っていった。女たちの誰も子どもの方へ寄っていかず、誰もその子を見ようともしなかった。 「あんたたちのとこの子じゃないのか?」 ダダジャンがカムルン・ムンシの妻に訊いた。「アブドゥル、10タカ札をこの子にやってくれ。かわいそうなことをした。ほらピッチ、チョコレートでも買いなさい。バブ、来なさい」 おじいちゃんはぼくを呼ぶと、「さあ帰るんだ」と言った。 女の人は何も言わず、アブドゥル・チャチャからお金を受け取ろうともしなかった。ダダジャンは歩き始めた。アブドゥル・チャチャは少し待って、それから地面にお札を投げるとダダジャンの後に従った。アラム・チャチャはそのときもう、帰りの旅のためにぼくを肩の上に乗せていた。 道を歩き始めてから、ぼくは、何であの女の人たちはあの子を抱き上げなかったの? あそこにお母さんはいなかったの? と訊いた。 「チャルアはあんな風なんだ」 ダダジャンがぼくに言った。「あの人たちはあちこちを移動しまわっている。住まうその土地そのものが仮の土地だ。土地が変わらずそこに残るものなのか、一ヶ月先にそこにあるかさえわからない。だからあの人たちはわたしたちとはだいぶ違う。アッラーがわれわれにくださったこの命を軽くあつかっている。どうでもいいことのようにな。そんな風だから家族を思う気持ちも持ち合わせてないんだ。子どもに対してもな」 雄鶏が一度大声で鳴きわめき、それから声を落としてクワックワッとしゃがれ声になったかと思うと、首をアブドゥル・チャチャの左肩から垂らした。 「あの人たちはああなんだ。そうであっても、わたしの持てる力の中で、あの人たちのためになることをやろうとしている。アッラーの目の届くところでは、われわれは皆ひとつ、みんな平等だ」 小舟が水に滑り込んでいくとき、ダダジャンがこう言っていたのを覚えている。ここを旅することが長く厳しいものだとわかっていてもなお、帰りの旅はイシュワリの衰えた水の流れのように、いつまでも続き終わりがないように思えた。 考えてみれば、あのときの旅がぼくの心に深く焼きつけたものは、太陽と砂のきらめきだけだったように思える。ぼくが見たチャルは今ダダジャンがいないのと同じように死んでしまったもの。ただぼくの記憶の中にだけあるもの、そしてその記憶があのチャルアの女の人を想い起こさせる。あのときの思い出の鮮明さのせいで、子ども時代のほかの記憶は、ぼくがどんなに必死になって想い起こそうとしても、ぼんやりとかすんでしまう。ぼくはオールが水に入るときのしっかりしたリズムをしばし耳に思い出す。ぼくはダダジャンが満足げにあご髭をなでている姿を、そして「われわれはみんなイシュワリの子どもたちなんだ」と言っていたのを思い出す。 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
