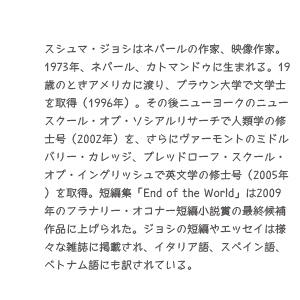|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
たとえば、マヘシュ。一番の友だち。少なくとも僕はそう思っていた。ひところは僕の人生を捧げてもいいくらいに思っていた。なのにあのとき、ある晴れた朝、僕らの友情はトリブバン国際空港で崩壊した。あちこちに散らばった事実とおぼろげに残っている感情をあとでかき集めても、どうしてあんなことになったのか、いまだ僕には理解できないのだ。 ボンベイのあの騒がしくて、蒸し蒸しした夜という夜を、僕らは一緒にたくさんの時間を過ごした、ネパールにいた頃の思い出話を、夢や希望を、徐々にしぼんでいく野心を語るに充分な時間、愛とか裏切りについて心を割って話すところまでいくのに、自分たちが生涯の友になるとわかるのに充分な時間があった。口に出すのが辛い出来事、傷つき、ひどい苦しみを味わったことを心置きなく話せるところまで、僕らはいっていた。 マヘシュは僕に、恋人が結婚式の前日に、カシミール絨毯の商人と駆け落ちしたと語った。僕の方は僕の奥さんラーダーは、僕と一緒になるために前のダンナのところから逃げてきたんだけど、またしても駆け落ちしたんだ、今度は彼女より十歳も若い警察官とね、と言った。「そいつはさ、彼女の足を毎晩マッサージするんだってさ、マヘシュ」 僕は最初にその男の存在がわかったときの、ひどいショックの中でそう告げた。晩に家に電話したら、なんてことだ、知らない男が電話をとって、野太い声が電話線の向こうから聞こえてきたんだ。ラーダーときたら、インド神話の貞節なラーダーとは似ても似つかない厚かましいやつで、今警察官の男と一緒なのって言うわけだ。で、その男は毎晩あたしの足をマッサージしてくれるの、だってさ。このオレにだよ、まるで仲良しのクソアマかなんかに言うみたいにさ。それから時を置かずして、息子のために家を譲渡すると契約書にサインしてくれって、まるでこっちには自分の家にも、妻や子どものことにも、何も言う権利がないみたいにね。あのクソオンナ。もっとよく知ってれば、結婚なんか絶対しなかった。でもこれからはもっとうまくやるさ。 僕がマヘシュに出会ったのは、二人がボンベイの建設現場で働いていたときだ。テクダールが僕らを狭苦しい一室に押し込んだわけだけど、そこは茶色いゴキブリが戦場みたいに走りまわってて、洗ってない服のいやーな臭いと、男たちがムスコを相手に我が手を駆使して湿っぽい夢想にふけった後の残り香が立ち籠めててさ。僕はダリ(綿の敷物)を床に敷いて寝てた。マヘシュの方は長くボンベイにいたんで、自分の木のベッドに緑のシーツ、スリデヴィのポスターをべたべた貼ったつい立て、小さなラジオを持ってて、そのラジオときたらパンパンに張ったポリ袋みたいにガーガーパチパチ一晩じゅう鳴ってて、朝も早くから部屋の者を起こすわけだ。マヘシュはそのラジオに夢中で、何時間でもその前にいる。音楽やら広告やらプロパガンダやら遠い世界からやってくるBBCやラジオ・アメリカの雑音を聴いている。もちろんマヘシュは英語なんかひとことも知らない、でも全然気にしてないみたいでラジオの前に座りつづけ、何時間も何時間も、ガーガー言う騒音と自分の預かり知らない、理解もできない世界のうなり声を聴いている、それもただ音を聞いてるだけ。「クソッタレラジオを消してくれ、マヘシュ」 僕が怒鳴っても、マヘシュは聞こえないふりをしてダイヤルを回しつづける。もちろんそのときは、つまり仕事で疲れた夜にあの雑音を聞いて、キチガイマヘシュと憎っくきラジオを呪っていたときは、それから十年の内に自分が英語を学んで海外に行き、新しい家を建てるまでになるなんて思いもしなかった。奇跡は起こるんだ。僕は読んだり書いたりを学ぼうっていつも意識していたんだな。でもこれはまた別の話。 十五年前のこと。腐るほどたくさんの手抜き工事のビルと死にそうな体験をした後、僕らは建設現場といかがわしいテクダールの元を離れて、もっと実入りがよくて簡単に儲かるホテル業に仕事を鞍替えした。そう僕を説得したのはマヘシュだ。「ネトラが足場から落ちた、新しいビルの現場さ。テクダールは遺体を故郷に送り返す金を払いたくないんだ」 ある晩、仕事の後でマヘシュは皆に言った。恐い顔をしていた。 「ビチャラ(そりゃ気のどくだ)」 仲間の中で一番年上のホムラージが声を上げた。「あの気の毒な男の嫁は三番目の子どもが腹にいるんだ。どうやってこの先、生きていけるんだ」 僕らにはわかっていた、誰も口に出さずとも、ネトラの奥さんはカマティプラ(ボンベイ最大の風俗街)に行くことになるんだ、彼女の実家が引き取らない限り。僕らは神妙な面持ちで百ルピーずつ寄付をした。それで遺体は飛行機で故郷に帰り、火葬できる。「オレらが飛行機に乗れる機会ってのは、死体になったときだけだな」と、ホムラージが僕の手から汚い札を受けとりながら自嘲気味に言った。誰も飛行機に乗ったことなんかなかったし、それがあるとすれば緊急事態が起きて、遺体を早く運ばなければならないときなんだ。 その夜、ベッドに横たわったまま、マヘシュが僕に言った。「ゴータマー、俺は出て行くよ。オマエも来るだろ」 どこへ? 僕は訊いた。マヘシュは夜中に急にたばこが吸いたくなったんで、話し相手が欲しかったんだ、と思った。 「俺らがあのテクダールとここにいれば、白い布に被われて故郷に帰ることになる」 マヘシュの声は淡々としていた。暗闇でその声を聞いていて、寒気がした。 「どこに行ったらいいのか、僕にはわからない」 そう言った。僕は十七歳になっていた。ボンベイに四年間いたことになる。セメントを混ぜること、砂を運ぶこと、レンガを並べること、それ以外のことは何一つ知らない。 「友だちが一人いるから、そいつのところへ行けばいい」とマヘシュ。「俺の村からやって来たのがたくさん、コラバのホテルで働いてる」 「それってどこなの?」 「海の方だよ。行けばわかる」 次の朝、マヘシュと僕はコラバ行きの電車に乗った。僕らがヴィクトリア駅に着くと、まだ電車が止まらないうちに、車両に飛び乗る男たちがいた。何百人もの男たちが、完璧に同じリズムで、空中ブランコの曲芸師みたいに車両の中に流れ込んでいった。僕はびっくりしてそこに立ちつくした。いったい何が起きているのか理解しようとした。男たちは、長旅に備えて席を確保しようとして飛び込んだようだった。男たちの一団が僕を席につかせようとするまで、僕はポカンと田舎ものみたいにつっ立っていた。 マヘシュが僕の腕をつかむと、さあ行くぞと言った。僕らはコラバの街に向かって歩きだした。そこは金持ちがたくさん暮らしている場所だとわかった。タージ・ホテルは宮殿のように輝いていた。ホテルの正面はまさにインドの玄関口、ただっ広い海が目の前に広がっていた。鳥たちがその玄関口を優雅に羽をはばたかせ、白い糞を撒き散らしながら飛んでいた。僕はこの新しい世界で生きのびる不安や緊張とともに、心が高く舞い上がるのを感じた。 「僕ら、仕事見つけられるのかな、マヘシュ」 僕が言った。「戻った方がいいんじゃないの」 マヘシュはにやりとした。彼がよくする皮肉っぽい笑いを見せて「バカ言うんじゃないよ」。「どうしたいっていうんだ? 籠の鳥か? そういうのがいいのか?」 マヘシュがパンを一切れカモメにむかって投げると、カモメは舞い降りてきてそれを素早く捉え、大きな鳴き声をあげて飛んでいった。 マヘシュのいとこが彼らのデラ(住処)に泊めてくれたので、僕らはそこにいることにした。その部屋には八人の男たちがすでに住んでいて、あと二人くらい増えても問題はなかった。僕は警備員の仕事をなんとか見つけることができた。オベロイという、マリーン通りにある大きめのホテルで、人事担当者は僕の愛想のいいネパール人顔が気に入ったようだ。マヘシュは、肌の黒さと大きな目が、ボンベイでは不利に働いた。ヒンディー語の会話能力もなく、ヒンディー映画のフィルミ音楽の知識もほとんどないのに、寝ている雇い主を刺し殺したりは絶対にしない正直で愛想のいいネパール人である、というマヘシュの言い分に何かと疑問符がつけられた。最後にはマヘシュの純朴さや悪知恵のなさそうな様子が気に入られ、グランド・ホイートリー・ホテルの支配人が受付係として彼を雇い入れた。グランド・ホイートリー・ホテルは大理石の階段に植民地時代の家具をちりばめた大時代的な建て物で、亜大陸へのお決まりの巡礼の旅を成し遂げるために、そして安い衣料品を買いだめするために、さらにはサヒーブダム(植民者の覇権)を再現したお手軽なパッケージツアーを味わうという重要な目的のためにやって来た元植民地の旅行者たちの、古き良き時代へのロマンティックな想いを満たしていた。 マヘシュと僕は居候として、すぐにいとこ達の九番目、十番目のルームメートになった。部屋はまあ、本当のところ、混雑はしていたが、でもそれが僕らの夜の討論会を阻むことはなかった。僕とマヘシュはこの頃までに、夜のグフガフの習慣を定着させてきた。国籍が同じだからではなくて、僕らが人生について、愛とその実存への疑問について、腹を割った率直な話し合いをずっとしてきたことを基本にしたグフガフ。こういう討論の全てが、みすぼらしい、零ワット電球の暗い台所でゴミのように排出された。台所は汚い皿が流しに山となり、食べものがガツガツとむさぼり喰われ、口と舌はただ食べるためだけに使われ、部屋を出るときも挨拶ひとつなし。「おまえら、うるさいよ。自分らは何だと思ってんだ? 政治家か?」 電波の浴び過ぎで不眠症の僕ら二人が、国について、インディラ・ガンディーと非常事態について、モハンダス・カラムチャンド・ガンディーの偉大さについて(そう、そんなことまでも)、そして自分たちの青春が、ボンベイというコンクリートとゴミの山の中に消えていくの見ながら、教育を受けるという夢をどうやって残飯といっしょにドブに流してしまったか、、、を議論していると、皆が寝床からどなりつけてくるわけだ。それから僕らは、女のところに性懲りもなく戻っていく。またもやだ、いつも女だ、僕らのエネルギーを搾り取り、熱くて湿った欲望で僕らの夢を満たす女たち。カマティプラの通りに並んでカラダも太ももも甘い味の性器さえも与えるのに、それ以上のものは何一つくれようとしないディディ・バヒニ、クソったれオンナたち、そこに行ったときでさえ、僕らは満たされない。 マヘシュは年の差から、僕のことを「バイ」(弟)と呼んでいた。僕はマヘシュより一ヶ月だけ年下だった。ゴータマ・ブッダと同じバイサカ月(太陽暦の4月か5月)の満月の日に生まれたんで、僕はゴータムと名づけられた。ブッダに因んだ名前をもっていることは嬉しかった。あの人が僕なんかよりずっと早く悟りの境地に達していたとしてもだ。でも僕はなんであれ遅咲きの花、人よりなんでもやることが遅い。僕は母親の子宮の中にまるまる十ヶ月もいた、かなーり長い。僕の母は出産のとき、ゾウの子を産むんじゃないかという噂が流れていたくらいだ。生まれてからは、四歳になるまで口をきかなかった。心配した母はジャンクリ(ネパールの伝統的療法士)を呼んで、僕の頭の上でニワトリを斬りつけたんだ。「ナー」。血が僕にしたたり落ちてきたとき、怒りと逆上の中でぼくは最初の言葉を叫んだ。それからというもの、「いやだ」「いやだ」「いやだ」、僕の子ども時代はこの言葉で埋めつくされていた、と母親は文句を言っていた。 僕の声変わりは他の子たちより遅かったし、ヒゲは同い年の子たちより三年も遅れて生えた。それに三十センチも皆より背が低かった。母親におんぶされているときから、女の人に対して強いあこがれがあったとしてもだ。僕は他の男の子たちよりこの分野では先んじていた。十三歳のときにはミナ姉さんと寝ていたんでね。ミナは僕の親友の姉さんで、四年間にも渡るダンナのインドへの失踪に耐えられなかったんだ。それで村の半分の男たちと寝ていると言われてた。僕には男として何か光るものがあったんだな、うん、そうなんだろうな、ミナは僕くらいの男の子たちの中から僕を選んだんだ、覚えておいて。皆より三十センチも背が低くて、声変わりさえしてない僕なのにね。たぶん、ミナは僕の子どもっぽさが気に入ったんじゃないか。女たちの好みというのは説明がつかないもの。女っていうのは皆、一貫性のない変人奇人、どんな女でもだ、とはいえ、このことがわかったのは少しずつ少しずつ痛みとともに、もっともっと後になってのこと。そんなこんなで僕はキビ畑のてっぺんで、マイリの上にまたがってとても幸せだった。からだの下でチクチクする草を感じながら、彼女があばずれみたいにハアハア、ウンウンいうのを見ながらね。たいしたあばずれだったよ。上等なね、でも僕はまた、それを超えて先をいく。 ということで、マヘシュと僕のことに戻る。僕らは一緒によくカマティプラに行った。しばらくして僕らは、セックスを死ぬほどやって満たされるという夢は、僕らの青春時代と同様、ドブに流れて消えたと感じた。それでついに、マヘシュは気づいたんだ。僕らが人生で見失っているのはセックスじゃない、ってね。それはしこたまやった。でも「愛」がないんだ。そうはいっても、絶望や孤独という巨獣がのさばるボンベイでは、それを見つけるのはまったくのところ至難のわざだ。人生を自分の手に取り戻そうとマヘシュは、カマティプラで気に入った女の子たちを何回か訪ね、その子たちとの結婚に手を染めようとした。女たちは嫌っているわけじゃないのに、ずっと、何回も何回もマヘシュの申し出を拒否していた。あたしたち借金をやっと払い終えたところなの、もう誰のものにもなるつもりはない、ごめんね、そう彼女たち。マヘシュは女たちに乞い願い、訴えた、僕はただ女性を愛して、その人のこの先の人生を幸せなものにしたいだけなんだ。女たちは不可解な笑みを見せて、彼に言った。悪いわね、可愛い人、あたしたちは一晩過ごすだけで充分なの、一生なんてとても想像できない。この絶望感のために、僕らはとうとう故郷に帰ることになった。まじりけなしの、ひどい孤独感を抱えて。 というわけで僕らは故郷であるネパールに帰って、生活を立て直すことにした。その間には数えきれないくらいのいろんなことが起こったけれど、核心以外の細かなことは省く。僕らはカトマンズに居を据えた。実家はまだ村にあったんだけどね。マヘシュと僕は土地を買って、小さな家を建てた。貯めてたお金で小さなレストランを始めた。新たに見つけた共同経営者は口のうまい男で、僕はマヘシュに気をつけるよう注意していたが、その男はマヘシュを様々な情報や数字や将来のプランの波でさらったあげく、ある晴れた夏の日消え去った。そいつはレジから現金を持ち去っただけじゃない、レストランの土地を担保にして銀行から三十万ルピーを借り出しそれも持ち去った。一ヶ月後、巣立ちしたばかりのレストランはつぶれた。 僕は丸々して可愛らしい、デヴィという名のおダンゴ娘と結婚した。お金にかかわるやっかいな諍いが、僕らの素晴らしい結婚生活に入り込んでくるようになるまでは、彼女をおダンゴ女神とあがめていた。マヘシュの強いすすめで、僕は占星術師のところへ行った。その占星術師は言った、今年は僕にとって土星回帰の年だと。一人の女が僕の前に現われるが、それは僕に適した人ではない。すべてが再び解決されるまで、あと二十九年待たねばならない。僕は百ルピーを払って礼を言った。クソッタレめが! 家に帰るときマヘシュに向かってこうどなった。家に帰ったと思ったら、借りてる家の中は空っぽで、ベッドはシーツまではがされていた。そして隣の人から、デヴィはマレーシア帰りのグルカ兵の男とオートバイで出て行ったと聞かされた。 僕は心砕けた。サイフにいつも入れていた彼女の写真を燃やした。着ていたシャツをズタズタに切り裂いた。それでも気が治まらず、彼女が入口のそばに残していった鉢植えを蹴り上げた。「そんなに怒んなくても、バイ」 マヘシュが慰めた。「ドゥカ・スカ(苦痛と幸福)ってのは皆同じさ。やって来て、どこかに消える」 「でもどうして、こんなやり方で?」 僕は怒っていた。僕が学び始めた英語の世界では、幸福と悲哀がシャム双生児みたいに尻でひっついちゃあいない。「なんでなんだ?」 憤りの中で叫んだ。 マヘシュは肩をすくめて、湯を沸かした。「ひとつだけ持つことは許されないってことさ」 お茶を僕に手渡しながらマヘシュはそう言った。「水なしでお茶を入れるみたいなものさ。できるか? できないだろ。悲しい想いなしに幸せを知ることはできない。逆も真なり」 マヘシュのこういう口のうまさには、我慢がならなかった。 僕はマヘシュといっしょに引っ越して、また五年以上も、兄弟のように共に暮らした。そしてデモクラシー運動が熱く盛り上がった。どうしてか自分たちが、なんでその真っただ中にいるかもわからず、マルクス・レーニン主義共産党のリーフレットを配っていたんだ。声を上げる二百万もの人々と、ロイヤルパレスの前で窓ガラスが砕け散っているのに囲まれて、初めて何が起きているかの意味がわかった。「デモクラシーを我らに! デモクラシーを我らに! デモクラシーを我らに!」 人々は叫び、年老いたネワール人の男たちは窓の向こうでぼんやり立ちすくむ。なんでこの人たちはこんなにも興奮して叫んでいるのか、「でもくわし、でもくわし、でもくわし」と騒いでいるのか。「でもくわし」とはこの老人たちにとっては、単に雄牛の精巣器官を意味するだけなのに。足を踏み鳴らし、角を突き立て、鼻を鳴らすデモクラシーがやって来て、雄牛の睾丸みたいな僕らの頭をひっぱたいていった。でも、それが何を意味するのか本当にわかったのは六年後のことだ。 で、マヘシュはマルクス・レーニン連合党に入った。僕はといえば、端っこから見てた。僕は遅咲きの花だと言ったよね。あるいは僕の方が少しものがわかってたのかもしれない。考えなしに頭から突っ込んでいく情熱家のマヘシュとちがって、注意深いし人をあまり信用しないし。数えきれないくらいの女たちからヤケドを負わされ、苦い裏切りの味も知っている僕は、どんなことであれ、何かにどっぷり手を染めるってことはしない。安全な政治なんて、安全なセックスがないのと同じように、あり得ない。僕は自分の人生を、何だかよくわからないウィルスに犯された政治グループのために、危険にさらすようなことはしなかった。それから六年後、何もよくならず、政治グループは皆、野犬の群れみたいに闘争を始め、デモクラシーなんかなかったときよりもっと腐敗は進んだ。ネパール共産党毛沢東主義派(マオイスト)に関する秘密のやりとりが僕らの間で浮上し、それに参加することに決めた。反政府分子になるというのはいい考えのように思えた。今のような職なしの惨めな状況ではなおのこと。活動家としての僕らの立ち場は、厳しい飢えと惨めな状況によって損なわれてきた。それはもう史上最低のもので、あとから思えばバラ色にさえ見えた、ユートピビアのようなボンベイでの懐かしい暮らしとは比べものにならなかった。失ったユートピアというのは取り返すことができないものだ。そういう場合にやることは一つ、即座に思い出を、できれば、思い出をとどめようとする体ごと分断すること。というわけで入隊にあいなった。 それで僕らはその夜、美しい丘陵の上で、木々に囲まれ、たき火としばらくぶりのちゃんとした食事、ぴっちりした兵服を着たきれいな女性たちが行き来するこの場所にいたというわけ。反乱軍のキャンプだ。僕は松の木々の匂いを深く吸って、にっこりした。ここは天国だ、アルガカンチだ。でも昼は、でかくて不細工な銃を手に、堅苦しい服を着て、血なまぐさい兵士みたいに行進するわけで、僕はまた別の考えを持ち始めた。いったい僕はここで何をしてるんだ? そう思った。当然のように僕は、人民戦争や革命や戦友に関するあらゆる文学作品を読んできていて、それは町にいるときはいいことのように見えた。でも今ここで、銃と百人ものイデオロギーに燃える人間たちにがんじがらめになって、僕は、遅咲きの花の僕は、不安になってきた。つまるところ、革命児になるなんてことは至難のわざだった。僕のような誰よりも背の小さいやつは、そして誰よりもヒゲが生えるのが遅いやつは、ほんとのところ太刀打ちしようったってできるわけがなかった。僕の中で何かが、これは僕のすることじゃないと言っていた。僕は相棒マヘシュに向かって言った。「そろそろここを出て行くときかな、ヤール(僕の友)」 でもマヘシュは顔をしかめてささやいた。「続けるんだよ、バイ。そうすれば幸せになれる」 で、僕はここにいて、気の進まない兵隊をやって、幸せになるためにいまいましい努力していたんだ。何が言いたいかわかるかな? 僕はほんとうに幸せになろうとしていたってことなんだ。 で、ひとことで言えば、当然の成りゆきとして、警察署を襲撃し、そこは血の海、バラバラ死体、叫び声でいっぱいで、僕は銃を抱きしめて超特急で走り出し、近くの裏山に逃げ込んだ。なぜかと言えば、前に言わなかったかな、僕は血の臭いがダメなんだ。ほんと苦手なんだ。それでそうなった。 マヘシュはその日の戦闘で、英雄のように戦った。敵味方両方で五百人が死んだとは言え、僕らが二百、向こうが三百、両者ともにこの戦果に満足だった。それは血が流され、頭が撃ち落とされて、勇敢さや固い献身や理想への執着といった自らの犯されざる権利を証明したからだ。僕をのぞいては、ということだけど。他の兵士たちが僕を見るとき、その革命的な顔には不快感が漂ったが、戦闘の小競り合いはひどく血なまぐさく、また混乱も多々あったため、運のいいことに誰も僕が岩陰に隠れて頭をおおい、「ジョムソンマイ・バザールマ」を(わかってるわかってる、これは良くない選択だ、あやまるよ、でもこれしか空で歌えるものがなかったんだ)、何回も何回もどこかの血なまぐさいポップスターみたいに歌っていたとは、そしてぼくが「頭ひとつとしてぶった切ったりしなかった」ことを誰も気づかなかった。職務怠慢だったけど、僕はこのことを、年長の同志ラムバハドゥルに申請するつもりはさらさらなかった。彼はこの手のことを重く受けとったし、僕の行為を無作法きわまりないと思えば、軍隊式処罰を課そうとしたかもしれなかった。それはちょっと困る。 そういうわけで、マヘシュと僕はここでも昼の間、人生や愛やそれにまつわるためになることについて火のそばで、また恐ろしい革命児になるための訓練に戻るまでのつかの間に、語り合っていた。もちろん季節労働者の新兵訓練所にいる誰も、どんな理由があれ、この体験を繰り返したいとは思わないだろうが、僕が反政府軍のキャンプから逃げ出そうと決めたのは、僕が革命による世界変革を信じなかったからじゃない、僕は心から信じていたんだ、毛主席の亡きがらに誓って言うけど、どうしても耐えられなかったのは不味いウシネコ飯なんだ。何を言おうとしてるかわかるかな。つまりボンベイで十五年間うまい飯を喰ったあとでは、もう元には戻れないってこと、兵舎の臭いクソなんか喰えないってこと。毛沢東主義運動のバラモンの指導者たちが、よく聞いて、上質のバズマティ米を食べてるって聞いたひにはね。これじゃ、どんな強い革命心をも挫かせるに充分。そして僕は、百五十センチしかないこの僕は、不満の種をそれ以外にも持っていた。 マヘシュと僕はその夜から、別々の道を歩むことになった。僕はこっそりとキャンプを出て短い足で走れるだけ速く走って、町へ逃れた。僕は逃亡していたわけで、それは僕がマヘシュと、兄弟であり、友であり、地獄をともに駆け抜けてきた仲間であるマヘシュとのいっさいの関係を絶つことだった。そして町に戻った、なぜならマヘシュはクソ革命児になることをあきらめようとしないからだ。そうさ、なんてクソッタレ。僕はおいしい米が食べたかっただけ、言えるのはそれだけ。 毛沢東主義派の夢から逃れた後、僕は資本主義者の描く夢の中で役割を担っている自分に気づいた。バートバテニ・スーパーマーケットで警備員の仕事をみつけたんだ。ここに集まる金持ち連中はパジェロを運転してやって来て、悪ガキや肉づきのいい妻を入口で降ろし、僕は小さな駐車場の中で右へ左へと車を誘導する。女も子どもも男も皆太り過ぎで、最新の西洋の商品を買いに、消費の殿堂の中へと入っていく。スーパーで働くのが、革命児であったときよりも気分がいいということはない。そしてついに答えは出た。それはたった六ヶ月後のこと、都市の特権であるチーズやチョコレートをしこたま積み込んで、グロテスクに膨れ上がった醜い姿を見続けてわかった、僕はこの国から出て行く必要があると。以上。僕は逃げ場が必要だった、隠れ家が。戦争をとることも、平和をとることもできなかった。僕は外へ逃げ出さなくちゃ、そして逃げなきゃいけなくなったら、僕は誰よりも速く走り出す。 それで僕は二年ほど、香港に落ち着くことになったというわけ。ここの人たちは皆、ネパールに自分探しに、神を探しに、平和を探しに、英知を探しに押し寄せる。僕にとってはこういうものを見つけるために行く場所と言えば、インドへの国境を超えるしかなかったのは、何とも不公平に見えてしまう。ボンベイは自分は元より、何かを見つけられるような所とは言えない。とにかく混雑がひどくて迷子になって、次の朝には自分さえ見失うほどだ。それに比べると、香港の方は、僕の親戚によれば、自分を見つけるのにとてもいい場所であると。スーパーマーケットしかり、いろいろなお店しかり、様々な仕事しかり、お金の面でも。ソニーのステレオやサムソンのカラーテレビ、白い冷蔵庫、素敵な扇風機、真っ赤なラジオが詰まった小さな家をもつ夢や希望を育むのは、こういった消費の場。そうなんだ、人々はキラキラピカピカした香港で、心の奥深くにある本能を発見したんだ。自分自身を「後期資本主義」の慰めの中にとどまらず、グローバル化した華やかではかない過剰消費の中に見いだしたんだ。僕は自分自身の巡礼の旅を始めなければと思った。 僕はスーパーマーケットでいろんな人に出会った。その人たちの中に、僕に運び屋の仕事をさせたらと考えた人たちがいた。僕がするのは香港に行って、法律が許す範囲内の金(きん)をもって帰ること。それだけのこと。ドラッグや不法なものを尻の穴に入れたりはしない。金だけだ。それにどうやら金というのは、僕みたいなニコニコしてさっそうとした運び屋に、香港までの飛行機代を払えるくらい、そこそこ儲かるもののようだ。それに加えて、セーターの十枚重ね着、ジーンズの三枚重ね、左右の手に五個ずつ合計十個の金の時計を運ばせて、個人使用ということで税金の支払いはなしで済ます。でもこれは香港旅行の特権を手にする、ほんの小さなやっかいごと。行ったり来たり二、三回やれば、自分でネオン輝く街への航空券を買えるくらい金がたまる。 僕はスーパーマーケットで警備員の仕事を見つけた(これでわかるかな、僕の身の処し方が。警備のニコニコ顔ってのは、美しいヒマラヤ王国ネパールによってもたらされる?)、そして二年後には、あの不実なラーダー、僕の子どもの母親でもあるあのクソッタレ女が、僕から奪った家に代わるものが買える金が作れた。だから僕はここに戻った。が、ご想像のとおり、これが僕の最大の過ちとなった。 僕はおろしたてのブルージーンと道端で二、三ドルで手に入れたシャネルのTシャツ姿で飛行機を降りた。緑のアーミーバッグの中には、オードトワレが三箱、新品のシャツが一ダース、金の時計二、三個、すべて道端で購入の品々が入っていた。ベルトには新札の香港ドルの束(サネパ近くの田んぼに小さな家が建てられるくらいの金)を挟み込んでいた。それが破滅の元だった。懐かしくも小便臭いトリブバン空港に着いて、目には家に帰りついた嬉し涙をためていた。涙も乾いた頃、税関の役人が僕を通そうとせず、厳しい目つきで隣の部屋へ行くように指示した。僕はびくびくして自分が安全ではないと感じた。この男に時計をやって逃がしてもらうことは可能か? それとも金の方がいい? いくらか握らせる? 持ち金全部? それとももっと何か要求してくる? 僕の魂とか内蔵とか僕のからだ全部とか、トリブバン空港の移民局役人が何かと要求する習わしがあるみたいに? この日は気力と根性の日となった。二人の警備員が隣の部屋に僕を連れていき、僕を裸にした。二人は僕のパンツを振ってたけど、金とか爆弾でも出てくると思ったのだろうか。彼らが何を探しているのか、よくわからなかった。警備員たちもわかってないように見えたけど。マネーベルトを取り上げた役人がいたのは、僕の予想通り。がっちりした体格の、渋い顔つき、狡猾そうな目をしていた。抵抗する僕の声は、無力で弱々しかった。 男たちは僕をテーブルにつかせた。一人の役人が片側に、もう一人が反対側にすわった。「どこでこの金を手に入れたんだ?」 役人が訊いた。「自分で稼いだんですよ」 僕はいらついてそう言ったが、すぐに恐くなった。僕は二人の手元からお金の束を奪い返して、逃げ出したい衝動にかられた。尻丸だしのまま飛び出して金を持ち去るという突飛な行動にでたのは、このバカげた欲望によるものだ。 「つかまえろ」 男たちが鉄の万力で僕に襲いかかったとき、背後でそういう声を聞いた。僕はカトマンズの寒さの中に立って、裸のまま震えていた。声はマヘシュだった、はるか昔の、懐かしい親友マヘシュの声だった。「マヘシュ!」 僕は大喜びで振り返ったけど、そこにいたのは、髪を短く刈り上げた、僕を見ることもできないくらいばつの悪そうな顔をした男だった。すぐにわかったのは、彼と会うために呼び出されたんではないこと。マヘシュは、入国しようとしている帰国者の列の中から、僕をつまみ出した男たちの一員だった。僕はマヘシュを見た。そのとき裏切りという行為が、一瞬の緊張とむちで切りとられ宙に浮いた時間の中で、目に見える形となって現われた。マヘシュは顔を伏せていて、僕と目を合わせることができなかった。 その役人はそばにやって来ると僕を平手打ちした。僕はぐらりとした。「特別捜査官マヘシュ・ティワリだ」 男は恐い顔をしてピシャリと言った。そして部下の方を向いて命令した。「この男を連れていけ。毛沢東主義派の疑いがある。よって検挙だ」 幾千もの想いが僕の頭をよぎった。じゃあマヘシュはもう毛沢東主義派じゃないのか? それとも、一方で毛沢東主義派に引かれつつ、警察官と見紛うくらい官僚機構に犯されてしまったのか? マヘシュの振るまいは、毛沢東主義者であれ警察官であれ、その両方であれ、今のこの国で、矛盾はなかった。ネパールにおけるころころ変わる政治的嗜好やモラルの泥沼の中で、僕みたいな、言ってみれば、香港で過剰消費の洗礼を受けてもまれた改宗者にとっては、カメレオンみたいに変化する忠誠というものへの理解が持てず、困惑するばかり。なんて言ってやればいいんだ、この男に。最後の晩、満月の下で、銃を赤ん坊みたいに抱いて、毛沢東の冊子を枕元に置いて眠っていたこの男に。反対側に鞍替えしたらしいこの男に、今、何が言える。彼が鞍替えしていたとしても、なんでまた僕みたいな出稼ぎ労働者を、革命分子扱いしてクソ逮捕するんだ? 八月末のあの決定的な夜に頭がいくつもふっとんだのを見たとき、鬼みたいに僕は逃げなかっただろうか? 「おまえは、ドカイバジだよ、最低のクソッタレだ」というのが、連れていかれるときに、口からこぼれ落ちたうめき声の中で唯一言葉になったもの。 僕にはよくわからない、マヘシュに何をしたから、僕は仕返しされたのか。これを書いている刑務所で僕は、毛沢東主義者であると糾弾されている百人ものジャーナリストや弁護士や学生、人権活動家たちとともに朽ち果てている。もしかしたら、マヘシュは自分で自分にしたことに腹をたてて、自分に対して仕返ししたんじゃないか。イデオロギーっていうのは、実際のところ、簡単に右から左へと向きを変えるような気まぐれなもの、あっという間に元に戻るもの、そうじゃないのか。そいつはいつの間にグルリとまわって出発点に舞い戻るのか、いつ反対の立ち場と混じり始めるのか。マヘシュは自分自身の離脱に対する怒りを、僕を罰することで葬り去ろうとしてるんじゃないのか。それは僕が離脱した最初の人間だったからだ、自分じゃなくて。暴力が幅を利かせる世の中で、人として現代を生きるのに、信念とか信条は本当に必要なものなのか。もしそうなら、あちこちの国の丘の斜面で朽ち落ちていく犠牲者たちも、革命に燃える心の高鳴りと同様、世界経済を燃えたたせるのに必要不可欠なものなのだろうか。ほんのつかの間支持しただけの、僕らが選んだものじゃない世の中など、当てにすることはできるのか。あるいは裏切り者になることなく、そのときそのときの選択から逃げ出すことはできるのか。他の言葉で言えば、僕の暮らしが米粒みたいにドブに流される前みたいに、ある昔々の友だちと、月明かりの夜に、モハンダス・カラムチャンド・ガンディーの議論に戻ることはできるのか。そこで、なんでこんな裏切りが起こるのか、訊くことは許されるんだろうか。でも当然ながら、どれだけこのことを考えて考えて考えようとも、問題じゃない、どんな弁解も、当然ながら、あり得ない。すでに永遠に音として刻まれている歌を巻き戻したり、再録音することは不可能なのだ。なんで裏切りが起きるかをちゃんと説明できる言葉など、どこにも存在しない。なぜ僕らは自分たちを、互いに、何度でも、裏切り続けるのか、説明は不可能だ。 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||