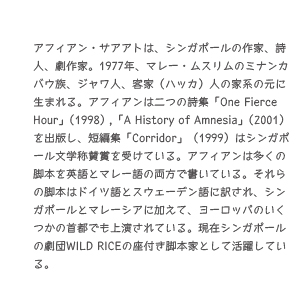|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
スハイリは寝室の窓のそばでたばこを吸っていた。刑務所からもどって三日目、その間、家でタバコを吸うのを我慢していた。でもこの部屋を自分のものに戻す必要があった。この一年、妹がこの部屋を占領していたのだから。そのためにやることは一つ、カーテンやシーツや枕に自分のたばこの臭いをつけること。 寝室の中はどこにも変わったところはなかった。妹がここに住んでいた形跡といえば、洋服ダンスの扉の内側に残された韓国スターのポスターくらい。スハイリはそれを見つけたとき、自分の不在を感じた。実際、妹がティーンエイジャーになるのを、自分は見ようとしてこなかった。 本当は妹が残していった痕跡は他にもあった。ジャスパーがスハイリに買ってくれた香水の瓶が、半分空になっていた。逮捕される二、三日前、誕生日プレゼントとして彼がくれたことを思い返した。妹は気にしながら使っていたのだろう、一年の不在の間に半分しかなくなっていないのだから。あるいは母が「使うんじゃないよ、それはスハイリのものなんだから」とでも言ったのか。そう考えると心が休まった。自分の一部がこの家にいつも存在していたと思える。 スハイリが刑務所にいたとき、ジャスパーは手紙をくれなかった。彼に書いて送った最初の何通かの手紙を思い出した。収監者は、折って端を糊付けすると封筒になる便せんを配られていた。限られたスペースにたくさんの文字を詰め込もうと、どれだけ隙間を節約して書いたことか、それでも最後は小さな消え入るような文字でプツリと終わることになる。最後に彼にあてて書いた手紙は九つの単語から成っていた。「ジャスパー、わたしの、愛する人、お願いだから、返事を、ください。あなたの、恋人、エリー」 スハイリはそれを大きな文字で書いた。それで少し気が晴れた。こんなバカげたふわふわした言葉はもうたくさん。 スハイリにアイスを教えたのはジャスパーだった。最初ジャスパーはこっそりとそれをやっていた。長いことトイレにこもって吸ったりしていたが、すぐにスハイリの目の前で堂々とやりはじめた。スハイリはやめさせようとしたり、アイス用のパイプを何度か壊したりしたけれど、新しいものを手に入れる術をいつも見つけてきた。ある日、スハイリは味見させてと頼んだ。ジャスパーは最初ダメだと言ったけれど、すぐにどうやって吸うか教えてくれた。 スハイリには計画があった。彼といっしょにアイスをやって、自分がやめてみせればいい見本になると思った。すべては意思の力だ。スハイリは自分の自制心に自信を持っていた。ウェイトレスとして働いていたが、美容学校で学ぶ時間をちゃんとやりくりしていた。 一ヶ月後、スハイリの作戦は消極的なものになった。むしろジャスパーが吸うのを促進させた。二人はアイスをやる時間を決めようとした。朝に一回、夕食後に一回というように。二人はやがて一日三回吸うようになり、それが五回になり、そのときにはスハイリは仕事も学校もやめ、彼の部屋に越していた。 ジャスパーの知り合いのアイスのディーラーとも顔見知りになっていた。逮捕された日、一週間分の補充をもらうためにディーラーと会っていた。その受け渡しが終わったとき、スハイリはおとり捜査でつかまり、尿検査の結果、アイスとエクスタシーの陽性反応が出たのだ。入手しようとしていたドラッグは自分の「個人使用分」であると、スハイリは捜査官に主張した。ディーラーにはジャスパーの名前を出さないよう口止めした。 スハイリはタバコを吸い終えた。ジャスパーとイタリアンレストランで初めて会ったときのことを思い出した。彼の最初の言葉はこうだった。 「天使の存在をきみは信じる?」 そうスハイリに尋ねた。 「どうして?」 「ぼくは信じない。信心深い人間じゃないからね。だけど見たんだ、今、ぼくのテーブルを片づけているのをね」 後になって考えれば、あれは薬物使用中の人間の会話だったのだ。そうであったとしても、その思い出は胸に痛みを残した。 昨日、スハイリはジャスパーのエレベーターなしのアパートを訪ねてみたけれど、そこにはすでに海外からやってきたカップルが住んでいた。ジャスパーのことは二人とも何も知らなかった。スハイリは思いめぐらした。刑務所で何度もそうしたように。ジャスパーも逮捕されたのだろうか、それともやり過ぎて死んでしまったか、あるいは自殺したのかもしれない。 ジャスパーがロンドンに今住んでいることを、スハイリは知らない。スハイリの逮捕はジャスパーにとって、生活を改めた方がいいという合図になった。スハイリが刑務所に入ったと聞いて、イギリスにいる両親の元へ行き、麻薬更生施設に入った。父親の会社でマーケティング部長の職を得た。信仰も見つけた。スハイリのことをときどき思い出す。神の加護の見本として。信仰心のない同僚の誰彼にむかってジャスパーはこう言う。「助けが必要なとき、神様はきみの暮らしを好転させるため天使を送り出す。それが哀れな生きものたちへの、神の愛なんだよね」
ヌール・ジャンナはいつも、息子のシャフィークに中国系の友だちをつくりなさい、と言っていた。ヌールいわく、「マレー系の友だちと仲良くすると、おしゃべりに巻き込まれるの。先生がなにを言っているか、聞こえないでしょ」 シャフィークが中国系の友だちといっしょにいれば、その子たちの習慣が身につくと思っていた。ヌールにとって、それは競争心をもち、数学の才能があることを意味していた。 離婚してから、ヌール・ジャンナは昼に屋台の手伝いで働く他、収入を補足するために服を縫ってきた。夜、シャフィークが本から目を上げると、母親がミシンのパイロットランプを眼鏡に反射させて、布地の上にかがみ込んでいるのをよく目にした。 ある日、シャフィークは学校からチョコレートバーとキャンディーの入ったビニール袋を持ち帰った。ヌール・ジャンナが怒りだす前に、シャフィークはこれはクラスの子がもうすぐ誕生パーティをするからくれたものだ、と説明した。ヌール・ジャンナはその子は何系なの、パーティには呼ばれたの、と息子に尋ねた。 次の日、シャフィークは学校に行くとその子(テレンスという男の子)に、自分も誕生パーティに行けるのかと聞いた。シャフィークは恥しかったけれど、母親がそうするように言ったのでそうした。誕生日プレゼントを買ったから、きみの家にそれをもっていったら喜ぶんじゃないかと思って、と付け加えた。テレンスは家の住所を教え、その日一日じゅう、プレゼンは何かとしつこく訊いてきた。シャフィークはそれは「秘密」と答えたけれど、実は答えようがなかったのだ。 パーティの場で、ヌール・ジャンナはマレー系の者は自分と息子だけだとわかった。ヌールはバンガロールスタイルの一軒家に招かれたのは初めてのことだった。シダの鉢を吊るしたバルコニーの一角にヌールは腰をおろした。近くに座っていた女たちの内の一人が話しかけてきた。その人はテレンスの叔母だと自己紹介した。 「英語、アマリうまくないんです」とヌール・ジャンナ。 女性は困ったような顔をした。そのとき、母親が何かの危険に晒されているのを感知したかのように、シャフィークが揚げバーミセリの皿をもって現われた。 「シャフィーク、それは食べてはだめ」とヌール・ジャンナ。 女性が笑いながら言った。「だいじょうぶ、豚肉は入ってないわ。ホットドッグも鶏肉なの」 「そうじゃないんです」 ヌール・ジャンナが答える。「これを食べるとあとでお腹が痛くなるもんで。シャフィーク、あとでケーキがくるから、それまで待てるわね」 ケーキが出てきたあとで、テレンスが居間にあるベビーグランドで、ちょっとしたピアノ演奏を披露した。それからテレンスはもらったプレゼントを開け始め、プレーステーションが出てくると、興奮の声を上げた。その他のプレゼントは、鉄道セットやレゴの消防署やリモコンのレーシングカーなどだった。ヌール・ジャンナはテレンスがプレゼントを全部開けてしまう前に、シャフィークをせきたてて家を出た。ヌールは家の主人に感謝の言葉を告げ、息子が具合悪いと言った。 その夜、シャフィークは歯を磨いたあとで、ヌール・ジャンナにこう訊いた。「ママ、ぼくにピアノ買ってくれる?」 ヌール・ジャンナはミシンから目を上げて、「なんで?」 「そうすればコンサートでピアノを弾いて、お金をたくさん儲けられるでしょ。そのお金ママにあげるんだ、そうすればもう働かなくてすむから」 「ピアノを買うお金なんかないのよ」 シャフィークは唇をかんだ。「じゃあ、銃を買ってくれる?」 「どんな銃なの、セイヤン(わたしの坊や)」 「大きな水鉄砲だよ、ママがテレンスにあげた。でも青いのがいいな。青が好きなんだ」 「だめよ、シャフィーク」 「どうして?」 ヌールは息子にこう言いたかった。自分の子どもへの愛情は、おもちゃを買って表すものではない、と。自分の息子への愛とは、毎朝学校に向かって、シャフィークがうら寂しい通路を重いカバンを背中で右に左に揺すりながら歩いていく姿を見ていると、胸に哀れみの感情がわき上がるようなことなのだった。ある日、息子が突然振り向いてヌールに笑いかけたことがあって、あわてて握りしめた手を振るはめになったことを思い出した。その手は泣くのをこらえて口元を被おうとしたものだった。ヌールはそのとき、自分がシャフィークのような子どもをもつ資格のない人間だと感じていた。 でもヌールが息子に言ったのは、「あたなはわたしの息子だからよ」という言葉だった。
今朝マリアに嘘をついた。マリアのトゥドゥンを見てないと言ったのだ。わたしはマリアが面接に着ていくアンサンブルにアイロンをかけることになっていた。アンサンブルは、バジュクルンとロングスカート、それに合うクリーム色のトゥドゥンだった。 「マク、わたしのトゥドゥンは?」 マリアが身支度をしながら大声で叫ぶのを聞いた。 「トゥドゥン? どのトゥドゥン?」 わたしは訊いた。 「あたしもう、遅れそうなの、マク、あれどこやったの?」 「なんでトゥドゥンを被っていくわけ? 髪がまだ乾いてないじゃない」 マリアはアイロン室から出てくるとわたしをにらみつけた。「乾いてなかったら何だっていうのよ」そう返す。「あたしの髪なんだからね」 マリアが自分の部屋に入っていくのをわたしは追った。マリアはたんすの引き出しを順に開けると、中のスカーフをつぎつぎに宙に投げあげた。まるで失敗しかけているマジックショーみたいだった。 「何で部屋を散らかすわけ?」 「帰ってきたら片づける。あたし遅れそうなの、マク」 部屋の入口に立って、この二、三ヶ月マリアに言い続けてきたことをここでまた何と言ってやったらいいものか考えていた。その間にマリアは明るい黄色のトゥドゥンを手に取っていた。 「マリア、もう何回も面接に行ったよね。あんたと一緒に卒業した人たちは皆、もう仕事を見つけた。あんたがまだなのはとても残念、でもどうやって手助けしたらいいのか。今日だけでいいから、トゥドゥンを被るのやめたら。仕事が決まったら、着ていけばいいのよ」 「そんな風に着たり脱いだり、あたしはできない」 マリアはわたしからタクシー代を受けとると、ムッとした様子で家を出ていった。わたしは門の鍵を閉めた。窓のところでタクシーがマリアの前で止まるのを見ていた。マリアがバタンとタクシーのドアを閉めるとき、トゥドゥンがドアに挟まるのをなぜか想像した。そういう場面を見たことがあるわけではないけれど、マリアの怒りはまるで風にはためく小旗のように思えたのだ。 二、三時間後、わたしは姉の家にいて、豆もやしの根を取る手伝いをしていた。透明な根の部分が新聞紙の上で山になっていた。姉はわたしが茎のところから根をもいでいるのに気づいているようだった。 「もったいない」 姉は言った。「そこは食べられるところよ」 「気になることがあって」 そうわたしは言う。「マリアからの電話を待ってるの」 「仕事もう見つかったの?」 「まだなの」とわたし。「募集広告はみんな中国語が話せる人を求めてるのよ」 「どうすればいいんでしょうねぇ」と姉はため息をつく。「この国は中国人のものになったってことね」 姉はわたしを玄関で見送るとき、息子の勉強をマリアはみてくれるからしらと訊いてきた。週末に息子をメンダキ塾にやっているのをわたしは知っている、姉はそのことを忘れているのだ。姉がメーソートを夕飯用にくれたのでお礼を言って帰った。 家に帰るタクシーの中で、姉が息子の塾のことで自分に嘘をついたことを考え始めた。わたしも同じことをマリアにしていたけれど、つまりトゥドゥンをわたしの部屋のたんすに隠したってこと。でも神様はわたしや姉がいいことをしようとして嘘をついたと知っているはず。きっとマリアもわたしの言いたいことをわかって、面接の前になってトゥドゥンをはずそうとしたんじゃないだろうか。姉の言うことは正しかった。ここは中国人の国になったんだから、彼らのやり方に従った方がいい。 携帯が突然鳴った。手に取るとマリアの興奮した声が何か言っている。タクシーの中の音楽がやかましいので運転手に小さくしてと頼んだ。マリアは息をはずませてこう告げた。仕事が見つかった。神様に感謝しなさいよ、わたしはマリアに言った。心の中では、わたしのお祈りの甲斐があったんだわとこっそり喜んだ。 電話をおくと、タクシーの運転手はラジオのボリュームを上げた。頭のうしろにあるスピーカーから、中国語の歌が流れ出した。わたしは前屈みになって運転手にできるだけ穏やかな声でこう言った。「アペク、チャンネルを変えてもらえません。曲を違うのにしてもらえないかしら」 こう言ったのは、わたしにはマリアがトゥドゥンを被って面接を受けたことがわかっていたからだ。
改宗 ジェイソンは結婚式ですべてのことをやりたがった。奥さんになるハワの方は、花嫁と花婿が台座の上に並び座って執り行われる披露宴「ベルサンディング」に神経質になっていた。中国人の夫がマレー式の伝統衣装に身をつつんでいる姿は、皆の注目を集めるに違いない、そうハワは思った。 それなのにジェイソンはと言えば、花嫁のバジュクルン選びを二人でしていたとき、ソンケットの精緻な織り模様に感動するばかり。ハワはジェイソンにこう言った。「使われているシルクは中国人のもの、金の織り糸はインド人の、織りの技術はマレー人のものなの」 「これ僕も着ていいのかな?」 ジェイソンはうきうきした調子で訊いた。 「ムスリムの男はシルクは着ないの。綿のソンケットなら腰に巻いて使えるわ」 「それとクリスも身につけていいのかな? 腰のところに突き刺してさ。写真で見たことあるんだよ」 「ばかなこと言わないで。何のためにそんなこと。ソンケットの中で突き刺して割礼したいとでも?」 結婚を取り結ぶアカッドニカの儀式のため、ジェイソンは義理の父の手を握りながら一息で言わなければならない宣誓の言葉を覚えた。英語で構わなかったにもかかわらず、ジェイソンはマレー語でそれをやって、義理の両親となる二人にいい印象を与えたかった。 「わたくし、ジャマル・ビン・アブドゥラー(これがジェイソンのムスリム名)は、ハワ・ビテ・イスカンダルとの結婚の承諾を持参金二百ドルの現金とともに頂きます」 カーディ(イスラムの聖職者)は厳めしい顔つきの男で、ジェイソンにその言葉をもう一度言わせたが、それはドルのところをリンギットに置き換えさせるためだった。ジェイソンはハワの方を見た。前の晩宣誓の言葉を教えたのはハワだった。ハワは自分の間違いに気づいて赤くなった。ジェイソンは訂正箇所をささっと変えてしのぎ、皆も安心してにっこりした。 二、三ヶ月後、ジェイソンは上司からよその部署に移転になったと告げられた。何の説明もあらかじめなかった。曹長の地位は確保されるが、歩兵隊技術センターで訓練を受けることになると言われた。 「しかし、わたしは戦闘技術者でありますが」と、手にした書類に目をしばたたかせながら言うのが、ジェイソンには精一杯だった。上司はため息をつき、ジェイソンと目を合わせないようにしながら言った。「人事からの指令でね。でも心配することはない。今までと同じ給料がもらえるはずだ」 上司への返答を思いついたのはその夜、眠る妻の脇で横になっているときだった。「わたしのことをジャマルと呼ぶよう、皆にふれ回ったことなんかありません。わたしは今もジェイソンなんです」 でも、果たしてそうだろうか。ジャマルは妻の方に向くと、うなじにキスをした。妻はもぞもぞと動いて、ジャマルのからだの窪みに背中を沈めた。 二年後、編集室で、一人のプロデューサーが国民の日のために使うラッシュを見ていた。シンガポールの町の人々が質問を受けていた。「あなたにとって守るべきものは何ですか?」 黒縁のメガネをかけたヤッピー風の男は「仕事ですね」。ボーイスカウトの少年はためらいがちに「自分の将来かなあ」。フードコートの女性は「自分よ」。そしてモニターにジェイソンが現われる。兵服を着て緑の歩兵ベレ帽ーをかぶっている。ジェイソンはカメラを見据えて、ゆっくりと、慎重な口調で言った。「わたしは家族を守ります。美しい妻と一歳になるわたしの息子を守ります」 プロデューサーはこれこそが最も心に響く誠実な証言だと考え、編集したビデオの最後に差し込んだ。それは、兵士の目にせり上がる涙を観る者に気づかせるのに、十分効果があったに違いない。 著者の注釈: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||