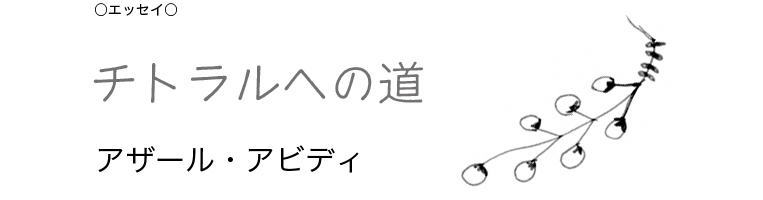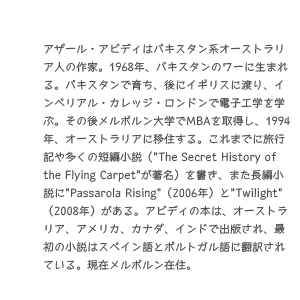|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
この三月、わたしはムルク大佐の死亡記事に出会った。生まれ故郷パキスタンの地での、九十六歳という大往生だった。インドのデへラードゥーンにある王立軍事大学で教育を受けた大佐は、亡くなったとき、かつてのイギリス領インド軍において現存する、最も地位の高い将校だった。 わたしが大佐と会ったとき、熟練した馬乗りであるムルク大佐は、アフガニスタン国境近くまで馬の背に乗って、ムジャヒディン(イスラム教のジハードに参加する戦士)の軍司令官であるアフマド・シャー・マスードを訪ねるために、どのような旅をしたかを詳細に話してくれた。途上、大佐はムジャヒディンのトラックの積み荷のせいで、かつてのソビエト軍の地雷原に道から追いやられた。馬の手綱を強く引いて止めなかったら、大佐は粉々に吹き飛ばされていたことだろう。旅に発つ前、大佐は息子に当てて書いたものを残していた。もしこの旅で死んでも悲しまないように、アフガニスタンの地に埋められることになっても悔いはないのだと。後に、ペレグリン・ホドソンがムジャヒディンと暮らしたときの思い出を綴った「Under the Sickle Moon(三日月の下で)」を送ったところ、万年筆でしたためた感謝の手紙を返してくれた。 わたしがチトラルへ行ったのは、カラシュ族について書きたかったからだ。肌の白さにくわえて金髪の彼らについては、様々なことが噂されている。ユダヤ人の末裔であるとか、アレキサンダー大王部隊の子孫だとか、ウルの生き残りではないか、などなど。わたしはカラシュの人々に会ってみたかった。(ウル:古代メソポタミアのシュメール人の都市国家) チトラルに行くには、ベシャワールを通らなければならなかった。わたしは翌朝のバスを待って、ペシャワールで一晩を過ごした。わたしはこの町が好きだった。ジャカランダの花々に、飾りたてたオートリクシャー。まだ小さかった頃、両親はペシャワールに住む伯父の家にわたしをよく連れてきてくれた。今はインターコンチネンタルホテルになっているが当時は馬の囲い地だったところの隣の、気象庁官舎に伯父一家は住んでいた。それから何年かして、ホテルをテロリストが爆破して、官舎の窓ガラスも粉々になった。でも今は、テロリストの爆破もない。当時、骨董品屋に行っては、女帝キャサリンの絵のついた1910年以降のロシアのルーブルを探したものだ。後年には、骨董品店は撤退の運命にあったアフガン戦のソビエト軍勲章まで売ろうとした。本屋では、ラジ(英国のインド統治)の間ここに住んでいたイギリス人の回顧録が売られていた。町の端にあるイギリス人墓地に「抑留」されているのは、その人たちの遺体だ。パン屋、仕立て屋、農夫、その家族の人々の墓に混じって、ビクトリア時代以来ここで死んでいったイギリス人兵士の墓もある。「部族民に撃たれる」「馬から落ちる」「アフガン戦で死ぬ」、簡単な碑文は今も昔も変わらないことを物語っている。 9.11によって引き起こされた事象を見て、それはアフガニスタンでの戦争であり、アルカイダの追跡であり、パキスタンにおけるタリバンの出現ということだが、わたしはこれから起こることの予兆を探そうとする。見つけるのはたいして難しくない。わたしを乗せたバスはマラカンド峠の急坂をくねくねと登っていく。スワット川を超え、スワット渓谷を後にし、前にそびえる山々に向かう。谷は肥沃な土地で、やわらかなカーブを描く段々畑が広がる。いつかここもタリバンと戦うパキスタン軍の戦場となるかもしれないが、十八年前でさえ、山肌のあらゆるところがスローガンでおおわれていた。反シーア派、反イスマーイール派、カシミールの解放を要求し、政治家を呪い、「アジアは我らのもの」と主張する。 チトラルへの山道は雪に阻まれていた。バスはそれ以上先に進むことができなかったが、バスの運転手は歩いていくことは可能だと言った。山を越えるには、深い雪の中から顔を出す電柱を唯一の目印に、四時間もの強行軍となる。しかしわたしは行き着けるだろうと見積もって、一人で出発した。今ではもしあのとき、土地の人が現われて山を下る手助けをしてくれなかったら、道に迷っていたことだろうと思う。 * チトラルで二、三日休んだ後、わたしはブンブレット近くにあるカラシュ族の住む谷に向けてジープで出発した。午後になって着くと、ちょうど子どもたちが学校を終えたところで、川のそばでクリケットをしていた。知り合ったカラシュの若者が近くを案内してくれた。一人の女性がカラシュ・ワインを一本わたしにくれた。夜になると、谷間に大きな月が昇り、森や野原をやわらかな月明かりで照らした。空には満天の星が輝いていた。森の向こうで川がうなり声を上げ、その向こうには雪でおおわれた山々がそびえていた。わたしたちはキノコのシチューを食べ、BBCのウルドゥー局の放送を聞いた。友だちになったカラシュ族の若者が、ここで殺された外国人の旅行者(若い男女二人)のことを話してくれた。女の子はレイプされた。殺人者たちは見つかり、女の子の父親の目の前で吊るし首になった。「神の存在を信じる者はこんなことはしない」 そうカラシュ族の友は言った。だが十年後、イスラム教徒はウォールストリートジャーナルの南アジア支局長ダニエル・パールを打ち首にした。彼らは自爆テロ犯をホテルに送り込み、病院やホテルを攻撃し、モスクに手榴弾を投げ込んだ。 この暴力の連鎖はいつ始まったのだろう、とわたしは考える。いつが元年(year zero)に当たるのか。たとえば1839年に、「外国からの干渉と党派対立を抑えるために」(ビクトリア朝時代の言い方では「体制変革」)、イギリス軍とインド軍がアフガニスタンを占領したときだろうか。それとも1757年、東インド会社がベンガルのナワーブ(大守)を打ち負かした、インドにおけるプラッシーの戦いのときだろうか。 わたしの考えでは、元年は1979年であったと思う。それはイラン国王シャーが王位を失い、イランの人々がホメイニにだまされて革命に身を投じ、自らを滅ぼすことになった年だ。それはパキスタンの首相ズルフィカル・アリ・ブットが、かつての参謀でその後宿敵となったジア将軍によって処刑された年だ。そしてその年はまた、ロシアの武装部隊がアフガニスタンにやって来た年でもある。ドミノ倒しが起きた。まずイランに、次にパキスタンに、そしてアフガニスタンに。わたしの目からは、チリにおいてピノチェトがしたように、イランのシャーが革命を押さえ込んでいたら、今日の歴史はずっと変わっていただろうと思える。シャーはアメリカによって完全武装され、ソビエトは自らアフガニスタンに入ろうとはしなかっただろう。そしてもしソビエトが来なかったら、アフガニスタンにはタリバンも、アルカイダも、テロリストの爆撃もなかっただろう。でもこれはわたしの勝手なばかげた想像にすぎない。 おそらく暴力と破壊は1947年のパキスタン独立のときに始まっていた。わたしの育ったパキスタンは、非宗教的な、自由で進歩的な国だった。確かに西洋の民主主義のような非宗教、自由主義と同じものではないけれど、今よりは進んでいた。(カラチにいるわたしの伯父の一人は、レストランでシャトーブリアンを注文し、上等のボルドーを流し込み、カンカン娘たちを観にキャバレーに行った時代のことをわたしに話したものだ。) いったいあれから何が起きたんだろう。今思うに、わたしたちが見ていたものは、多分間違いだったのだ。ただの見せかけの現実だったのだ。昔ながらの召使いとご主人の社会、昔ながらの社会秩序、家長制、そしていつもそこにある宗教的緊張をただ隠していただけなのだ。イギリスが去った後釜には、上流、中流クラスの者たちが居座っただけ、結局何も変わらなかったということだ。 わたしがムルク大佐に会いに行ったのは、彼は作家でもあったからだ。大佐はここ数年に書いたものをわたしに見せてくれた。インディラ・ガンディーへの公開書簡、野生動物保護についての手紙、アフガニスタンへの旅を綴った8ページの紀行文など。わたしもこれから書こうとしていることについて話した。 「どうして欧米諸国は我が国の女たちがヴェールをまとったり、男たちがモスクに行くことを恐れるんだろう」 そう彼は聞いた。それはわたしたちがよそ者だからではないですか、そう言うべきだったかもしれないが、わたしにはよくわからなかった。後で思えば、彼には答えがわかっていたのだろう。1940年代に彼は、イギリスに対してジハードを遂行していた狂信者、ファキル・イピと戦うため、ワジリスタンに送られた。狂信者をテロリストという言葉に変えれてみれば、今日との類似性は明らかだ。ムルク大佐のような人が体制を維持し、ファキル・イピのような人がそれを覆そうと戦う。無人偵察機がブーンと飛びまわり、カラシニコフが複葉機とマスケット銃に置き換えられても、それ以外はまったく同じだ。彼らの名前をカヤニ将軍とバイトゥッラー・マフスードに置き換えれば、類似はここでも明白になる。(カヤニ将軍は現在のパキスタン軍陸軍司令官。バイトゥッラー・マフスードはパキスタン・ターリバーン運動の指導者の一人。2009年、アメリカの無人偵察機のミサイルにより爆死。) 紀元前330年にアレキサンダー大王がアフガニスタンを暴れまわり、ジンギス・カンが1221年にそれを荒廃させた。ティムール(イングランドの作家マーローが描いたタンバレン大王)が、ビクトリア女王より500年前にそこで怒りをかっていた。その後、ブレジネフの番が来て、トニー・ブレアとブッシュなどが続く。おそらく元年は存在しない。 そろそろ出発の時間が来た。ムルク大佐にチトラルから出るにはどうすればいいか訊いた。雪に閉じ込められたロワリ峠を歩いて戻るのは気が進まなかった。フォッカー機のフライトがチトラルから毎日出ていて、ムルク大佐の口添えでそれに乗れないだろうかと願っていた。大佐が言うにはそのフライトは全く当てにならない、とのこと。彼の考えでは、一番いいのはアフガニスタンをまわって戻ることだと言う。地元の人間は一年を通してそのルートを使っている、ということでわたしもそれに従うことにした。 * アフガニスタンへの道は未舗装で、国境にはファルシ語(ペルシャ語)で「アフガニスタン・イスラム共和国へようこそ」と書かれたブリキのプレートが掛かった遮断門があった。前方の道は、溶けた雪がザーザーと流れ込み浸水していた。そこを超え、バリコットという国境の町を通り抜けた。リンゴ、アプリコット、プラムローズの果樹園が厚い土壁の向こうに見えた。二匹のラクダが主人を待っていた。赤い服を着た女たちが畑を耕していた。 のどかな町だったけれど、傷跡が散見された。道の脇にソビエト軍のトラックが横たわり、フロントガラスには銃弾の跡がいくつもあった。座席はなかった。ぺしゃんこになったタイヤのまわりは背の高い草に取り囲まれていたが、扉に描かれた赤い星はまだ消えずにあった。ソビエト人は去ったけれど、その遺物が誰の目にも見えるところに残されていた。町の中心部には瓦礫の山があり、殉教者の広場と呼ばれていた。町はずれにはここで死んだ名もなき人々の墓があった。大きな墓のそばに小さな墓もあり、それは子どもたちのものだった。 わたしたちはイスラミック・ホテルという名の茶店に昼食で立ち寄った。外にある朽ちたロシア軍戦車の小塔に、店名が白いペンキで描かれていた。乗客たち(毛深いの、あごひげを生やしたの、目つきの鋭いの、といった男たちの群れ)は古びたバスから降りて、流水で手を洗い、白い部屋に据えられた高い台座にすわった。ロシア式卓上湯沸かし器サモワールが中央に置かれていた。ジャラーラーバードから来たという老人がわたしの前であぐらをかいてすわり、ピラフを他の者と同様、手で食べていた。 わたしたちのバスはでこぼこの荒れた道を走った。やっとのことでバスはパキスタン国境に向けて曲がり、舗装された道が始まり、わたしは救われた気分だった。トラ・ボラ山脈の険しい稜線の手前に大きな平原が広がり、流れる川は水銀の帯のように輝いていた。橋を渡るとき、難民の一群が反対方向に向かっていくのを見た。ペシャワール郊外にある難民キャンプから自分たちの故郷に戻る人々だった。小型トラックやトラクターには、家族全員が積み込まれ、女たちは赤ん坊や小さな子をしっかりと抱き、マットレスやベッド用木枠が荷台に縛りつけられ、やかんや鍋がガチャガチャとぶつかり、メーメー鳴く山羊の群れが通った後には砂ぼこりがたっていた。移動し続ける人々。見るに値するものだった。九年後に、アメリカのB52がこの山岳地帯を爆破することになろうとは。わたしにはそのとき、黄金に輝く日没の中で、それを想像することはとてもできなかった。 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||