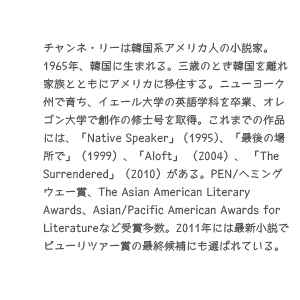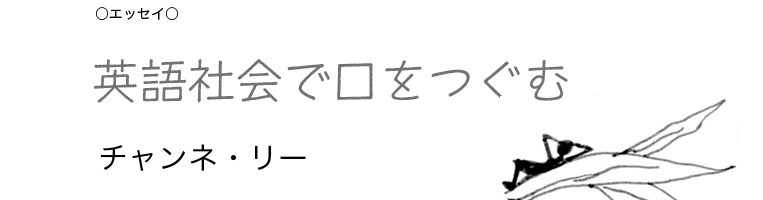
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
合法的に居住し、町の一員である人々に対する排除の思想は、まったく許しがたいことだ。しかし韓国系移民の家族で育った者として、わたしは慣れない価格表示や言葉に圧倒される日々を経験してきた。英語だけの世界ではよそ者だった母親といるときはなおのことそうだった。わたしの家族がアメリカに住み始めた最初の何年かは、母はごく基本的な英語しか話せなかったし、外に出かけるたびに様々な困難に遭遇していた。 わたしの家族は1970年代の初頭、ニューヨーク州ニューロシェルに住んでいた。地元商店の多くは移民の子孫が経営していて、何世代か前にニューヨークの中心街から郊外へと移ってきた者たちだった。メインストリートやノースアベニューに誇らしげに点在しているのは、イタリア人のペストリーやチーズの店、ユダヤ人のテイラーやクリーニング店、ポーランド人やドイツ人の肉屋やパン屋だった。母は日常の買い出しが、父が同伴できる週末まで待てないときは、わたしが学校から帰ってきて一緒に行けるのを待っていた。 わたしはそのとき六歳か七歳にしかなっていなかったけれど、母親は妹を連れての買い出しに、わたしもついてくるよう言い張った。その言いつけがわたしは嫌だった。ひとつには午後友だちとキャッチボールができなくなるからだったが、もうひとつは、買い物に行けば不恰好な様を人目にさらすことがわかっていたからだ。それに母親に代わって店の人と話さなければならなかった。 わたし自身、アメリカに来て英語を身につけているところだったが、子どもは新しい言葉に慣れるのが早いので、飲み込みは早かった。幼稚園時代はほとんど黙って過ごした。先生の鼻にかかった高い声を聞いても意味がわからず、子どもたちのキーキーいう泣き声や叫び声ばかりが耳についた。でもすぐに、ほんの数ヶ月の間に、わたしはへたくそな役者か物まね芸人のように、学校の先生、父の友人たち、ときに父親までも物まねの種にして、父を大笑いさせていた。母は父のしゃべりの物まねをするわたしを叱った。母親の英語のしゃべりを真似してみせたときは、お尻をぴしゃりと打たれるはめになった。 母にとって英語は、何も面白いところはなく、面倒の原因であり、大恥の種であり、ときにかなり傷つきもした。英語を読むことについては、韓国の大学で学んでそれなりの知識もあったけれど、英語での会話は経験が全くなかった。それでアメリカでは、母は英語の単語帳や慣用句集を手元に置き、わたしたち子どもと一緒にテレビを見ていた。そしていつも律儀に、線画の人物イラストと穴埋め文が載っている英語のポケット練習帳を携帯していた。 でもそれが母親の英語の上達に役立っているようには見えなかった。子どもたちの世話で家にいることが多く、いろいろな単語や表現を実際に試してみる機会があまりなかったのだ。英語で話すとき、たとえば郵便局の窓口で、用意してあった言葉はうまく流れ出ず、固まってしまい、ときに何もかもに破綻をきたすことになる。 ある日、いつも以上にひどい目にあった。わたしたちは父が母のために買ったフォード・カントリー・スクワイアの新車で町に出ていった。それは外洋船のように長くて速い、大型のステーションワゴンだった。その週末のお客を迎えるために、特別の肉を買おうとしていた。母は韓国伝統のスープに必要な新鮮なオックステールを、ある肉屋が扱っていると聞いたのだ。 その肉屋の店内には入ったことがなかったが、母は丸ごとのハムや王冠型ローストや手作りの鎖状ソーセージなどがいつも並ぶウィンドウの前でよくたたずんでいたものだ。母はその品々を感嘆しながらじっと見つめ、妹とわたしも同様だったが、一転して、物欲しげに抵抗するわたしたちを店の前から追いたて、フィナスト・スーパーでパッケージされたものを買うのだった。そこなら母は緊張することなくゆったりと肉を眺め、値段もすぐにわかった。それに当然のことながら、店の人と口をきかなくてもいい。 でもその日、母は心を決めた。肉屋の中は混雑していて、ドアを開けて入るとチリチリンと鈴が鳴った。誰もわたしたちに気づかないようだった。わたしたちは少しの間待っていたが、後から来た人がすでに応対を受けていた。すると年配の女の人が母を軽くつついて、小さな券を振った。わたしたちはその券をもらってなかった。それからまた辛抱強く順番を待ち、やっとガラスケースの向こう側で立ち働く太った男たちの中の一人が、わたしたちの番号を呼んだ。 母はわたしたち子どもを前に押し出し、ケースの中を探し始めたがオックステールはどこにもなかった。店の男は太い腕を胸の前で組んで、強い調子で言った。「はいはい、奥さんの番だよ、ナンにすんの?」 その声が母を怖じ気づかせた。オックステールを意味する朝鮮語「ソッゴリ」をわけなく口走っていた。 肉屋の店員は、酸っぱいものでも口に入れられたような顔をすると、電光掲示板を振り返り、次の番号を呼んだ。 わたしがそれに気づくより早く、母はわたしと妹を店の外に追いやり、止めてあった車に戻ろうとした。車は混雑のため、路上に二重駐車してあった。母は逆上していて、恐怖と心痛で震えんばかり、今にも泣き叫びそうに見えた。 母は車の中に逃げ込みたかったが、うちの車に邪魔されて出られない隣の車の運転手が車を出したがっていた。母はわたしと妹を追い払った。まだ運転免許をとって間もない母は、激しくペダルを踏み込んだが、あまりに慌てていて、エンジンがかからない。隣の車の運転手がクラクションを鳴らすと、他の車も同調し、すぐに通りじゅうがわたしたちに金切り声をあげているような状態になった。 それから何年かのうちに、母は英語に徐々になじんでいった。朝鮮語を話す母は、激しく、厳格で、ユーモアがあり、皮肉屋でもあったが、英語の場合は、それが少し弱まった。母の英語が流暢でなかったとしても、自分がどういう人間かを誰にでも、特にわたしに対して、はっきりと示すことで大きな自信を得ていた。 五年前に母ががんで死んで、埋葬の後何ヶ月かして、父の家の車庫のそばで母のセダンを洗っていた。母のものを手入れするのがわたしは好きだった。母が近くにいるような気持ちになった。助手席の小物入れを掃除していると、英語のポケット練習帳を見つけた。あのばかばかしいイラストが描かれたやつだ。もう二十年近く、目にしたことがなかった。黄ばんだページはもろくボロボロだった。母はその本を白い紙でおおっていた。中身を保護するためだったのか、それとも隠すためだったのか。 わたしは母がパリセーズパークの新ブロードアベニューでの買いものを、きっと楽しんだだろうと思う。と同時に、朝鮮語だけの看板に文句を言っている人たちのことも理解したんじゃないか、そうも思いたい。 その人たちがもし、母が英語の練習帳で勉強しているところや店で言葉をなくしている場面を見たら、どうしただろうか。彼らは母に優しくうなずいただろうか、何か親切な言葉をかけたりしただろうか。 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||