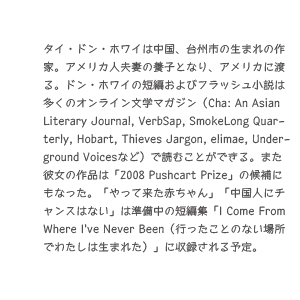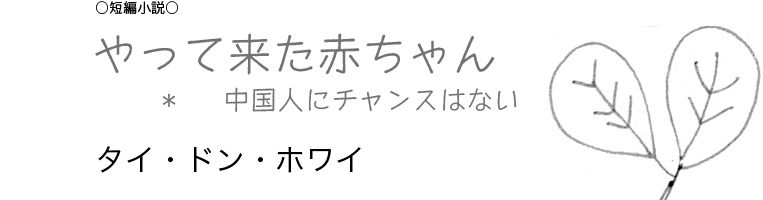
|
わたしの注意を引いたのは、シンシアのムッとするようなベビーパウダーの匂いでもなく、まっすぐに突ったったヤマアラシのような髪の毛でも栄養不良気味のからだでもない。シンシアがコワンチョウ(広州)の白鳥ホテルでもらったオモチャの人形だった。アメリカに向けて、シンシアとその養母(つまりレイチェル)が飛びたつ前に、滞在していたホテルでもらったものだ。 それは「お家に帰るバービー」(Going Home Barbie)と呼ばれる。わたしも同じものを箱入りのまま持ってるので知っている。レイチェルがまるで珍しいアートみたいに扱っていることから見ても、うちでもずっとそのまま取っておかれるんだろう。箱の中には二つの人形が入っている。一つはバービー、白い肌にブロンド、ホリデーインのラウンジで夜遊び中のバツイチ女のようなドレスを着ている。もう一つはバービーの赤ん坊、中国人というよりアステカ族みたいに見える。このバービー、入れられているボール紙の箱の家と柵に対して、あまりにデカイ。それにバービー母は若すぎる。二十歳になるかならないかに見える。中国から赤ん坊を連れ帰る養母というより、マヤの子を誘拐したステロイド漬けのスウェーデン人子守りのよう。 もっと事実に沿って描写するならば(わたしのママとわたしが最初にケネディ空港ターミナルから家に向かったときの写真みたいであるなら)、きっとこんな風。バービーは中年で、睡眠不足気味で、もっと太ってて。ナンジン(南京)で15ドルで買ったベビーカーを押して、その中では赤ん坊がおびえて泣き叫び、手がつけられない状態。バービーはしわになっただぶだぶの服を着て、わたしの最初にして最後の記憶でいえば、口にタバコをくわえているはず。 この一対のプラスティック人形は、存在価値があるんだろうとは思う。この女性(子どもの養母)が、一部始終をいつか養女に説明するときのために。捨て子とその発見、児童養護施設、お役所的縁組み、行ったり来たりの終わらない旅の数々。 でもわたしはもう13歳、人形遊びをするほど子どもじゃないし、他のことが見えてくる。バービーに養父の人形がないとしたら、養母はレズビアンだと見られるかもしれない。「あの女と、コトを最後までやり遂げたいと思う男が、一人もいなかったんだろうね」。誰にも聞かれてないと知れば、こう言って人は笑うかもしれない。もし養父がいるとするなら、そいつは「役立たず」だったんじゃないか、と言うだろう。あるいは、養父は普通の男たちがやってることを楽しめないやつだったのかも、と。 養母は子どもの目の前で、いろんなことを聞かれているはずだ。たとえば、「なぜアメリカ人の子を養子にしなかったの?」とか「この子はいくらだった?」とか「自分の生んだ子のように愛せると思う?」とか。 で、シンシアみたいな子はどうなる? 中流家庭の子が行く学校に行って、そこでは白人の子がほとんどで、彼らは「特別」であることを居心地悪く感じてる。先生たちは中国の新年を赤い祝い封筒と月餅で祝おうとするかもしれない。地理の授業では、中国人が濡れないための傘や人を追い散らすための火薬を発明したことを話すかもしれない。木曜日には、カフェテリアではタオ将軍のチキンが用意され、中国人の子どもがチキンでなくホットドッグを頼めば、人目を惹いてしまうかもしれない。教室には仏陀の小さな象さえ置いてあったりして。それがキリストのような神ではなく、リンカーンみたいなヒトであったことが強調されるとしても。 この人形についてあれこれ考えるうちに引き出されたことに、わたしは打ちのめされた。養母はついに自分が妊娠したことに気づいて、赤ん坊を養護施設に返そうとするんじゃないか。赤ん坊は、まだ幼いのにすでに口がきけて、見知らぬ女を「ママ」と呼ぶのを拒否して、名前で呼ぼうとするかもしれない。そういうことが起きたときは、人形の箱にある句読点を修正しなくてはならない。 「お家に帰る、バービー?」(Going Home, Barbie?)そのように書いたほうがいい。 「こちらがリン夫人よ」と養母が言う。「リンさん、これが娘のリーアです」 リン夫人はわたし同様、針金ように細い。髪も、わたしと同様、濃い茶色、ほぼ真っ黒。十三歳のわたしの鼻はアジア系の女の子にしてはかなり高い方なのだけど、この中年の女の人の鼻も同じように高い。 「ニーハオ」 にこりともせずにその人は言う。 「ハーイ」 わたしは返す。 リン夫人のことはママから聞いていた。リン夫人の夫は、妻が英語の読み書きをボランティアから習うことにいかに反対しているか、夫とやっているアイスクリームのチェーンストアを離れられる時間がいかに少ないか、というようなことを。 今日、わたしはリン夫人に初めて会ったけど、同じ血がわたしたち二人に流れていることは疑う余地がないと感じた。 「今日はここで勉強をするから、あなたのほうはお仕舞いにしてね」 そうママが言う。 わたしはオートミールクッキーを作り終えて、ラックの上で冷ましているところだった。 「かまわないよ」とわたし。 「ちょっと車まで行って教科書を取ってくるわ」そうママは言い、「郵便も見てくるわ、ちょっと待っててね」 わたしにはわかっている。ちょっと待ってて、というのは、ガレージへタバコを吸いに行くということ、ママはわたしが知らないと思っているようだけど。 扉がしまって、リン夫人はキッチンのテーブルにすわり、わたしは食器洗い機をつかう。 「中国語は話せるの?」 リン夫人が聞いてくる。 「少しなら」 そうわたしは言ったけど、ほとんどウソと言っていい。わたしが「母語」で言えるのは、こんにちは、さようなら、ありがとう、くらい。 「わたしたちは共通点が多いわね」とリン夫人。 ガラスの計量カップがわたしの手から落ちて、セラミックタイルの床で砕ける。「ったく」とわたしは大声を出す。 リン夫人は、わたしが冷蔵庫の脇にある箒を取りにいくのを座って見ている。「手を切らないようにね」とリン夫人。 「共通点が多いって、どういう意味ですか?」 わたしは聞く。 リン夫人はやっと笑顔を見せる。でも歯を見せて笑ってはいない。「アナタは中国語少し話せて、ワタシは英語が少し話せる」 わたしがちりとりを手に取ると、リン夫人はこう聞いた。「中国のどこ?」 「タイジョウ(泰州)だけど」とわたし。「ああ、ジャンスー(江蘇)のね」 リン夫人はそう言うとちょっと間をおいてから、「アメリカに来てラッキーだったわね。ジャンスーにいたら、もう工場で働かされていたかもね」 「あたし、捨て子なんです」とわたし。 「知ってるわ」 わたしは流しの下のゴミ箱に割れたガラスを投げ入れる。「子どもはいるんですか?」 わたしは聞く。 「息子が二人」とリン夫人。「一人はMITに行ってて、一人は高校生」 「女の子は?」 「いないの」 「いたらよかったと思います?」 「何かを願うということはしないの。願うっていうのは、失望するってことだから」とリン夫人。 その言葉をわたしはちょっと考えてみる。それから「クッキー食べます?」と聞く。 「クッキーがあるなら、クッキーをいただきます」 まだ温かいクッキーをお皿に少し入れる。「オートミールのクッキーです」 そう言って、リン夫人の向かい側に腰を下ろす。 リン夫人はテーブルの上のナプキン立てに手を伸ばし、ナプキンを広げ、クッキーをその真ん中に置く。そして小さく砕いて、口にかけらを入れる。 「おいしいわ」とリン夫人。 「黒いのはレーズンです。焦げたんじゃなくって」 わたしはリン夫人にそう言う。 リン夫人がちょっと笑う。ちょっとの間、わたしとリン夫人はだまってクッキーを食べる。リン夫人が聞く。「で、学校ではナニ勉強してる?」 「普通の学科ですけど。数学、社会、英語、、、」 わたしが言う。 「それも、ワタシと同じ」 リン夫人はにっこりする。 「そんなとこですね」 「歴史はやるの?」 わたしは頷く。「いまはゴールドラッシュをやってます」 「ゴールドラッシュって何?」とリン夫人。 「1849年に、カリフォルニアに、世界中から人が富を得ようと集まって来たんです」とわたし。 「まあ」とリン夫人。 「学校の先生は『中国人にチャンスはない』という言い方はここから来てると言ってます」 「それどういう意味なの?」 わたしはテーブル越しに顔を近づけて、「ええっと」と始める。「中国人っていうのは、とても遠くからやってきたんで、そこに着くのが一番遅かったの。だから中国人は何も見つけられないと皆思ったわけ」 「でも見つけたのね」 「中国人は皆で一丸となって、チームで取り組んだの、それで金を見つけた」 「中国人のチャンス、ね」とリン夫人。 わたしは頷く。 「あなた、いい先生だわ」リン夫人は言う。 ポーチでママの音が聞こえたので、リン夫人とのひとときもこれで終わりと知る。パパ(養父)がここにいたらこういう場合、こんな風にわたしをけしかけるかも。「やるだけやってみろ」とか「一発狙っていけ」とか。 「あなたは、あたしのおかあさんなの?」 わたしは尋ねる。 リン夫人はちょっとの間じっとわたしをみつめる。最初、わたしの言っている意味がわからないのかと思った。ごめんなさい、そうわたしは言おうとする。バカげた質問でした。でもリン夫人はわたしの想いをさえぎって言う。「アナタのお母さんは、」 そのときキッチンの扉が開いた。 「、、、ちょうどいらしたわ」 ママがキッチンに入ってきた。ニコチンとミント粒の匂いを漂わせている。悪くない匂いだ。ママは英語の文法の本をあいた椅子の上に置く。 「じゃあ、はじめていいかしら」 ママがリン夫人に聞く。 「はい、大丈夫です」 リン夫人が答える。 「ティーポットをお願いね」 ママがわたしに言う。もう行く時間よ、というママなりの言い方。 「計量カップをこわしちゃった」 わたしはママに言う。 「でもすっかりきれいに片づけてあるわ」 リン夫人が言う。 リビングルームでソファに寝ころんで『大いなる遺産』のページを繰っていると、二人の話す声が聞こえてくる。わたしの養母であるママとあの女の人と、わたしは一つの世界を分け合っている。 「昨日わかっていたら、わたしは着いていたはずだ」 ママが言う。 リン夫人がほぼ完璧にその文章を繰り返す。 「もし彼の列車が遅れなかったら、彼は時間に間に合ったはずだ」 わたしはディケンズの本をよこに置いて、背すじを伸ばしてすわり直す。くちびるが動きだすが、わたしの声は煙のように音が出ない、リン夫人の声がわたしのどこか深いところから出てくるように感じる。 「もし状況が違っていれば、二人は一緒に到着したはずだ」 |
||||