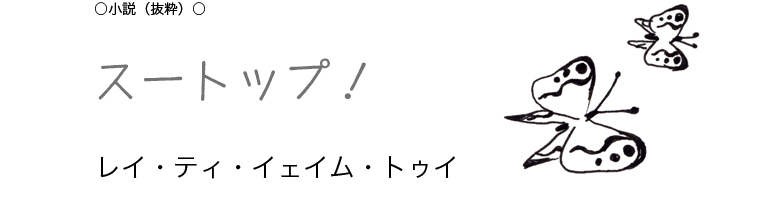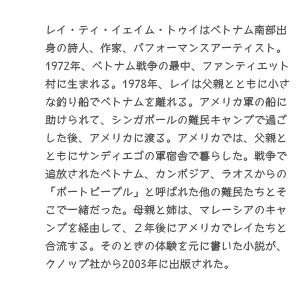黄色い家並みがつづくリンダ・ヴィスタは、わたしの家族が最後に流れ着いた場所。リンダ・ヴィスタに来る前は、ノーマルハイツの三十丁目通りとアダムス通りに面したグリーン・アパートに住んでいた。グリーン・アパートの前は、東サンディエゴの四十九丁目通りとオレンジ通りに面したレッド・アパートに住んでいた。レッド・アパートに住む前は、今のように家族では暮らしていなかった。別々の場所で、いっしょに暮らせるのを待っていた。マーがベトナムの海辺でたたずんでいるとき、バー*とわたしはカリフォルニアで、同じ舟で逃げてきた四人の男たちといっしょだった。
この四人の男たちとは、血ではなく水つながりの仲だった。わたしたち六人は、南シナ海をともに渡ってきたのだ。逃げてきた村の人たちといっしょに、海を漂流した。最初は小さな漁船で、次にアメリカ海軍の船に乗って。シンガポールの難民キャンプでは、この六人で隣りあって寝起きしていた。書類が整い、スタンプが押されると、身のまわりのわずかな荷物を抱えて、いっしょにキャンプを離れた。わたしたちはいっしょに、いくつもの空港の回転ドアを通りぬけ、飛行機を乗り継いだ。そして太平洋の空高く、舞い上がった。互いに手を握り合い、雲の中を、霧の中を、時差をぬけて空を渡った。着いた場所で、わたしたちは霧雨の中を歩き、いっしょに車に乗り込んだ。見慣れない明るい通りをとおって、暗い家の前で降ろされると、降りそそぐ雨の中、不揃いなステップを五段上って家のドアを押した。
1978年、サンディエゴに住む年配の夫婦が、教会の団体を通じて、シンガポールの難民キャンプにいる五人の若者と六歳の女の子を保護することを決意した。ラッセル氏は退役した海軍軍人だった。太平洋地域に従軍していたことがあり、そこの人々がからだが小さくて親切だったことを覚えていた。ベトナムからのボートピープルの話を聞いたとき、ラッセル氏は何日も眠れない夜を過ごした。天井を見つめ、大海に浮かぶ小さな舟の中に横たわる、名前も顔も知らない人々のことを考えつづけた。ラッセル氏の心の中で、ベトナムのボートピープルの姿は、沖縄やサモア、さらにはハワイの人々との思い出とひとつになった。
ある夜、ラッセル氏が眠りにつくと、夢の中で、舟が波の上に降りたつ海鳥になった。水の中から手が現われ、海鳥の一群をすくった。それはラッセル氏の手ではなかった。神の手でもなかった。
夢の中で海鳥たちは、まばゆいばかりの青空いっっぱいに散っていった。が、海鳥たちはふたたび一つ方向をとり、夢の視界の外にある、待っている自分のところに向かっているのだと気づいた。
最初の計画では、わたしの父さん、四人のおじさん、わたし、この六人がラッセル夫妻と住むことになっていた。ところが書類が処理されている間に、ラッセル氏は死んでしまった。さてわたしたちはどこに送られるべきなのか。東京? シドニー? それともミネアポリス?
ラッセル氏は妻に夢で見た海鳥の話をしていた。夫が死んだ後、ラッセル夫人はその夢の話を思い出し、考えた結果、わたしたちを引き取って、息子のメルヴィンの家に招き入れることを決めた。
バーが言うには、わたしたちがメルの家にたった一年しかいられなかったのは、誰の責任でもない、と。
空港でメルが近づいてくるとき、チャリチャリという小さな音が聞こえた。金銀の鍵をいっぱいつけた輪っかを腰のベルトからぶら下げていたのだ。歩くたび、メルの腰で鍵が揺れ、チャリチャリと音がした。鍵はメルが最近手にしたものだった。メルは背が高くひょろりとしていたのに対して、鍵はずっしりとかさがあってさも重要そうだった。メルは鍵の束をつかむと、ポケットに押し込んだ。これでチャリチャリは治まった。メルはみんなの手をとって(わたしのも)握手し、緊張気味に笑顔を見せながら「アメリカへようこそ」と言った。
メルが手をふって指さすのでそっちに目をやると、ビーチに横たわる男女のポスターがあった。カップルは大きなヤシの木の間に、ストライプのタオルを広げ、太陽を浴びていた。ヤシの木の上に大きな文字があり、その字は燃え上がっているみたいだった。「太陽の街、サンディエゴ」 男の方は腹這いになり、両腕の間に顔を埋めていた。女は仰向けになって、日焼けした脚を片方だけ曲げて立てていた。そのひざと腿とふくらはぎがつくる三角のフレームの向こうに、静かに眠る海原が見えた。わたしの母さんは、ああいうところにいるんだ。そう父さんが言っていた。
メルとラッセル夫人は家につくと、わたしたちを部屋に案内し、そこでいっしょに寝るように伝え、お休みと言って静かにドアを閉めた。二人は廊下で立ち話をはじめ、それはわたしたちの耳によく聞こえた。何を言っているのか一言も理解できなかったけれど、その声の調子にわたしたちはすくんだ。言葉はわからなくても、こんな風に言ってるのだなと感じた。
「ボート一艘(そう)分の人を相続しちゃった気分だよ。だって、ずっと一人でここに住んできたのに、今は見ず知らずの男を五人も抱え込み、それにあの小さな女の子だろ」
「でもねぇ、あなたのお父さんがここに引きとることを望んだのよ」
「たしかにアメリカのここにね、でもオレとじゃないだろう」
「うまくいっていたと思ってたのに。お父さんさえいてくれれば」
ラッセル夫人は泣き出した。
「ごめん、母さん。悪かったよ」
二人が廊下を歩いて、居間の方に向かう足音を耳にした。
部屋の中で、わたしたち六人はだまって座っていた。バーはドアに背をあずけていた。四人のおじさんは二つある二段ベッドにそれぞれ座り、わたしはダブルベッドの上で、ひざを抱えていた。
おじさんの内の一人が大きなため息をついて、ベッドに横になった。おじさんはまだ靴をはいたままだったけれど、足をベッドの端から出していたので、ベッドカバーを汚す心配はなかった。
バーが立ち上がって、わたしたちにこう言った。メルはアメリカへの航空券を買ってくれたんだ。メルはいい人だ、とも言った。わたしと四人のおじさんたちは、その話をぼんやりと聞いていた。そしてうなずいた。メルは空港の入国ゲートで、わたしたちが入国しても大丈夫と話してくれたんだ、さらにバーが言う。「メルがいなかったら、わたしらは送り返されていただろうな」
わたしたちはそれぞれ、海の上で漂っていたあのときのことを、夜また夜のことを思っていた。何一つ見えない、どことも知れぬ暗闇の中を、前に後ろに揺られて浮いていたときのことを。通りがかる船が、わたしたちのボートに近寄ろうとしなかったことを覚えている。船上の人たちは、双眼鏡を手にデッキから身を乗り出し、こちらを見ていたけれど、見なかったことにしてどこかへ去っていった。もしあのメルという男が、わたしたちがあそこに(潮風に吹きつけられる日々へと)戻らなくていいようにしてくれたなら、感謝するしかないではないか。感謝して余りある。廊下から聞こえてきた声くらいのことで、なんでそんなに悪くとらなくちゃならない。
バーはわたしたちは少しがまんが必要だと言った。
おじさん二人がうなずいた。もう一人は目を閉じた。残りの一人はベッドに横になり、壁の方に顔を向けた。わたしはひざを抱え込み、はだしの足を見つめた。足には砂も塩もついてなくて、きれいだった。
バーはこう言った。メルのことをを考えるときはいつも、あの人がわたしたちに道を開いてくれたことを忘れちゃいけない。忘れちゃいけないのは、そのことだ。
わたしたちについて、メルが知らないこと、覚えていないだろうことはあった。わたしたちはメルが導き入れてくれたドアを、何の躊躇もなく通り抜けたわけではない。六人で身を寄せ合って、どこにも身寄りのない者がするように、おずおずとゲートを出てきたことを、あの人は覚えていないはずだ。アメリカでの最初の夜、メルが母親と居間のソファで抱き合って、父親の死を嘆き悲しんでいたとき、バーも家の前の芝生で、迷い犬のように月を見つめて泣いていたことを知らないはずだ。バーは部屋の窓から抜け出して、ヤシの木の下で長いこと座っていた。
***
メルの腰のところでチャリチャリ音をたてる、輪っかにつけられた金銀の鍵、あれは補修が必要なマンションや集合住宅、テラスハウスのものだった。メルは道具扱いが下手で、小さな頃に自転車事故にあったことから、恐がりでもあり、そのことに(中でも父親からの叱咤激励に)ずいぶんと苦しんできた。メルはわたしたちを家に住まわす代わりに、バーと四人のおじさんを、家の修繕やペンキ塗りの要員として雇うことにした。これは「死に際の遺言」だからという母親の頼みを、メルが不承不承受け入れてやったことである。おかげであの人は、ぐらぐらするはしごに上ったり、天井裏の暗がりを這って、修繕箇所を探す必要がなくなった。
所有するどこかの家の白壁が、黒ずんだり、住人の手垢などできたなくなっていたら、メルはバーとおじさん四人に「壁を塗り替えてくれ」「新品みたいにしてくれ」「元の白壁に戻してくれ」などと指示をして、そこに送り込んだ。
バーとおじさんたちは、ほとんど毎日のように働いた。がたいの小さなベトナム人の男が五人、空き部屋ではしごに上り、白壁を白く塗り替えていた。
「こんなに白くするのは不吉じゃないか」
「ペンキとペンキの間に、人を埋めるんだ」
「最初の壁と三番目のペンキの間だな」
「死人がそこに滑りこんでさ、それで」
「壁の中に押しこまれて、それで」
「白い膜でおおってしまうんだ」
「葬式のために白く飾りつけてんだよ」
***
みんなの中で、バーが一番英語に通じていた。戦争の間、アメリカ兵から聞きかじっていたからだ。おじさんたちはバーに、どうしてそんなに壁を白くしなくちゃならないのか、メルに訊いてくれと頼んだ。バーは「そんなに」という言葉を知らなかったので、こう訊いた。
「なぜ、白くする?」
メルいわく、「きれいに見えるから」
会話はここで終わる。
バーがメルの返事を伝えると、おじさんたちはぽかんとした顔でバーを見つめた。
「なんだそれ、よくわからないな」と言って、白壁に目をやった。
おじさんたちは、ハケとローラーとぼろ布を取り上げて、また仕事に戻った。
バーはメルの言い方を何とか説明しようとした。メルの声は、寝ている人の顔にいきなりライトを当てるような、そんな調子だった。言葉で説明するのではなく、人を驚かせるような口調で何かを伝えようとするような。わたしのバーは、そんな言い方はしない。バーの声は、井戸の底から聞こえてくるカエルの歌みたいに、深く響く。バーの声は、アシの茎を通り抜ける水の音みたいに、悲しげだ。そしてその悲しげな声は、いつも問いを発し、自分でそれに答える。呼びかけては、戻ってくる。バーの心の中の、潮の満ち引きのように。その声を聞いていると、バーの頭の中にある、さまよう舟の姿が見えることがある。どこかへ逃れようとする人々をいっぱいに積んだ、いくつもの舟だ。
***
メルは何年か前から、教会に行かなくなっていたが、父親が死んでから、また行くようになっていた。日曜日の朝には両親の家に行って、母親を拾って教会に行っていた。メルの家に住むようになって最初のひと月、バーとおじさん四人、それにわたしはその車に乗り込んで、いっしょに教会に行った。でも何回か行ったあとに、おじさんたちの誰かが説教の間に寝てしまったり、ぼんやりと床を見て、手や指についたペンキをはがしているのがわかり、わたしたちは家に残ることになった。
教会が終わると、メルは母親がわたしたちに会えるよう連れ帰った。
みんなで居間のコーヒーテーブルのそばに集まって、メルは隅の背もたれ椅子で新聞の日曜版を読み、バーと四人のおじさん、わたしは、代わるがわるラッセル夫人に笑いかけた。夫人はソファに座って、一人一人に笑顔を返してくれた。
「今、世界では何が起きてるのかしら?」 ラッセル夫人がメルに訊く。
「うーん、いつもどおりのことだよ」とメル。
ラッセル夫人はいつもお化粧をしていて、わたしがおずおずと頬にキスをすると、甘いおしろいと口紅の匂いがした。ラッセル夫人は鮮やかな赤と紫の石がついたネックレスとイヤリングをしていた。イヤリングは耳のところで花の形になっていて、そこから光のしずくが落ちるように、両頬にそって垂れていた。
この男ばかりの寄り合い所帯から、ラッセル夫人はバーとわたしをお気に入りとして選んだ。たぶん、わたしたちの以前の暮らしには、母親というものがいたことを感じとっていたのだろう。学校に着ていくためのパステルカラーのドレスと、わたしに着けさせたいと思った子ども用のネックレスとイヤリングを買ってくれた。その宝飾品は、コットンを詰めた白い小さな箱に入っていて、夫人が振ると小さな音がした。
アメリカに来て最初の冬、日曜の午後になると、ラッセル夫人はよくわたしとバーを乗せて、山への遠出ドライブにでかけた。電線や街並がゆっくりと、木々の梢と砂利道に変わっていき、やがてわたしたちが車を降ると、そこは雪に囲まれた世界だった。小さな木が一本立っていて、来た道ははるか遠くの方に消えていた。何もない世界、雪と空だけの世界。そこでわたしたちがしたことと言えば、やわらかな雪の上に足跡をつけながら、輪になって歩いたことくらい。
三度目の山行きのとき、バーに訊いた。どうしてメルのお母さんは、わたしたちをいつも雪のところに連れていくのかと。
バーが答えた。「メルのお母さんはきっと、おまえとわたしが雪は魔法みたいだ、と感じてると思ってるのさ。あったかい街のこんな近くに、雪で埋まった場所があるってことをね」
「なんで海に連れていってくれないのかな?」 わたしは訊いた。
バーは首を振った。「いや、それはないだろう。海に行かなくちゃいけない理由がない」
「でも、マーがいる」とわたし。
「いや、いない」 バーが屈んでわたしのジャケットのファスナーを締めながら言った。
「バーは、マーは浜にいるって言った」
「ここの浜じゃないんだ。ベトナムの海辺のことだよ」とバーが言う。
どこが違うのだろう。
ラッセルのおばあちゃんは、山に行くとき小さなカメラを持っていった。おばあちゃんはカメラを通して世界を見るのが好きなのだ。最初に山に行ったとき、バーとわたしがメルの青い車の前に立っているところを写真に撮っていた。
写真を見ると、バーは茶色のズボンをはき、ターコイズ色のベルベットのスウェットシャツを着ている。髪を横で分け、分けた毛を片耳にかけていた。わたしはブルージーンをはいて、黄色と赤のストライプのセーターを着ていたのだけれど、写真には写っていない。おばあちゃんが生成りのセーターを車のトランクから引っぱり出して、ほこりをはらい、わたしに着せたからだ。シャッターが押される前、バーがわたしの額の髪をなでつけた。それで前髪が目の上にかかっていない。
この写真のバーとわたしは、手をつないで、青い車に寄りかかっている。二人はカメラをじっと見つめ、フラッシュが光るのを待っている。光が放たれると、カメラの中で何かが起きたことがわかる。何かが起きてわたしたちを記憶する。顔を記録し、服を記録し、震えながらその瞬間をまっている、ぼやけた手の形を記憶する。
写真を撮り終えると、おばあちゃんはわたしたちを森へと導いた。
***
山に行った最初の日、わたしはバーの足跡を踏んで歩くという遊びをやった。そうすると雪の上に自分の足跡が残らない。立ち止って、来た道を振り返ると、バーとおばあちゃんの足跡しか見えない。二人の足跡は車のところから始まり、遠くからみるとそれは、空から落ちてきたキラキラした青い箱みたいだった。
わたしはバーがゆっくりと、森の中を進んでいくのを見ていた。両手を背中ににまわして、地面を見て歩いていた。おばあちゃんがバーの前を歩いていた。カメラで空を、木のてっぺんを覗き、ときどき振り返ってこちらにもカメラを向けた。
わたしは二人のあとを追いかけた。
森のいちばん深いところまで来て、おばあちゃんは立ち止り、こちらを見て笑った。わたしはどんな風におばあちゃんが頭をかしげて、耳につけた光る玉をサーチライトみたいに揺らしていたか、覚えている。
おばあちゃんは一本の木の幹に手のひらをつけて、指でそこに彫られた文字をなぞった。そして笑いながら泣いていた。
わたしは目を閉じた。目を開けると、バーが雪の中でしゃがんで目を閉じ、両耳に手を当てていた。ベトナムにいた頃、かくれんぼで遊んでいたとき、釣り舟の影にしゃがんで、目をきつく閉じていたわたしみたいに。そうすれば誰にもみつからないからだ。わたしは走っていって、バーの首に手をまわし、背中に乗った。
「バーはどこ行った?」 わたしはバーのことを大きな岩だというふりをして、訊いた。「バーはこの雪の中のどこに隠れているんだろう」
大きな岩が立ち上がり、木になった。木は枝に乗せた雪を振り払おうと、からだを揺らした。わたしはしっかりとつかまった。木は今度は野生の馬になった。その首にわたしはしがみつき、馬は雪原を走った。馬は走って、走って、走った。馬は走りながらこう言った。「わたしの小さな女の子はどこに行ってしまったのだろう」
わたしはバーの目に手をあてて、陸に上げられた十匹の魚みたいに、指をくねくね動かした。そしてこう言った。「バー、バー、ここだよ。あたしはここにいるよ」
わたしを乗せたバーは、雪に足型を押しながら、走って森を抜け出した。二人で互いの名を呼び合い、その声をあたり一面に響かせて。目の端で、森がどんどん小さくなっていった。バーが一息つくのに立ちどまったとき、おばあちゃんの足音がはるか後ろの方から聞こえてきた。
バーとわたしは、おじさん四人をうらやんだ。おじさんたちは一度も森へのドライブに招かれたことがない。日曜の午後、おじさんたちは近所を歩きまわり、誰かベトナムからやって来た人がいないか、探していた。少ししてついに、おじさんたちはビリヤード場で、ベトナム人を見つけた。それからというもの、日曜日はきまってビリヤード場に行くようになった。
バーとわたしがおばあちゃんについて雪の中を歩いている間、おじさんたちは友だちになったベトナムの兄弟たちと、タバコを吸い、アイスコーヒーを飲み、ビリヤードをし、やり方を覚えてからフットボールの賭けをしたりしていた。そんな楽しい時間を過ごしていたから、日曜の夜は遅くまで家に帰ってこなかった。バーとわたしが月曜の朝早く起きると、おじさんたちはまだ二段ベッドの中で眠っていた。
ときにおじさんたちはコートを着たままで寝ていて、上の段で寝ているおじさんの一人は、靴を両足ちゃんと脱いでいなかった。バーがわたしを持ち上げて、わたしがおじさんの足から靴を脱がそうと引っぱった。そして前の晩にベッドの下に脱ぎ捨てられたもう片方の靴を拾ってきた。わたしは両方の靴を揃えて、先っぽをドアの方に向け、部屋の真ん中に置いた。
学校のある日は、朝歯をみがいて顔を洗ったあと、おばあちゃんが買ってくれたパステルカラーのドレスの中から、バーが一枚選んでわたしに渡す。チクチク、シャラシャラするドレスを頭からかぶって、ちょっとの間、首にぶらさげている。花びらがひだになっている、大きな一輪の花、真ん中にはわたしの不機嫌な顔がある。
「アメリカの服は着たくない」 そうバーによく言っていた。
バーは口の端をゆがめ、同時にまゆを上げて、泣きそうな道化師みたいな顔をした。バーはわたしを見て肩をすくめると、ベッドの下から学校用の靴を引き出した。透明なビニールのサンダルで(それもおばあちゃんからもらったもの)、校庭で地面を蹴るたびに、小石が指の間にはさまってしまう。
わたしは闘鶏が始まる前のおんどりが毛を逆立てるように、首のまわりでドレスをバタバタさせて、部屋を走りまわった。
「誰がアメリカのドレスを着たい? だれ?」 小さな円を描きながら、わたしは「だれ、だれ、だれ?」と繰り返し歌いながら走った。
バーもときどき、片足立ちをしてもう片方の足を後ろに蹴りながら、わたしの歌に参加した。両手をまるめて脇の下につけひじを突き出し、羽みたいにしていた。頭を片方にかしげ、顔をしかめて歌った。「だれ、だれ、だれ?」
「そこにいるのは誰だ」 おじさんの一人が眠そうな声を上げる。
わたしは首にドレスをつけたまま、廊下に飛び出す。部屋の中からバーのなだめる声が聞こえてくる。「あの子が踊ってるだけだよ」
「ハトの鳴き声みたいだな」 もう一人のおじさんが言う。
「毎朝あの子は、頭を切られたニワトリみたいに走りまわってる」 別の一人が言う。
「学校に遅れるんじゃないのか」 さらに別のおじさんが訊く。
わたしは廊下で知らんぷり、壁によりかかって足を組んで立っている。少ししてバーが部屋から出てきて、後ろ手にドアを静かに閉めた。ビニールのサンダルをわたしに渡す。わたしは床にすわって、サンダルに足を入れる。バックルを締めていると、部屋の中から、おじさんたちがベッドの中で転げまわって、もう一度寝ようと苦労している様子が伝わってくる。
バーとわたしは玄関までつま先立ちで歩いていく。メルは昼まで寝ていることがよくあったから、家を出るときは起こさないようにするのだ。
舗道に出ると、バーが指でわたしの髪をといてくれる。それからシャツのポケットから髪留めを二つ取り出して、前髪が目にかからないようになでつけて、優しくパチンととめる。
学校へ向かう道でバーは、朝はあまり騒がないようにな、と言ったりする。
わたしのペチャクチャいうさえずりで起きてしまった、とメルが文句を言っている、と言われたことがあった。そう言われてわたしはバーにこう返した。「さえずるのは口のきけない鳥でしょ。わたしはさえずったりなんかしない」 バーはわたしの手をぎゅっと握って、それ以上何も言わなかった。
学校の手前の角にある、赤に白文字の標識のところで、バーとわたしは立ち止る。わたしは標識の支柱に腕を巻きつける。毎朝これをやるのだ。バーはわたしのそばで待っている。わたしは片足を支柱に巻きつけて、頭をぐっと垂らす。
こうやって下からものを見るのが好きだった。まわりのものがみんな、逆さまになっている。校庭のまわりを囲んでいる銀色の長い鎖を見る。校庭の生徒たち全員がしっかりと足を地面に押しつけて、頭を鎖に向けて、ゆっくりと青い空の方に向かって進んでる、と想像したりした。生徒たちが宙に浮いて、服をふくらませ髪をなびかせているところを頭に描いた。わたしは逆さになっているバーの方を見て、バーも腕を組んだまま浮いていると思った。
わたしが頭に血をのぼらせている間、バーは標識の文字をじっと見ていた。バーは言葉を覚えようとしていたのだ。ゆっくりとくちびるを開け、それから閉じた。そして「スートップ」と発音した。「スートップ」「スートップ」
わたしは学校でただ一人のベトナム人の生徒だった。最初に学校に行った日、先生はみんなに紹介するとき、地球儀を片手に持ち、もう片方の手でそれをまわして、海の近くにあるSの形をした場所を指差した。
わたしはそこからやって来たのだろうか?
イースターの卵みたいな色のドレスを着て、ビニールのサンダルに足を突っ込んだわたしが、みんなの前に立っていると、クラスの生徒たちは地球儀とわたしを交互に見た。手で口元を隠して何かささやいている子。だまってじっと見つめる子。わたしはドレスの下の下着の縞が、信号機みたいに点いたり消えたりするのを想像した。
最初に登校した日の休み時間、わたしは校舎の隅にある大きな分電盤の影に立って、兄さんのことを思い出していた。わたしがここにいるのを、兄さんは見ているだろうか。なんでわたしが他の子と遊ばないのだろう、と思っているだろうか。わたしは、ベトナムの学校の足の悪い校長先生みたいじゃないだろうか。校舎の入口に立って、生徒たちが口々に叫びながら、浜辺を走りまわっているのを見ていたあの校長先生。
「おーい、オレより速く走れるやつはいるか?」
「ここよりもっと高く飛べる人は?」
「水平線まで泳いでいって、休み時間が終わる前に帰ってこれるのは誰?」
大きな音で始業のベルが鳴ると、わたしの通っていたアメリカの学校では、アスファルトの校庭の端っこで生徒たちが列をつくる。列に並んで、クラス全員が緑のビニールマットが何列も敷かれた大きな部屋に入っていく。マットは二、三枚のかたまりごとに、おもちゃの棚で仕切られていた。そこに横たわって、先生が目を開けていいと合図するまで、目をつむっている。
「さあ、寝ましょう」と先生。「眠れなくても、目を閉じて休みましょう。目を閉じて。そうすれば眠れますよ」
兄さんがいなくなってから、わたしは昼寝をすることができなくなった。アメリカの学校では、緑のマットに横になり、白い天井をじっと見ていた。すぐ横の棚に置かれた金髪の赤ちゃんの人形を、見ていることもあった。人形のゴワゴワした髪の毛に指をからませて、じっと横になり、他の子たちの寝息を聞いていることもあった。人形は青い目を茶色の長いまつげでおおって、神妙に目を閉じていたけれど、わたしはじっと天井をにらんで、そこに見えるものを言い当てていた。椅子、木の幹、頭のはげた人、銀色の月。
天井を見て遊ぶことをわたしは始めた。漁船に乗って海にいたとき、空で遊んでいたときのように。あの頃わたしは、もう会えない人、見たり触れたりできないものを、空の向こうに漂っているんだ、と考えていた。その遊びには、空の継ぎ目、引っぱることのできる糸を探すことも含まれていた。その糸を見つけることができて、目でしっかり捉えることができたら、空を切り裂くことができる、そうすれば母さんも、兄さんも、おじいちゃんも、わたしのサンダルも、貝殻の宝物も、みんなそこから落ちてくるんだ、と自分に言い聞かせていた。
わたしが天井をぱっくりと切り開く糸を見つける前に、先っぽに光る星のついた銀の棒をもちケープを着た生徒が、わたしたちを起こしにきた。星の従者は眠る生徒たちのからだをそっと、ひとりひとりその星でなでていった。眠っていた子どもたちはざわざわと起き出した。星の従者がわたしのところに起こしにくると、わたしはその子が触る前にパッと起き上がった。一度、指がまだ人形の髪に巻きついているのを忘れていたことがあった。わたしがすわったとたん、棚のおもちゃの果物ともども、人形ががくんと前に転がり落ちた。プラスチックのりんごとオレンジが床の上で跳ねた。その日、星の従者はわたしの前を急いで通り過ぎていった。
「シーーーッ」 先生が長い指をぼってりしたくちびるにつけて言った。「シーーーッ」
ラッセル氏と夫人は、ずっと長いこと、ガラス製の小さな動物の置き物を集めていた。多くは馬の置き物だった。ガラスの動物たちは、細い透明の脚をもっていた。ラッセル氏が死んだあと、夫人は夫のものだった他の遺留品とともに、息子のメルヴィンに、このガラスの動物をいくつか持たせることを決めた。
ある日曜日の午後、メルが母親といっしょに車で家に戻ってきて、バーとおじさん四人に手伝うように声をかけた。メルの車のトランクが開けたままになっていて、その中にガラスの飾り棚が押し込まれていた。おじさん二人に飾り棚を注意して外に出すよう指示してから、メルはバーと残りの二人に後部座席に置かれたダンボール箱三つを、家に入れるよう言った。みんながメルの手招きのあとにつづいた。メルの母親が入り口のドアを押さえ、バーとおじさんたちが不揃いなステッップを五つ上って、家に入った。飾り棚と三つの箱を長い廊下を通って運び、家の裏手にあるメルの事務所に降ろした。わたしはジーンズの後ろポケットに手を突っ込んで、みんなのあとをついていった。
メルの事務所は小さくて、ものでいっぱいの部屋だった。開けかけの箱がいくつも床に散らばっていた。壁際に並べられた棚が、本と書類の重みでたわんでいて、中央には大きな四角いデスクがあった。その上はペンや書類、領収書ファイル、鍵や小銭の入ったトレイでおおわれていた。デスクの向こう側に、革の回転椅子があった。
メルはおじさんたちに、ガラスの飾り棚を一番奥の隅に置くように指示した。そこなら、メルがデスクにすわっているとき、飾り棚を眺めたり、中をのぞくことができる。
わたしたちが見守るなか、メルと母親は三つのダンボール箱を開けて、中から出したものを注意深く飾り棚に置いていった。最初に出てきたのは、青と白の五つの陶器だった。次に赤い革表紙の本が少し。メルはおもちゃの消防車の車輪をまわして、飾り棚にそれをしまった。メルの母親は、まだタバコの詰まったパイプを取り出し、メルに渡した。メルはそれを注意深くそっと棚に置いた。最後に出てきたのが、ガラスの動物の置物だった。全部で二十個くらいあって、それを二列に行進でもしているみたいに並べた。
わたしたちは飾り棚のそばに来て、中を見てもいいと言われた。わたしたちが中を覗き込んでいると、母親がメルに、中のものに触らないよう、わたしやおじさんたちに伝えるよう、バーに言ってくれと告げた。
バーはそれについて何も言わなかった。ただ「わかったかな?」と訊いただけだった。わたしは「わかった」と答えた。みんな飾り棚の中のものは貴重品なのだと感じていた。それは見た目がわたしたちにとって、価値がありそうに見えるからではない。飾り棚の中は、この部屋の、そして家じゅうの乱雑さと比べて、別世界だったからだ。
メルの事務所を出るときに、デスクの書類の上に置かれていた黄金色の蝶に気づいた。わたしは手を伸ばして触ってみた。蝶の羽の粉の感触ではなく、冷たいガラスが指に触れた。ドアのところから振り返って、デスクの方を見た。あれは何?
毎日学校の始業終業のとき、年長の生徒が二人、校門前の道路の真ん中に立った。二人は標識を、まるで戦いのときのサーベルみたいに掲げていた。それは車が(どんな車も、一台残らず、黄色い大きなバスでさえ)、子どもたちが通るときは、止まらなければならないことを示していた。それで生徒たちは安心して道を渡れた。学校へ行くときも、家がどこであれ学校を終えて家に帰るときも。
毎日午後になると、わたしはその標識の横を通って、迎えにきてくれたおじさんの誰かとメルの家まで帰った。バーとわたしが毎朝足を止める、赤と白の標識のところも通った。わたしは支柱を指でさっとなで、「こんちわ」と小声で言った。
おじさんがわたしを家の中に入れると、わたしは廊下を走り抜けて部屋に行き、チクチクするドレスをジーンズとTシャツに着替えた。バーかおじさんの誰かが帰ってきて夕飯を食べるまでに、いつも一時間くらい一人の時間があった。
最初の頃、わたしはその時間をぬり絵の本に色を塗ったり、それを読んだりしていた。男の子と女の子、それにスポットという二人の犬がいて、その犬はボールのあとを追いかけるのが好きだった。でもメルが飾り棚にものを入れているのを見た日から、わたしはメルの事務所に忍び込んで、蝶やガラスの動物を見たりすることにその時間を使うようになった。
蝶は黄金色をしていて、前見たときと同じように、手紙や賃貸受領書の束の上に置かれたまるい厚いガラス盤の中にいた。ガラス盤を持ち上げると、蝶は黄色いジェリーの液体に包まれた。ガラス盤をぐるぐるまわしても、蝶がどこに飛んでいってしまったのか、どこに逃げ出したのか、わからなかった。
わたしはガラス盤を耳のところまで持ち上げて、耳を澄ました。最初聞こえたのは自分の息だけだったけれど、少しして窓ガラスに羽をこすりつけるような、シャラシャラという小さな音が聞こえた。シャラシャラいう音は、ささやく歌声だった。蝶が話すときのやり方なのだ。わたしはその言葉がわかると思った。
両手のひらにガラス盤を乗せて、中の蝶を見ながら、裏庭に向かった窓までそれを運んだ。太陽光線にガラス盤を当てると、ガラスはキラキラと黄色い光を放った。その黄色の真ん中に鮮やかな茶色の蝶の形が見えた。
わたしはガラス盤をデスクのところに運び、手紙や賃貸受領書の束の上に元通り置いた。ガラス盤は、バーが夜寝るときずっしりと重い頭で枕を押し下げるように、紙束を下に押しつけた。バーは本当はジャックフルーツ・アイスクリームみたいに甘くて楽しい夢が見たいのに、いっぱい考えることがあって、悪夢に引きずりこまれてしまう。
ある晩、バーの隣りで夜寝ようとしていたとき、わたしはバーの耳にこうささやいた。「チョウチョを見つけたんだけど、困ったことがあるの」
「困ったことって?」とバーが訊く。
「チョウチョは生きてるの、、、」
「それがどうしたの」 バーが言う。
「罠の中にいるの」
「なんの?」
「ガラス盤の中」
バーは黙っていた。
「でもチョウチョはそこから出たいの」
「どうしてわかる?」
「わたしにそう言ったの。シューシュー。シューシューって」
バーは起き上がってすわり、重い頭を前後ろに振って、片耳の縁をたたき、反対の耳もたたいた。
「何してるの?」 わたしが訊いた。
「音が大きくなる前に、チョウチョの声を頭から追い払わないと」 バーはそう言いながら、頭を傾けて耳から言葉がこぼれ落ちるようにした。
「あー」 バーは息を吐いて、両耳たぶを引っ張った。「チョウチョはみんな出ていったよ。これでやっと眠れるな」
次の朝、裏庭の隅で仕事をしているおじさんたちのところへ行った。おじさんたちは木を剪定したり、草を抜いたり、鳥のえさ箱を補充したりしていた。おじさんの一人がわたしに、どうしてそんな浮かない顔をしてるのかと訊いてきたので、助けてほしいことがあるの、と言った。そこにいたおじさん全員が、やっていた仕事の手をとめて、いったいどうしたのか知りたそうな顔をした。
わたしは指をまるめて両手で円をつくり、チョウチョがガラス盤の中にとらわれている、と訴えた。光の方にガラス盤を持ち上げると(両手をお日様の方に掲げて)、チョウチョは黄金色に輝くの、とつけ加えた。
わたしはおじさんたちにチョウチョを逃がすのを手伝って、と頼んだ。
「できないよ!」
「チョウチョはガラス盤の中に自分で飛び込んで、大変なことになってるの」
「でも僕らが何か手を貸せるようなもんじゃない」
「そうさ、ガラスの中に入ってしまったチョウチョをどうしたらいいかなんて、わからない。そんなのベトナムで見たことないもの」
「でもそれって、かわいそうじゃない?」とわたし。
「もう死んでるよ、そのチョウチョ」
「死んじゃった蝶はどうすることもできない」
「ううん、わたし羽をカサカサさせる音を聞いたの。外に出たいのよ!」
「いいか、あのな、ガラス盤の中で生きていられる蝶なんていない。もしからだがまだ生きていたとしてもだ、魂はずっと前にどこかに飛んでいってしまってるさ」
「そうだな、オレもそう思ったよ。そのガラス盤の中に魂はないと思う」
「もし魂があそこにないとしたら、チョウチョはどうやって助けが呼べるのかしら」とわたし。
「でもさ、この国で泣いたからといって、どうなる? おまえのバーは毎晩、庭で泣いてるけど、何もよくならない」
「メルの芝生の水撒きの足しになるくらいさ」
「何も起きない」
おじさんたちは仕事に戻っていった。
泣き声をたてる蝶は一度だけ飛んだことがあるけれど、メルの飾り棚に整列しているガラスの動物たちは、どこにも出ていったことがなかった。動物たちは砂ぼこりを上げて走ったり、川岸の泥地に深く足跡を残したりするような、しっかりしたひづめがなかった。何かを蹴ったり、誰かに触れたり、遊びでもしない。木の幹にからだをこすりつけたり、地面を転がりまわって足を宙でバタバタさせたりもしない。この動物たちは透き通った脚をもち、小さなガラスの口を食べたり飲んだりするために開くこともなかった。眠ることすらしない。脚をまげることができないのだ。たてがみは硬い。ちょっと風が当たって倒れても、わたしが立たせてあげないと、そのままいつまでも寝転がったまま。わたしが見たことのある動物で、いちばん間抜け。何かなくしたものがあっても、気づきもしない。
メルの事務所にいくと、わたしは飾り棚のガラス戸を開けて、動物たちが外の空気を吸えるようにした。いつもガラスの動物たちに触った。動物たちを窓のところに連れていって、日の当たる窓枠の上に置き、わたしの金の蝶の横に並べた。そしてガラスの動物たちにお話を聞かせた。シックス婦人の家の上に住んでいるハトの話をした。メルの事務所の床にしゃがんで、ハトが屋根の端にすわって、シックス婦人が前日の残り物を中庭に投げてよこすのを待っている真似をした。それからパッとからだを起こして、米粒めがけて音をたてて飛んでみせた。おんどりの話もした。浜でわたしが走るあとをついてきて、濡れた砂浜に変な足跡を残していったおんどりの話。メルのデスクからペンと紙をとって、ガラスの動物たちに、おんどりが砂浜に残していった文字を書いて見せた。それからマーがしてくれた約束のことも話した。大きくなったら、いっしょに汽車に乗って街まで行って、大きな市場を案内してくれるという約束。市場っていうのは、キミたちが住んでる飾り棚よりずっと大きくて、メルの家よりも大きくて、裏庭よりも大きいんだと説明した。
バーと四人のおじさんとわたしが逃げてきたときの舟の写真のことも話した。その写真は、わたしたちを助けてくれた船の人が、デッキの上から撮ったものだった。写真を撮ったのが誰なのか、どうやっておじさんがその写真を手に入れたのか、わたしは知らない。写真に写っているわたしたちの舟は、大きなたらいに浮かぶおもちゃの舟みたいだった。小さな人間たちがその舟の上に立っていた。わたしやバーもその人たちの中にいたけれど、どこにいるのか、あまりに人間が小さくてわからない。たくさんの小さな顔、小さな頭、小さな手に向けていっぱいに伸ばされた小さな腕。船の上のアメリカ人たちはきっと、わたしたちを笑っていたことだろう。だからあのひとたちははしごを降ろすのに、あんなに手間取ったのだ。わたしたちを見て、小さな人間がいると言って笑い転げたに違いない。デッキの上をビー玉を転がしたみたいにのたうちまわり、きっと立ち上がるのに手を貸しあわなければならなかったはずだ。わたしたちを船に上げて、ラン、クオン、ホアン、と名前を言わせ、ファンティエット、ビントゥアン、と出身地を口にさせたとき、自分たちの名前がグレンやマイクやロンだということを思い出し、アビリーンやテキサス、ヤングスタウン、ペンシルバニア、タコマ、ワシントンからやってきたのだと思い起こしていたに違いない。
わたしの話は何であってもかまわなかった。話の内容は、ベトナムの家の中庭で起きたことでも、わたしたちを海から拾い上げた海軍の船のデッキや、シンガポールの難民キャンプのハンモック、カリフォルニアに運ばれてきたときの飛行機の中でのことでもよかった。暑い昼のさなかのことでも、涼しい夕方でも、バーの悪夢の中に現われる奇妙な天気の中で起きたことでもよかった。魚醤の匂いがする夢でも、ハンバーガーやジャスミンの匂いの夢でもいい。わたしの見た夢の話だったり、出会った犬の話、いなくなった男の子の話でもよかった。わたしのマーの髪が夜どんな風にあたたかな匂いに包まれるか、遊園地の滑り台が朝はどんなに冷たいか、庭の草がわたしの足首をくすぐるとどんな気持ちか、そんな話でもよかった。バーや四人のおじさんやわたしに襲いかかった出来事が、どんなに「突然」のことだったか、そういうことについてでもよかった。毎週金曜日、授業で先生が読んでくれる童話の中の話のように、「ずっと昔のこと」「あるところで」の話だった。
ガラスの動物たちはまばたき一つしなかった。笑うこともない。話を聞いているとき、まゆを上げたり、首をかしげたりもしなかった。うなずいて賛同の意を表わすこともなく、異議を唱えて足を踏み鳴らすこともなかった。質問もなし。何か知りたいという風には見えなかった。わたしは動物たちに話をするのに疲れてきた。そしてガラスの動物を長いこと日に当てていたら、粉々になってしまうかもしれない、と思った。
わたしはTシャツのすそを引っ張って、窓枠の上にいる動物たちを一匹ずつ、シャツの舟に乗せていった。飾り棚まで運ぶとき、細っこいガラスの脚が、服をとおしてわたしをつっ突くのを感じた。動物たちを大きいの、小さいの、大きいの、という風に、最初のときにメルのおかあさんがやったように並べた。わたしは飾り棚のガラス戸を閉めると、動物たちがこちらを見ていた。わたしのことがわからないみたいだった。わたしが飾り棚と壁の隙間に隠れても、首を向けたり、顔をガラス戸に押しつけてわたしを探そうとしたりしなかった。魂がなくなっているのはチョウチョじゃなくて、ガラスの動物たちなんだ、ということにおじさんたちは気づいてないと思った。
チョウチョはわたしの胸ポケット中にいた。わたしがメルの事務所の中を歩きまわると、からだにそれが触った。わたしは蝶の重みが好きだった。庭で目を閉じて、両手をポケットにつっこみ、ゆっくりと太陽の方に顔を向けていくときの感じみたいに、この蝶が好きだった。持ち上げて日にかざしたときの蝶の色は、庭で舌を突きだしているときに感じる太陽の味みたいだった。
クリスマス休暇が始まる一週間前の十二月のある金曜日の午後、わたしは蝶を逃がそうとした。その結果、わたしたち六人は荷物をまとめて家から出ていくよう、メルから言われるはめになった。バーはわたしが悪いんじゃない、と言った。誰のせいでもない。バーが言うには、こういうことは起きるもんだ、と。
その日、わたしはガラスの動物たちに、前の晩に見た夢の話をした。その中で、わたしは学校前の道路横断用の標識を盗んで、メルの家に持ち帰った。長い廊下を引っぱって歩き、船のマストみたいに立てかけた。バーと四人のおじさんたちは眠っていた。わたしは五人を起こして、標識に登るように言った。支柱に五人を縛りつけて落ちないようにしてから、五人をそこに残し、部屋から部屋へと走って家じゅうの蛇口をあけてまわった。
ガラスの動物たちに、わたしはこう話した。夢の中で水が押し寄せてきて、バーと四人のおじさんとわたしを持ち上げて、家の外に連れ出し、玄関の五段ステップのところを越え、通りに連れ出し、学校やおじさんたちのビリヤード場を通り抜けて、ずらっと並ぶ真っ白な壁のアパートの列の向こうまで押し流していった、と。標識に乗ってわたしたちが航海しているとき、わたしはガラス盤を望遠鏡みたいに目に当てて、チョウチョの向こうに見えるものを眺めたら、マーが遠くの浜辺に立っているのが見えた。
ガラスの動物たちはわたしの夢の話をしんぼう強く聞いていたけれど、それについて何の感想もないみたいだった。動物たちを窓枠のところから、飾り棚の中に戻した。ガラス戸を閉めると、わたしはメルの革の回転椅子によじのぼって、ぐるぐると椅子を回転させた。わたしは目をまわしながら、夢の中のマーの顔を思い出し、ガラス盤からチョウチョを逃がす方法を考えた。
回転椅子がとまったとき、飾り棚のそばにある本棚の下の段に、ガラス片が落ちているのに気づいた。回転椅子から降りて、本棚の方に歩いていった。蝶はTシャツのポケットにいた。わたしが屈んでガラス片を見ているとき、蝶が重みでTシャツを引っぱっていた。落ちているのは写真フレームだった。
ガラスのフレームは割れていたけれど、中の写真は無事だったようだ。割れたガラスの向こうで笑っているのは、まだ少年のメルと若々しいメルのお母さんだった。二人は互いに腕をまわしてぎゅっと抱き合っているみたいな格好で、それを見てわたしは、これでは息ができないのではと思った。でも写真の中の二人は楽しそうにしていた。二人の鼻はピンクに光っていた。その頃のメルのお母さんの歯は輝いていて、きれいに揃っていた。メルのカールした髪がお日様に光っていた。二人ともとても生き生きとして見えた。
バーとわたしがしたように、二人は雪の中で、青い車に寄りかかって立っていた。雪の上を一つの影が伸びていた。写真を撮った人のものなのだろう。
わたしの目が飾り棚の中のパイプにいった。パイプは横になっていて、口の中には今もタバコが少しつまっていた。
わたしは立ち上がると、部屋をみまわした。部屋はものでいっぱいのように感じられた。書類の束が棚に乱暴に詰め込まれていた。本の入った開けかけの箱が、てんでバラバラに床の上に放置されていた。メルが通るとき、あっちに押し、こっちに押ししたのだろう。空の箱は、部屋の隅に積んであった。
わたしはメルの事務所の壁を見渡して、ガラスの飾り棚とドアの近くの壁の間に隙間を見つけた。そこまで行って、手のひらを交互に壁に当て、その巾を測った。
そこに目をやりながら、あとずさりして壁から離れ、部屋の中央のデスクのところで立ち止った。ポケットからチョウチョのガラス盤をとりだして、片手にそれを乗せた。そして少しゆすって、手の上の重みを量った。
蝶はガラス盤の中にいた。息をとめたり死んだ真似がうまい人みたいに、まったく動かなかった。
ガラス盤を耳のところに当てて、耳を澄ました。心臓がドキドキしていた。わたしはガラス盤をからだから遠くに離し、首を振ってからまた、耳のところに戻した。
わずかに小さな音が聞こえた。薄くて透きとおったカーテンがさざ波をたてるような音だった。
ガラス盤をきつく握りしめ、腕をできるかぎり後ろに振って、わたしの手のひら三つ分の隙間に狙いを定めた。一回弾みをつけてから、腕を前に思い切り振って、ガラス盤を投げた。
ガラス盤はすごい勢いで飛んでいったけれど、わたしが目指した方にいかなかった。それは飾り棚のガラス戸をガシャンと突き抜けていった。ガラスの動物のひざがくだけた。倒れながら、頭がとれたもの、からだがまっぷたつになったもの。割れたもののうち、隣りの動物がこなごなになるのを防いでいるものもあった。そのそばで、ガラス戸の外を見つめて転がっている動物もいた。
ガラス盤は飾り棚の背板を直撃し、跳ね返ってくるときに、陶器に当たって跳ね飛ばした。メルの事務所は動物たちがたてる音に満たされた。
バーとおじさん四人がパッとドアを開けて入ってきた。
わたしは椅子の上で回転しながら目を天井に向け、蝶を探していた。
「シューシュー、シューシュー」
「スートップ! スートップ!」
「シューシュー、シューシュー」
「スートップ!」
*バー、マーという呼び方は、ベトナム南部のものらしい。北部の方言では母親は「メ」、父親は「ボー」。これらは中国語とよく似た呼称と言われる。(テキストに戻る)
日本語訳:だいこくかずえ
*この作品は、2013年7月発売のレイ・ティ・イェイム・トゥイ著の小説「私たちみんなが探してるゴロツキ」に収録されています。(詳細はこちら)
Kindle版、コボ版
ペーパーバック版
*「スートップ!」は2014年7月17日まで、著者レイ・ティ・イェイム・トゥイの許可により掲載されます。(2012年7月17日より24ヶ月間)
Suh-top!
Copyright © 2012 by lê thi diem thúy
Originally published by Knopf in 2001 as the first chapter of The Gangster We Are All Looking For. "Suh-top!" is an excerpt from the novel.
Reprinted by permission of The Marsh Agency on behalf of the Author.
レイのリーディング : "The Gangster We Are All Looking For"より
"The Gangster We Are All Looking For" at amazon Japan: