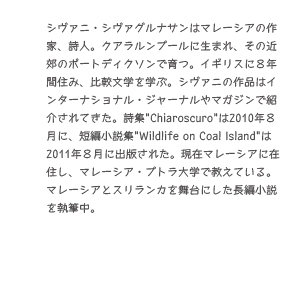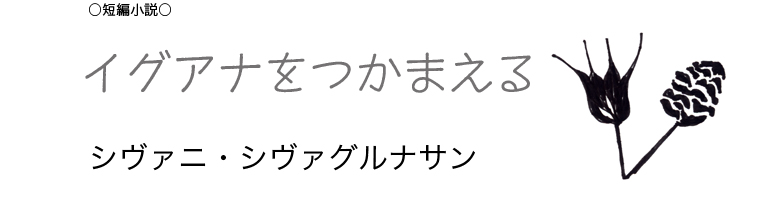
|
「だめ! ぜったいダメなの。あたしが将来何になるか、口出ししないで!」 メアリーは大声で叫ぶと、ドスドスとけたたましい音をたてて、階段を駆け上がっていった。葉っぱ集めは、以前、死んだバッタを黙って集めていたことの代償行為だった。 こんな風にいつもことは進んだ。メアリーが何か宣言して、沈黙の中に入り込む。そしてある日、絶対的な存在が自分の中で増殖しはじめると、それを一気に信じ込む。 「ちょっと、聞いて」 メアリーは声をかすれさせてこう言う。「ほら見て、すべてを見るのよ。すべてよ、いい? この朝顔、このリス、この嵐、この魂。神よ、神、神なのよ。神さまはどこにもいるの。あたしは神の存在を見つけたの。神は教会にいるんじゃない。神さまはここにいるの、この花びらにね。見てよ。ほら」 「それはいいことよ」 母さんは紫の花びらを受けとりながら言った。そしてそれを落とすと、花びらはゆりかごのように宙を舞いながら床に落ちた。「ジョン牧師が喜ぶわ、あなたが神を見つけたと聞いたらね。でも神さまは教会にもいるのよ、わかった? じゃあ、いい、言ってごらん。ここにいる男の子は誰?」 「それにね、今日、太陽があたしに話しかけたの」 メアリーは母親がしゃべったことなどなかったことのようにして、続けた。「こう言ったのよ、ここには地上でただ一つの幸いがある、とね。それって素晴らしいでしょ。ほんとうに素晴らしい。夕べはね、月がこう言ったの、闇の中でもここには光がある、ってね。わたしは祝福されているの。世界で一番素晴らしい場所がここにあるのよ」 すると父さんが言った。「メアリー、なんで母さんの質問に答えないんだ。ここにいる男の子は誰だ?」 父さんの目はやつれ、真夜中みたいに暗かった。 でもメアリーは意に介さない。「緑の葉っぱ、土、虫、巣、オレンジの雲、雨、パイナップル、コブラ! どろぬまさかなあろえかぜあらし!」 二日間、メアリーは世界を探索した。庭で穴を掘り、ミミズを巣ごと取ってくると玄関ポーチに置いた。台所からトゥドゥン・サジ(食卓で皿の上にかぶせておくザル)を持ってきて、それをミミズの巣の上にかぶせた。手製のミミズテント。それから朝顔、ハイビスカス、プルメリア、アンスリウムの花をとってきて、ミミズテントの上にばらまいた。メアリーは花びらを八宝菜のように、混ぜこぜにした。すぐに蜘蛛、カマキリ、バッタ、トンボがその仲間入りした。メアリーは眠らず、食べることもしなかった。出来上がったテントのそばにすわり、家族が近寄らないようにした。僕はメアリーがつくった世界を覗いてみたかったけれど、いつもメアリーが見張っていた。トゥドゥン・サジのすきまから見えたのは、鮮やかな色だけだった。これみよがしの、哀しい色模様だった。 そしてメアリーはこう言ったのだ。「いいこと、声が聞こえたの。あたしがこの星を統治する者として選ばれた、その声が言ったの。どうしたらいい? あたし、無視するなんてできない」 トゥドゥン・サジをメアリーが持ち上げると、ハエたちが嬉しそうにブンブンとたかってきた。 「さあ、ここに大きな混合体があるのがわかるでしょう」 メアリーは続ける。「この大きな混合体はこの星の写しなの。だからあたしはすべての仕事をしてきた。自分の天職としてやっていたとは知らずにね。新しいこの仕事で、あたしは公の会議をたくさんこなさなきゃならない。パパ、その準備をしてくれるかしら?」 僕の両親はこっそり、メアリーを島で唯一の精神科医のポー先生のところへ連れていった。二人はその先生の「明るい未来診療所」へ行くのに、ぐるぐる旋回しながら行った。コールアイランドのような所では、精神病に対して、姦通や近親相姦よりもっと悪いイメージがあるのだ。よくわからない病気を直そうとして生きている人より、足を骨折した人の方がずっと、人々から同情が得られた。 両親は無言のうちに、メアリーを家に連れ帰った。母親は麦芽飲料を一杯つくって、庭にある一本のパパイアの木をじっと見つめながら、ロザリオを手でもてあそんでいた。父親はメアリーに薬を数錠を飲ませてベッドに休ませ、長いことトイレに籠っていた。一人残された僕は、冷蔵庫にあった缶ビールを二、三個もって、自分の部屋ですわっていた。コップの中のビールを覗くたび、底から泡がのぼってきて、表面でぶつかってくだけるのを見ていて、どうして泡がそうなるのかわかった、と思った。きらめく筋が(金の糸のようにではなく)、泡の世界へ、カールスバーグの聖なるお守りの元へと、僕を近づけた。その一体感の中で僕は、メアリーの存在とその病状がうちの屋根に座りこみ、僕らに全身全霊でひれふして救済を求めるよう告げているんだと理解した。 メアリーの病気は三番目の子どもになった。僕は二番目だったけれど、最上級に格上げされた。上位にいると、人はヘラクレスになる。巨人が好きなときに家を離れるのは当たり前のこと、自分に与えられた才能をいくらでも掘り起こすことができるし、自分の影を友に生き残ることさえできる。メアリーは山ほどの錠剤とともにベッドの中に埋もれていて、両親の四次元監視網はときに、残酷な愛の仕打ちとなった。残酷という言葉を、僕は普通の意味で言っているわけではない。基本的に、両親はメアリーのことがあきらめきれていなかった。炊飯器は永遠の粥製造機となった。粥は心を静める食べものだ。家ではパパイヤの実は、もう熟して木から落ちることはない。「さあ食べて」 母親はメアリーの口元に、つぶしたパパイヤの一さじを近づけてはそう言った。「気持ちが落ち着くからね」 メアリーはたいていそれを拒んだ。父親はクレジットカードの新しい使い道を見つけた。物置に本棚を置くと、そこを双極性感情障害に関する本で満たしていった。父親はその本を繰り返し読み、そこから引用もした。メアリーの居場所は、自分の毛布と空飛ぶスプーンの中にあった。自分で水を注いで飲むことさえ、メアリーには許されていないように見えた。 ゆっくりと、きらめく筋が(金の糸のようにではなく)、僕の新しい役割、第一子であること(巨人)をもてあそび始めた。その筋は僕のからだにからみつき、ベッドで泡とともに過ごす僕を恋人の暖かさで包み(時間がたてば消えてしまうものだが)、そして僕が膨らませた自分の偉大さをぺちゃんこにする。僕はパレードのときのゴム風船人形で、一日か二日の行進の間大きく膨れて愛想をふりまき、宙に浮いてふわふわとねり歩くが、その後しぼんでしまう。中身はただの空気、安くてどこにでもある空気、入れたときと同じようにいとも簡単に抜けてしまう。 泡ときらめく筋は、両親の部屋からの声に僕の耳が耐えられなかったり、メアリーのしゃべりがえんえん続くとき、なくてはならない友となった。「このラジオはけだもの」 メアリーは二時間言い続けたことがあった。両親は精神安定に効きそうな食べものを買いに、市場に出かけていた。「どのラジオ?」 二十分たった頃、僕は訊いてみた。でもメアリーがどのラジオのことを言っているのかわからなかったし、どうしてラジオがけだものなのかもわからなかった。病気は悪くなっているように見えた。僕はメアリーを、具体的に言えば、メアリーの妙な病気に対して嫌悪を持ちはじめていた。いろんな声が出没するので、僕はいつメアリー本人が話しているのか、判断することができなかった。両親が市場から帰宅し、メアリーのために睡眠剤を水に入れた。メアリーが眠りについた静かな時間、僕は両親の素に返った顔を目にした。しわが刻まれ、あちこちから泡が吹き出ているような、不安気な顔。二人は僕をまともに見ず、僕がそうしてほしいと願っていても、僕の目を見ることはなかった。それはもし僕の目を見たら、どんな親も見たくない半人前の息子と対面することになるからだ。 二年後、メアリーはほぼ寝たきりになってしまった。両親はなんであれメアリーに自分でさせることをしなかった。母親は今も昼に夜に粥を与えていて、どろどろにしたパパイヤを夕方にやっていた。僕は両親に自分のことを少し自分でさせては、と言ってみた。そうしたらもっと生きてる感じがして、自分のことがわかるんじゃないかと。でも母さんはこう言った。「こういうことはね、ケヴィン、大人にまかせておけばいいの」 だから僕は従った。 マンチェスター大学で歴史学を学ぶ奨学金を勝ちとったという手紙を受けとったとき、僕は両親に何ヵ月か家を離れることになると告げた。パパイヤの木の前でロザリオを手にすわっていた母さんは、「それはよかったわ。行く準備は大丈夫? パパもママも寂しくなるわ」と言った。父さんはうなずくと目をそらした。 「ぜんぜん大丈夫だよ。とうとう自分でやるときがきたな」 「どういう意味だ、それは」 父さんが顔を僕からそむけたまま訊いた。父さんはハンカチを出して、流した涙を拭っていたのだ。僕はそうとは気づいていなかったけれど。 「なんでもないよ。男の子が世界を見に出ていくときが来た、ってだけのこと」 父さんは振り返って、僕のことを見た。目に涙はもうなかった。「そうだ、おまえはもう大きくなった。未来のない両親と一生過ごす義務はない。おまえには、ママとパパは、わたしは、、、ほんとうに、、」 「みんながもっと自由になれる。少しだけね」 二人はそれには答えなかった。 三ヵ月後僕は家を離れ、雲におおわれた朝、薄着の格好でマンチェスターに着いた。通りは濡れていて、空は百日分くらいのたっぷりの水分を蓄えているように見えた。空港からアパートまで、贅沢してタクシーに乗り、最初の10ポンドを使った。バスは苦労なく乗れる人たちのためのものだったから。タクシー運転手が僕に言った。「兄さん、どっから? アジアのどっかからじゃないの。はっきりとは言えないけど」 運転手は白髪の、無精髭をはやした、顔じゅうにしわを走らせた男だった。この男は僕が何から逃げてきたのかを言い当てて、客待ちの間の手慰みにできる人じゃないか、と思わせるところがあった。 「コールアイランドです。マレーシアのことですけど」 「マレーシアか。そりゃきれいなとこだ、うん、きれいなとこだな。ベトナムの隣りだっけ?」 「いいえ、シンガポールの上です」 「そうだそうだ。別のとこと勘違いしてたよ。タイね、そうタイと勘違いしてたんだ。でもマレーシアもきれいなとこだと思うよ、きっと。で、兄さん、ここで何を? イギリスの太陽でも浴びにきたのかな。ハ、ハ、ハ」 「違いますよ。勉強しに来たんです」 「そうか。うまくやれよ。ここで滅入らないようにな。マンチェスターはそういうとこだからさ。知ってるよな?」 「いや、知りません」 アパートは狭くて、寒くて、ゆとりがなかった。寝室が二つ、そこに三人が住む。つまり僕は、人が夜中にトイレで通るかもしれない、部屋の外にフトンを敷いて寝ることになった。ルームメートは二人ともイギリス人で、缶詰からものを食べ、いつの日か妖精がやってきて、部屋をすっかりきれいに掃除してくれると思い込んでいるやつらだった。「心配すんなって、ケヴ」 僕が掃除当番表をつくってはと言ったら、ジョンがそう答えた。「どこかのご婦人がやってきてこのクソをなんとかしてくれるって。まあみてな」 そんなご婦人がやってくることはなかった。 ジョンとデイヴィッドは英文学の学生だったけど、二人が授業に出ていくところをほとんど見かけなかったし、授業について話しているのも見なかった。で、僕は二人はあほか天才かのどちらかだと思うことにした。実際のところどちらにしても、二人は自分たちのことを話そうという素振りさえ見せなかったし、僕は家にあまりいなかった。二人と話したくなかったからでも、僕のまわりをすごい勢いでゴミ溜めにするのを見たくなかったからでもない。夜眠りにつくために、汗臭いソックスや食べかけのピザの箱、転がるベークドビーンズの缶、あちこちに撒き散らかされた下着のパンツ、こういったものを忘れるために、僕は道の向こうのパブにすわって、フトンでの深い眠りを保証してくれる、ステラアルトワを四パイント(約二リットル)飲んでいた。目覚めについてはちょっと事情が違う。ベッドから飛び起き、ライス・クリスピーの箱が誘惑するのを我慢して、歯を二回磨いた。こういう口の開いたシリアルの箱は、マレーシアならとっくにゴキブリやヤモリの住処になっているはず。朝食は学部のカフェテリアでとった。揚げパン、ベーコンサンド、ポテトサンド、ポテトチップサンド、なんであれ腹の酸を吸い取ってくれそうなものを食べた。 大学では、服や教科書、カフェテリアで買ったサンドイッチ、パスポート、歯ブラシを入れたリュックを背に、砂利道を歩いていた。他にどこにも行く場所がないとはいえ、毎晩アパートに戻らなければと思っていたわけでもない。学科の学生と友だちになろうとしたけれど、会話は限られたものだった。最初に僕が話かけたのは、ジムという名のイギリス南部からやってきた男子学生だった。「よろしく。マレーシアから来たケヴィンです」と僕。 「ケヴィン? それってアジアっぽくなくない?」 「そうかも。でもジムってやつもいるけど」 「ウソだろ」 そう言うと、教科書を見はじめた。 クラスメートたちの飛躍の多い話し方や、ビール一杯の誘いも考えてないくせに、僕を仲間みたいに呼ぶときのやり方が理解できなかった。それと僕の話し方のせいで、本当はよく知らないものを周知の事実のように感じることもあるみたいだった。 一度友だちになりかけたやつがいた。グレッグという同じ学科の学生で、マッカダム教授が来るのを待っているとき、こう僕に言ったのだ。「授業のとき、君、しゃべらないよね。言ってることがわからないとか、あるの?」 自分のことが観察されているとは全く気づいていなかった。誰かが僕のことを見てて、こうだと判断したりしているわけだ。 「いや、そんなことはない。わかってるさ。ただよく知らないことを、しゃべるのがちょっと苦手なだけ」 「そういうことじゃないんじゃないか。誰だって自分の意見ってものがあるだろ」 「もしなかったら?」 「そりゃ、おかしいよ」 「そうなのか? 知らなかったよ」 「そうだよ。いいか、僕らはみんな、、、」 グレッグは冷水器のそばに立って、ヒットラーのことか何かについて、言い合っている男女のグループの方に目を向けた。しばらく見つめた後で、こう言った。「もしドイツが戦争に勝ってたら、アジアはどんな影響を受けた?」 それについて考えてみた。第二次大戦のことはよくは知らない。何かわかってる風なことを言おうとしたが、できなかった。 「そんときのことだよ」 そしてこう言った。「わかった、もういいよ」 「きみらは何をしようとしてたの?」 「ああ、何にも。ほんと、心配ご無用」 「もしよかったら、僕のアパートに来てよ。食いもんつくるよ」 「真面目なはなし、心配ご無用」 グレッグは冷水器のグループに合流した。その後、僕らは会釈するようになった。 僕はヨーロッパの歴史を調べはじめた。自分をネロ皇帝やヘンリー八世やナポレオンに設定して、頭の中で様々な戦争を再現したりした。読めば読むほど、自分が巨人だったときのことが思い出された。 マンチェスターに来てから、僕は毎日、違う種類のチョコレートバーを買っていた。そしてそれについて、家にメールを書いた。「ママとパパへ」 一通のメールに連名で書いた。「マレーシアにエアロ・チョコレートがないのは残念なことです。チョコレートの中に気泡が入っています。びっくりでしょ。イギリスに住む利点の一つだと思うけどね」 バウンティを見つけたときは、こう書いた。「ママとパパへ。これはちょっとした皮肉だよ。僕らはココナッツを育てているけど、イギリス人は世界一のココナッツ・チョコレートを造っているよ。二人がバウンティを試す日が来ますように。ほんとに最高なんだ」 二人に知らせたかった、僕がここで何とかやってること、うまくいってること、お城と剣と時間通り走る電車とおいしいチョコレートの国で、ここならではのものを逐一体験していることを。にもかかわらず、本当にここでうまくやるには、ちょっとはパーティに行ったり、何か受けるジョークを言ったり、誰かと店を歩きまわったり、さらには、もしもっとうまくやることができたなら、白人の女の子の隣りで目覚める、なんてことが必要だとわかっていた。でもジョンとデイヴィッド、この二人しか僕に話しかけてくる本物のイギリス人はいなかったし(牛乳が酸っぱくなったのに気づいたかとか、僕が替え刃を持ってないかなど)、加工食品や露出狂じみたマスターベーションやらで溢れた彼らの世界は、僕を招き入れるには、あまりに閉鎖的だった。それに、僕らは知り合ってもう一年くらいたっていて、今さら二人に僕の友好を向けても、悲惨な事件に間延びした反応を示すみたいなものだと思った。 大学でも運がなかった。僕は過去の支配者たちを気味悪く演じてみせる、内気なアジア人学生で、その印象がいつまでも残ってしまった。よく行っていた地元のパブ「馬とやかん」は、たいてい人気がなく、人がいるときも六十歳を超えた男たちばかりだった。試してみるチョコレートバーもなくなり、僕はコーニッシュパイに鞍替えした。でもこの活況を呈するはずの、あるいはスーパーマーケットでの実験を通して何か達成しようという希望は、僕を気落ちさせただけだった。 で、僕がこの味見実験をあきらめたところに、ジェンマが「馬とやかん」に、ある木曜の夜遅く現れた。イギリス人としては小さな人だった。中国人くらいの体型だったけれど、肌は真っ白で、ジャスミンの花か絞りたての牛乳みたいだった(粉っぽい白さではなく)。目はきつい緑色だったけれど、視線はやわらかで、クッションのような優しさをたたえていた。彼女は僕の隣りにすわり、赤ワインを注文した。その間ずっと、どうも、僕の存在を意識しているみたいだった。彼女の指がカウンターを、グラスの底をコツコツたたくのが見えたが、目は目の前のビール樽のタブに集中しているふりをしていた。でも実は彼女は、目ん玉をぐーっと下の方に沈めて、僕のことを盗み見ていたんだ。 僕は自分で止める間もなく、こう言ったのを覚えている。「こんばんわ、奥さん。すてきな夜ですね」 指のコツコツがとまった。僕の方を見もせずに、パブの薄汚れた空気に向かって答えた。「そう?」 赤い巻き毛の先を指でねじって、グラスに半分残ったワインを一気に飲んだ。 「もう一杯飲みます?」 僕が訊いた。 「そうね、喜んで。あたし、ここに酔っぱらうために来たんだから」 グラスが来ると、その人はほんの二、三分のうちにそれを飲み干した。僕はもう一杯頼まざるを得ないと思い、その次の一杯もと、彼女のくちびるがワインの赤味で黒く染まるまで、口が腐った果物みたいな臭いを発するまで、頼みつづけた。 「なんの、、、誰なのあなたは」 彼女が僕の肩に頭を乗せて訊いてきた。 「ケヴィンです。奥さん、この近くにお住まいですか?」 「どこ、、、か。あっち、わかるでしょ。近いか? さあね。あたしはジェンマ。大丈夫とおもう」 僕はジェンマをアパートに連れ帰って、僕のフトンの上に寝かせた。僕はジャンパー四枚、ズボン下とズボン二枚はいて、床の上で寝たけれど、それでも震えるほど寒くて、起きていることにした。暗がりの中にすわって、ジェンマンのことを考えた。僕のフトンのごわごわした感触を味わった初めての女性、一日じゅう遊びまわって夜寝ついた子どもみたいに、寝息をたてている人。この人は僕よりも年上(多分、十五歳くらい?)で、でも僕と同い年のどんな女の子より、知っている子知らない子全部入れても、ずっときれいだった。ジェンマが目を覚まし、あたしたち寝たの?と訊いてきたときも、まだ彼女のことを考えていた。 「まさか、寝てないです。奥さん」 「ちょっと、その奥さんっていうの、やめてもらえない? アジアの人は何にでも尊敬の念を表わすのは知ってるけど、正直、そう言われると年とったみたい」 「わかったよ、ジェンマ。朝食は何を食べたい? ベークドビーンズと紅茶ならあるけど。パンは切らしちゃってて」 「男の子って。ちゃんとした暮らしってものができないのよね。じゃあこうしない、夕べのお礼として朝食をご馳走するっていうのは。その辺の浮浪者みたいに、公園のベンチで寝ないですんだお礼よ。それと、お水一杯もらえる。頭がガンガンするわ」 ジェンマと僕はその日ずっと、カフェでいっしょにおしゃべりして過ごした。「マレーシアねえ、ふーん」 そう彼女は言うと、クッションみたいに柔らかな目を空に向けて見ていた。いったい空の何を見ているのか、僕にはわからなかった。空は青くはなかった。雲はないのに。彼女は何かそこにないものを連想していたのかもしれない。もっときれいで、もっと素敵なものを。 「そうです。行ったことあります?」 「ない。でもいつか、、、こんな風にしてるのを想うの、バックパックをしょって、タイ、マレーシア、インドの暑い通りを歩いて、屋台で甘いものを買ったり、土地の男たち女たちとお茶を飲んだり、でもその人たちはあたしの言っていることはわからなくて、でもそんなことどうでもいいって感じで」 「マレーシアでやればいい。コールアイランドで。僕が案内するよ」 ジェンマの太ももはピンクに輝いていた。むき出しのままでも、寒さにきっと耐えられるのだろう。僕は手をそこに置き、彼女の暖かさを感じた。 「ほんとう? あなたが? 優しい子なのね」 「もちろんですよ。夜市にも連れていきますよ。村に行けば、好きなお茶をいくらでも飲めますよ。僕らお茶を作ってるんで。村には茶畑が広がってます。山あり谷ありのところにね」 「なんて素敵なの。あなたってほんとにいい人ね。ほら、ヒンドゥの神さまみたい」 「僕、半分中国人なんです」 「ならもっといいわ」 カフェが閉まると、僕らは前の晩みたいに「馬とやかん」に行って、酒を飲んだ。ジェンマは酔っぱらっているのに、家に帰ると言い張った。 「ぶっ倒れたらどうする?」 僕は彼女の腕をなでながら言った。ジェンマは僕のももの上の方をつかんだと思ったら、パッと手を股間にやった。 「あのね、いい子、あたし気絶するわけにはいかないの。夫がいったいどうしたのかと思うからね」 ジェンマが誰かと結婚してるなんて、想像もつかなかった。もし誰かの妻だとしたら、それは僕のだ。おそらく二人は円満離婚の最中なのだ。 「夕べ君は家に帰らなかった。でもだんなさんから電話もなかった。どうして今夜はだめなの?」 「ジョンは心配するわよ。もちろん。夕べは彼は会議でパリにいたの。今夜はあたしが家にいると思ってるはず」 「じゃあ、、、きみもその人といっしょにいて幸せだってこと?」 「彼は子どものときの初恋の人なの。だからイエスよ。二十五年もいっしょにいるの」 「へぇ、こういうことはよくあるの? よその男といちゃついて、頼りになるジョンのところに戻るみたいな」 「ないわよ、こんなこと初めて。もちろん負い目を感じてる。あたしにもこれが何なのかわからない。でもジョンには悪いことをした。あの人は、あの人は、、、、ああ、あたしが何をしてたか知ったら、あの人がどうするか、わからない。でもわからないけど、あなたとは何かあるのかしら。前世でいっしょだったとか。あたしアジア人だったかも」 「僕にキスするのは好きだった?」 「ええ。もう行かなくちゃ。ほんとに」 「また会える? ジェンマ、お願いだ。君は僕の、、、こんな風に感じたこと初めてなんだ。男として、、、その、女の人に、男として見られるなんて」 「ああ、神さま。どうしたらいいかわからない。ジョンは、ジョンは、、、ジョンがどう思うかわからない。そうしたい、あなたとまた、また会いたいのはほんとう」 「じゃあ、ここで会おう、明日の晩」 彼女の顔が、蕾から花が開いていくように、一瞬のうちに変化を見せた。ジェンマがうそを言ってないことはわかった。実行が無理だったとしても。 「いいわ、行くわ。でもあなたのアパートで会うのはどう? ワインをもっていくから」 その後、ジョンが家を空けるときはいつも、ジェンマがアパートにやって来た。僕らはフトンの上にすわって、話をした。ジェンマはパンを焼くのは大好きだけど、それ以外の家事は嫌いな主婦だった。ジョンは気にしていなかった。家事が苦手なジェンマを笑い飛ばし、彼女の子宮が頑固で思い通りにいかないと気づいたときも、ジョンはこう言った。子宮と結婚したわけじゃないからな。ジェンマが夫のことを話すとき、からだの中を冷たくて鋭いものが渦巻いたけれど、夫を称賛する彼女をとめる方法はなかった。ジョンのことを話していないときは、いろいろな自分の野望のことを話した。旅をして世界じゅうのパンを食べ歩くこと、温かな気候の土地に住むこと、料理の本を書くこと、自由でいること。 ジョンがどういう人なのか、僕が知ったのはジェンマとの交際から二ヵ月もたってからのこと、というのは奇妙なことではあった。彼女はジョンについてたくさんのことを話したけれど、僕の方から彼のことを訊いたことはなかったのだ。ある日、「ジョンは何している人なの? つまり、何で生計を?」と訊くまでは。 「ああ、彼はマンチェスター大の歴史学科の教授よ」 これはおそらく、僕の過失だ。もし僕が自分の専門のことを二人の会話から締め出していなかったら、もっと早くに気づいていたことだろう。 「ジョン・マッカダムじゃないよね、まさか」 「そう、その人よ」 マッカダム教授は、僕がこれまで出会った人の中で、いちばん優しくて、頭のきれる人だった。僕が真面目に出席する唯一の授業が彼のもので、僕には世界史要項を書き上げるだけの知性がある、と言ってくれたのも彼だった。そのことが何を意味しているのか、よくはわからなかったけれど、その賛辞をありがたく受けとり喜んでいた。 「ジョンがあなたの教授だなんて、あんまりだわ。彼の生徒と遊んでるなんて。酷い。でもどうしようもない。あなたのことが好き、ケヴィン。でもジョンも愛してる」 「二人とも、っていうのは無理だよ。そんなの不健康だ」 「わかってる。事態はひどくなってるわ。ジョンにあたしたちのことを秘密にしてたときより、もっと酷くね。とてつもない秘密になってしまった。無限大の秘密よ」とジェンマ。 「で、これからどうする?」 「家に帰る。お風呂に入って、考えてみる」 僕は自暴自棄になったけど、なんとか自制し、がくぜんとしたまま彼女を帰した。僕は両親に、僕の人生はついにほんものになったよ、と書きたかった。でも実際にはクマルに書いた。 クマルへ。 今から言うこと、信じられないだろうな。いったいどうしてこんなことになったのか、わからない。すべてが狂ってる、、、つまりこういうことだ。僕は夫のいる人と関係をもってしまった。彼女とは地元のパブで出会ったんだけど、僕より二十歳年上なんだ。すごくきれいな人だよ。白い肌に緑の目、赤い髪。真性ガイジンだよ。彼女の夫が誰か、想像もつかないだろうな。いいか、、、僕の歴史学の教授だったんだよ! 映画か小説の話かと思うだろうが、信じようと信じまいと、これが僕の運命なんだよ。どうしたらいい? 二日たって、クマルからメールが届いた。 ケヴィン、おまえはこのソープオペラに興奮してるんだろうけど、これは今起きてる現実のことだからな。もうやめろ。おまえは自分で思っている以上に、取り返しがつかないことをしてる。 ところが一週間後、ジェンマがジョンと離婚しようとしていると告げた。「いっしょに住む場所を見つけましょう」 そう彼女は言った。「お金なら少しあるし、、、もし厳しくなったら、失業手当がもらえるし、住宅手当ももらえる。あたしにとって、二人にとって、国籍も違えば、世代も違う、それから、それから、何もかもが違う二人にとっての、新しい生活が始まるのよ。いいことじゃない、ケヴ。なんかいい予感がする。東と西。あたしとあなた。すばらしいこと、そう思わない?」 僕らはワンベッドルームのアパートに越した。マッカダム教授は妻を連れ去った者が誰か知った後、僕と話すのをやめた。びっくりしたのは、僕の成績評価は変わらなかったこと。ジェンマとの暮らしは、僕が今まで経験したことのないものだった。アパートは僕らの暮らしのすべて、外の世界がかすんで見えた。ジョンのことでときどき、ジェンマがメソメソすることはあった。僕はジェンマの泣き言はなかったことのように扱った。どうしてかと言うと、そうなったとき、僕は自分が何ものでもない者になってしまったから。でもたいていのときは、僕らは幸せだった。 最終学年になって、僕はジェンマに言った。「もうすぐビザがきれる。どうしたものかな」「仕事をすれば」 「もしそうしなかったら?」 「わからない」 「僕と結婚してよ」 「できないわよ。法的にはジョンの妻だもの」 「なんでそんなに時間がかかってるの?」 「いろいろ面倒なことがあるのよ」 「それが終わったら、僕と結婚してくれる?」 「そう難しいこと、言わないで。離婚したと思ったらすぐに再婚するって、どうかと思う」 「まだジョンのこと、愛してるんじゃないの?」 「ジョンのことはこれからも愛していく。二十五年よ。きれいさっぱり忘れて、次に進むことは簡単じゃないの。彼のことを愛せなくなったから、別れたんじゃない。彼じゃない人のことを好きになってしまったから、別れたのよ」 「僕はきみにとって何なの?」 「恋人」 「じゃあ、結婚しようよ」 「そんな単純じゃない」 「そんなことないよ。たのむよ、ジェンマ。僕がここから出ていったら、どうする? 僕がマレーシアにいて、きみはここにいたら。はるか離れたところにいて、一緒にやっていけると思う?」 「あたしは、あなたには年とり過ぎてる」 「きみが僕にとって年とり過ぎていたことなんかなかった。なんで今になって」 「実際のところの現実の話。ジョンは大人で安定してる、経済的にね。あたしたちを見て。もがきっぱなし」 「でも、それが愛ってものでしょ」 「ジョンとも愛し合ってたし、耐えなきゃいけないことはなかった」 「それなら、戻れよ。死ぬまで彼にひっついているなら、なんで無駄に僕らの暮らしを続ける」 「大人になって。誰かと二十五年間暮らせば、あなたにもわかる」 「僕はそれをきみとしたい」 「でもあたしはもう、それをしたの。わかるでしょ。あなたが経験したいと思ってることを、あたしはもうやってしまったの。この食い違い、決定的ね」 「でも僕はきみを愛してる」 「あたしだって、愛してる。あなたは遅く生まれ過ぎたの。悲しいことだわ。ほんと悲しいわよね」 「なんでそんなこと言うんだ」 「ずっと考えてきた。ジョンはあたしを許すと言っている。あなたとあたしは、すべてが不確定なことばかり。あなたはこの国に、これ以上いることすらできない。だけどあたしには生活がいる、現実のね。ケヴケヴ。あたしたち楽しくやってきたけど、、、」 「わかった。彼のところに戻ればいい。僕をおいてね。気にするな。僕がどう思うかなんてほっておけ。きみが夢みていたコールアイランドで、僕は朽ち果てるさ」 「すてきなところみたいなのに、なんでそんなに嫌うの?」 「みんな知らないふりしてるだけで、家族はあそこで崩壊してる。僕が帰ろうとしてるのは、狂った娘のことしか頭にない親のところなんだ。この三年というもの、僕がここに来ていた間、両親は姉のことにめったに触れなかった。僕も訊いたことがない。だから想像するだけだけど。姉はもっとおかしくなってるだろうな。最後に両親から聞いたことと言えば、姉が下水にいるイグアナを殺したがっている、ということ。そんなとこにどうやって戻れる。教えてくれよ」 「お姉さんはきっと、イグアナを殺す理由があるのよ。それを誰か訊いたことがあるのかしら。いずれにしても、あなたは家族とは別に、自分の生活を始めればいい。あなたはもう立派な大人よ。同じ世代の女の子を見つけて、結婚するの。ジョンとあたしがやってきたみたいにね」 「たのむよ、ジェンマ」 「ケヴケヴ、難しいこと言わないで。あたしはもう決めた。夫のところに帰る」 何ヵ月後にマレーシアに帰ると、両親は喜んでいたみたいだけれど、僕の方は両親にも姉にも、心をよせるふりさえできなかった。仕事をする気分にもなれなかった。こんな傷ついた心を抱えたままで、仕事がうまくいくとは思えなかった。なので僕は自分の部屋にこもり、セピアカラーのリールがまたまわりはじめ、光る筋が現われるのを感じながら、イギリスのことを夢想していた。 ある日、両親が親戚の家に行っているとき、メアリーの様子を見に行った。昼食の世話をし、ベッドに連れていくのが僕の仕事だったけれど、メアリーは話しつづけていた。メアリーの話しは簡単には終わらない。延々とつづく。 「イグアナが一匹。イグアナが二匹。下水にすわってる。だからあたし辛いの。ケヴィン、イグアナをつかまえて。お願い、お願い、お願いだから。イグアナが一匹。イグアナが二匹。下水にすわってる。だからあたし辛いの」 「イグアナが姉さんに何をしたの?」 ジェンマが言ったことを僕は思い出していた。おそらくやるべきことは、メアリーに何故、と訊くことだったんだ。 「イグアナは下水であたしたちの排泄物を食べるの。あたしがどんな味か、イグアナに知られるのはいや。イグアナはあたしたちの出したものをなめて、食べて、それであたしたちの出したものを排泄するのよ。あたしがどんな味か、イグアナに知られるのはいやなの」 「そりゃそうだな。でもそれでどうしようっていうんだ?」 「いい聞いて。イグアナはきたない。尊敬の念がないの。あたしたちの排泄物は、イグアナの食料じゃない。だから捕まえなくちゃいけない」 メアリーの声がこわばった。突然険しい顔つきになると、決意を固めたようだ。 「でも捕まえられないよ。どうやったらいいかわからない」 「イグアナは危険を察知したら、すばやく逃げる。だから気づかれないようにしなくちゃいけない。ロープを用意して、投げ縄にして、こっちを見てないときに、さっと投げるの」 メアリーはこのアイディアを考え出してはいた。彼女が言うには、去年、それをやろうとしていたと。僕には、いくら疑っても、メアリーに狂気があるようには見えなかった。僕が見たのは、地下にいる生きものに自分の一部が暴かれて、動揺している一人の女の子の姿だった。メアリーは、自分の排泄物の中に、自分の魂が残っていると信じているようだった。イグアナが排泄物を食べたということは、魂も手に入れたということ。メアリーが望んでいたのは、自分をそこから取り戻すことだった。 「ケヴィン、やってちょうだい、あたしたち二人のために」 「二人のためって、どういうこと?」 「あたしたち、もう一度ひとつになる必要があるのよ」 その日の午後、メアリーの指示に僕は従った。メアリーは僕のあとを追って庭まで出てきた。これまで両親が許さなかったことだ。そこで僕らはイグアナを何時間も待った。その爬虫類が僕らの足元に現われるのを、しゃがんで待ち続けた。 「どうして幸せじゃないの?」 メアリーが訊いた。 「ここが嫌いだから。コールアイランドが嫌いなんだ。マンチェスターに戻りたい」 「何から逃げたいの?」 この質問には、驚かされた。 「島だよ。ラー、、、島にある何もかもだよ」 「マンチェスターの何がそんなにいいの?」 「自由だったから。見たままの僕をそのまま受けとめて、それを好いてくれる人がいたんだ」 「ケヴィンを見てて、そこに見えるものが、あたしは好き」 僕らはイグアナが動く音を耳にした。イグアナは下から上がってきている。 「何が見える?」 「自分のことが見えてない男の子。しっかりした足を持ちながら、人を出し抜くことができない子、だから守られている必要があるの」 「どうやったらそんな風に見えるの?」 「イグアナはあたしが何も知らないと思ってる。頭が狂ってるんじゃないの。あたしはちょっと、、、おかしいだけ。ときどきすべての内側が、あたしには見えるの」 イグアナは下水の真ん中へと集まってきた。僕らがしゃがんでいるところからほんの数センチのところまで。 「ゆっくりね」とメアリー。「投げ縄をとって、そっと投げて。左のをお願い。あたしは右のをとるから」 イグアナは抵抗しなかった。僕らは投げ縄をきつく締め、イグアナをポーチの柱に結びつけた。 「これをどうしたいの?」 僕が訊いた。 「ママの方の親戚に売るの。中国人は何でも食べるからね」とメアリー。 僕は笑った。「もっといい考えがある。これでカレーをつくるんだ。そしてパパの方の親戚に持っていって、チキンカレーだって言うんだ。インド人には絶対わかるわけないからね」 メアリーが笑った。僕らはイグアナを下水に戻そうと決めた。そうすればまた明日、庭に来て、投げ縄で捕まえることができる。これは僕らの新しい遊び。まるで二人が子ども時代に戻った証のように。 インターネット初出(英語版):Cha: An Asian Literary Journal (2011年11月) この作品は、シヴァニの短編小説集“Wildlife on Coal Island”(2011年8月出版)に収録されています。 |
||||