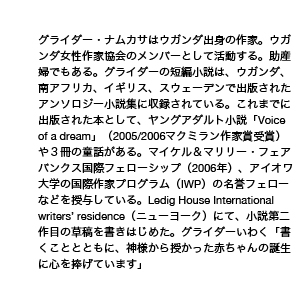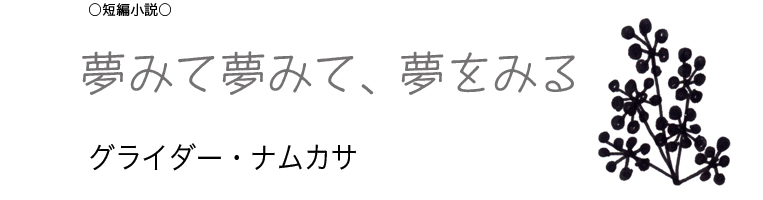
|
カンカンというくわの音が、地面に埋まった石を叩くたびあたりに響く。その音は延々とつづく。地面は石だらけだし、丸めた背を伸ばそうものならムチが飛ぶからだ。男はすばやく左右を見渡す。仲間の囚人たちの丸めた背中を、照りつける太陽に反射して光る、黒い裸の背中を目に捉える。男は後ろを盗み見る。肩にライフルを掛けた看守が、マンゴーの切り株にすわっている。おっと。看守は、男が背を伸ばしたのにもう気づいていた。 「おまえ」というのが自分のことだと男はわかっている。自分のくわの刃にちらっと目をやる。自由への武器となる「石」は確保している。他の看守二人ははるか向こう。仲間の囚人たちに危険はない。肩越しに、さっきの看守が近づいてくるのが見える。酷いガニ股。突き出た腹が、制服をふくらませて威嚇する。丸顔を残忍そうに赤く火照らせ、額に風でも送るように、帽子のへりをもちあげる。 「他の者はつづけろ」 看守が近づいてくる。「このバカに話があるだけだ」 実行の時だ。自由への道をつける時がきた。男は暗い森の方をちらりと見た。自分を待ってくれている場所。両手を広げて歓迎してくれる避難場所。自分をかくまってくれ、無慈悲な看守たちから逃れられるところ。男は武器をさっと振り上げ、近づいてくる看守めがけて投げた。うまくいった。 男はゾウ草の中を、考えることなく駆け出した。逃げなければならない。捕まってはだめだ。もう二度と。妻のいる家に、帰らなければ。そして子どもに、まだ見たことのない子どもに会うために。銃声があたりを満たす。看守たちの怒声と混じり合っている。ゾウ草の長い葉が、顔を、裸のからだを斬りつける。トゲが足にささり、前からあった傷口をさらに痛めつける。それでも男は逃げなければならない。 家の匂いを思い出す。トント、妻が手渡してくれる瓜のカップに入ったバナナ酒の香り。炉でいぶした魚の匂い。そうなんだよ、ぼくのあの家! 男は走る。暗い森ははるか彼方に思える。そこに飛び込みたい、深い下草の中に潜り込みたい。そして世界から消えてしまいたい。 聞こえてくる音。追跡者たちの足音、銃声。銃弾は草の中を通り抜け、男の頭に胸に届くだろう。走りつづけなければ。弾丸より速く、光より速く、時の流れより速く走らなければ。そうだ、時だ。時の流れは速い、そう人は言う。でもそんな言い草は反証しなければ。もし時の流れが速いのなら、どうして刑務所で過ごしたこの十年が、何十年もの長さに思えるんだ。強く羽ばたかなければ。宙に飛び出していかなければ、鷲のように空に舞い上がって、逃げ出さなければならない。 生け垣が男の目の前に立ちふさがる。刑務所を囲む高い壁のように。近づくにつれて、生け垣は高くなっていくみたいだ。天に届こうかというくらい、そびえ立っているが、これを越えなければならない。男は体勢をととのえて、宙にからだを引き上げる。右の脚を生け垣の上部にひっかける。もう片方の脚を引き上げて、薮木のかたまりにくらいつく。痛みが左の腿を襲う。下に降ろした足が割れたガラス瓶を踏みつける。傷ついた腿から血が流れ出す。その血は脚をつたって流れ、足の裏の血と混じり合う。 男はもがきつづける。自分の肉体の痛みを感じることから、長く遠ざかっていた。刑務所にいた年月、男のからだは丸太のように愚鈍になっていた。肉体の痛みにはもう慣れきっている。残されたのは心の痛みだ。刻一刻侵されているのは、男の心だった。妻を失った痛み、子どもを失った痛み。その子どもはまだ見たことさえない。その痛みは十年前に始まった。こうして薮を抜けて暗い森へ逃れようと戦っている今も、あの運命の夜のことがはっきり思い出せる。時の歯車が反転する。男の心にあの夜の出来事が、まるで昨日のことのようによみがえる。
運命の夜、エドナの陣痛が始まったのは夜の九時だった。男の妻エドナは十六歳で、初めての出産だった。昔ながらの助産婦は、病院に連れていくように言ったけれど、病院は三十キロ以上も先だ。男は隣りのムカサのところに駆け込んで、自転車を借りた。 エドナの痛みがどんどん激しくなったので、男は近道をとり、ワッタの森に入っていった。ムカサが通るのを反対した道だ。そこは真っ暗で、でこぼこの道。森からは不気味な声。コオロギが甲高く鳴き、カエルが張り合うようにゲロゲロ声を上げ、エドナの痛みは激しさを増す。森の中で、エドナは自転車にすわっていられなくなる。エドナは声を上げ、激しく震えていた。エドナが大声を上げると、その声が響いてまたエドナの元に返ってきた。 「エドナ、エドナ」 そう男は言うと、一旦走りだし、また戻った。男は最大の窮地に陥っていた。どうして妻を森に残していけるだろう? でもそれ以外にどうやったらエドナを助けることができる? 「助けを呼んでくるから、エドナ、静かにしていて」 ひどい痛みなのに、どうやって静かにしてられるのか。「すぐだから、エドナ」 男は自転車をつかむと、助産婦を呼びに自転車でもと来た道を戻っていった。男が道を必死で走っているとき、何かがぶつかってきて、どすんと音をたてて自転車もろとも倒れ込んだ。起き上がると、五人の男たちに囲まれていた。その中の一人が、男のほおをなぐりつけた。その衝撃で男の頭はもうろうとなった。そして気を失った。 その後、どうなったのか男は知ることがなかった。朝になって、自分が刑務所にいるのがわかった。地獄だ。深い穴だ。もうエドナと会うことができない、深い深いところ。男は無実の犯罪者となった。機械のように働かされた。世界から、妻から、子どもから、断絶されて投獄されたのだ。もう子どもの顔を見ることはないだろう。 男にしつこくまとわりつき、日々心をバラバラに切り裂くような痛みだった。今こうしてからだを行き来する痛みなど、どれほどのものか。 傾いた夕日が男を、避難場所の森に招き入れる。追手から男は逃れたのだ。いつのことか、言うことはできない。おそらく薮を通り抜けるのに苦労していた間ではないか。森に入ってから、男はここは避難場所などではないと気づいた。どうしてここに希望を託せるものか。この森は男を、あの五人の暴漢に引き渡した場所だった。鉄格子の中へと連れ込んだ場所だった。それでも葛藤しつつ、男はこれはただの森なのだと思った。追手からかくまってくれる場所なんだと。 夕日はすぐに別れをつげ、ここが闇につつまれることはわかっていた。男は闇がきらいだった。男は森がきらいだった。男は人間がきらいだった。おしよせる疲れに男はうちのめされる。逃亡で長いことのたうちまわっていたからだ、と男は思う。倒れたイロコの木に近づき、幹の端にすわる。エドナはまだ生きているだろうか。出産を乗り切っただろうか。ワッタの森から抜け出ることができただろうか。からだ中の力が流れ出るように感じ、目に涙が湧いた。エドナ。もし彼女が死んでいたら、何のために逃げてきたのか。「エドナは生きている!」そう自分に言い聞かせた。「彼女の元に帰るんだ」 男は目をしばたたかせ、腿にある傷を見つめた。深い傷だった。血が固まって黒くなっているが、そのうち癒えるだろう。からだの傷はいつかは癒える。指で脚のあちこちにある傷跡をさわる。手の平で顔にふれてみる。そこにも傷がある。日々の殴打や暴行によるものだ。拷問が罪として口外されることはない。怒りが燃え上がり心を石のように固くする。それでも、エドナのことを考えると、その石に裂け目ができる。エドナは自分がわかるだろうか。自分を受け入れるだろうか。もう一度愛してくれるだろうか。エドナの元に戻ったとして、彼女はまだ一人でいるだろうか。もう再婚してしまっただろうか。不安が彼を襲う。その不安に浸される。男は深く深く沈んでいく。自分を失い、心をさまよわせる。 男はわれに返った。「ぼくの妻は再婚なんてしてない」そう自分に言い聞かせる。「エドナはぼくを待っている」 破れたカーキ色のシャツをつかむと引き寄せた。決意とともに歩きはじめ、疲れを乗り越える。カウレの薮がボロボロになった半ズボンをさらに切り裂く。男は半ズボンの片方を腿から下で切り取る。下草が生い茂る中を、トゲがさサルのも無視して歩いていく。暮れていく森の声が、耳に鋭く響く。甲高い声のコオロギに、ゲロゲロ鳴くカエル、サルが木々を飛びまわる。おやすみ、とでも互いに言い合っているのだろうか。 そよ風が突然、流れてくる。野バラの甘い匂いを漂わせて。その香りは男に家を思い出させる。エドナは敷地の中に、赤とピンクのバラをきれいな色模様に植えていた。夕方二人で外にいると、バラがあたりの空気を甘くした。 夜こうして歩くのは穏やかな気分、家に向っているからだ。安全でもある。野生動物は人間よりずっといい。こちらが何かしなければ、向こうもこっちに何かしてくることはない。満ち足りていれば、動物が何かすることはない。一日中、彼らは狩りにあけくれているから、腹が減っていることはない。それに動物は友好的で偏見もない。敵になるのは同族の人間、人だ。 怒りが心の中で渦巻く。滝から落ちた水が泡立つように。男は道を急ぐ。どんなものが襲ってきても負けないように身構える。 一羽のフクロウが近くで鳴く。男は立ちどまる。フクロウはすぐ目の前の木にいた。男はフクロウの光る目をやり過ごして、歩きつづける。男が恐いのは森を包む闇ではない。自分を取り囲む生きものでもない。恐いのは捉えられることだ。足の裏がひりひりし、脚のあちこちが傷だらけだ。脚の下の方で、傷に血がたまっているのがわかる。そこから流れ出た血が、傷だらけの皮膚をつたうのを感じる。男は突然走り出す。左足を曲がりくねった木の根っこにとられる。顔から落ちて、気を失う。そこから先に進めなくなる。
夜明けの太陽が木のてっぺんから射している。木の葉が風の調べで踊っている。踊る葉が汗をかき、その滴りを地面に落とす。水滴を額の上に受けて、男はどことも知れぬ深い場所から目覚める。目を開けると目を細めてあたりを見る。これは月明かりなのか。それとも日の光か。水滴がまたからだの上に落ちてくる。男は目を大きく開ける。太陽の明かりだ。木々の頂上は、空に届かんばかりに高く伸び上がっている。世界が彼に向って笑いかけている。男は自由になったのだ。あたりに漂う枯れ葉の匂いを、鳥やサルが放つ夜露の香りを、樹液の匂いを吸い込む。そうだ、これだ。自由の匂い、生きている証。牢獄の不快なにおいではない。淀んだタバコの煙、汗や小便、排泄物、血のにおいじゃない。自分は自由になった。 朝の冷気が男のボロボロになった服から忍び込む。男は起き上がり、自分のからだに視線を落とす。埃まみれの皮膚は、傷口の血のかたまりや砂や腐植土でおおわれている。足がひりひりと痛む。腹が空腹でゴロゴロ鳴っている。でもかまわない。これから家に帰るのだ。前夜のことを追いやるように、男は目を閉じた。 突然、静寂をやぶる音が聞こえる。男は耳を傾ける。ドシドシという足音。小枝を踏む靴の音。そして人の声。パニックが男の全身をおそう。それが恐怖へと変わる。恐怖になめつくされ凍りつく。捕まるという恐怖に囚われる。「おれは家に帰るんだ」と自分に言い聞かす。後ずさりして下草の茂みに潜り込む。小枝が腿の傷の裂け目をひっかく。男はうつぶせになり、柔らかな土にからだを押しつける。何か固いものが腹のあたりを突く。石だろう。気にすることはない。からだの痛みは長くはつづかない。 聞こえていた音が大きくなり、足音が近づいてくる。ガサガサという茂みを歩く音が高まる。そして声も。何人くらいの捜索隊がいるのか、男にはわからない。男の心臓を切り刻むのは、捜索者たちが自分が隠れているすぐそばまで来ているという事実だ。嗅ぎ慣れたにおい、監獄の不快なにおいが、すぐそばまでやって来ている。向こうもこちらの臭いを嗅ぎとるのではないかと、恐れる。あまりに長い間ともに過ごした臭いだから、互いが互いの一部のようでさえある。しかし男は、どうしてもこの臭いから逃れなければならない。 「じきに見つかるさ」 鋭い声がひびく。知った声だ。その声は独特の強いひびきを放つ。「生きたまま逃がすわけにはいかない。まったく、いったいどうやって逃げおおせたのか。やつを探せ!」 指令の声は、男自身の決意を奮起させた。連れ戻されることはありえない。妻の元へ、子どもの元へ男は行くのだから。 「やつを見つけろ」 別の声が言う。「必ず捕えてみせる。捕まえずに戻ることは許されない。さあ行くんだ。散れ!」 少しして、音は低くなる。鳥の声しか聞こえない。おそらく朝の挨拶でもしているか、その日のことを話し合っているのだろう。新たな潜伏していそうな場所に手をつけるとか、捜査領域を広げるとか。と突然、また音が聞こえる。今度は離れたところからだ。男は複数の人間が動くのを耳にする。さらなる捜索隊が集結しているようだ。音は近づいてくる。声が再び聞こえる。 「おまえたちは左へ行け。残りの者はあっちだ」 最初の声がまた轟いた。 「アファンデ(隊長)、村の住人たちに警告しておく必要がありますね。みんなもう畑に出ているだろうから。森から湿地へつづくこのあたりは、特に注意が必要ですね」 「これはおまえの隊じゃないだろ。いいか、わたしの言うとおり行動するんだ。森を一掃しろ。あいつが地面に転がり落ちるまで、森を揺さぶるんだ。今から30分、わたしはここで待機する。そうしたら次に行く。いいか、獲物が頭を出したら一刻も早くおれを呼ぶんだ。さあ始めろ。裏も表も森じゅうをひっくり返せ」 天が男の上に崩れ落ちてきたかのようだ、激しく、復讐でもするように。男の世間知らずへの報復なのだ。拷問と厳しい労働から逃避したことへの報復なのだ。薮が言葉を発するように口をひろげ、男を捜索隊に突き出そうとしているかのように見える。頭上の葉の一枚一枚、小枝の一つ一つが、男をあざ笑っている。いつでも消え去ると告げている。ここが安全だと信じるなんて、ばかなことだった。自分が、火の上で溶けていくギー(澄ましバター)のように感じる。目にたまった涙を抑えるように、男は目をつぶる。もし涙を流したら、妻に、子どもに会える希望も押し流してしまいそうだから。 まだ見ぬ子のことを思うと、目にコショウでも振りかけられた気分だ。家に帰らねば、我が子に会わなければ。男は再び耳を傾けた。最初パチパチいう音に驚かされる。さっきのアファンデがそこまでやって来ているのか。闘わなければ。捜索隊に見つけられなかった昨日はついていた。でも幸運にいつも恵まれるとは限らない。今、男はあのアファンデと対面するときがきたのだ。バタバタという足音に続いて、大きな叫び声がする。男が忍び寄ると、「このやろう!」という声が聞こえた。 アファンデの声だった。男はアファンデが銃を落とし、もごもごと服を脱ぐのを目にする。アリだ! アリがアファンデを襲っている。男は立ち上がる。幸運が男の戸口をたたいている。ドアを思い切り開けよう。男は這って進み石を手にする。アファンデに投げつける石だ。石がこめかみを直撃すると、アファンデはよろめいて崩れ落ちた。 男は前に走り出ると、銃をつかんだ。「動くな!」 そう血を流すアファンデに言う。「声を出したら撃つぞ」 男は震えていた。銃など触ったことがなかった。銃を撃ったこともなかった。銃は嫌いだった。威圧的だからだ。銃口が向けられたら、人は凍りつく。自分を失い、何であれ命令に従うようになる。この十年間、銃は男の暮らしの一部だったにもかかわらず、ひとたび我が手にそれを持てば、手に汗をもたらす存在となる。引き金をひいて自分が誰かを、あるいは自分を殺してしまうことを、そして捜索者たちをそれで脅すことを恐れた。 「頭をさげろ」 声を抑えて男はそう命令する。男は恐ろしい銃を降ろし、大きな石を振り下ろしてアファンデを気絶させる。そしてアファンデをさっきまでいた潜伏場所に引きずっていく。アファンデの服を脱がせ、自分が着る。アファンデのブーツには触れず、男は走り出す。足の痛みがひどく、ブーツに足を入れるのは無理だからだ。それに自分の人生で、靴というものを履いたことがない。男は走る。かぶっている帽子が顔をおおっている。 左の方から聞こえてきた声に驚かされる。「ああアファンデ、何か見つかりましたか?」 足音が彼の方にやってくる。またなのか?! いや、服のせいでアファンデと見間違っているだけだ。男は立ちどまり、素早く考える。やって来る男たちを手で追い払い、ズボンの股のところをたたいてみせる。そしてジッパーを降ろそうしているように手を動かす。急いで大きなセタアラの木の後ろにまわって、のぞき見る。警備の男は向こうを向いている。男はまた盗み見る。今度はその男が離れていくのが見える。男は捜索隊にさよならと言う。男は森にさよならと言う。さらに森に、自分をかくまってくれてありがとう、と感謝する。鳥に、ヘビに、サルに、虫に、あらゆる森の生きものに、そして木にも、いたわってくれて、逃避を助けてくれてありがとう、と感謝する。 絶え間ない沼からのカエルの鳴き声に、町の音が混ざり合う。最初は教会の鐘の音。結婚式の鐘のように、ずっと鳴り響いている。それから車の警笛の音。自由の香りが、アファンデの服のいやな臭いを覆い隠す。遠くの方に、花をつけたトウモロコシが、花咲くコーヒーの木々が、踊るバナナの葉っぱが、そして家々が見えてくる。希望の声が、男の耳に響く。この十年間、聴覚を失っていたかのような男の耳にも、よく聞こえる大きな声で。森での潜伏は終わらない戦いのように見えたけれど、もうそれも終わったのだ、そのことが男は嬉しい。彼は走りつづける。こうして家に向っている!
静寂の中を歩いていると、自分の足音が異様に大きく響く。男は静寂より騒がしさの方が好きだった。沼地や森が恋しかった。そこではガアガアとカエルが鳴き叫び、傷ついた心が音で満たされる。男は静寂がいやだった。過去の記憶を呼び覚ますから。過去の出来事が、二度と語られない物語になってくれればと願っていた。この十年間が、心から永遠に消されてなくなることを願っていた。 これは運命だ、運命なのだ。運命が男をぬすっとにした。ぬすっとはいやだ、自分が種を蒔かなかったものを収穫するからだ。囚人とはぬすっとのこと、だから男は囚人たちを憎んでいた。今、彼は自分自身も嫌っている。それは男もぬすっとだからだ。たった一度とはいえ。男はズボンとシャツを盗んだ、そしてそれを広げて乾かした。アファンデの服が疑念を呼ぶかもしれないから。でも男がぬすっとだったのは、たった一度のこと。道を歩きながら男は、家について自分の服に着替えたら、この服は戻そうと心に誓った。もはや囚人ではないのだから、ぬすっとでもなくなるはずだ。 男は右手にキボ川が流れている道へと歩をとった。天気が怪しくなり、空が曇ってきた。太陽の光をどれだけ望んでいたことか、それは自分の影の長さで時間がわかるからだ。川がワッタの森に向う分岐点で、男は立ちどまって耳を傾けた。太鼓の音だ。その音は前方からやってくる。男にはその太鼓の音が何かわかる。あれを最後に聞いたのは、父親が死んだ日のことだ。運命の日が来るたった五日前のことだった。そうだ。あの太鼓は村の誰かが死んだことを告げている。エドナなのか? その考えは男の頭に銃弾のように衝撃を与えた。エドナが死んだ? なぜ自分のことを待っていてくれなかったんだ。近くのジャックフルーツの木をつかんでからだを支えた。「帰るんだ」 すぐに自分に言い聞かせる。「エドナはワッタの森で生き延びた。エドナは出産から生き延びた。なんで彼女が死んだなどと思うのか」 男は木から離れ、先を急いだ。川が大きく湾曲しているところをまわったとき、のどが乾いていることに気づく。ジャックフルーツの木のところまで戻り、その葉を一枚むしって川の水をすくった。冷たい水で男の生気はよみがえった。男は急いで川の縁の湾曲した道を行き、大きな舗装道に出る。
家や畑が目の前に現われた。村は夜におおわれている。男は歩き、満月に感謝する。自分の影で今が夜の九時だとわかるからだ。誰にも出会わない。農園に忍び込む若い恋人たちも見かけない。そうだ、ここは自分の故郷、ブリジだ、夜の九時にはみんな眠りにつく村だ。男は故郷に今いる。 自分が故郷に今いると思うと、男の顔には笑みが浮かんでくる。泥と編み枝でできた家々が十年前と変わらず立っていて、コーヒーの木やバナナ農園に囲まれている。敷地はとても広く、コーヒーを乾燥させるのに充分な場所がある。家に近づくにつれ、さっき聞いた太鼓の音は消え去っているのに気づく。あれは自分の頭に響いていただけの幻覚だったんだ、とわかる。 家は静まりかえっている。コーヒーの花の甘い香りが漂い、今は開花のときだと男は思い出す。刑務所にいなかったら、この二、三ヵ月のうちにコーヒー豆を収穫しているはずだ。 隣りの家が近づく。男は立ちどまり、この先のことを想い気をもむ。どうやってあの不運の夜に借りたムカサの自転車を、返せばいいのだろう。男はこれから起こることの一瞬一瞬に打ち負かされながら歩いていく。敷地の向こうのムカサの家から、灯りがもれているのがわかる。ムカサの家はいつも遅くまで起きている。よかった。十年間の不在にもかかわらず、何も変わっていない。 敷地への入口のところで、男は立ちどまる。入っていってムカサに会いたいという衝動は強く、それと葛藤する。エドナこそが、ブリジの村の最初に会うべき人じゃないのか。二つの影が家に入り、ドアが閉まるのを見ている。 男は口元を大きく緩めて笑顔で歩みを進める。自分がドアをノックするのを思い浮かべる。エドナが起きてきて、どなたですか、と低い声で訊く。柔らかでなめらかな声だ。エドナの声は柔らかでなめらか。彼女を驚かさないためには何と言えばいい? エドナがドアを開け、自分たちの子どもが母親のスカートにしがみついているのを思い浮かべる。エドナは灯油ランプに手をのばし、彼の顔をまじまじと見て、目をパチパチさせ、自分が見ているものが本当なのか確かめるだろう。 男は急に立ちどまる。自分の家はどこだ? ムカサのコーヒー農園の隣りにあるはずだ。男は確かに農園がそこにあるか、首をまわしてじっと見る。うん、ある。真ん中には二本のムシジの木がそびえている。男は向き直る。壊れかけた家をおおうように伸びる、ゾウ草しか見えない。 男は目を満月に向け、悪態をつく。荒れ果てた自分の家を照らして、男をあざ笑っているみたいだから。家には屋根がなかった。どれだけ苦労して花嫁のためにトタン屋根の家を建てたか、よく覚えている。木のドアと窓が一年分の貯金を使い果たしたことを、泥レンガを汗を流してつくったことをよく覚えている。彼が花嫁のためにつくった我が家は、どこへいってしまったのか。花嫁はどこにいるのだ。子どもはどこにいる。それとも自分は場所を間違えているのか? 男は数メートル前に進む。魚をいぶす場所だったところが、マトブの薮になっていることに気づく。 男は身をかがめて顔をおおう。その場にしゃがみこんで、長いこと動かない。 カサカサという薮の音で驚く。男はじっとしている。くんくんと鼻を鳴らす音が薮の音に混じる。男は死にたいと思う。薮で動く何かに身を捧げたいと願う。それがライオンだったらと願う。エドナがどこかに行ってしまった(多分再婚して)と知るくらいなら、死んでしまったほうがましだと思うから。 カサカサという音は近づいてくる。男は自分が死にたいとは思っていないことに気づく。身をかがめ息をとめる。カサカサいう音は近づいてくる。あわてふためいた頭で最初に考えついたのは、ムカサの家に逃げ込むことだ。立ち上がると、寄ってくる生きものに脅しをかける。その生きものはキーキー声をたてながら、逃げていった。豚だ! 男は立ち上がると荒れ果てた家に再び目をやる。「変わってしまった」 ムカサの家のほうに戻りながら、男はそう口にする。
「カト」とムカサがつぶやく。「カトは死んだ。十年前に殺されて、、、あいつはいなくなった」 「家に入れてください、ムカサさん。説明しますから」 ムカサはランプに手を伸ばし、男の顔をまじまじと見る。「カト、、、」 ムカサはそう口にしたものの、それはささやくような声だ。「おまえか? どこで、、どうして、、、どうやって、、、」 ムカサはランプを元の場所にもどし、寝室から出てきた妻の方を見る。「ここにいるのは、あのカトだよ、生きていたんだ。村に戻ったんだ!」 ムカサは大きくドアを開けると、竹の椅子に手を伸ばす。 「ええ、わたしですよ」 カトはニッコリする。ムカサはカトのことがわかったのだ。さあ、男は今度こそ妻のことを知らねばならない。「教えてください、ムカサさん、妻はどこですか?」 「水と食べものを持ってきてあげなさい」 ムカサが妻の方を向いて言う。「ああ、ちょっと待った。まずは瓜のカップでトントだ。口が渇いているだろうからな」 ムカサは妻の前を横切り、隣りの部屋へ走り込みながら言う。「そうさせてくれ。カトが戻ったんだ。彼は生きていた」 「ええ、わたしは生きてます。戻ったんです」 カトの顔から頬笑みが消え、不安な顔になる。ムカサは自分の質問を避けようとしている。カトはムカサのすわっていた椅子を見つめる。 「さあ飲んで。おまえにはこれが必要だ」 ムカサが戻ってきた。 「どうもありがとう」 カトは瓜のカップに手を伸ばし、それを飲み干す。「ぼくの妻は、、、」 酒にむせて、カトは咳き込む。しばらく咳き込みがつづいて、隣りの部屋の寝ている子どもたちを起こしてしまいそうだ。「すみません」と言いながら咳をする。 「さあ、これを飲んだほうがいい」 ムカサがトゥンペコ(マグ)に入った水を渡す。 「ありがとうございます」 カトはトゥンペコに手を伸ばし、水を飲む。「妻は、、、」 水にまたむせそうになる。 「さあこっちも」 ムカサは妻が持ってきた食べものに手を伸ばす。「これを食べて。食べたほうがいい」 ムカサは妻のほうを向くと、「二人だけにしておくれ、ナバロンゴ。おまえは休んだ方がいい」 「食べますよ、ムカサさん。でも教えてください、ぼくの妻は、、、ぼくの妻は、、」 「奥さんは元気だ。息子さんもな」 「息子、、」 カトは十年分くらいのため息をつく。そしてガタンと椅子から立ち上がる。「ぼくの息子、、、会えるんだろうか、、、子どもと妻に」 「まず食べて、カト、食べてからだ」 「わかってます」 カトは座ると、蒸したカッサバと魚のくんせいにかぶりついた。食べている途中で、口をやすめて考える。妻は生きている、でもまだ一人でいるのだろうか? 「妻は今も一人ですか?」 口の中をいっぱいにしながら、そう訊く。ムカサの表情が曇り、カトは心配になる。心配でどうにかなりそうになる。皿を持ったまま立ち上がり、それから椅子にどさりと崩れ落ちる。椅子がギシギシと音をたてる。ムカサの顔から目をそむけ、食べかけの皿に目をやる。 「食べなさい、カト。食事を終わらせて」 カトはカッサバを一切れとって、それをかじる。そして飲み込もうとするが、のどに詰まって飲み込めない。カトは水をすする。苦い。「ぼくは連れ去られたんだ」 半分飲んだトゥンペコを見ながら言う。「無力な彼女を置いていった。陣痛の苦しみにあった彼女を。ワッタの森の真ん中に」 「カト、まずは食べなさい。奥さんも子どもの元気なんだから。話す時間はたっぷりある。今は食べることだ」 「二人はどこなんです? 一つだけ教えてください、彼女は今も一人でいますか? ぼくは刑務所にいたんです。地獄です。彼女に会いたくて、彼女のために逃げてきたんです。彼女への愛があったから、何とか逃げられたんです。僕を拉致した、あのやつらめ。僕は無力な彼女を置き去りにした、、、エドナは一人ですか?」 カトは皿を置いた。 「カト、ものごとは変わる」 ムカサは歯ぎしりして深いため息をつく。「ものごとは変わる。子どもが生まれ、子どもが大きくなり、人は死ぬ、、、人は結婚もする」 「ぼくの妻は結婚しているのですか? ムカサさん」 カトが勢いよく立ち上がり、ムカサの前にひざまずくと、食べかけのカッサバがカトの手からこぼれ落ちる。カトはじっと耳を澄ます。恐怖が立ちのぼる。痛烈な恐怖、死に至る恐れ。心臓が引き裂かれるような痛みが何度も襲う。カトは震えている。からだは熱く燃え上がり、汗が滴り落ちる。息が荒い。心臓が早鐘をうつ。「エドナは結婚してるのですか?」 「いや、まだだ、カト」 ムカサはカトを椅子にすわらせる。「息子よ、わかるだろう、もっと別なことをおまえに言えたならと思うよ。でもおまえは知る必要がある。エドナは待てるだけ待った。今、結婚式が準備されている」 カトは自分の耳をたたく。今ムカサが言ったことは、これまでの人生のどんな言葉よりはっきり耳に届いたが、まだ自分がそれを聞いたことが信じられないのだ。納得するにはもう一回聞かないことには。でももう一度聞きたいかと言われれば、聞きたくもない。カトは死にたいと思った。拉致されて、刑務所に入れられたいとさえ思う。そして永遠に出てこないのだ。もう耳にしないために、聴覚を失いたいとさえ思う。が、もう彼は聞いてしまった。エドナ。彼女の結婚式はもうすぐなのだ。これがぜんぶ夢で、目を覚ませるものならと思ったが、これは現実なのだ。夢ではない。ムカサは彼の向かい側にすわっていて、妻は結婚の準備をしていると言ったのだ。 「結婚式」とカト。結婚式、この言葉が、まだ真実に直面していないカトの心を引き裂く刃物になった。「結婚式」 カトは涙をためた目をムカサに向ける。「十年も。そんなにも長い間、会えなかった、、、」 涙がカトの目にあふれる。男は泣いていた。が、すぐに涙を抑えるとこう言った。「彼女には何も言えない」 「エドナはおまえが死んだとは、まったく信じようとしなかった。そう思っていたのは彼女だけだ。いつか戻ってくると言いつづけていた。いつもな」 ムカサが言う。 「結婚式はいつなんです?」とカトが訊く。ものごとは変わる、本当にいろんなことが変わった。エドナの結婚式がこれからあるなら、自分も変わってしまうということか、それが恐かった。「いつエドナは結婚式をするのです? ムカサさん」 「すぐだ。今日が金曜、エドナは日曜に、故郷の村の金持ちのイスラム教徒と結婚することになっている。結婚式は日曜日だ。カト、わたしの親しい隣人であり息子のようなおまえに、別のことが言えたならと思うよ。でもこれが真実なのだ」 「ムカサさん、ありがとう。本当のことを言ってくれて。それが知りたかったんです。エドナに会う必要があるのと同じように、その真実はぼくに必要です。エドナの美しい姿が永遠にわたしから失われる前に、妻に会わなければ。彼女にあやまるために。自分が犯していない罪のことを、彼女のために逃げてきたことを言ってあやまらなければ。彼女のことを恋しく思っていたことを言うために、彼女を愛していることを、息子とともに二人がかけがえのない存在であることを言うために。そしてこれからもずっと彼女を愛していることも。エドナは今どこです? 朝のうちに彼女に会いに行きたい」 「家にいる。彼女の両親の家だ。一年前にエドナはここを去った。彼女が希望したことではない。おまえの親戚が追い出したのだ。だけど家はそのままほっぽってあるがな」 「もう荒れ果てた家は見ましたよ、ムカサさん。見ています。わたしの親戚、、、」 カトは最後に自分の親戚のことを考えたのがいつか、思い出せなかった。親戚たちはカトを嫌っていた。それは妻のことばかり、男が気にしているからだ。あの人たちは愛が何かを知らない。あの人たちは、彼にとってエドナがすべてだということを知らない。そして今、彼らは、カトがまだ見ぬ息子以外のすべてを失ってしまったことを知らない。「もう一度彼女に会えたなら、それから息子にも、それだけが願いだ。親戚たちはどうでもいい」 「そうだな、おまえには、、、彼女に会う権利がある。だが今は、少し休んだほうがいい」 「そんなことはいい、カト。自転車はなくなったが、おまえは戻ってきた。それが大事だ」
カトが道をゆくと、一番鶏が鳴いた。ムカサの茶色のスーツは似合っていなかったけれど、なんとか役を果たしそうだ。盗んだ服を返さなければならないことを、カトは忘れてはいなかった。自分の傷だらけのやせたからだ、剃った頭、不健康な顔色、自分の容貌は自覚していた。顔にぬったサモナジェリーの効果はなく、手で皮膚にさわると皮膚が剥がれ落ちた。エドナは一秒でも、彼に目をとめるだろうか? カトは自分のもろさに気づいていたけれど、ことを進めなければ。マトブの薮に縁どられた上り坂を歩いているとき、自分はエドナをあきらめられるほど強くはないとわかった。エドナにさよならなどと言われたら、その場で死んでしまうかもしれない。 エドナの家への道が、燃えさかる火のように目の前に立ちはだかる。朝の太陽があらわれる。カトは立ちどまり、頭の上を旋回するツバメの群れに目をとめる。ツバメたちは互いに空を行き交い、それは声をかけあっているのか、それとも互いの状態を確かめあっているのか。カトは自分もその一員になりたいと思う。そうすればこれから起こる心を切り裂かれるような体験をしなくて済む。愛する妻の結婚式という苦難。カトはひざを落とし、道にしゃがみこむ。なぜ運命はこんな風に自分の元にやってきたのだ。どうして自分は生まれてきたのか。自分が逃げてきたのはなぜか。 モーという牛の声でわれに返る。なんとか努力して立ち上がる。カトは歩き始める。エドナの家に近づくと、自分の足がしっかりとからだを支えていてほしいと願う。心が穏やかでいることを願う。からだじゅうの水分がなくなることを願う。そうすれば汗をかくこともない。今だけ。たった一度、今だけでいいから。 最初に入口に現われたのは、年老いてしわにおおわれた女性だった。そのしわの顔の持ち主は、くわを手にしていた。エドナの母親だ! 母親は口をあんぐり開けて、彼を見つめた。手の中のくわが足元に落ちる。台所から別の顔が現われた。エドナの妹だ。カゴの中の揚げ落花生を選り分けながらやってくる。カトに目をやった瞬間、カゴを落とす。妹は声を上げて言う、「幽霊よ、カトの幽霊!」 カトはその場に立っている。さらにいくつかの顔が現われる。いくつかの声が重なる。「カトの幽霊!」 いくつか顔の中に、(彼が想像するに)十歳くらいの少年の顔があった。間違いなく、彼の息子だ。祖母のスカートにしがみついている。息子だ。一度も目にしたことのない彼の子ども。その子はエドナのまるい顔をもっている。「息子よ、わたしがきみの父さんだよ」 そうささやく。前に進み出て抱き上げたいと、カトは思う。 別の声が彼を驚かす。そちらを向くと、それはエドナではなく、エドナの叔母だった。この人たちは結婚式のために集まっているんだ、と気づく。家の中に次から次へと現われ、動きまわる人々を見つめる。カトは目をさまよわせる。エドナがいない。もう結婚式は終わったのか? ムカサは勘違いしていたのだ。聞き間違えていたのだ。エドナはもうここから出ていったのだ。 エドナが現われる、まるで彼にだけ見える天使みたいに。緑のキテンゲをまとい、それに合うスカーフを頭に巻いている。大きな目をくるくるさせ、彼を見る。二つの目が彼の目の中に光を放つ。その輝きは、彼が暮らした十年間の闇を光でおおう。エドナのまるい顔。柔らかなからだの線。彼女に腕を巻きつけられたときの温かさを思い出す。エドナが頬笑む。エドナが笑うと、前歯のすきまが見える。エドナが笑うと、彼のひび割れた心がなめらかになる。エドナが笑うと、この十年間の過去が心から消されていく。エドナは彼が考えうることのすべて。エドナは彼が目にできるもののすべて。エドナ、それは彼の花嫁であり、妻であり、息子の母。でも、エドナの結婚式は近づいている。 エドナは彼の方に、腕をひろげて歩いてくる。エドナは彼の腕の中に向ってくる。カトは彼女をふたたび感じようとしている。彼女は彼をふたたび愛そうとしている、、、、。 今、彼はエドナの腕の中にいる。涙が彼女のキテンゲに溶けていく。彼女の涙も彼の借り物のスーツに溶けていく。男は彼女を抱きしめ、それは永遠のものとなる。彼は息を吹き返した。彼は生を取り戻した。エドナは今、彼の胸にいる。もう絶対に彼女を離さない。もう彼女を一人きりにはさせない。エドナが美しい顔を上げて、彼の目をのぞく。そして言う。「今わたしがしたいことはたった一つのこと。世界中の人たちに言いたい、わたしの結婚式は取りやめになります。わたしの夫が戻ったんです!」
男は口元に頬笑みを貼りつけたまま目を覚ます。頬笑みはしぼみ、涙があふれる。男は囚人たちに囲まれて寝ている。ボロ布のような毛布は、腰のところまでしかない。脚が冷たい。部屋の隅から咳き込む声がもれてくる。それが咳の連鎖を呼ぶ。しけた巻きタバコの臭い、刻みたばこ、小便や汗、それからあれだ、部屋の奥にあるバケツからの悪臭はそのせいだ。警報のジリジリンという音が男を驚かす。声が響く。「アムカ・トゥエンデ・カジニ!(起きて仕事につけ)」 涙があふれた。あれは夢だったのか?
|
||||