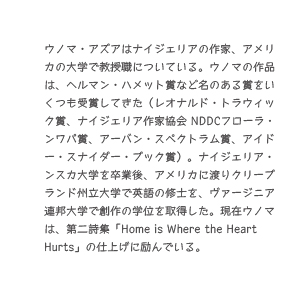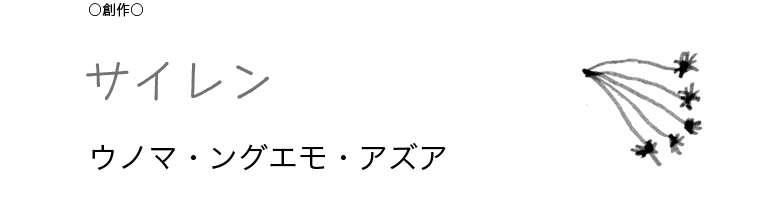
|
ブルークという文字が、濃い緑の標識に白い太文字で書かれているのが見えた。カイトは家の番地を確かめようと、住所録を繰った。ブルーク1437番地。通りを見まわすと、1431番地の家があった。1437番地ではない。カイトは早足でさらに歩を進めた。通りの両側の家々は木におおわれていた。木々は空にのびていくお城の塔みたいで、家々のきれいに刈られた芝は鮮やかな緑色をしていた。鳥の鳴き声をのぞけば音はなく、ひっそりとしている。カイトの故郷とは大違い、カイトの住む小さな町でさえ日中のこんな時間には、どの通りも歩きまわる人々の群れ、散在する人影、おしゃべりする人がうじゃうじゃいて賑やかで騒がしい。小さな風がカイトの頬をなでていった。カイトは十回も住所を見直し、家の番地を何度も確かめた。でも1437番地はない。カイトは少し心配になってきた。午後は夕方に変わりはじめていた。近くの家に立ち寄って聞いてみようとカイトは決心した。白い大きな家はツタでいっぱいにおおわれいた。玄関につづく通路は、壊れた自転車のパーツが散らばり、カイトはそれを踏まないようにして玄関のドアに近づいた。ツタのつるがドアのすきまや蝶つがいにまでからみついていた。カイトがドアをノックしようとして手を伸ばしたとき、スプリンクラーが作動して勢いよく水が噴出しはじめた。カイトはびっくりした。水は大きな弧を描き、あたりの芝や花に水を撒き散らした。胸の鼓動が治まってから、カイトはドアをコンコンとノックした。六歳くらいの男の子が、玄関のそばの窓からこちらを見て、消えた。カイトはもう一度、小さくノックした。頭の上で窓がギシギシと開いて、頭のはげた中年の白人の男があらわれ声をあげた。
「何かようか?」 「すみませんご主人、ブルーク1437番地の家を探してるんです」 「なんだって、ここはブルーク1437じゃないぞ。東サイドに行ってみろ」 「わかりました。ありがとうございます」 「どっから来たんだ? その英語はどこのもんだ?」 「ナイジェリアから来ました。アブダという名の兄さんに会いに来たんです」 「あー、アフリカね。南アフリカに一人友だちがいるよ。そいつはズールー族の踊りの面白いテープを集めてるんだ。そのグループ知ってるか?」 「いえ」 「そうか。東サイドはここから歩きだと少しあるから、この通りを端まで行ったらG5かレッドラインに乗っていけ」 鉄道駅はさびれていた。カイトは食べものを思い浮かべて生つばを飲み込んだ。電車がやって来ないかと、伸びていく線路の照り返しを目で追った。空港に降りたったときから、行く先を定めるのに苦労していた。掲示板の案内はわかりにくかった。空港のラゲージ・エリアに着いて自分のカバンを取ると、そこから先どっちに行っていいのかわからなかった。あたりを何度もうろつきまわったあげく、十代の少年に助けを求めた。その少年は方向が同じだからと言って、カイトといっしょにダウンタウンまでの道を歩いてくれた。そんなことを思い出していると電車が近づいてきたので、カイトは頬をゆるませた。 東ブルークの住宅地は、ブルークと比べると上等とは言いがたかった。多くはくたびれた長屋式の家並みか荒削りなレンガ造りの家で、大きさもせいぜい並程度。子どもたちが通りで遊び、上半身裸の男たちがバスケットボールに興じている。雰囲気はカイトの故郷のようで親しみが持てた。カイトは東ブルーク1437番地のドアをノックすると、ほっとした気分になった。少しして、ドアのところから女の声があがった。「誰なの?」 カイトが答える。「ぼくです、ナイジェリアから来たアブダの弟です」 白っぽい肌色をした五十半ばの婦人が、チェーンをかけたドアを半分開けて顔を見せた。その人が再度訊ねる。「誰ですって?」 カイトはこの女の人が黒人なのか白人なのかわからなかった。モップのような髪が顔を半分おおい、タバコの煙をふかしていた。
「カイトです。ナイジェリアから来たアブダの弟です」 「誰って?」 「アブダの弟です」 カイトはまた言った。 「ああ、アブダはもう死んだわ。ここにはもう住んでないの」 「死んだ? いつ?」 カイトが訊いた。目を大きく見開き、首のところの血管が浮き上がっていた。
カイトは右手を胸に置いた。心臓が飛び出してきそうにドクドクと打っていた。アブダが死んだのなら、それはどんな風だったのか。道端で寝るようなことになり、殺されたとか。カイトは故郷の家にいるとき、銃や暴力に満ちたアメリカ映画をたくさん見てきた。俳優たちは考えることなしに、銃を放っていた。もしカマルとも会えなかったら、カイトはどうなってしまうのだろう。それにどうしてアブダの亡きがらは家に運ばれなかったのか。長男であるアブダは、先祖の墓に埋められるはず。見知らぬ国ではなくて。そんなことはあってはならないはずだった。カイトは自分の手の平がじっとり汗ばんでいるのを感じた。「アブダにいったい何があったんです? なんで死んだんですか?」 カイトが訊ねる。
「あたしにとって死んだっていう意味。何ヶ月か前に追い出したのよ」 「じゃあ、どうやってアブダを見つければいいんでしょう?」 「知らないわよ!」 「すいません、奥さん、水を少しいただけますか、それとほんの少し休ませてもらえれば。お腹がすいてくたくたなんです」 「冗談じゃないよ! あたしはあんたなんか知らないからね」 「ぼくはアブダの弟です」とカイト。湿った手を旅行カバンの中につっこむと、アブダの写真を取り出して婦人に見せた。 「ああ確かに、アブダだわ。でもアンタがあたしんとこから何か盗もうっていう、贋くそったれアフリカなまりの贋くそったれニガーじゃないって、なんでわかる?」 「お願いです、もしどこに行けばアブダに会えるのか教えてくれて、ほんの少し休ませてくれたら、ぼくはすぐ出ていきます。約束します」
女は躊躇していたが、ドアチェーンをはずした。カイトは中に入った。リビングルームはタバコの煙が漂いけむっていた。カイトは軽く咳き込んで、ドアのそばの革の長椅子に腰かけた。長椅子のそばには、小さなテーブルがあり、コーヒーの染みのついたマグが五つ置いてあった。床にはひっくり返った灰皿が一つ。
「何か飲み物をいただけますか?」 「ソーダでいい?」 「ソーダ?」 カイトはとまどった。ナイジェリアではソーダは石鹸の一種。婦人はカイトの困った顔を見て、コカコーラの缶を投げてよこした。それをカイトは空中でつかみ「ありがとう」と言った。 「残ったチキンがあるけど。それからあたしはエイプリル」 フライドチキンの入った大きな容器をカイトの前に置いて婦人は言った。バケツ型容器の側面いっぱいに、赤い太い文字でKFCのマークがあった。 「はい、ありがとうございます」 カイトはこんなにたくさんのチキンが、いっぺんに出てくるのをこれまで見たことがなかった。 「じゃあ後は自分で。二階に行ってアブダの友だちの電話番号を探してみるから。アブダの居場所を知ってるかもしれないからね」
カイトはチキンを最後のひと切れまできれいに平らげて、コーラをガブガブと飲み干した。げっぷをすると満足げに長椅子にもたれかかった。そのときお腹に鋭い痛みが走った。カイトは両手で腹をつかみ、痛みに耐えた。大きなおならをひとつすると、急にトイレに駆け込みたくなった。「エープリル! トイレはどこ?」 カイトは二階に向かって叫んだ。 「右側よ」 カイトはトイレの座席に排泄物を撒き散らす前に、かろうじてパンツをおろした。カイトは座るとすべて出し切るまで身をまかせた。ひどい臭いが立ちこめた。カイトは終えると、窓枠のところから芳香剤の缶をとりスプレーしようとしたが、中は空っぽだった。トイレットペーパーを長く引き出し、トイレの座席を拭いた。便器のふたをしめる前に、数回トイレの水を流したが、臭いは消えなかった。
「ちょっとぉー、何なの、この臭いはー」 エイプリルが階段のところから、顔をゆがめてどなった。 「あのー、トイレです」 「何? あんたなの? 出ていって!」 「ごめんなさい」 「このくさいアフリカのケツ持ちは出ていって! このクソったれが」 カイトがあやまっている間、エイプリルは乱暴に家じゅうの窓を開け放った。玄関のドアは開けたままにして、椅子をひとつ外に引っぱり出した。 「ほんとにゴメンナサイ」 「あたしんちから出ていかないと、おまわりを呼ぶよ、この小僧」
カイトはおびえた。どうしてなのかわからない、なんでうんこの臭いくらいでこんなに怒るのか。カイトは歩道を早足で歩いた。もしこれがナイジェリアの家なら、笑いのめすくらいのことだ。家ではカイトがいる前で、家族の誰かがおならをするのだって自由だ。カイトの父が大きなのをぶっ放すと、母親はそそくさとどこかへ行き、また戻ってきて父親を叱りつける。まったく問題になることじゃなかった。父親はあとであやまったかもしれないが、おならやうんこが臭いからといって、放り出されるなんてことはなかった。誰もそんな目にあわない。神さまは人間の世界に、おなら用の部屋はつくらなかったわけだし。それにトイレは母屋のすぐそばだから、いつだって排泄物の臭いはあたりに漂っている。でも誰も文句なんか言わない。カイトは心乱されていたけれど、カマルを(できればアブダも)探しに行こうと心に決めた。 失意のうちに、カイトはダウンタウンへとなんとか戻った。27番のバスを探していたが、カイトは見つけることができない。27番バスというのは、駅の料金所で教わったクウェンティン大学へ行くためのもの。バス停でカイトがバスの時刻を訊いた人たちはみんな、聞こえないふりをしたり知らんぷりをした。その人たちはたいてい中年の人だった。カイトは生まれて初めて、人々が集団で何か叫んでいる光景を見た。その人たちはT字路のすぐ脇にある、庭のような場所に集まっていた。カイトは急いで道を渡ると、庭に入っていった。キリスト教伝道者の人々が、拡声器で世界の終わりについて大声で語っているのをカイトはじっと見つめた。ハトの群れがパッと飛びたった。カイトのそばには、水がほとばしる彫像が立っていた。噴水の水は止むことがなかった。噴水の水場の底には、硬貨がきらめいていた。二十分くらい説教を聞いたのち、カイトは伝道師のそばに立っている男たちの中の一人の肩をたたいて道を訊いた。カイトはその人が何と答えたのか、ほとんど聞きとれなかった。探しているのは27番バス。カイトは歩道のそばに寄って来て停止した、隣りのバスの方に駆け寄った。それが27番バスだった。カイトはそれに乗ると、運転手にクウェンティン大学に着いたら教えてくれるよう頼んだ。
カマルの寮は四階建てのレンガ造りの複合棟の中にあった。カイトがロビーに入ると、コーヒーの香りが漂ってきた。受付にいた白人の女性が、何か御用ですか、と訊ねてきた。その人はにっこりと愛想よくほほえんだ。黒い髪をブルーのひもでポニーテールに結び、ほつれ毛が耳のところにいく筋か垂れていた。女性はカマルをこのところ見ていない、とカイトに告げた。カマルの部屋に電話してくれたが、誰も出なかった。女性が言うには、カマルは町を出ていない限り、普段は夜九時には戻ってくるとのこと。カマルは夏の特別授業を受けるために、南の方によく出かけるとも言った。
カイトはこぎれいに整えられたロビーに座って待った。巨大なテレビ画面で映画をやっていたが、カイトは見る気がしなかった。もしカマルが戻らなかったらどうしよう。カイトは心配する。少しして、受付の女性がコーヒーカップを二つ手にして、カイトのところにやって来た。女性の白いカップの縁には、赤い口紅がべったりとついていた。化粧した顔の下から、しわがかすかに透けて見えていた。 「名前は、なんだっけ?」 「カイトと言います」 「コーヒーは?」 「いえ、けっこうです」 「旅の疲れをいやすと思うけど」 「そうですね、ありがとう。あなたのお名前は?」 「ベスよ」 「カマルは町の外に出かけているんでしょうか?」 「そうねぇ、ここ二、三日、姿を見てないのよ。カマルとどういう関係?」 「カマルは兄さんなんです、、、、ぼくの村からやって来た」 「カマルはあなたが来るの知らないんじゃないの?」 「携帯にメールを送って、伝言も残してあるんだけど、返事が来る前に航空券をとりあえず買ったんです。旅行ビザがもう切れてしまうんで」 ベスの視線がカイトの腕の筋肉に据えられた。「あなた、いいからだしてるのね。運動選手かなにか?」 「いいえ」 「あんたとカマルはどこから来たんだっけ?」 「ナイジェリアです」 「村の名前は?」 「ぼくの村の名前はイウといいます。写真、見せましょうか」 カイトはカバンから写真を数枚取り出した。 「この写真のあんたが釣りしてる湖、きれいだわね」
二人が写真を見ながら過ごしているうちに、真夜中を少し過ぎた。ベスの勤務時間は終わっていたが、カマルの気配はなし。ベスはカイトと共に待った。十二時半をまわっても、カマルは現われなかった。そこでベスはもう家に帰ると言った。 「このあたりに安いホテルはあるでしょうか」 「安いってどれくらい?」 「有り金全部で70ドルしかないんです」 「それじゃあ、一晩以上は無理ね。じゃあ、こういうのどう? 50ドルくれたらカマルが戻ってくるまであたしのアパートで寝泊まりしていいわ。でも誰にも知られないようにね。アパートの管理人が誰か置いていると気づいたら、あたしが追い出されるから。あたしにはカイルっていうルームメートがいるんだけど、その人はしばらくいないの。一学期分、仕事を休んでてね」 「それでいいです、感謝します。ありがとうございます」
ベスの赤いトヨタカローラの中は、紙くずや破れた本、空の紙コップ、タバコの吸い殻が散乱していた。ベスは助手席の床の紙くずを拾い集め、カイトに椅子の上にある破れた本を後部座席に投げてくれと言った。そしてダッシュボードの上の四角い口にCDを入れた。大きな音で甲高い音楽が鳴り出した。「ガールズ・オブ・サマーよ。エアロスミスのね」 「あ、はい」 ベスは音楽に合わせて頭を振っていた。カイトはうるさい音楽だと感じて、ベスはいったいこの音楽の何がいいんだろうと思った。でも訊くことはしなかった。二、三分後に、ベスはクルマをアパートの敷地に乗り入れた。そこは静かではあるものの、あまりきれいではない通りから私道に入った先にあった。ゴミの袋があちこちに散らばり、大きなプラスチックのゴミ箱がひっくり返っていた。ベスとカイトはミシミシいう玄関につづく階段を昇っていった。ベスは片手でカイトの背に手をやり、もう片方の手でドアを開けた。リビングルームには片隅にCDプレイヤーとテレビがあるだけで、家具らしいものはなかった。長椅子が一つ、部屋の真ん中に陣取っていた。ベスはビールと「ピーナッツサンドイッチ」と称するものを持ってきた。サンドイッチを食べ終え、ビールを飲んだあと、ベスは小さな紙を出してきてそれに葉っぱを置いて巻いた。そしてカイトに葉っぱを吸うか、と訊いてきた。カイトは迷ったあげく、葉っぱを巻いたものを手に取った。二人は夜明けまでそれを吸った。
目が覚めたとき、カイトはいつ眠ったのだろうかと思った。股間が痛み、自分のパンツが部屋の向こうの隅にあった。カイトはニヤリとした。ベスはいなかった。書き置きがあり、「仕事に出ます。夕べは素晴らしかったわ」とあった。それを見てカイトはにっこりした。カマルやナイジェリアの友だちに、白人のガールフレンドができたんだと言いたくてたまらなくなった。人生で初めて、カイトは白人の女の子と寝た。とても幸せな気分で、ベスと知り合えてラッキーだったと思った。 カイトのそれからの日々は、音楽を聴き、エンターテイメント・チャンネルをあちこち回して映画を見、食べたいだけ食べ、と部屋の中での生活になった。それは「アメリカみたいな感じ」に思えた。たくさんの食べものや香りのいいシャワーに満ち、ストレスもなく電気が突然とまることもない。カマルのことは頭から消えかかっていた。それから何週間かたち、カイトは少し落ち着かない気分になってきた。ベスは食べものとコンドームの箱の補充を切らさなかった。カイトの股間の痛みは消えなかった。無事にこちらに着いたことを故郷の両親に知らせていないことも、気にかかっていた。カマルが夏期講習に行っていると思われる学校に電話するのを、ベスが手伝ってくれた。学校側はカマルは講習を終えて帰ったと言い、それ以上のことは知らなかった。カイトは近所に住むアフリカ人たちを探して、訊いてみようと決心した。ベスの方はカマル探しには、もう興味がないようだった。アパートが何かのワナのように感じられ始めた。ベスはカイトが黙って近所を歩きまわることに文句を言った。見つかると危ない、そうベスは言った。ルームメイトのカイルの代わりにカイトがいることを、アパートの持ち主に知られないようにしなくては、と。
ある日カイトはこっそり外に出て、ベスの家から三、四キロ先のところで一軒の店を見つけ、テレフォンカードを買った。その店の主人はアミンと自己紹介をした。カイトはまだ五十ドルと硬貨をいくらか持っていたが、その硬貨の名前もいくら相当なのかもわからなかった。店は小さかった。あらゆる種類のスナックと食べものを売っていた。そのいくつかはカイトがナイジェリアで見たことのあるものに似ていた。透明の袋に入って、「干し肉」と書かれたものがあった。カイトはそれをしばらく見ていて、これはスヤではないかと思った。トウガラシ味の焼いた肉、ナイジェリアでカイトが大好きだった食べものだ。ココナッツ・チップと書かれたスナックもあった。小さい頃に祖母が作ってくれた、揚げココナッツのスライスを思い起こさせた。店には種々のテレフォンカードも置いていた。ひょろりとした濃いあごひげの男が、店の奥からまゆをひそめながら現われた。カイトが挨拶すると、男は無愛想にああ、と言った。が、カイトがにっこりするとすぐ、表情をくずした。カイトはナイジェリアに電話するには、どのテレフォンカードがいいか訊いた。
「アフリカから来たのか?」 男が訊く。 「そうです、ナイジェリアからです。カイトといいます」 「わたしもアフリカ人だ。ここはわたしの店、名前はアミンだ。モロッコから来た。通りの向こうのクウェンティン大学には、ナイジェリア人の学生が何人かいるな」 「カマルを知ってますか?」 「カマルは知らないが、ナイジェリア人のモモドゥなら知ってる。院の学生で、クウェンティンで修士を今やってる」 二人はしばらく話をし、親交をかわした。カイトが店を出る前に、アミンはモモドゥの住所を渡し、バスを使っての行き方と店までの戻り方を教えた。モモドゥに会えなかった場合に備えて。
モモドゥは打ち解けたところない人だった。モモドゥは研究所のような所にいて、カイトが訪ねていったとき顕微鏡を覗いていた。その場所は風通しが悪く、薄暗かったが、モモドゥの頭の上には照明機器があった。モモドゥはカイトを見ると顔をしかめて黙っていた。カイトが何か訊くたびに肩をすくめ、カイトの質問や言ったことにいちいち「え、何?」とか「だから?」と答えるばかり。ところが、モモドゥが言ったことは驚くべきことだった。カマルは二、三週間前にアトランタから戻ってきている、と。カイトはモモドゥの言ったことが信じられなかった。ベスは違うことを言ったじゃないか。手の平がじっとりと汗ばんできた。カイトはモモドゥにカマルのところに連れていってくれないかと頼んだ。モモドゥはそれはちょっとと言い、二、三ブロック行けばいいだけだと教えた。モモドゥは一つだけ開いている窓の外を指した。カイトは、モモドゥの建物のすぐ隣りといっていいくらい近くにある四階建てのレンガの建物を見て驚いた。
カイトはカマルの寮に行こうと急いでいて、かんかんに怒っているベスとばったり会った。ベスは顔を真っ赤にぎらつかせていた。汗をかいていた。頭にかぶったスカーフは半分ずり落ちていた。 「あたしに無言でなんで出ていったのよ」 「どうしてこうなったか、わからない。ある人がぼくにカマルは帰ってきたと言ってた」 「どこの誰よ。あたしに何も言わないでうろつきまわっていたわけね」 「ごめん。でもカマルが戻ったって言ってくれればいいのに」 ベスはカマルが戻ったことは知らなかったと言った。受付のところからカマルの部屋に電話するのをようやく認めさせたが、カマルは電話をとらなかった。ベスはカイトに部屋の番号を教えた。カマルはカイトがドアのところにいるのを見て、びっくりした。カイトがクリーブランドにすでに何週間もいると聞いて、さらに面食らった。
「いったい今までどこにいたんだ? ここに戻ってきてからすぐ、一週間以上も前、おまえにメールの返事だしたんだぞ。家にも電話したし。何やってたんだ?」 「それがさあ、時間の感覚がないんだ。ベスがぼくを家に置いてくれて。兄さんが戻ったの気づかなかったんだ」 「ベス? ベスって誰だ?」 「受付の人だよ。いい人だ」 「ここに戻ってからベスに会ったけど、おまえのことひとことも言わなかったぞ。おまえ、頭おかしいんじゃないか。あの女は気違いだぞ」 「でもベスは、兄さんに会ってないって言っていた」 カイトとカマルはすわって話をした。カマルがベスについて明かした。あれは売女だ。ヤクをやってて何人もの男とやってる。カイトはカマルの言うことが信じられなかったが、その日にベスのところから荷物をとってきて、カマルのところに来ることを決心した。カマルはそれが簡単ではないことを、ベスのところから脱出するのがたやすくはないことを知っていた。そのようにカイトに言った。でもカイトの答えはこうだった。「あのさあ、ぼく待ちきれないよ、ここで兄さんと暮らしてさ、アメリカドルを増やすんだ」 するとカマルがどういうビザを持ってるんだ、と訊いてきた。それは観光ビザで、たった六週間のものだった。
「まったく信じられないよ。ビザのことをすっかり忘れて、不法に住み込もうなんて。何のために? 二ヶ月もか? おまえはここがナイジェリアだと思ってるのか? 今おまえは不法滞在してるんだぞ。あの女と結婚でもしてない限りな」 「誰と? あの人は結婚の対象じゃないよ。ぼくを夜の相手にしてるだけさ」 「そうやっておまえを利用してたんだよ」 「あの魔女からどうやって逃げる? どうしたらいいか教えてよ。どんな仕事でもするよ。どこかのカフェかなんかで、皿洗いとか床掃除とか、小さな仕事から始めるよ」 カマルはカイトの無知を笑い、社会保障番号や雇用についての法律、猟犬と呼ばれる出入国管理官のことを教えた。カイトは冷たい汗がからだ中から吹き出すのを感じた。カイトには訊きたいことがたくさんあった。カマルの答えはどれも、カイトを困惑させるものだった。 「じゃあ、ぼくはどうしたらいい?」 「さあね。アミンをたよりに始めてみるのはどうかな。もしアミンがおまえを不法にやとってくれたら、ラッキーだけどな」
不安が押しよせ、カイトはパニックになりそうだった。そういう話はナイジェリアではよく聞いていた。カイトはウディにある名のある大学の歴史学科を卒業していた。でも六年間、仕事を見つけることができなかった。最終的についた仕事は、大卒を買ってのことではなく、からだの頑丈さのためだった。カイトはナイジェリアのアメリカ大使館の警備員になった。友だちはみんな、うらやんだ。そこで働くうちに、観光ビザのことで口をきいてくれそうな知り合いがいるという大使館の人と親しくなった。カイトはオハイオにいる姉が病気になって、訪問看護士を雇う余裕もなく、緊急に家族の手助けを必要としている、と嘘をついた。カイトの両親は航空券を買うために、残っている土地を売った。カイトを学校にやるために、以前に三つの土地を売り払っていた。カイトがもっていた70ドルは、友だちが餞別にくれたものだ。アメリカで何も成せなかったなどと家族や友だちに言うことを考えただけで、カイトは胸が苦しくなった。みんなはカイトに、車を家族に買ってよこしたり、家を建てたりするナイジェリア人たちはもっと利口なのかとか、おまえには頭が一つしかないのに、その人たちは二つくらい持ってるってことか、などと訊いてくるかもしれない。でもその一方で、カマルはアメリカに二年もいて、何もなし得ぬまま遅々として日々を送っているではないか、とカイトは思う。
翌日、カイトとカマルはベスの家に荷物を取りに行ったが、ベスは渡そうとしなかった。「あんたは払うべきものがあるのよ、このうすのろ!」 そうカイトにくってかかった。 「支払い?」 「そうよ、支払いよ。あんたが持ちだしたものの代金よ、あたしの気持ちとか、水とか、食べものとか、居場所とか」 カマルがベスにいったいいくらになるのか訊ねた。カイトは唖然としてしまった。数週間いっしょに過ごした好ましい人間が、数時間のうちにモンスターになってしまうとは、信じられなかった。 「1200ドル。それを払うまで、この人はどこにも行けないってこと」 カマルはカイトを脇に呼んで、金が貯まるまでこの女といっしょにいるように告げた。カイトはカマルが車をもっていないことにがっかりした。1200ドルを融通できないことで、カイトは見捨てられる運命におちいる。 「1200ドルためるには、一年近くかかると思う」 「ええっー。でもこの人といっしょにいたら、死んでしまう。それだけは言っとくよ」 「セックスをいやがる男なんて聞いたことないぞ」とカイトの耳元でカマルが笑う。 「おかしくも何ともないよ。野蛮人の襲撃みたいなもんなんだから」 「もしおまえが、六週間かもうちょっと耐えられれば、その先はなんとかなるさ」 カイトの目に涙が浮かんだ。それが溢れそうになるのを感じた。カイトはなんとか押しとどめて地面を見つめた。そして二人で部屋の中に押し入って、荷物をとって逃げたらどうかと言ってみた。カマルは、もしベスが警察に通報したら、直ちに家に送り返されるぞと言うのだった。
ベスは少し離れたところから二人を見ていた。そしてこう言った。「ちょっとー、モカ肌ってのはそう悪くなかったわよー。あたしたちお似合いのカップルになれたんじゃない。あんたが主夫をやってあたしが外で稼いでくるのよ」 カイトはこの女を殺してやりたいと思ったが、それを払いのけた。 ベスへの支払いは一年以上かかった。アミンはカイトに最低賃金の半分しか払う余裕がなかった。カイトはカマルとともに引っ越した。でもベスはまだ、カイトとときどき夜を過ごそうと声をかけてきた。カイトはそれをことわり、早くすべてを払ってしまうことに気持ちを傾けた。カイトは朝から晩まで仕事した。カイトは店番をし、暇な時間にはチキンを揚げ、店のショーケースに並べた。またお昼にかかるまで、コーヒーポットを補充するのを忘れなかった。一年の間に、カイトは体重をずいぶんと落とし、誰ともあまり口をきかなかった。カイトはアミンの店が強盗にあうまで、ずっと働いていた。
それは暑くてじっとりとしたある夏の日に起きた。十八くらいの、頬にそばかすのある白人の若者が店にやって来て、カイトに笑いかけ、箱詰めのビールが入っている冷蔵庫の方にまっすぐ向かって行った。ビールの箱を一つ取り出すと、冷蔵庫の扉をバタンと閉めた。カイトは乱暴なやつだな、と思った。カイトは首をのばしてその男を見ていた。するとその男はカイトをにらみつけた。 「なにこのバカ見てんだよ」 ピシャリと言う。 「大丈夫かなと思って」 「ああん、そうなのか?」 カイトはうなずく。その若い男はずり落ちたズボンを引き上げながら、カイトの方を見もせずに、ビールの箱をレジのそばにドサッと置いた。 「身分証明を見せてもらえますか?」 「なんのために?」 男はそう訊くと、ジャンパーのフードを引っぱって目を隠した。片手でズボンをもちあげ、もう片方の手でサイフを引っぱり出した。カイトが身分証明を見ていると、男は大きなホイル紙を投げてよこした。そしてこれから言う通りにしろ、銃をもってると言った。「そのホイルでカメラをおおうんだ。早く!」 「椅子がいります、ないと届かないです」 カイトはそう嘘を言った。 「できるだろうが、やれっ」 カイトは手を伸ばし、レジの後ろの防犯カメラの画面をおおった。カイトが終えると、若い男はレジの台に近づき、中に入っている金を全部出せと言った。 「それほどありません。ここには50ドルしかないです」 「頭ぶっとばされたいか? そこにある金、全部とってこっちに投げろ!」
カイトはレジを引っ掻きまわし、札束を床に落とした。両手をあげて、男に落ちた金をひろってもいいか訊ねた。男はベンソン・アンド・ヘッジスのタバコの箱をつかむと、カイトに投げつけた。そして下着の下から銃を取り出し、カイトの顔の前で振ってみせた。 「おまえにかかずりあってる暇はない!」と叫ぶ。「いいか、片手で札束を拾っておれに渡せ。おれから目を離すな。もう片方の手は上に上げておけ。余計なことしたら、おまえを殺す」 わずかな時間に、カイトはラゴスのアメリカ大使館で警備員をしていたときに習った防犯手法を思い出そうとした。札束を拾う格好で片手を下ろした瞬間に、カイトは逃げ出した。男はカイトがどこに隠れたのかわからないようだったので、カイトはじっとしていた。カイトは店の奥の扉の後ろに立っていた。扉の音がしたかと思ったら、ドアが開き、銃が放たれた。めくら撃ちだ。男はカイトの叫び声がして、その後静まるのを聞いた。金をそのままにして、男はビールの箱だけもって逃げだした。銃はカイトの右耳の端に当たった。
アミンはカイトを国外追放にさらすのを避けて、警察に届けるようにとは言わなかった。そのかわり、カイトを解雇した。カマルが部屋でカイトの治療をした。カイトが貯めていたお金で、カマルは市販の薬を買った。カイトは両親に、売った土地のいくらかを買い戻せるよう、送金したいとずっと思っていた。 カイトは家の中で過ごすことが多くなり、お金のことを案じていた。そんなある日、カマルがアブダの元妻を訪ねてみるのはどうだろう、と提案した。アブダがカイトに仕事を見つけてくれるかもしれない。カマルはアブダが町のどこかでマグドナルドの店長をしているのを知っていた。でも知っている携帯の番号は繋がらなくなっていた。 カイトとカマルの意に反して、アブダの元妻エイプリルは二人の訪問を喜んでくれた。アブダの友だちの電話を教えてくれただけでなく、アイスティーとコーンブレッドを出してくれた。カイトは食べるのを遠慮したが、カマルは自分の分を食べ、残りを学校のカバンにしまった。エイプリルは、最初にカイトがここに来たときの恥ずかしい出来事には触れなかったが、食べるものには注意した方がいいわよと言った。 アブダはからだの大きい、頭を剃り上げた六十代半ばの男だった。アブダはカイトとカマルを小さなリビングルームに招き入れた。部屋の床には本が散らばっていた。ナイジェリアの大学でやっていた社会学教授の職から、十二年も前に身を引いていたけれど、マクドナルドで働いていないときはいまだに調査したり論文を書いたりしているんだ、アブダはそう語った。カマルがカイトを紹介すると、アブダの顔がほころんだ。 「きみのおじいちゃんを知ってるよ。わたしの大叔父さんの親しい友人だったんだ。わたしが十代の頃、二人に連れられて狩りに行ったよ。きみは何してるんだ?」 カイトはここまでの話を聞かせた。ここ一年にあったことを語った。アブダはカマルに、カイトの居場所探しをちゃんとやっていないことを叱った。モモドゥや他の学内のナイジェリアからの学生に頼むこともできたはずだった。アブダはエイプリルがおどしのメッセージを入れてくるので、携帯を処分したと打ち明けた。「女ときたらまったく。何をしだすかわからん。わたしはついてなかった。近頃は誰もそうだな、だからあまり気落ちするな。何であれ仕事がみつかったら、それをやって、一日一日を生きのびることだ」 そうアブダはカイトに言った。 アブダは自分の管理しているマクドナルドで、カイトが仕事できるようにしようと約束してくれた。でもそのことは他人に言わないようにと注意した。アブダはカイトに一年くらいしたら、町を離れるよう忠告した。跡を追われないように、とくにベスには気をつけた方がいい、と。カイトには頼って行けるような知り合いは、この国のどこにもいないとカマルが言うと、そのときが来たら、カリフォルニアにいる自分の友だちが助けてくれると思う、とアブダは請け負った。
家への帰り道、カイトは嬉しくて飛び跳ねた。カイトは今持っている300ドルを両親に送ろうと決めた。新しい仕事が始まれば、いくらかお金が貯められると思ったからだ。仕事始めの日に、お金を送ろうと思っていた。その日カイトが仕事に出ようと準備をしていると、ドアが突然ノックされた。ベスだった。カイトは口から心臓が飛び出そうだった。ベスは妊娠したことを告げるためやって来たのだった。中絶するのにお金がいると。カイトは持っていた皿を落としてしまい、カマルの方見て、それからベスに視線を戻した。ベスの黒いブーツはひざのところまであり、ブーツと白いミニスカートの間から白い肌が見えていた。カイトはドアのところに駆け寄ると、ベスの髪をつかんで部屋に引っぱり込んだ。そしてベスの顔をピシャリと打った。さらに打とうとしたとき、カマルがカイトをベスから引き離した。ベスが金切り声をあげた。カマルは走っていってドアを閉めた。
「おまえは狂ってんのか?」 カマルがカイトに声をあげた。「おまえ気でも違ったか? ここはナイジェリアじゃないんだ。おれらの生活をダメにするつもりか」 ベスが泣きながら床から立ち上がり、ドアの方に向かった。カマルがそれをとめ、頼み込んだ。カマルの頬に涙がしたたり落ちた。カマルはひざをつき、ベスに訴えた。ベスは中絶のためのお金を請求し、それからカイトから暴力を受けたことを訴えるとも言った。カイトはカマルの涙を見て、自分のしたことの重大さを認識した。カイトもベスにあやまりを入れ、持ち金全部を渡すと申し出た。カマルも、ベスに許してもらうためにいくらかを足すことになった。ベスは手術代を払い終えるまで、何回でも来ると告げた。
その夜、カイトは悩み疲れ果ててマクドナルドにやって来た。アブダには何があったか言いたくなかった。自分の心に収めておこうと決めた。アブダはそれでも何か察したようだった。カイトは指示されたとおり、グリルを掃除し、調理場をきれいに片づけた。アブダはドライブスルーのところで注文を取っていた。カイトはカウンターのところで注文が来るのを待っていた。このマクドナルドは、ラゴスにあるスイートセンセーションという名のファーストフード店と、ほとんど同じデザインだと気づいた。子ども用の区画も、ラゴスにあるものとそっくりだった。ただナイジェリアには、ドライブスルーというものはまだなかったのだが。
二、三時間して、アブダはカイトにちょっとここを変わってくれ、と言った。トイレに行くのだった。アブダはなかなか戻ってこなかった。痩せて背の高い、金髪のロングヘアの女性がやって来たので、カイトは注文カウンターの方へ駆け寄った。その人は四十代くらいに見えた。カイトは自分の英語のなまりを聞かれるのが恥ずかしかった。カイトの方にやって来た女性は、まゆをひそめ、目をぎらつかせていた。カイトは腹の底にずっしりと重いものを感じた。まっすぐに背を伸ばすとカイトはこう言った。「マクドナルドへようこそ、何にいたしましょう」 「うるさいわね、店長を呼んでちょうだい」 「奥さん、落ち着いてください」 カイトはやっと言った。 「あたしがぶん殴る前に、とっとと呼ぶんだよ」 「すみません」 カイトは小さな声で言って、アブダのところへ急いだ。 「いらっしゃいませ。わたしはAB・マーチンズですが。何か問題でもありましたでしょうか?」 「この店にはびこってるクモのせいで、あたしの娘は入院してんのよ。あの子は死んでしまうわ」 そう女性は大声をあげた。 「奥さま、わたしどもの店には虫などいませんが」 「ここがあの子が食事をした最後の場所なの、このマクドナルドなの、医者が娘の口や鼻の中にクモの卵をいくつも見つけたのよ」 女性は泣きながら言った。「あんたたちクズが、あたしの娘を殺してしまうかもしれないのよ」 女性はそう怒鳴ると、カウンターの後ろにいるカイトのところまでやって来た。カイトのすぐそばまでやって来ると、涙を流し始めた。女性は激しく泣いていた。アブダが走りより、女性の肩をつかんだ。カイトが渡したティッシュに手を伸ばしたと思ったら、女性はすっと背を伸ばした。 「この件については地域マネージャーにお話ししていただいた方が」とアブダが言った。 「何言ってんのよ! この店の店長と話したいのよ!」 「奥さま、さっきも申したように、この店には虫などいません。何か申し立てされるのでしたら、ここではないです」 するといきなり、女性はジーンズの後ろポケットから銃を取り出した。 アブダは銃を取り上げようとして、女性ともみ合いになった。「警察を呼ぶんだ!」 アブダがカイトに向かって叫んだ。カイトが電話をつないで「もしもし」と言おうとしたとき、銃声が響いた。女性が走り去った。アブダが脇に倒れ込み、うめき声をあげる。アブダの足元には血の海ができていた。アブダは床に崩れ落ち、意識を失った。グリルの端にいたもう一人のコックがカイトの後ろで悲鳴をあげて、911、911と騒いだ。カイトはめまいに襲われた。頭の中がぐるぐるとまわり始める。アブダのぐったりしたからだがカイトの腕の中にあった。カイトの耳が捉えていたのはサイレンの音、そしてベスの顔がアミンの店が銃声の響きが頭に浮かんでは消えた。カイトはこれからどこへ連れて行かれるのか。故郷、あるいは刑務所か、それともカリフォルニアなのか、サイレンが連れていくのはどこなのか。それでもカイトは、アブダのからだを冷たいコンクリートの床に置こうとはしなかった。 *「サイレン」は著者のまもなく出版される長編小説「Edible Bone」からの抜粋です。(第一章)
訳:だいこくかずえ
ウノマのウェブサイト:
|
||||