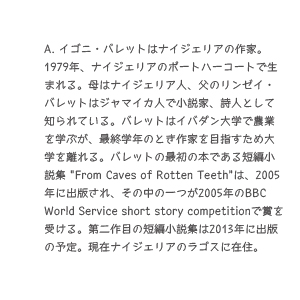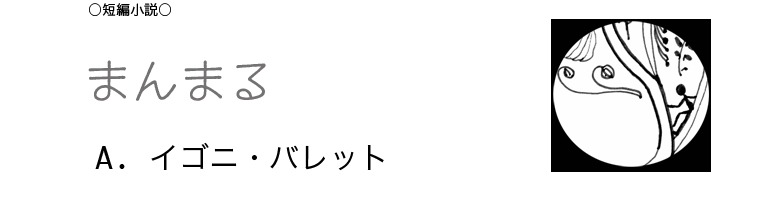
|
1
この建物は売り家ではありません 入口のドアは掛けがねが壊れているせいで半開き、灯油の燃えかすとネズミの毛の臭いがする通路の方に開いていた。通路には九つのドアが向かい合っているが、どれもすすで汚れ、いいかげんな修理が施され、けばけばしいステッカーが貼られて、それぞれに異彩を放っていた。通路は中庭に通じている。そこは貯蔵庫と調理場、人の集まる場である。
母親のダオジュ・アナブラバはベッドで脇腹をつけて横になり、顔をドアの方に向けていた。胸からひざのところに、赤と黒と緑のプリントの布を掛けている。汗で肌が光っていた。白い三枚花弁の花のついた薄緑のシーツは、汗でへたっている。ベッドのそばの床には、ジンの空ビンが転がっていた。ディミエ・アブラカサは母親が返事をするのを待っていたけれど、返事を返さないことはわかっていた。返事がないので、ディミエはあきらめて、部屋の隅の方に制服を脱ぎにいった。 電球がひとつ、天井から吊り下がり、部屋を照らしていた。ドアの向かい側の壁に窓がひとつあったけれど、木のシャッターがおりていて、さびた釘で打ちつけられていた。壁にそってベッドがあった。ベッドの足元のところに、木の机が置かれていた。机の上には、古びたメッキのフォトフレームに入った写真が一枚。ディミエ・アブラカサはそこでパンツを脱ぎ、一番下の引き出しをあけて中をかきまわし、ジーンズと黄色いTシャツを引っぱり出した。 メネイアとベナエビはテレビの前であぐらをかいて座っていた。スクリーンから放たれる光が、黙ってテレビを見る二人の顔の上でチカチカしていた。メネイアは母親とそっくりで、一ヵ所だけ違うのは、ダオジュ・アナブラバが右頬に毋斑があるのに対して、メネイアは同じ場所にレーズンのような色形の黒子(ほくろ)があることだった。メネイアはベナエビより四つ年上、弟は八歳で乳歯が抜けかわっている最中だった。ベナエビは親指をいつも吸っていた。姉のメネイアはなんとかしてその癖をやめさせようとしていた。手を苦い葉っぱの汁につけてみたり、ニワトリのふんを指にぬってみたりしたけれど、ベナエビは指吸いをやめなかった。ツメをかんでいないときは、抜けた歯の間に親指を突っ込んでいた。両手の何本かの指は、ヒョウソで瘢痕(はんこん)になっていた。親指の皮膚は白くしなびて、ホルマリン漬けの標本のようだった。 ディミエ・アブラカサは机から離れた。メネイアが顔を向けてきたが、目はテレビ画面に当てられたままだった。
以前は漆黒だった道路は、灰を流したようなグレーに変わり、埋め込まれたボルトやビンのふたが太陽を浴びて、光を放っていた。アスファルトにはニキビのような穴があちこちあいていて、歩道の上は、枝が伸びたように割れ目が入っていた。溝はところどころ泥で埋まり、別のところはゴミが詰まっていた。町の暮らしを彩る音楽といえば、エンジンの回転音、車のクラクション、カンカンドンドン音をたてる職人たちの仕事場、そして人々の怒声怒号(世界で有数のやかましい地域だ)。町は騒音に満ち、塵がうずまく。 第二砂地を通り過ぎ、向こうからやってくるヤムイモを高く積んだ手押し車を避けて道を渡ると、ディミエ・アブラカサは急に小便がしたくなった。ディミエは立ち止まり、まわりを見まわし、目をつけた路地を入っていった。路地は影になっていて、焼けつく太陽は外の世界だった。太陽のぎらつきを逃れると、急に切迫感が増してきた。急いで路地を行き、歩を進めながら息をつめていた。路地は糞の山があちこちにあり、小便の臭いが漂っていた。道の両側にある建物の窓は板でふさがれていて、はがれたペイントが苔のついた板の上で丸まっていた。男の子の一団が路地の向こうでたむろしていた。 ディミエ・アブラカサは立ち止まると、ズボンの前を開けた。壁に書いてある文字を黙殺する。そこにはこう書かれていた。 ここで小便をするな ディミエは壁に向かって放尿した。背中をそらせふーっと気をゆるませた。そして泡だつ流れにさわらないよう足をずらした。路地の向こうの少年たちのあげる興奮した声に一瞬気をとられる。ディミエが最後の一滴をしぼり落としていると、少年たちがワッと歓声をあげ、同時に悲鳴があたりをつんざいた。びっくりしてディミエは飛び上がり、ズボンのジッパーをひっかけてしまった。小さく悲鳴をあげ、自分のものをつかむとシーと息を吸う。注意深く指をつかって、ジッパーの歯からなんとか解放する。 ネコの口臭を感じて何だか知りたくてたまらず、ディミエ・アブラカサは少年たちの方に近寄っていった。少年たちが道をあけた。ディミエはその並びの中に入っていった。袋だたきにしているのは、何か人間以下のもののようだった。血の海に横たわっているのは、みすぼらしくも哀れな犬、あるいは山羊かと思ったが、それはボロをまとった女が縮こまっている姿だった。女は少年たちに囲まれてうずくまっていた。ひざを抱え、両手で耳を押さえていた。ひざ頭は荒れ、手は垢で木の根っこのようだった。もさもさした茶色っぽい髪の束が肩に落ち、その上にゴミ捨て場のゴミが撒き散らかされていた。悪病の臭いが漂っていた。 ディミエ・アブラカサは少年たちの方に目をやった。何人いるのか数を数えはじめたが、十二人目まできたとき、一人が動いて邪魔をした。ディミエのいる端からまた数え直すのはめんどうだった。何人かは手に棒を、他の者はレンガを持っていた。両方手にしている者も少しいた。ディミエはこの中の二人は同級生だと気づいたが、そのほかは知らない子ばかりだった。 ディミエは女をまた見た。その女は歯を鳴らしてうなり、しゃがんだまま体を揺らせていた。目は恐怖で血走っていたが、顔は笑っていた。女は取り囲む少年たちに目をさまよわせ、鳥がするみたいに、とうとつに首を回した。ディミエ・アブラカサは目をそらし、知り合いの二人の内、近くにいる方のバリドムのところまで、列をかきわけて進み、肩に手を置いた。 「このキチガイなにした」 ディミエが訊く。 少年たちは再び放心状態になっていた。もう遊びではない。この子たちは魂を昂揚させ溺れさせていた。女が萎縮したことで、さらに気を高ぶらせていた。何人かが大声で叫びながら輪から飛び出し、心はやらせてうずくまった女に突進していく。 一人が言う。「気違いにかまれたら、オマエも気違いになる」 そうだそうだという賛同が、少年たちの輪をめぐった。 エリガが隣りにいたディミエ・アブラカサの方に振り向いた。「石もってるか?」 ディミエ・アブラカサはいや、と首を振った。バリポが訊く。「石いるか?」 答えを待たずに、バリドムがレンガをひとつ差し出す。エリガとバリドムの間に立っていたディミエ・アブラカサは、それに手をのばし、持ち上げ、「気違い女」に投げつけた。レンガは女の側頭部に当たり、バラバラと崩れて破片が散った。女が恐ろしい悲鳴をあげ、その声は路地に響きわたった。それは痛みと怒りの入り混じった爆発だった。そして超人的な勢いで、傷口から血を撒き散らしながら、やられた相手に飛びかかってきた。少年たちは隊列をくずして路地から逃げ出した。服を脱ぎ散らしていくように、走り去る少年たちの叫び声が尾を引いていった。 # 腹の中で煮えたぎっていた恐怖はおさまりかけていた。ディミエ・アブラカサは路地からも、少年たちからも、市場からもはるか遠くまで来ていた。電柱のまわりのさびたフレームに寄りかかり、何とか息を整えようとした。激しい呼吸で胸が波うっている。両手でのどをつかみ、汗で濡れたTシャツの襟首を引っぱった。追っ手に捕まりはしまいかと、あたりに鋭い視線を放っていた。通行人がそばまで来ると歩をゆるめ、ディミエをちらりと眺め、また足早に去っていった。
5 鳥の群れが悲鳴のような声をあげて空を渡っていく。ちょっとした間があって、すべてが凍りついたように一瞬静まり、それから草原が燃えるような音がしたかと思うと、雨が落ちてきた。雨粒が地面に届く直前、フォークで空を引っ掻いたように青白い稲光が走り、光の一矢が逃げるツバメを直撃した。ツバメは空中で動きをとめ、雨が地を打つように転がり落ちた。 激しい雨の幕の中を、歩行者が走って逃げる。歩道に水たまりができ、溝に向かって激しく流れ出し、そこも溢れると車道に大量の水が溢れた。道路は川になっていた。車のエンジンが水を飲み、水蒸気を上げ、そしてダメになった。道の端も歩道も水が溢れていっぱいになった。あちこちで車のクラクションが長々と鳴り続けた。 # ディミエ・アブラカサは歩道を離れて道路に出た。立ち往生している車の間を縫って歩いた。車のボンネットは触るとまだ温かかく、車は空っぽなのにエンジンが回っていた。ドライバーは車を降りて走り、渋滞のいちばん前の人が群れているところに合流した。 ディミエ・アブラカサは群衆の方へと進んでいき、その群れをかき分けて先頭までたどり着いた。そこには大きな穴があり水が溢れていた。渋滞は家畜を積んだボロトラックが、穴を通り抜けようとして起きたものだった。トラックは立ち往生していた。運転手は泥水にひざまでつかり、タイヤの下から泥をすくっていた。水が運転手の胸をピチャピチャと洗った。 群衆は言い争いをしていた。トラックを脇に押しやった方がいいという人々、迂回すればいいという人々。ディミエ・アブラカサはそれを見ていてわくわくした。人々は党派にわかれ、面と向かって声を張り上げていた。二人の交通巡査と警察官が群衆の中にいた。交通巡査官の一人は頭の後ろで手を組み、声を上げる人々の顔をぽかんと見ていた。もう一人はトラックをにらみつけ、顔をしかめていた。警察官は人々を仲裁しようとしていたが、争いに巻き込まれてその努力も水の泡、論争は激しさを増すばかりで、そこから脱出するために手錠をちらつかせなければならないほどだった。 そのとき群衆の前の方で、言い合いの頭越しに、誰かが叫んだ。「助かったー、軍隊が来たぞ」 軍隊の列が軍靴を鳴らしながら、早足で近づいてきた。群衆が道をあける。隊列がトラックのところまで来ると、ずんぐりした太鼓腹の、両ほほにエグバ族の誇りを表す四本の印をつけた司令官の軍曹が声をあげた。「クア・シュン!」 兵隊が歩を止めた。兵隊は皆、片手にむちを片手にライフル銃を持っていた。軍曹はむちを振りながら群衆の方に向いてこう命令した。「今すぐ、ここから立ち去れ」 群衆が散った。あちこちで車のドアをバタンバタンしめる音が響く。 交通巡査官二人はその場から消えたが、警察官はそこにつっ立っていた。胸をそらせて、軍曹のところに歩み進んだ。軍曹が振り返った。 警察官は答えながら、不安げに硬い表情の押し黙った兵士の隊列に目をやっていて、軍曹が怒りで顔をゆがめて怒鳴りつけるところを見逃した。「このいまいましい平民が!」そう言って、警察官ののど元にむちを見舞った。警官は地面に倒れ、舌を飲みこまないようにぐっと押し出した。その襟首をぐいとつかむと、軍曹はむちで顔を打ちつけ、それから水の溢れている穴のところに引っぱっていった。そこで手を離し、一歩退いた。軍曹の顔が平常に戻った。 「泥ん中を這いまわれ、このクソが」 軍曹は声を落として言った。 警官は四つ足で水からころがり出ると、息をついた。軍曹が兵隊の方に向いて命令を下した。「道からトラックをどけろ」 兵隊たちがいっせいに動き出した。トラックの運転手を殴りつけると、積み荷台から牛を放ち、尻を蹴りあげて追いたてた。それから群衆の中に入っていって、屈強そうな男を何人か選んだ。その男たちがトラックを引っぱり、兵士たちが押した。軍曹は大声で指示を与えながらむちを振り上げ、トラックの移動を指揮した。数分のうちに、渋滞した車の列は喜びのクラクションを鳴らしながら走り去っていった。 # 雨はやんでいた。ディミエ・アブラカサはびしょ濡れで、腹が減って、ぐったりしていた。ずいぶんと長い時間がたってしまった。メネイアとベナエビはきっと待ちくたびれていることだろう。二人で道に出て、どっちの方向から帰ってくるか、どちらが先に兄を見つけるか、見張っているかもしれない。と思ったとき、自分の名前を呼ぶ声がした。ディミエは顔を上げて車の海を眺めた。ディミ! エンジン音の上の方でまた声がした。手を振っている車があるのを見つけ、それが家主のアルハジ・タジュディーン(タジュディーンさん)だとわかった。家主は片手で車を押し、もう片方の手でハンドルを操縦していた。後ろに付いた車の列が、家主を急かしてクラクションを鳴らしていた。ディミエ・アブラカサは家主のところへ飛んでいった。
「何ガいるんダ?」 女はディミエの前に立ちふさがった。「あんたニ飲みものやるなんて思うナヨ、ッラ」 「へっ、なにミてる。オマエくちきけンのか?」 そう言うと尻に手を置いた。ディミエ・アブラカサは目を落とした。 「おーおー、マダム・グローリー、あんたッサ」 さっき口をきいたベンチの男が叫んだ。「だれがこの子を寄こしたか知ってんだろ?」 Tシャツのへりをねじっていた手をズボンのポケットにすべらせながら、ディミエ・アブラカサは本当のことを言おうとした。母親が寄こしたんだと。手をポケットから出し、マダム・グローリーをびくびくと見つめ、それから今度は両手をポケットにつっこんで、声を上げた。 ディミエ・アブラカサは侮辱の言葉を背に、燃える耳を手でこすりながら、そこから立ち去った。
競技場の端の、ゴールポストの後ろにピンポン台が据えられていた。三人の少年がそのまわりに立っていた。二人がピンポンに興じていた。ボールがネットにかかると、ナイラ札の束を片手に持ったもう一人の少年が叫んだ。「アウト5回!」 エリガが後ろに退いたと思ったら、ぐるっと向きを変えて走り出した。クロテムボが笑いながら声を上げる。そしてチブゾの方に顔を向けたとき、ガラスの割れる音を耳にした。迫りくる危険を目の端に感じて、クロテムボが逃げ出した。 チブゾが言った。「クロテムボみたら、おまえ逃げろや、ッラ。あいつ容赦しないぞ。そんでと、おまえら180かけたろ、オレの取り分どけて、おまえの金は30、あってる?」 # カナ通りが終わるあたりで、ピンクの三階建てのホテルが現われた。ホテルを囲む壁の上部はガラス片で縁どられていて、庭にはたくさんの果樹が植えられていた。門の近くにある大きなアーモンドの木が、奇妙に幹を傾げて枝を伸ばし壁にもたれかかっていた。その葉陰は、子どもや浮浪者が集まる場所になっていた。 壁のところに着くと、エリガは木の下へと向かい、顔を道路の方に向けて枯れ葉のたまったところに腰をおろし、壁に寄りかかった。ディミエ・アブラカサもそれに続いた。風が少し吹いて、腐りかけた果物の臭いがあたりに漂った。 二人が来たとき宙に舞った葉っぱが落ちつき、しばしの静寂のあと、エリガがディミエ・アブラカサの肩に手をおいて訊いた。「名前なンてんだ?」 ディミエ・アブラカサは腕の上を這っているアリをつかまえた。アリをつまんで、バタバタする脚とパチパチいうはさみを見た。指先でアリをつぶすと、手をジーンズでふいた。 「なんであのキチガイに石なげた?」とエリガ。目はディミエの手を見ていた。長くてほっそりした指、噛んだつめ、静脈の線。ディミエ・アブラカサはその視線を感じて、手を丸めた。 「別に」とディミエ。そのとき心に浮かんだのは、自分の母親の姿、ベッドの上でひざを抱えてすわり、両手で耳を塞いでいる格好の母だった。丸めた手を振り上げて自分のひざを二度打ち、それから葉っぱの地面に手をおろした。 「おまえ変なやつだな、ッラー、デキチよ」とエリガ。 道路に学校で課外活動を終えた生徒たちの姿があふれた。制服姿の女生徒のグループがホテルの方に歩いてきた。女の子たちはディミエたちの方を見ながらこそこそ何か言っていた。その列が通り過ぎるとき、先頭にいた女の子がエリガの方に顔を向けて、鼻で笑った。 エリガはすくっと立ち上がり、その女の子の方へ向かっていった。女の子は背が高くがっしりとしていて、髪は短く刈られ、サッカー選手のようなふくらはぎをしていた。着ているのは高校の制服のワンピース、唯一のアクセサリーは、イングランド・サッカーの強豪クラブ、チェルシーFCへの愛と忠誠を誓うゴムのリストバンドだった。 エリガがその女の子のそばに近づいて言う。「だれミテ笑ってンだ、このオンナ男」 エリガは女の子の腕をひねった。それほど強くではないが、自分の力を相手にわからせるには充分だと思った。「もう一度笑ってみろ」 そうエリガは言って、手を前に引いた。そして女の子の足を踏みつけた。 女の子たちが寄ってきて、ハチの巣をつついたようにザワザワと声をあげながらエリガを取り囲んだ。人質にされている女の子がエリガの手の中で動いたと思ったら、次の瞬間、エリガの腹にげんこつをくらわせた。エリガは手を離し、痛みで声を上げながらからだを屈めた。 「泣いてんのぉ?」と女の子は言いながら、かがんでエリガの肩に触れ、見せかけの同情心をしめす。「からだ起こして、、」と言おうとして吹き出し、「できるものならね」と続けた。 歯ぎしりしながら、エリガはやっとのことでからだを伸ばした。女の子たちがエリガが次に何をするか見ていた。エリガはどうしていいかわからない様子で立っていた。ディミエ・アブラカサが立ち上がった。「あんた、知ってるよ」 ディミエは殴った女の子に言った。「おんなじ学校に前行ってたんだけど、覚えてる? 聖イグナティオスだけど」 女の子たちが角をまがって声が遠ざかると、ディミエ・アブラカサは訊いた。「腹だいじょうか?」 エリガの顔を見ていて、胸の動機が激しくなった。「っさあ」 出てきた声はかすれて、つばが歯にまとわりついた。「金、借りられるかな?」 二人は互いの顔を探りあっていた。ディミエ・アブラカサは目を落とした。「たのむよ、かあさんの金を今日なくしちゃったんだ」と言う。
ディミエ・アブラカサは家主が車を駐車し、取手をまわして窓を閉め、ドアをロックするのを見ていた。白いプジョー404だった。車体がさびて腐食している。フロントガラスは右隅のところに、クモの巣状のひびが入っていた。 「かあさんはいるか?」 タジュディーンさんが車のキーを揺らして、ディミエ・アブラカサの方に歩きながら聞いた。 沈んだ気分でディミエ・アブラカサは家主の顔をのぞきこんだ。タジュディーンさんは見たこともないくらい、鼻の穴がでかい。鼻の穴は白っぽいもさもさした毛でいっぱいで、耳の中の毛の束と同じ色をしていた。頭はつるつるに剃ってあるのに、鼻と耳の毛はぼさぼさのままだった。家主が母親に会いたいという理由はただひとつ。ディミエ・アブラカサは家主にうなづいて「います」と答え、こう付け加えた。「でもかあさんは具合がよくないんです」 家主は建物の入口に向かった。「それがどうした?」と肩越しに荒い声を投げつけてくる。「いつだってそうだ。あんたたちがここに越してきてから、かあさんの具合がよかったことが一日でもあるか?」 家主は廊下を歩いていく。ディミエ・アブラカサはその足音と、各部屋から上がる家主へのあいさつの声を追ってついていく。 「あんたんとこは今日、ここを出ていってもらう」と家主が大声をあげた。「まるまる三週間、あんたんとこの家賃は切れたままだ。もう待てないぞ。おれがここで慈善事業をやってるとでも思ってんのか! いったいどんだけの人がこの部屋貸してくれと言ってるか、知ってんのか?!」 ここで一息ついた。「あんたんとこが人間らしく暮らすのが無理ってのなら、外で犬みたいに生きろってことだ。どっちでもおれには関係ない。でもな、おまえは今日、ここを出ていくんだ、わかったか!」 ベナエビが鼻をすすった。メネイアが手で口を押さえる。ダオジュ・アナブラバは足を動かし、手で太ももをこすり、ため息をついてこう言った。 ダオジュ・アナブラバは顔を上げた。「でもだんなさん、そんな言い方しないでくださいよ」 ダオジュはからだに巻いた布がゆるんでいるのを脇の下に挟みこんだ。そしてその手で顔の汗をぬぐった。 家主がじっとダオジュを見ていた。からだの線を追いながら目をじょじょに下に向け、頭から足元を見て、また足から頭へと視線を戻した。そして咳払いをして言った。「わかった。話を聞こうじゃないか。あんたが誠意をもって話すならな。だが話す前に聞きたい、家賃をあんたは持ってるんか?」 ダオジュ・アナブラバは黙っていた。 ダオジュ・アナブラバはその意味を理解した。そして目を見開いて、「んまあ、だんなさん、、、」 家主は肩をすくめた。「あんたもおれも大人だ。あんた次第ってことだ」 もみ手をするとその手を開いて前に伸ばした。「あんた次第だ。三週間分の家賃を今日払うか、荷物をまとめて今日出ていくかどっちかだ」 顔をあげて長男の方を見ると、硬い声でこう言った。「ディミエ、妹と弟を連れて外に出て。ドアを閉めて」 # 足音が廊下でして、親しげな別れの挨拶の言葉が聞こえ、家主が出てくるのがわかった。建物の入口に出てきた家主は、ちょっと立ちどまって、夜空に上がった満月に目をパチパチさせた。顔がアスベストの灯りの下で光っていた。家主はあくびをし、手をあげて額をぬぐい、その手を下ろして腹をこすり、両脇に垂らした。車の方に歩いてくるとき、子どもたちの方に目を向けることはなく、鍵をあけ、エンジンをかけ、そのまま走り去った。 車がブルブルとエンジン音をたてて消え去り、ぽっかり残された静寂の中でベナエビが言った。「お腹すいた」 ベナエビはお腹をへらして、親指をチュウチュウと吸っていた。 メネイアがディミエ・アブラカサのひざに手を置いた。「ずいぶん長くかかったんだね。もう待って待って待ちくたびれた。ンマ怒ってたよ。何買ったの」 「ディミエったら!」とメネイア。怒りと不安で声がふるえている。「ンマのものは買えたんでしょうね、少なくとも」 「おまえは何をなくしったって?」 暗闇の中で最初の一発が放たれた。ディミエはバランスを失った。母親は息子に馬乗りになり、打ち据え、引っ掻き、蹴り上げた。ディミエ・アブラカサはひざをついて、頭を抱えた。ディミエはきつい蹴りを腹に受けて、うなり声をあげる。母親がコンクリート板を持ち上げて降りかかろうとしたとき、見ていたアパートの住人たちが母親を抱きとめた。母親はそれを振り切ろうとして、悪態をついた。 住人の何人かがダオジュ・アナブラバを部屋に連れていき、別の何人かがしゃがみこんでいるディミエ・アブラカサのまわりに集まった。メネイアは兄のそばにひざまづいていた。顔を両手でおおい、肩を震わせていた。母親の暴力のすさまじさに驚いたベナエビは、胸のところで両手を握りしめ兄の後ろに立っていた。一つ向こうの部屋の住人のママ・マラチがディミエ・アブラカサの肩に手を置いた。「あんた何かママを怒らせるようなひどいことしたんだろう?」 そう言ってかがむと、ディミエの腕をつかんで手を頭から引き離した。誰かがトーチを点けて、ディミエの方に灯りを当てた。ディミエの目はヘッドライトにとらえられた野うさぎのようだった。くちびるには血の斑点があり、首の横には白い引っかき傷が四ヵ所あった。灯りを当てられると、それに反応したように傷から血が流れ出した。メネイアが息をつめた。ママ・マラチがディミエの腕を離した。ディミエの腕がひざに落ちた。 住人たちは片隅に集まって、あれこれ相談しているようだった。子どもたちの耳に、いくつかの言葉が繰り返し聞こえた。「母親」「家主」「酒」などの言葉だ。そしてモガジ氏が子どもたちの方にやってきた。
子どもたちがおばあちゃんの家に着いて、門をしばらくの間ガタガタいわせた後、やっとおばあちゃんの声がした。「何のよう?」 「よく見て」とおばあちゃんがさらに言う。 ドアにかんぬきをかけると、アナブラバおばあちゃんは腰をかがめて、ドアのそばの椅子に置いてある台風用のランプの火を強めた。よっこらしょとからだを伸ばすと、子どもたちの方を向いて、門のところで音がするもんで、あんたたちだとわかるまでは恐かったよ、と話した。「おかあさんはどうしたんだい?」 ディミエ・アブラカサの顔ををのぞきこんで訊いた。ランプの火は弱々しかったので、ディミエの首の引っかき傷には気づかなかった。
アナブラバおばあちゃんが子どもたちの食べものを用意して、台所から声をかけると、うとうとしていたベナエビが飛び上がって、暗い廊下を走っていった。メネイアがディミエ・アブラカサに料理をもってこようか、と訊いてからベナエビの後を追った。ディミエはうんと言って椅子に沈んだ。妹の足音が遠のくと、部屋の暗さが海のように押し寄せてきて、ディミエの首の傷を洗った。ディミエは母のことを思った。ひとり家にいる母。母親も今日一日何も食べていなかった。その上、薬もなく、家主に辱めを受けて耐えなければならなかった。家主のことを思い出し、ディミエ・アブラカサは起き上がって首の傷にさわった。パタパタいう足音で考えが中断された。 アナブラバおばあちゃんが部屋の中央にあるテーブルに台風用のランプを置いて、ディミエ・アブラカサの正面にすわった。冷ましてから食べなさい、というおばあちゃんの言いつけを無視して、ベナエビは椅子に腰をおろすなり皿の料理に食らいついた。料理はヤムイモを茹でた料理だった。ベナエビはこれが大好きで、いい香りが湯気と共にあがっているのを、ハフハフ言いながら口にした。メネイアがディミエ・アブラカサに皿を手渡し、その横にすわった。カチャカチャというフォークの音が部屋を満たした。 アナブラバおばあちゃんがディミエが食べものをつついているのに気づいた。 メネイアは食べ終わると、皆の皿を集めた。兄の皿をよけると、ディミエが首をふって皿を突き出したので、それも一緒に下げた。灯りを手に、メネイアは台所に向かった。暗闇の中で、ベナエビが眠りに落ちていった。部屋にその息づかいが満ちる。 「明日は学校がある日だね」とアナブラバおばあちゃん。自分に問いかけるような口調で、一語一語確認するように言った。それから思いついたように、「あんたたち、そうとう早く起きないと。そうすれば家に寄ってから学校に行けるよ。メネイアはわたしと寝なさい。男の子たちはお母さんの昔の部屋で寝ればいい」 メネイアが台所から戻ると、アナブラバおばあちゃんは、頼みの綱というように顔を向けた。「あんたの兄さんは、アダカ・ボロに今晩帰るって言ってるよ」 「急いで行くのよ。安全じゃないんだから」 ドアの鍵を外しながらアナブラバおばあちゃんが言った。メネイアに鍵を突き出すと、こう指示した。「ディミエについていって、門を開けて。開ける前によく外を見てね。ディミエが外に出たら、すぐに鍵を閉めるのよ」 アナブラバは、マンドレイクの根っこのような節くれだった手を孫息子の肩に置いた。「おやすみ、いい子。おかあさんによろしくね。おかあさんに会ったら、、、うんん、いいの、何でもない。さあ急いで」 アナブラバはディミエを押し出すとき、一瞬ツメをその肌にくい込ませた。
部屋は闇に包まれていた。ポリ袋の中に手を入れて、ろうそくとマッチ箱を探した。帰る途中で買ったものだ。モグラが巣に戻るときの確かさで、木の机のところに歩いていった。そこまで来ると、マッチを擦り、ろうそくの芯に火を移した。溶けたろうを机の上にたらし、ろうそくを固定した。ゆらめく黄色い炎が、子どものときの、まだフロックを着ていた頃の母親の写真にあたる。父親のひざに腰掛ける母親、その横には母の母がすわっている。ディミエの母の目は幸せに満ち満ちていた。ディミエは振り向いた。 ダオジュ・アナブラバはベッドの頭のところにすわって、ディミエを見ていた。腕をひざの上に置いて、手の先をぶらさげていた。ディミエ・アブラカサは机のところを離れ、さっきポリ袋を置いたところに行った。袋に手を突っこんでステンレスの容器と、透明の液体の入ったビンを取り出す。ろうそくの火がステンレス容器とガラスビンに反射すると、ベッドのスプリングがきしんだ。ディミエはベッドに近づいて、手にしているものを差し出した。母親がベッドを降りてディミエを見た。母親はビンをつかむと匂いをかいだ。「ディミエ、あんたいい子だね」 その声は涙でしわがれていた。息子の額とほおにキスをした。涙とよだれに濡れたキスが、ディミエの顔をしめらせた。母親は息子の手からステンレスの容器を取ると、ベッドの上に置いた。それからビンのキャップを開けると、頭をうしろにのけぞらせた。 「ああ、いい子だね、あんたは、あたしの一番の、たった一人の息子だよ。ありがとね」 そう歌いながら、腰をくねらせて即興の踊りをやってみせた。それから向き直ると、しっかりとディミエを胸に抱きしめた。 夜も更けていき、母親は、ダオジュ・アナブラバは、食べものをつまみビンから液を流しこみながら、息子に何度も何度も詫びの言葉を吐いた。今までの生活について、母親としての至らなさについて、ディミエの祖父を殺してしまったことについて。ディミエ・アブラカサはこういう話は耳にたこができるほど聞いていたので、黙っていた。 母親のしゃべりはろれつが怪しくなり、まぶたが下がり、あらがいながら、閉じられた。眠りの中ですすり泣き、胸にはビンを抱きしめていた。大きなおならを続けざまにした。母親のすすり泣きがいびきに変わると、ディミエ・アブラカサはすわっていたベッドの端から立ち上がった。ディミエは母親の手からビンをはずすと、壁際のすぐに手の届くところに置いた。朝になって母がビンを探さなくていいように。それからフトンを母親に掛けてやり、ろうそくの火を吹き消した。 # 朝になって、ディミエ・アブラカサが目を開けると、頭のところの電球に灯りが点いていた。ディミエはそれをじっと、目の中で黒い斑点が現われるまで見つめていた。そして首をひねり、母親が起きているのに気づいた。母親はベッドの端で、死んださなぎのように丸まって、ディミエの顔をじっと見ていた。ディミエはおはようと言ったが、答えはなかった。胸の鼓動がディミエの中で響き、のど元に苦いものがこみ上げて口をまずくさせた。立ち上がり、家を出る準備を始めた。ディミエが制服を広げていると、母親がベッドから降りて、ビンに少し残った液を飲み干すと、横に投げ捨てた。そしてディミエの方に迫ってきた。からだをゆらゆらさせながらくちびるをなめた。酒臭い息がディミエの顔をおおった。母と息子はじっと見つめあった。母親は爬虫類のように目がすわっている。息子は絶望で光を放つ目をまんまるに見開いている。ダオジュ・アナブラバがひびわれたくちびるに薄笑いを浮かべて「おまえの目がいやなんだよ」、そう言ったとき、ディミエは母親をぴしゃりと打った。 *2)ネパ電:NEPA(National Electric Power Authorityの略称)。ナイジェリアの電力会社。NEPA Lagosというサッカーチームをもっている。 *3)ワハラ:<英>trouble、問題、災難、やっかいごとを意味するナイジェリアのピジン。
|
||||