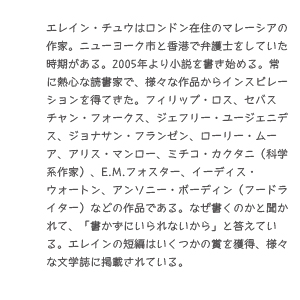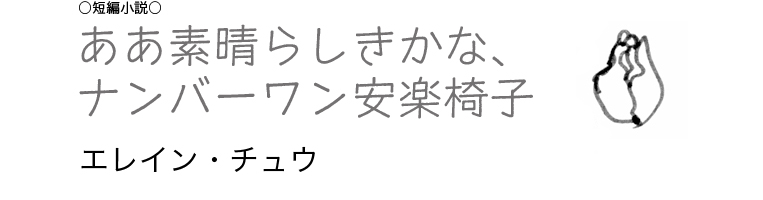
|
全部で十六人の患者がそこにはいました。その内の五人とは、懇意になりました。ダニエル・チーというひょろっとした青年は、我々の中ではいちばん元気そうでしたが、オートバイ事故で腎臓機能をなくしたそうです。パク・アジズは、へき地出身の退職した郵便配達員で、好物のドリアン・ライスを持ち込むので、空気の出入りの少ない病院ではひどい臭いが病棟中に漂います。クマル夫人は退職した学校の先生です。シルクのアイピローを付けている姿は、透析を受けているというより、寝椅子で日光浴をしているようでした。クリサンセマムは思いやりに溢れた料理上手です。彼女はいつも、我々の昼食に添える何か特別な一品をもってきてくれました。そして最後にご紹介するのが、クー夫人です。中国製の孫の手(木の熊手のようなもので、先がフォーク状になっています)を持つ、つむじ曲がりのごくつぶしです。この人の服は合繊でできているのか、動くたびにシャリシャリと音がしました。そしていつもぶつぶつ文句を言っています。甲高い声は、吹きそこねたピッコロのように耳をつんざきました。 そしてもう一つ、素晴らしくも夢のような安楽椅子が、体重計と冷水機のすぐそばにありました。そのあたりには乾いた気流が渦巻いていて、ゆっくりと休める隅にあり、静寂にして催眠作用を促すような冷水機のゴロゴロいう音に守られ、他の患者の臭いやおしゃべりを彼方に遠ざけています。そういうわけで、この椅子は、透析を受けるときの誰もが競って座りたがる椅子になっていました。透析治療のときのからだのほてりも、ここに座ればずいぶんと楽に耐えられます。この椅子に称賛を表す呼び名がつけられていたのも、不思議なことではありませんでした。「ナンバーワン安楽椅子」みんながそう呼んでいました。わたしが一番ぐっすりと眠れるのも、その椅子でした。その椅子以外の椅子で治療を受けた日は、機械に縛りつけられて四時間たつと、治療前よりからだが弱ったようで、無気力とけん怠感におそわれ、食欲も意欲もげっそりと削がれるのです。ところがナンバーワン安楽椅子から降りたつときは、すがすがしい活力を一時的に注入されたような、老いぼれの股間に元気が(半ば硬くさえなって)よみがえり、胸には明るい希望が満ちあふれます。気怠い午後にセブンイレブンで買ってきた、スイカのスラーピーのような素晴らしさです。 ルールはごく単純なものでした。朝早く来た人がこの椅子の権利を獲得するのです。ここには公正さがあり予測も可能、その場限りのやり方が避けられます。もしどうしても椅子を獲得したければ、病棟の誰より早く着くようにすればいいのです。それには透析機にかけられるまで、二時間も待たなければならないとしても、です。たいがいの時間は、クリサンセマムがナンバーワン安楽椅子を確保していました。彼女は朝のラッシュアワーの前に、スクーター・タクシーの荷台に乗って、テルク・インタンからやって来なければならなかったからです。行きに一時間、帰りに一時間、わだちのついた砂利の脇道をガタガタと揺られて、道の両側には建設工事の柵、砂粒やセメントスプレーの粉塵に鼻の穴をつまらせてやって来るのです。髪飾りの上をタオルで巻いてバイクのヘルメットを被り、ふっくらした赤いほおに陽気さをはちきらせながら、輝くばかりの笑顔でやって来ます。特筆すべきは、自分がナンバーワン安楽椅子を独り占めしているおわびとして、五段重ねの弁当箱を持ちこんでいたことでした。それぞれの段においしい料理が詰まっています。煮込んだ鶏の足、鶏の腎臓に入れて蒸したキノコ、子牛の腸のトウガラシ詰め、ハスの葉で包んだやわらかなご飯、クワイ・テオウ・ヌードル。恵みの天使である彼女は、お気に入りのインド料理の屋台で買った、チャパティと山羊のカレーの特製弁当をインド系の人のために、ビーフ・レンダンやナシ・レマクをマレー人のために、持ち込んだりもしていました。 クー夫人がこの病棟にやってきて、すべてが変わりました。クー夫人は金切り声とぐだぐだとした不平で病棟を支配し始めました。ある意味、彼女はわたしたちの縄張りのガキ大将でした。大声で怒鳴りちらし、自分のしたいように他の人を従わせる。クー夫人が来てから、ナンバーワン安楽椅子は彼女のものとなりました。「タン教授、いい人はいつも、さもしいやつの前に屈服するということでしょうな」というのは、パク・アジズがわたしに言った言葉です。「あの人がえらそうに自分のことを触れまわるのを聞きましたか。自分だけが成功した息子をもつ人間と、思ってるんですかねえ。息子はインターン医でね。首席で卒業とか。この病院をいつか運営するようになると思い込んでるみたいですよ」 クマル夫人が追って言う。「あなたは大学教授でしょう、ドクター・タン、博士号をお持ちよね。でもわたしたちにその特権でいばり散らしたりしませんもの」 わたしはクマル夫人の率直なほめ言葉をうれしく思いました。たしかに、わたしにはそうすることもできました。マレーシアの社会では、そういう特権を示せる立ち場にありましたし、その権利をうまく使うこともできたでしょう。 翌朝、病棟で、わたしはクー夫人の傍若無人ぶりを直接見る機会を得ました。クー夫人は、息子の腕にもたれて入ってきました。息子はやせたまだ若い青年です。クー夫人は着くなりナンバーワン安楽椅子の方へと向かいました。そこでは、クリサンセマムが毛布をかけて、椅子にからだを沈めようとしているところでした。クー夫人はクリサンセマムにおおいかぶさり、金切り声を静かな病棟中に響かせて、年長者に対して尊敬の念をみせなさい、と要求したのです。「自分を見てごらんなさい。アナタは若くて、頑丈で、しなやかさがある。自分勝手になるんじゃないの。少しは恥じなさい、いつも自分だけが特権を得ようなんてことは」 クリサンセマムは自責の念と猛攻撃に耐えられず、わっと泣き出しました。これにはわたしも頭にきました。クー夫人が言った内容そのものというより、そのガミガミ言い散らす声にです。これから耐えなければならない四時間もの透析時の麻痺状態を思って気を落としているときに、クー夫人の金切り声はとことん人を壊滅させます。
大きな銀の十字架を胸にかけた、ずんぐりむっくりの看護婦長シスター・パンドラは、クー夫人がナンバーワン安楽椅子の権利を主張しても、自分はそれに干渉できないとわたしに言いました。わたしにはとうてい理解のできない、ルールに対する別の基準があったのです。病棟には二種類の患者がいました。支払いのある患者と支払いのない患者(政府の補助金による)です。扱いにくい患者と従順な患者という区分もありました。クー夫人のような小うるさい患者は、間違いなく前者に入ります。シスター・パンドラはこんな風に説明しました。「クー夫人はたしかに迷惑な患者かもしれませんが、そういう患者の扱いというのはとても難しいんですよ。でもあの人は支払いのある迷惑な患者だから、できるだけのことをするんです」 そのときシスター・パンドラは、簡単な言い方で、病棟の力関係を言い表そうとしていたわけです。患者と看護婦の終わりのない押したり引いたりの力関係、起きたこととその反動の連鎖というような。看護婦たちを敵にまわすのは得策ではない、それは明らかでした。わたしたち患者は、彼らの掌中にあります。週に三回、看護婦はわたしの血管に十センチくらいの注射針を刺しますが、ゴム手袋をつけた看護婦を見ていて、彼女が気を散らさないことを、そのとき月経前症候群でないことを、髪がうまくまとまらなかった日でないことを、乱暴な配偶者からひどい目にあっていないことを、理由はともあれ感情的でもむら気でもイライラもしていないことを、そして熟練した射手のように一回で針を血管に刺してくれることを、願わずにはいられません。 わたしの人生で、自分が無力で不利な立場に置かれていると感じた、似たような経験があったことを思い出しました。ロータリー・クラブの三人の審査官の前で、オックスフォードへの奨学金がもらえるかどうかが決定されるときのことでした。どの審査官もわたしの論文が素晴らしいと言い、運動、学問ともに能力の高さに驚かされたと述べ、わたしの心は大きな希望で舞いあがりました。が、その後でこう言われたのです。他のもっと経済的に貧しい学生に奨学金を与えることにしたと。英国へ行くというわたしの希望を、強く打ち砕く言葉でした。でもそのことで、わたしはアメリカに行くことになりました。融資を受けてシカゴ大学の授業に出席し、およそ十年後にカーネギー・メロンで数学の博士号を取得しました。当時、数学の博士号を持つ者は、わたし以外マレーシアにいませんでした。
飼い犬のムッソリーニが病気になりました。吐き気をもよおし、食べたものをみんな戻してしまい、糞には血が混じっていました。ドリーンがすぐに獣医に連絡をとりました。わたしのその朝一番にすることが、「透析に行く」ということになりました。かなり早い時間に妻はわたしを病院の前で降ろしたので、病棟は開いていませんでした。 わたしが病棟に入ったとき、シスター・パンドラはまだ洗いたての毛布をたたむのに忙しくしていました。シスターはわたしに会釈し、好きな席に座るよう言いました。さて、わたしはクー夫人がナンバーワン安楽椅子を、来る日も来る日も占領していることを知らなかったのでしょうか? その日、クー夫人が来ることをわたしは知らなかった? 彼女の席に座ることで、わたしが何かはじめることになると、気づかなかったのでしょうか? 潜在意識のどこかに、デカルトの倫理観がいまだ潜んでいたようです。最初に来た者が権利を得る。これは皆が望んでいるものを分け合うときの、最も公平な方法です。次に、わたしはクー夫人は一番に来ることで、席を独占しているだけだと思っていました。彼女の優先権は確実ではありません。多くの権力争いはこけおどしだ、というのがわたしの経験から得たものです。はったりをかければ、ガキ大将も引き下がるはず。最後にもう一つ言えば、わたしもまた、支払いをする患者の一人でした。 そこでわたしは、自分でたたんである毛布をとり、ナンバーワン安楽椅子の方に歩いていきました。自分は戦争を始めているのかもしれない、わたしの知性がそう告げていたので、そこで一呼吸しました。そうであっても、午前中いっぱいこの素敵な心地よさをナンバーワン安楽椅子で味わう魅力は、抵抗し難いものでした。わたしの側にはあらゆる点で道義的に正当性がありました。わたしは毛布を椅子に広げ、端を中に折り込みました。首のところに、膨らませた飛行機用クッションを当てます。今朝ドリーンが持っていくように言った防虫剤臭い古びたジャンパーを引っぱり出して着ました。気持ちよく椅子におさまると、わたしは看護婦がやって来て機械にかけるのを待っていました。どうしたことか、そうしている間に、眠りに落ちていました。 わたしはあばら骨を突かれて目を覚ましました。 クー夫人がわたしをにらみつけていました。孫の手がわたしの顔の上を舞っていました。間違いなく、それでわたしを突ついたのでしょう。「アナタ、どこに座ってるのよ」とクー夫人。 「はい?」 「アタシの席だと言ってるの。聞こえないのかしら」 「席はいっぱいあるじゃないですか、奥さん」 わたしは病室の空いている椅子をぐるりと指しました。 クー夫人はにらみつけてきました。「でもね、ここはアタシの席なの」 「わたしが一番に来たんですよ」 「アタシが他の椅子じゃなくて、ここに座るのは皆が知ってます。ここにアタシが座るのには理由があるの。病状がとても重くて、いつも通りにやることが大切なの。あなたと喧嘩しようってんじゃないの。アタシがこんなにも可哀想な老婆だってわかるでしょ」 クー夫人は声を荒げました。 「そうですか、でもわたしも可哀想な年寄りですよ」とわたし。「それにわたしが一番に来ました。ここがあなたの席だとか、この椅子があなたのものだとか、そういうことではないでしょう。それとも」 わたしはここで少し口調を変えました。「この椅子に名前でも彫りましたか? 少しお金を出したとか、所有者である証拠でも?」 クー夫人のほおがふくらみました。目も飛び出して。「アナタ、なんてことを。なんてことを」 「取り乱しておられる」とわたし。「おすわりになっては。ここで起きた問題はなんであれ、友好的に解決しようじゃないですか。平和な市民がしているように」 クー夫人は立腹していました。息継ぎで胸を大きくふくらませながら、シスター・パンドラを大声で呼びました。そのときには、病室は治療中の患者や家族、付添人などでいっぱいでした。皆がわたしとクー夫人を見ようと視線を向けていました。 クー夫人は孫の手をわたしの前で振りかざしました。本当に腹がたちます。クー夫人が声を上げました。「あなた、アタシをいじめてるのがわからない? アタシもあなたと同じ人間なの。あなたは何事にもキチキチして教養もあるんでしょうね。地位を利用できるわけ。そんなものに気後れなんかしませんよ。アタシはね、あなたの七回分の人生で感じる辛さを合わせたよりもっと、辛い目にあってきたの。だから言ってんのよ。あなたはアタシの席にいるの。あんたみたいな男はね、特権をかさにきて」とそこでクー夫人は息継ぎをしました。「年老いた女と喧嘩するような真似をしちゃいけないの」 「何が不満なんですか、奥さん」 わたしは怒鳴り返しました。クー夫人がわたしを脅したので、弱みを見せないようにしたのです。わたしが立ち上がり拳を強く振って見せると、クー夫人は縮こまりました。「あなたにこの椅子の優先権があるなんて、どうして思うわけです? 自分だけが誰よりも辛い目にあってるとでも? 注射針は差別も区別もしないのがわからないんですか? 我々は同じこの場所で耐えてるんですよ、ガーガー言いたてるのは、墓穴を掘るようなもの、あなたにとってもね」 シスター・パンドラがそこで口を挟んできました。そっけない言い方でした。「デニス、もうしわけないけど、ここはクー夫人の指定席なの。こちらの席に移ってもらえないかしら」 こういうやり方で、シスター・パンドラはこの病棟の当否の天秤をひっくり返してきたのです。最優先ルールというものを作りあげ、それを指定とか優先割り当てのように呼んで、それによって我々がもっていた平等な場を壊してきたのです。もちろんどんなルールも、世間と無関係には働かないものです。学校の教室を例にとれば、生徒たちは自分の好きな席をとろうとする傾向があります。後ろが好きな人たちはいつも、教室の最後列に座ります。ガリ勉タイプは前の方に座り、どの教室でも同じ席をとろうとしたりもします。そうであっても、これは誰かが指定席を所有しているということではありません。所有権というのは、道義的に最も高い権利なのですから。しかしながら、優先権というのは一般に、任意の行動の結果生まれる権利と考えられています。ですからより公平な原理が適応されていれば、誰か先に来た者がいれば、他の人はその人の優先権を認めるべきなのです。シスター・パンドラは、この不公平な優遇措置をすることで、ここには裏の決まり事があることを示唆しました。患者の気分とか、患者の性格とか、看護上の都合とか、部外者には関与できない決まり事です。シスター・パンドラのしたことは、クー夫人の言ったこと以上に、わたしの怒りを誘いました。わたしは怒り青ざめていました。その日の透析の間ずっとわたしの怒りは煮えたぎり、血圧が上がってしまうのを防ぐため、なんとか心の平静を保とうとしました。終わった後には、ひどいめまいと吐き気に苦しめられました。実際のところ、これまでに受けた透析治療の中でも、かなり辛い体験だったと言えます。 それに加えて、ひどく屈辱的だったのは、下の名前で呼ばれたことです。「タン教授」とか「先生」と呼ばれ続けてきたこのわたしが、今になって名前で呼ばれるとは。シスター・パンドラに、何のことわりもなく、地位を剥奪されたような気分でした。退官した数学の教授であり、カーネギー・メロンで博士号を取り、マレーシア大学で最高位の講師であったこのわたしですが、今はご覧ください、使い物にならない二つの腎臓持ちで、作り物の管にしがみつき、残りの人生を排尿のために、週に三度は機械に縛りつけられるのです。病気であることで我々はある種平等であると思ってきましたが、病人や死にかけた人がいっぱいの病院で、椅子の奪い合いという形ではありますが、ここでも互いの生存競争への戦いは絶えることがないのだと、そのとき理解しました。
クマル夫人はいわば女復讐鬼でした。「そうそう、分をわきまえなさいってこと。あのずうずうしいドロボウ猫が」 クリサンセマムは忘れ去ることを選びました。「わたしの作ったチキン・マッシュルーム・パンを食べてみて。夕べ自分で生地をまるめたのよ。朝一番で蒸したんだから」 でも、話した人たちの誰ひとり、わたしが考えたやり方がよくないと反対はしませんでした。椅子に座りたい人はくじを引くのです。くじを引かない人は「選択権放棄」と見られ、権利を失います。くじは1、2、3というように番号が振られます。引いた番号がその人の順番を示します。公平で秩序ある割り振りです。いさかいもなく、基本のルールは何か、奥の手があるのではなどというあいまいさは消えます。 この時期、わたしは妻のドリーンがわたしの病気に協力的でないと感じていました。わたしが公平な解決策のためのやり方を説明すると、くちびるをかんで、じっとわたしを見るのでした。そしてこう言いました。「デニス、あなた忘れたのかしら。そういうやり方ってここではダメよ。切り札的に使えるルールってものがないの。なんでもありなの、ほとんどのことは。マレーシア人が飛行機に乗るときのやり方を見て。来た人から順番に、なんてのはない。整列することがないんだから。われ先にの大群が飛行機になだれ込むんだから」 「でも、わたしたちは飛行機じゃない」 ドリーンの言うことは的を得ていましたが、わたしは言い張りました。「我々も文明人になる努力はできるはずだ」 「あなたが何をしようとしてるのか、わからない。あなたを理解できないわ」と妻。 頭にきつつ、わたしはことを進めました。皆がわたしのやり方に賛成してくれました。クー夫人を除いて。クー夫人はわたしと話すのを避けていました。 クー夫人は鼻をならして言いました。「どんなゲームもアタシはしません」 「ゲームじゃないですよ。公平なシステムを実行するためのものです」 「何のシステム?」 クー夫人は心から困惑しているようでした。「これはアタシの椅子です。なんでそれを皆と分け合おうと思わなきゃいけないの」 わたしはため息をつきました。「ねえ、そうでしょう。それが問題なんですよ。これはあなたの椅子じゃない」 「クー夫人。あなたが毎日座っていられてるのは、他の患者、皆が大目に見てくれてるからですよ。好きなようにさせてくれてるだけです。ここに座る心地よさをあなたに譲ることで、皆は自分の愉しみをあきらめているんですよ」 クー夫人は張りつめた顔になりました。目を細め、声の調子が鋭く高くなりました。「何を言っているの、あなたは。何を皆があきらめているですって」 わたしはおでこをこすりました。「限界効用っていうものです。あなたは、皆があなたほどこの椅子に座りたいとは思ってないでしょう。でも皆座りたいんです。わたしもです。ナンバーワン安楽椅子に座れることは、わたしにとっても、大きな喜びなんです」 「ドクター・タン。アタシ、あなたの言う玄関供養の意味がわかりません。あなたには、アタシにとってこの椅子がどれほどのものかわからないんですよ。どうやってもね」 わたしはだんだんいらいらしてきました。「それはわたしたち皆、同じですよ。パク・アジズにとってナンバーワン安楽椅子に座われるってことがどんなことか、あなたわかりますか。わたしにとってもです。このシステムは公平です。誰にとっても公平なんです。皆賛成してます、だからこれについて、あなたは従うしかないんです。わたしはあなたの優先意識を放棄してくれと頼んでるだけです」 「それがどうかしました?」とわたし。「わかりました、では、クー夫人は参加、それとも不参加?」 クー夫人がにらみつけました。しまいには彼女は頭をふり、わたしはほくそ笑んでクー夫人の名前をリストからはずしました。
わたしたちは順番に椅子を使いました。どの人も安楽椅子を自分流に使うやり方をもっていました。クマル夫人はレースの椅子掛けを持ち込みましたし、ダニエル・チーはスパイダーマンが跳ねまわっている派手なタオルを、パク・アジズは水のボトルにローラー付きマット、小さなバナナの房を常備しました。他の人たちもイニシャル入りの枕やタイガーバームの瓶、ペパーミントの芳香剤などを持ってきました。クー夫人は看護婦詰め所近くの椅子に追いやられ、そこから敵意を感じさせるきつい眼差しを向けてきました。これについてドリーンはこんな風に言っただけです。「どうしてなの、デニス。道徳で一人の老婆を打ちのめしていい気になってるのね。つまらない古椅子のために」 この言葉にわたしは傷つきました。妻がことの重大さをまったく理解していなかったとしても、何が論点なのかをつかみそこねていたとしても、です。
でもそのとき、クー夫人はこう言ったのです。「タン教授、あなたは貧乏というものを知らないんですよ。あなたは銀のさじを与えられて育ったみたいに見えるわ」 わたしは眉をひそめました。「いやそんなことはないですよ」 わたしはどれほど奨学金を得るために努力しなければならなかったか、ロータリー・クラブでわたしの希望がどのようにして断たれたか、そのせいでわたしの父は、わたしを大学に行かせるために、家と商売である建設事業を担保にしてローンを組まねばならなかったか、そういうことをクー夫人に話しました。カーネギー・メロンに着いたばかりのときは、中華レストランでフロア係の仕事にありつくまでの一週間、パンと水だけでしのいだことも付け加えました。「本当に辛い時期をわたしだって経験してるんですよ」 クー夫人は口の中で入れ歯を転がしました。「ふーーん、そうねえ、かなり違うと思いますけど。あなたにとっては、そうだったんでしょうね」
ある朝のこと、わたしたちはナンバーワン安楽椅子のレバーが利かなくなっているのを見つけました。この椅子は他の椅子が二、三段のリクライニングしかないのに対し、ゆっくりからだを横たえられるようずっと後ろまで倒すことができました。なんと足台までもが故障していました。誰かが故意に手を加えた跡もなかったのですが、ひとたび論議が始まると、皆の憶測はとどまることがありませんでした。クマル夫人は、昨日の午後の治療をちょっとした理由で、クー夫人と交替したことを告げました。透析治療は一日に二回だけです。午前に一回、午後に一回、四時間ずつです。すると誰かが昨日の午後は正常に動いていたと言いました。椅子を最後に使ったのはクー夫人であることが判明しました。別の誰かが、ここで何か不正行為があったことを疑うのは理にかなっているだろうか、と訊ねました。 クー夫人をあからさまに非難する人はいませんでした。これ以上この件についてあれこれ言うのはなしになりました。椅子はもう使いものにならない、そういうことでした。シスター・パンドラはナンバーワン安楽椅子を、新しいコバルトブルーの椅子に置き換えました。ここの透析患者は縁かつぎな人々です。椅子は置き換えられますが、ナンバーワン安楽椅子の素晴らしさを受け継ぐことはできません。革のクッションは、赤ん坊が膨らませた風船をつかんだときのようにキューキューいいました。レバーも硬く、油をいくら注しても楽に動かすことができませんでした。 我々は仮想のいけにえを、今こうむっている不利益を非難できる対象を探していました。一種の群集心理が働いていました。クー夫人はその仲間内の輪の外にいることを選びました。そしてそのために、代償を払うことになりました。病棟の空気は、クー夫人への恨みで煮えたちました。すべてにおいて、クー夫人は排除されました。誰もティーケーキやケクロクのチキン・ビスケットや上等なウーロン茶をすすめたりしなくなりました。わたしは、何の証拠もないのにこうやって有罪判決をくだすのは公平なことなのだろうか、と思いました。誰もクー夫人が椅子を壊しているところを見たわけではありません。また彼女に動機があるかどうかも疑問でした。なんであの人が我々の人気の椅子を壊したいと思うのでしょう。 面白いのは、ナンバーワン安楽椅子がゴミとして捨てられたあと、誰もあの椅子について話したり、懐かしがったりしなかったことです。順番のシステムもなくなりました。わたし自身、椅子を恋しがることはやめました。使える間はあれほど称賛されていたのに、ひとたび壊れると、あっさりと葬り去られたのです。数学の博士号などなくとも、突然の病で倒れた我々の中に、元の健康なからだに戻れる者が現われるという、幸福をもたらす見本としてあの椅子が見られていたことは見当がつくことでした。 数日後、シスター・パンドラが掲示板を書き替えていました。わたしが近寄って見ると、シスターはクー夫人の名前を朝の治療から午後の治療へと替えていました。「何かあったんですか?」 わたしは訊きました。 「息子さんの話では、クー夫人は足の組織が冒されているらしいの。足を切断しなければならないかもしれないって。クー夫人は治療効果をあげるために、午前中、酸素治療を始めたんですよ」 「それは、、、」とわたしは絶句しました。 「クー夫人を気の毒に思うわ。去年、だんなさんを亡くしたところで、そのあと娘さんが流産して、今度は自分が足を失うかもしれないなんて」 この言葉を聞いて、わたしは首を締め上げられたように感じました。そのような底なしの不安と苦悶を受けとめるだけの、心の準備ができていなかったのです。わたしは自分を恥じました。その気持ちはヒリヒリとわたしを痛めつけ、何日も自分を見失いました。観念してドリーンに秘密をうちあけると、頭をかしげてこう言いました。「あのねデニス、わたしあなたに何か言うことなんてできない。だって透析を始めてから、どんなにあなたが辛い目にあってるかわかってるから。あなたも、あのピリピリしたおばあさんとそれほど変わらないのよ。あなただって、ささいなどうでもいいことにずっと囚われてきたの。わたしから見ると、あなたは自分のからだの健康状態を維持できなくなって、せめて取るに足らないあれやこれやを何とかしようとしてるだけなのよ」 ドリーンが言ったことはすぐに胸に響きました。わたしの妻はいつも洞察力に溢れ、混沌とした現実から、的を得た言い方で理にかなったことを切り取ってみせます。でもそのときのわたしは、あまりに自分を恥じていたので、ドリーンを怒鳴りつけることで、それを隠そうとしました。わたしは黙りなさいと言いました。自分の言ってることが全然わかってない、自分が病気でも死にそうでもないときには、そうやって好き勝手に偉そうにもったいぶった口がきけるんだ、と。 「そんなこと言わないで、デニス」 「そのペラペラとわかった風な言い方をいつやめるつもりだ」 わたしは大声を出しました。
それから何ヶ月かたって、トング・ファットの生鮮食品店でクー夫人とばったり出会いました。クー夫人は手術を受けたらしく、店の外のコンクリートの舗道のところで車いすにすわっていました。切断した足は肌色のリンネルの靴下でおおわれていました。その光景に、地獄の縁に立たされた気分を味わいました。わたしは回れ右をして、あいさつをするのを避けようとしました。クー夫人の息子がわたしを見つけ、手を振って呼びとめました。「タン教授じゃないですか」 わたしは今気づいたという風に、声がした方に振り返りました。 「ああ、こんにちは、クー夫人。お元気でしたか?」 クー夫人の目が、無表情にわたしの方に向けられました。「そうでもないわ」とクー夫人。苦痛と困難が性格をゆがませているのは明らかでした。そして彼女が以前と変わらず嫌みな女であることに、救いを感じました。 居心地悪さをわたしは感じていました。会話がつづきません。すると息子さんが言いました。「お元気そうですね、ドクター・タンは」 「ええ? まあ、年寄りは年寄りですがね」 わたしは咳払いしました。お見舞いの言葉が口をついて出ました。「足のことはお気の毒です、クー夫人」 「ああ、そうですか」とわたし。「そうなるといいですね」 クー夫人は頭をそらして肩を沈ませました。それは彼女の心のありようのままに見えました。からだの苦痛に打ち負かされた人の姿です。わたしはクー夫人の息子が、ビニールサンダルをペタペタと鳴らしながら、きびきびとした足どりで車いすを押していくのを見ていました。息子は母親の脇の下に手をあて、車の中にからだを押し込もうとしていました。クー夫人の体重に少しふらつきながら、前かがみになってズボンの尻を張らせて、母親のからだを車の中に押し込んでいました。車いすをたたむところもじっと見ていました。息子さんはやり方をまだマスターしていないようで、ストッパーを解除するのにノブを何度も動かしていました。そしてクー夫人親子が車で走り去るのをわたしは見送りました。友情では築けなかった絆が、憎しみと無念さという形で、クー夫人との間に生まれました。病気とはいかに平等なものであるかを言い続けてきたのに、共に病気に耐える仲間に対して、わたしはほんの少しの同情心さえ持とうとしてこなかった。ドリーンは正しかったのです。わたしたち患者は皆同じです。とはいえクー夫人とわたしは全く同じではありません。病気の大変さ、辛さはあったにしても、わたしは公平さや道徳的な正しさという自分の尺度にしがみついていました。それはわたしにはまだ、希望や美しさ、真実や奇跡を思うだけの余裕があったからです。わたしがクー夫人と同じだと、はたして言えるでしょうか。赤々と燃える朝の太陽のもとそこに立ちすくみ、クー夫人の息子がわたしに軽く会釈して、車で走り去ったときの光景を思い出していました。クー夫人は窓のところに頭をもたせかけ、多くのことが意味をもたなくなった孤立した世界へ、ひとり病苦に耐える世界の中へと崩れ落ちていきました。
|
||||