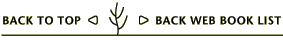
|
|
|

|
白皮の松(1)
|
|
|
白皮の松は、松の中でもっとも高い場所、そこから上には茶色っぽい草か、割れ岩の下で咲くバラ色のシエラの桜草くらいしか生えないような、キアサージュの斜面のとても高いところで育ちました。ずんぐりと背は低く、幹は岩を這って伸び、葉は冬の厳しさのせいでかやぶき屋根のように密生して木全体をおおっています。キアサージュの斜面では、雪は一年のうち八ヶ月もあり、松の木やギザギザ岩の上をすっぽりとおおうように降り積もっています。雪のない季節は、猛烈な雨嵐が何回もあり、いつも強い風が山あいをゴーゴーと吹き荒れ、そのせいで、木がまっすぐに伸びようとしても、この高さの場所では無理なことなのです。白皮の松は地面に寝そべるように生えていて、四百歳になろうというのに、幹は人の太ももほどの太さもないのですが、七十五年から百年くらいの若い枝たちは、とても柔軟で、くるりと自分の枝でコブを結んでみせるほどです。この木は、山の頂上を越えて反対側に伸びていく山道のすぐそばで育ちました。
春が近づくと、道のあちこちで珍しいことが起こりました。年が開けてまもなく、山の高いところの雪が溶け出す前、ビッグメドウズの先に寝ぐらのあるのっしのっし歩きの大グマが行き過ぎて、キアサージュのふもと町の子牛小屋や豚小屋に向かって降りていきました。大グマは冬眠から覚めた空腹期に、二、三十キロメートルのちょっとした遠出をしてあたりをさまよい歩き、ときに、銃をもち犬を連れた猟師に出会うことはありましたが、それ以外には何ものにも出くわすことがありませんでした。雪の斜面からの雪解け水が小川になって道の上を走りはじめると、森林警備隊の男が歌を口ずさみ、両腕をバシバシたたいてからだを暖めながら山道をやってきました。そして雪解け水がぜんぶ掃けてしまった後、再びやって来て、その道を修復しました。夏の間は、坑夫や猟師たちの一団が荷を背負った長いラバの隊列を引き連れて、ビッグメドウズかキングス・リバーの支流のところで野営するためにキアサージュを越えていきました。家族連れのインディアンの一行もそこに来て、ベリーや魚やシカ肉のご馳走を楽しげに囲むこともありました。ほとんどの場合、この山を越えていくものはまたやって来ること、同じ人々が何回何回もやって来ているのだと、白松は気づいたのでした。四百年間の観察と思考を経て、そのような認識が得られたのです。白松はだんだん山の反対側の方がきっといい場所に違いないと思うようになりました。
「そうでなきゃ、なんで」と白松、「あんなにたくさんの人たちが毎年あっち側に行くんだ?」
|

|
白皮の松(2)
|
|
|
きっと誰もがそう思うでしょうけれど、白松の側はそれは素晴らしいところで、でもこの木はこんなにも何年もの間ここにいてあらゆるものを見てしまったので、もう何も楽しいことが見つけられなかったのです。白松は自分の育った場所から、ざわめく木々がうっそうと生え上がる、くねくねした峡谷の間でまばたきしている青い湖を見おろしました。開けたところでは、谷に流れ落ちていく白い水の足どりや、滝が白皮の松に向かって投げキッスでもするように、虹色のしぶきを送ってよこすのが見えました。眼下には、子ジカ色をした茶わんのようなくぼ地があって紫色の靄(もや)が降り、農場や果樹園がカップの底のおりみたいに横たわっています。谷の向こうには気高い連山が立ち上がり、その斜面をおおうように雲の影が戯れていました。
「おんなじものを四百年もの間、見続けているってのは、まったく退屈なことだよ」と白皮の松。「ああ、頂上にちょっとでも行けたらなぁ。ねえ教えてよ、あっち側はどんな風なの?」こう風に聞きました。
「そうだな」と風。「雨や雪が降ってるよ。木があって、やぶがあって、青い湖があるよ。こっち側とまったく同じだね」
一番高い松の木のかやの下で一晩明かしたシカも同じことを言いました。「草地と丘ばかりさ。ときどき草の状態が悪くなったり、良くなったりするくらいでさ。こことそっくりおんなじさ」
「みんなの言うことは信じない」と松はひとり言。「ぼくが野心に取りつかれたりしないように、なぐさめを言ってるだけさ。でもぼくはもう若木じゃないんだからね」
「少なくとも」とまだ背の低い若い木が言います。「あなたはわたしたちの中では、一番高い場所にいるのですから」
「ぼくがどれだけ頂上に近いかってことが、なんでそんなに問題なの?」と楽しくない松の木。「青い花の群れがあそこにあるけれど、あの花が尾根を乗り越えていっているのが、ここからちゃんと見える。ぜったいにぼくもあの青い雑草と同じように、尾根を越えていくことができるさ」
「でもね」と若い松。「雑草っていうのは、松かさを付けなくてもいいんですよ」
「あー、松かさね」と白松は不機嫌そうに声をあげました。「季節が短すぎて、ぼくはまだ熟させたことがほとんどないんだ。熟せばリスがやって来るだろうけどね。この二百年というもの、ぼくは種木を育てたことはないと思うよ。ぼくにそんなこと言っても何の意味もない。ぼくは山の向こう側を見ることだけが幸せなんだからね」
|

|
白皮の松(3)
|
|
|
それは長年のあいだ心から望んでいたことが、ある形でやっとかなった、という風に見えました。白皮の松が、まさに、キアサージュの山を越えた年。夏のはじまり、バラ色の桜草が丸石の間にたまった雪のそばでちょうど咲きはじめるころ、坑夫の一団がツルハシとシャベル、小麦粉にじゃがいも、その他坑夫が使うさまざまな道具を負わせた荷ラバの長い隊列とともに道を登っていきました。キアサージュ・トレイル最後の登りはもっとも厳しく、雪崩のようなごう音をたてながら、遥か下の渓谷に転がり落ちていきそうなゆるんだ石の急斜面を越えることでした。坑夫たちは声を荒だて、ラバたちは急斜面をよじ登り、あえぎ声を出しました。最後の白皮の松のところに来たとき、一匹が足をすべらせ、ギザギザ石の上をごろごろと転がり落ちていきました。荷を積む動物にとってそれはよくあることなので、ラバはたいしてけがもしませんでしたが、クラの方はかなり傷みました。
「できるだけの処置をしよう」一人の男がこう言い、白皮の松を切りにかかりました。大枝を切り落とし、幹部分を四つに裂き、荷を補修しました。木は大変な樹齢でしたが、とても小さい木でした。
「あーあー」と木が叫びました。「痛い痛い。でも望みがかなうなら、気にしないさ。ぼくはいま、頂上に行こうとしているんだからねぇ」。こうしてこの木は年老いた旅人のように、ラバの背に乗ってキアサージュを越えたのでした。
「よしよし、これであいつの不満話を聞かなくてすむ」。隣に立っていた松の木が言いました。「その上、これでわたしが一番高いところにある松ということになる。ほんとうにあっち側はいいところなのかねぇ」
その木の昔の仲間、今や四つの切れっぱしは、山の反対側を揺れながら降りてき、その途中で高い峰々や芝の草原、水が飛び散るくねくねとした長い峡谷を眺めました。そして滝のコーラスも聞きました。日が暮れると坑夫たちは火を焚き、荷をゆるめました。暗くなって風が木々の間に起こりはじめ、焚き火の火が低くなったとき、一人の坑夫が白皮の松の一切れをその中に投げ入れました。
「あちあち!」松は火に囲まれて叫びました。「これがぼくの旅の終わりってこと?」
「生木がこんなにパチパチいうなんて!」と男。「焚き火にこれはむかないな」。
次の日、風が灰をつかんで峠の向こうに運び返し、切り倒された弱々しい枝が横たわる地面の上に落としていきました。
「あれ、この灰があの?」と松の木たち。「さあ、あっち側がどんなだったか、言ってもらおうじゃないか」
「なんてきみたちは無知なんだ」と灰になった白皮の松。「旅したことがなかった、って知っただけだろ。こっち側とまったく変わらなかったんだろう?」。でも松の灰はみんなが言っていることが聞こえませんでした。そのとき風が灰を巻き上げていったからです。
(2003.9.20.改校)
|
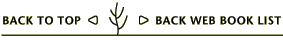
|
|
|