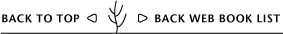
|
|
|

|
黄金運(1)
|
|
|
レックス・モンテに向かう道から少し山の方に入った、豪雪域の境界からさほど遠くはない場所に、まあるい暗い穴のようなものがあります。それは昔の鉱山のトンネルでした。以前には、松材むきだしの小さな家が、トンネルのかたわらの石捨て場のところに立っていましたが、大きな雪崩のときに、家も石捨て場も押し流されてしまい今は跡形もありません。ジェリーという名の坑夫が小屋を建てて、ひとりっきりで住んでいたのですが、その男のことはいまでは、キアサージュのふもとの町の人々も、誰ひとり覚えてはいないでしょう。
ジェリーは年老いて肉がそげ落ち、若かった頃は黒かった髪も鉱山にころがっている鉄錆の岩のように色がぬけていました。三十年の間、ジェリーはキアサージュからコソ・ヒルズにかけての一帯に目をつけて採掘してきましたが、いつも他の者にしてやられ続け、そしてついにレックス・モンテの岩棚に行き着いたのでした。外見を見ただけの者には、そこは男が死ぬほど働いてもほんのわずかの鉱石しか採れない岩壁の間のやせた鉱脈にしか見えませんでしたが、ジェリーの話に耳をかす者がいたならば、ここで何があったのか、ジェリーが何を待っていたのかというおどろくべき物語を聞くことができたでしょう。ずっとずっと昔のこと、ジェリーは長いさすらいの旅の果て、もう疲れてあきらめようとした矢先に、ここを見つけました。ある昼さがりのこと、レックス・モンテからさほどないところを歩いていたジェリーは、休憩のために大きな岩影の下にやって来ました。そこで疲れて横になってうとうとしているとき、まばらな草のあいだにまき散らかされた石クズに目がとまりました。見ているうちに、それはがれきからこぼれ落ちたある鉱石の破片ではないかと思い、じょじょにその思いはふくらみ、確信が湧きはじめ、ついに、思いが頂点に達しようとしたとき、その石クズが目くばせをしたのです。ジェリーは手をのばして、手の中に石クズを取り、金がその中にふりまかれているのを見ました。ジェリーがどんなに喜んだことか。とび起きて、もっと石を見つけようと探しはじめると、金のこぼれたあとが見つかり、それを追いかけて草地やヒースの間をぬけて行くと、風化した大岩のそばにある実りの岩棚にたどりついたのです。そしてその岩棚は、あああ、なんて見事な。いまやジェリーは、鉱山の主です。そこを黄金運と名づけ、そこを見つけたことは誰にも言うつもりはなかったけれど、キアサージュのふもとの谷あいの町に降りていって、採掘するのに必要なものだけ手に入れて戻って来ました。
夏の終わりごろになると、長い長い雷鳴と地をうつ雨が山々をおおい、それから何週間もたたないうちに、静かに雪の嵐がやって来ます。ジェリーは、冬が来る前に、黄金運の場所を安全にいい具合に整えました。傾斜地に降り積もる深い雪にじゃまされないように、岩の方に向かって小屋を建て、そこから金鉱のトンネルまで道におおいを作りました。これで冬のあいだ、雪嵐が来ても心配なくここで作業ができそうです。
|

|
黄金運(2)
|
|
|
ジェリーがこの辺のあらくれ男がするように忙しく立ち働いてひと月くらいたったころ、寒さは霜をともなって夜ごときびしくなっていました。朝には河淵(かわぶち)に張った薄い氷がチンチン音をたてているのが聞こえてきました。それは雪の兆しを感じさせながらも、暖かで空気の乾いたある午後のことでした。ジェリーは小屋の屋根を熱心に葺(ふ)いていたので、声をかけられてはじめて、道に男が立っているのに気づきました。ジェリーは男を見てすぐ、服も話し方もこの辺りの者ではないこと、山越えや野宿の用意がないことを見てとりました。ジェリーがそのことに気づいていたのは確かなこと、でも家のことと金鉱のことで頭がいっぱいで、気にとめようとはしませんでした。自分の幸運が誰かにもれてしまいはしないかと、恐れて続けてもいました。それで通りがかりの男が道についてあれこれ質問しているときも、ジェリーは一刻も早くその男を追い払いたいようでした。男は若く、血色のいい顔に青い目をしていて、無頓着にものを言う坑夫たちが「オランダ人みたいな連中」と呼んでいる外国人のようでしたけれど、実際何者であるかを知る手だてはありませんでした。ジェリーは、この男がビッグホーン鉱山の方へと続く道を行こうとしているのを知りました。そこでこの男は仕事を見つけようとしているようです。二人はうなずきあったり肩をすくめあったりしていましたが、ジェリーはこの道を行けば問題ないと言わんばかりにそちらを示しました。若い男はジェリーの小屋と空模様を何か言いたげに見ていましたが、ゆっくりと道を去っていきました。男がちょうどレックス・モンテに通じる角に来たとき、尾根から名残惜しそうに手を振ってきたので、ジェリーも振り返し、男はやっと姿を消しました。そのとき太陽が、空の四半分をおおうくらいの大きな灰色雲の影に、姿をかくしました。
夜になって、ジェリーはあの若者のことが思い起こされ、心を悩ましました。風が吹き上がり、峡谷じゅうを走りまわり、斜面を雪がすべり落ちはじめました。三日三晩、それは続きました。その間ずっと、灰色のとばりがジェリーの小屋をおおっていました。ときおり風がヒースの上の積雪を見せつけるかのようにザザーッと雪をすくい上げていき、その雪嵐で小屋はやわらかな雪音とともに白いベールにつつまれ、視界を失います。ジェリーはと言えば、黄金運で働いてはいましたが、あの若者のことを心から追い出すことができませんでした。
太陽の熱と凍てつきで雪の表面に硬い皮ができ、その上を人が歩けるようになると、ジェリーはビッグホーンへの峠を越えていき、あの男がこの辺りに来たかどうか探りに行きました。あの日男が小屋を通りがかったのは遅い時間だったことや、男が名残り惜しそうに小屋の前を立ち去ったこと、どんな空模様が予想されたかなどについて、だれにもしゃべっていませんでしたし、その後もずっとそうでした。雪は山道をおおいつくし、松の木にはふんわりと、くぼ地にはたっぷりと降り積もり、あの男がこの深い雪の下に埋もれていたとしても、いったい誰が見つけられるでしょう。それにあのよそ者は、ビッグホーンで知るものもいないはずですし、もし雪の下で見つかるにしても、それは春の雪どけ後のことです。あの男にかかわることは何であれ、ジェリーは非難をうけなければならず、その自分がひき起こしたことのために、その日以来、ジェリーの黄金運は消えてなくなりました。鉱山の涸(か)れや減少なくして、黄金の粒は消え去ったのです。その後ジェリーはあらゆる努力はしたものの、レックス・モンテの傾斜地の小屋を維持していくことができなくなりました。小屋のドアはしばしば閉ざされ、道具類は黄金運のトンネルの中で何ヶ月も錆びついていました。ジェリーは豊かな金鉱を前に稼(かせ)ぐことから見放されたのです。
|

|
黄金運(3)
|
|
|
それからの日々、ジェリーは以前の黄金運を懐かしみ、それと同時に、あの嵐の夕べに山道へと追いやったよそ者の男のことを思って過ごしました。そうするうちに、徐々に二つのことがつながっているように思え、頭を混乱させるのでした。自分の幸運は、あのとき、よそ者といっしょに、深い雪の中に葬り去られたのだと。ジェリーは自分のことを釈明できると思っていましたが、キアサージュとコソ・ヒルズの間のこのような地帯では、よそ者の面倒をみないそのことが、手ひどい攻撃になってしまうのです。
毎年のように、ジェリーは金鉱にもどってきては少し仕事をしましたが、あるときは有望のように思え、またあるときはそうでもないといった風でした。そして、自分が与えた損害をつぐなわない限り、幸運はもどってこないと思い至ったのです。ジェリーはそのチャンスを探しはじめました。そしてしょっちゅうそのことをぶつぶつと口にしていたので、しまいには坑夫として生きる自分へのお告げであるかのように思いはじめました。さらに年をとって、黄金運のところで住みつくようになってからは、夕方になるといつも道行く人々を監視し、あらゆる人に自分の小屋で一晩泊まるよう説得するほどでした。風が吹いて、雪が滑り落ちているときなど、吹きだまりで誰かが叫び声を上げているのを聞いたような気がしました。そうするとランタン片手に嵐のただ中に出て行っては、泣きながらじっと外を見つめるのでした。
そのころになると、月に一度食料の補給などでキアサージュのふもとの町に降りて行ったとき、町の人たちが笑いながら頭をふったりするのを見ては、みんなが昔の自分の不親切なふるまいを噂してると思い、さらに臆病になり、人の集まるところにはめったに行かないようになりました。そして自然の中で多くの時間を過ごすようになり、山の中に埋もれるようにして暮らすのでした。ジェリーの小屋は岩と同化したように風化して、ウサギが入り口から出たり入ったり、シカが水を飲みにきたりしていました。
町から登ってくる道が、小屋のたっている斜面のところから先は峡谷に沿ってくねくねと峠を越え、シカやオオツノヒツジの牧草地になっている高原地帯へ、さらに高く険しい頂上へとのびています。レックス・モンテの峡谷は、高地の谷間から低山に降りる道が、冬のあいだも緑があって、いいエサ場なのです。毎年ジェリーは、山に雪が降り積もると低山の牧草地へ降りてきて、春になって溶けた雪が滑りおちてくると山にもどっていく野生動物の一群に目をとめていました。だから年を重ねるごとに、ジェリーは野生の鳥や動物がどのように季節を過ごすのか、高い尾根のところでは何をしているのか学んでいきました。ライチョウとウズラが山を降りるときは、牧草や小さな薬草が雪におおわれたしるしで、シカが雲の中を美しい群れをなして通り過ぎると、バックソーンやヒースに雪が吹きだまっている証拠というように。最後に、オオツノヒツジが軽快な足どりで峡谷を走りおりていくと、ジェリーはキアサージュやレックス・モンテの山頂付近で、つらく厳しい不毛の仕事を始めるのでした。ジェリーが嵐の中で人の声を聞くのはたいていそんなときで、煙突の通風溝の中みたいに風が峡谷を上へ下へと渦巻く中を、骨まで冷たくなって、ランタンを手に降りしきる雪嵐の中をよろめきながら歩いていくのです。そして小屋の暖かな火のもとへ這うようにして帰り、あの青い目のよそ者が帰って来て、黄金運をふたたびもたらしてくれたらと夢想するのでした。そうやってあの「大雪の冬」がやって来るまでの何年かを過ごしました。後にそう呼ばれるようになったその冬は、キアサージュの東斜面ではかつてない大雪になりました。
|

|
黄金運(4)
|
|
|
その年はいつもより早く、暖かな数日につづいて、靄(もや)が空いっぱいに広がって太陽や月をおおい、冬がはじまりました。生暖かい空気のかたまりが嘆き声をあげながら、松林の間を逃げまどっていました。シカは野生の感で雪が降り始める前に山を降りていき、ジェリーはそれを見つめ、親しみの気持ちでいっぱいになり、シカといっしょに山を走り回った日々ことを、雪の季節の前にはいつも暖かな日々が通り過ぎることを、何年か前にこの黄金運から幸運が去っていったことを思い出していました。やがてもうもうたる嵐に小屋が閉じ込められ、雪がそこらじゅうに舞うころになると、年老いた男はあのよそ者のことをもてあそぶように考えはじめ、外の声に耳を澄ますようになりました。雪が本格的に降りはじめ、どんどん激しく、どんどん積もっていき、吹雪になりました。
雪が激しくなって三日目の晩、ジェリーは降り積もる雪の中から聞こえてくる、自分の名を呼ぶこもった弱々しい声で目を覚ましました。そのようにジェリーには聞こえたのでした。で、急いでそれに答えようとしました。外は風もなく静まりかえっていました。小屋の立っている険しい斜面には、やわらかな雪がひざくらいまでたっぷり積もっていました。谷間では松が半分くらい雪に埋まっていました。ジェリーのランタンが弱々しい光でじっとあたりを照らしました。声はもう聞こえませんでしたが、道の下の方で、何かがうごめいていました。人間ではない影のような何かが吹き降る雪の中で暴れていました。ジェリーは吹き降りの壁に遮断されながら、大丈夫だぞ、とそこに向かって声をかけました。
丘の正面の傾斜地には小さなくぼ地があって、道はそこから先、小屋の方に向かってのびていきます。くぼ地に湿った雪が溜まると、小屋からの道は砂州のようにその中を走っていって、途中で消えてなくなります。雪嵐が最後のひと暴れをしている時、この道を、大きな頭に軽快な脚力、冬山の証であり、そびえる胸壁にたたずむ「神の羊飼い」と言われるオオツノヒツジが降りてきました。高原では草も、やぶ木も、ヒースの小枝すらなくなったので、暗くなってから小屋のそばの湿った雪だまりを食べに降りて来たのです。雪の吹きだまりの中をはるばる、大きく巻いたツノを振りながら、やって来たのです。そしてここで、道が白い雪の塊の中に消えているところで、オオツノヒツジたちは足をとられ、その中にはまってもがき腹の深さまで沈んでいきました。さらに沈まないようにじっとしていることもできないようでした。ジェリーの夢の中に自分たちのちぎれしわがれた鳴き声が届くとしても、ヒツジたちはそうはしようとしなかったし、同じような直観から、ジェリーも、雪のベールの向こうで起きていることを実際に目にすることなく、ヒツジたちが助けを必要としていることがわかりました。湿った吹きだまりから固い地面にはい出てくるまで、音のない激しいもがきがありました。オオツノヒツジたちはふらつく年老いた男の手の中の、光の亡霊に追いたてられて、影のように進んでいきました。その晩は人が外に出ていくような天候ではありませんでしたが、ジェリーは吹きだまりの中に入っていって、探し物を手に入れるまで作業をつづけました。吹きだまりが一番深く、毛織物のようにやわらかい場所で、ジェリーはついに、肩まで埋まりもがいたあげく弱り果て、それでも気高く抵抗しているヒツジを、群れの中で最も年老いた一匹のヒツジを見つけました。どれだけの年月、人生最大の悪事を働いたこの場所で、良きことをする機会を待っていたことでしょう。ここ何年ものあいだ、ジェリーは人間か獣かわからないような状態の中を生きていました。ジェリーはヒツジの胸の下に体を入れて、恐る恐る心臓が脈うつ音に耳を澄ませました。
ジェリーは自分の採掘場と同じように、足元の地面の感じをつかむ仕方で、この道のことを熟知していました。それでジェリーの肩に担がれていく雄ヒツジもだんだん静かになって、くぼ地の中から抜け出すためにジェリーが額から大汗をかいているあいだ中、おとなしくジェリーの努力に手を貸しました。しかしオオツノヒツジはそれっきりなすすべもないようでした。やわらかな羊毛のような雪におおわれて、おびえ、震えながら立ちつくしていました。雪がサーッと降りかかり、道にいるヒツジの群れを追い払いました。でも年老いた一匹は動きません。そんな風にして山岳地帯の野生のヒツジが死んでいくことはよくありました。突然の嵐に老いたからだを捕らえられ、雪に足をとられてオオカミの餌食になるか、吹きだまりで凍えるがままになっているしかないという。老いたヒツジは吹き上がる風で傾きはじめた嵐の渦に背を向け、二度とジェリーの方へも、自分が育った丘の方へも目を向けようとしませんでした。それでもジェリーは雪でずっしりと重くふくらんだオオツノヒツジを見つめつづけ、それから小屋の建っている傾斜地の方に目を上げ、ヒツジにやる食べ物がないことを思い出しました。再びからだをかがめ、老ヒツジを引っ張ったり押したりをしたおかげで、そして男からヒツジへとしみわたっていく何かがあったのでしょうか、少しずつ道を進んでいくことができました。ゴツゴツした岩山を越え、吹きだまりの中では半ばジェリーがヒツジを引っぱり、半ばヒツジのりっぱなツノにジェリーが支えられながら、もがきもがき進んでいきました。降りしきる雪の中、音もなく流れるパイン・クリークをジェリーとヒツジは渡っていきました。雪は落ちるさきから急流に巻きこまれていきます。雪片がジェリーのランタンにシンシンと降り積もり、目も開けられない状態でしたが、行く道の間中、ジェリーの手助けで老ヒツジは少し楽になり、だんだん自信をとりもどして健気に進んでいきました。そしてついにジェリーとヒツジは、丘全体がバックソーンと桜の弾力ある枝でおおわれた雪嵐を寄せつけない場所に出ました。そしてヒツジがひとり茂みの下に行って大角を振っている間に、長葉の松の下でジェリーはからだを休めるのでした。ジェリーは迷いや過去を振り返ることから解放され、死を迎えるときのように穏やかに、人生の新しい門出に出会っていたのです。すっかり疲れ果て、頭の中では歌が鳴っていました。松の木々が風を押しとどめ、ジェリーの休んでいる木の下に雪のリースをふるい落としました。年老いた男にはこの上ない場所に思え、すわったままうとうとし始めました。
|

|
黄金運(5)
|
|
|
「もし眠れば、凍死するだろう」とジェリー。それも悪くないように思えました。そしてしばらく時間がたちました。闇の中から何かが現われ、ジェリーの肩をゆすり、その名を呼びました。ジェリーは一時間ほど前にもそうやって目覚めようとしたときのように、夢の世界から目覚めようとしました。ジェリーにとって、辺りは夜で、嵐でもなく、暗闇の中照らし出されているのが青い目の男でないということ(それはランタンの灯りのせいかもしれないと思いましたが)、そのどれもがちっとも不思議ではありませんでした。ジェリーは肩の雪をはらいました。
「ずっと、君のことを待っていたよ」とジェリー。
「だからこうして来たんです」と男は言って笑いました。
「君は幸運を返しに来てくれたのかな?」
「こっちに来て見てください」と男。
ジェリーは男の手にすがり、二人して雪の吹きだまりの間の道を登って行きました。
「君はぼくのしたことを恨んではいないのかい?」とジェリー。
男は「いいや」と答えました。
「取り返しがつくものならと、何度思ったことか」年老いたジェリーが言いました。「今夜ここでその償いをしようとしていた」
「何でそれを償おうとしていたのですか?」
「ただのヒツジさ」
「神の生き物ですね」男が言いました。
二人は道を登っていきましたが、ジェリーは暗がりの中をひとり歩いているようにも思えました。ジェリーは凍え、ランタンも消えてしまいました。するとまた男がジェリーに話しかけ、励ます声が聞こえました。やっと小屋の見えるところまで来て、窓から明かりがもれているのを、暖炉で火がパチパチはねているのを目にしました。ジェリーは金鉱のことを、あの男が黄金運を返してくれたのではないかと思いました。その若い男はそうジェリーに約束したように思えました。確信があるわけでなく、自分が家に帰ってこれたということ以外は、すべてがぼんやりとしていてよくわかりませんでした。でもジェリーがトンネルに近づくと、中から輝きが、明るいすばらしい光が見て取れたのでした。震えながら中に入ると、その光はトンネルの壁から、そしてずっと奥の方の鉱脈からも放たれているのがわかりました。それは純金の輝きでした。にっこりと笑うとジェリーは手をそこに伸ばし、幸運が戻ったことを手の内でしっかりと確かめるのでした。
大雪の過ぎ去った後、ジェリーのことを思い出した町の人々は、雪の間ジェリーはどうやって生き延びただろうかと考えました。そこで雪の表面が固まると、風すさぶ峡谷沿いに登って行って、ジェリーの家の中を探しました。ドアは開け放たれたままで、ランプの火が弱々しくゆらめいており、鉱山の中に入ると、トンネルの奥の方にジェリーがいました。そこで笑みを浮かべて眠っているかのようでした。
「もう価値のない鉱脈なのに」とみんなは言い、「でもこいつはここを愛していたんだな」と。
人々は火薬を取り出してそこを爆破し、石の山を積んでトンネルの奥を外界から遮断しました。だからジェリーは戻ってきた幸運と黄金の鉱脈とともにそこにずっと眠っているというわけです。
(2003.12.25..改稿)
|
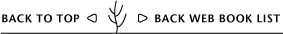
|
|
|