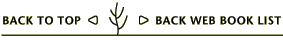
|
|
|

|
クリスマスツリー(1)
|
|
|
シエラ山脈の東の方に、パイン・マウンテンという名の真っ赤な丘があります。インディアンたちが夏雪の丘と呼ぶ丘です。そのふもとには板塀の家百軒ほどの町があって、町ぐるみで採鉱業に身をゆだねていました。採鉱所の騒音は昼も夜もやむことがなく、まきあげ機のキーキー音、選鉱場のゴロゴロうなり音、くず石場に駆けおりる車のガシャガシャ音、そして酒場の開け放たれた扉からは弾けるような笑い声と歌声がいつも聞こえていました。高い煙突からは煙がもくもくと吹き上がり、夜にはゴーゴーと爆音をあげながら溶鉱炉の火が赤く燃えさかっていました。
炭焼きの息子は、その赤い煙やギラギラした溶鉱炉の熱い吹き出しを見て育ちましたが、それはまるで町をときどき通るといわれる邪悪な生き物の吐く息のように思えました。といっても、その子が邪悪な生き物について聞いたのは、町の人々のうわさ話や子どもだましの作り話にすぎなかったのですが。炭焼き一家の小屋はパイン・マウンテンの支脈、町から六百メートル登ったあたりにあって、少年は父親が炭を届けに町まで下りて行くとき、荷を積んだロバの背にまたがって一緒に行くことがありました。その子が知っていることといえば、山の生き物や木について、嵐や小さな花々について、それと松の木の燃えさしみたいな、森の匂いがする遠い母の思い出くらいでした。母親が生きていた頃、一家は町に住んでいて、父親は鉱山で働いていました。その頃、町には女や子供は少なく、鉱山の男たちは短気で荒っぽかったので、まだ若かった母親は幸せではありませんでした。
「こんな所でこの子を育てたくない」母親は死の床で言ったもの。母親の亡きがらを荒くれた土でおおって埋め終えたとき、気を紛らわせるつもりで父親は、太陽の下で真っ白に美しく輝く、夏雪の丘の方を見やりました。その丘は、すすけた汗まみれの町の上に空高く、その名のとおり涼やかに泳いでいました。父親は小さな息子をつれて山に入り、アメリカカラマツの下に小屋をたて、炭を焼く炉のための穴を掘りました。
|

|
クリスマスツリー(2)
|
|
|
男の子を育てる場所として、パイン・マウンテンの丘ほどすばらしい場所はなかなかないでしょう。樹脂のしたたる松の木、ブドウ酒のような香り高い風、泉に湧く透明な水、そしてほっつき歩くのに不自由しない山あいのそこかしこ。炭焼きの息子ははるか山の上の方まで出かけて行っては、雪の境界線のあたりの土手で摘んだ珍しい花々や、キラキラしたホタル石やクジャク色の鉱石や、帽子いっぱいの木の実や、ピチピチしたマスをたずさえて帰って来ました。まるまる午前中、氷河の牧草地でワシの鳴き声をききながら遊びほうけたりもしました。もやの中を歩いていってシカに餌をやったり、深いシダの茂みの中の寝ぐらまでシカを起こしに行ったこともありました。冬には雪靴をはいて積もった雪の吹きだまりの上を歩いていって、松の木のてっぺんにいるスズメやライチョウをのぞいたり、緑のテントの中で冬越ししている寒そうなコマドリを見つけたりしました。深い雪に持ち上げられて、木々のひみつを知ることができたのです。でもそれは男の子が、小さなモミの木のようにすくすくと成長してからのことです。まだ小さかったころは、斧や炭焼き場のところに行けないよう長いロープで松の木に結ばれて、一日中過ごしたもの。そして、ひとりで出歩けるようになったとき、父親は三つの約束を息子にさせました。熊のあとをつけたり、熊の子にかまってはいけないこと。ワシの子についてワシ岩に登っていってはいけないこと。ガラガラヘビがよく出る日の当たる南斜面で寝ころがったり、眠ったりしてはいけないこと。それ以外のことは、森でなにをしても自由でした。
その男の子、マシューは十才になると、炭焼き場を手伝うようになりました。これから切る木にしるしを付けたり、木炭を袋につめたり、家事や父親の弁当づくりもしました。同じ年くらいの友だちはいませんでしたが、銀モミの木たちがそばにいたので、とくに友だちが欲しいとも思いませんでした。銀モミの木立は小屋の下の湿ったくぼ地から、美しく空高く生えあがっていました。モミの木の生えている地面はすべりやすく、枯れた刺葉でいっぱいです。枝を重ね合わせるように密集して生えているところでは、木々のてっぺんは緑色にあかるく輝いていましたが、その下の幹の間は暗く、もやのようなうす青い光がさしていました。それは古いモミの木立で、三百年もの間、頭をくっつけ合って生きてきた仲間なのです。この老木たちを取り囲むように、親木のまいた種で育っている苗木や若木が点在していました。そしてそこから少し離れたところに生えている一本の木、それがマシューの友だちでした。そのモミはほっそりとした白銀の幹から扇状に枝をひろげ、美しいピラミッドの形をしていました。春になって、木の表面がクモの巣がかけられたように若葉でおおわれると、かぐわしい匂いが漂いはじめ、お母さんがいたころのことが思い出されました。マシューはモミの木に花の輪をかぶせ、枝からたわわに頭をたれている白クレマチスを飾りテープのようにかけました。木の皮のカップに、摘んだ木の実や泉で汲んだおいしい水を入れては、モミの木のところに運んだりもしました。マシューにとって、そのモミの木には心があるように思えたのです。
|

|
クリスマスツリー(3)
|
|
|
雪靴をはいての最初の冒険は、モミの木が雪の吹きだまりの中でどうなっているかを見に行くことでした。そして雪のふきだまりの上にのって、モミの木のてっぺんにある細い十字を見つけては、幸せな気持ちになりました。そのころのモミの木はそんなに背が高くなく、雪は炭焼きの小屋のあたりにほどよく積もっていました。そう、マシューとモミの木のてっぺんがちょうど同じ高さになったのです。でも少しすると、マシューはそんなに早く背が伸びないのに、銀モミの木の方は、毎年ずんずん若枝をのばして大きくなっていきました。
マシューは心のうちをいつもモミの木に話していました。さびしく心ふさぐとき、それはお母さんのいないさびしさのようでしたが、下枝をつたってモミのほっそりした幹を登っていきました。そして両腕を幹にまわして、静かなときを過ごしました。モミの木は男の子をいやすことができました。地上から遠く離れて、静かであたたかな腕の中に、その子を抱きとめました。マシューは木の下に自分の宝物を埋めて、その上に石のケルンを積みました。
こうしてモミの木に入って寄り添っているとき、整然と腕を伸ばしている枝のあいだに静かに手をすべらせては、どうやってモミの木はこんな風に育つ方法を知ったのだろうかと考えるのでした。モミの木はどれも、星が光をなげかけるように外へ外へと枝を伸ばし、ひとつ、またひとつと、季節ごとにその枝数をふやしていきます。どの枝もまっすぐに幹から腕をつきだし、生えはじめの若枝も、たくさんの小枝をつけて腕を広げ、針葉の重さで腕をしならせるようになった大枝の先端の小枝も、新たな枝を垂直に出すことで十字をつくり続けます。そしてたくさんの十字を抱いた木のてっぺんに、新しい若枝が伸びあがると、それは長くてほっそりとした十字になり、ひとつ星になって輝きます。そうやって若枝が次々に十字をつくり、十字と十字があちこちで重なって星になり、モミの木全体がまるで星を散らしたように見えるのです。整然ときちょうめんに枝を伸ばしていくモミの若木の成長ぶりは、木いちごなどほかの山の木の中で、とても不思議な見映えでした。成長していくときのこの木の楽しさを知っていれば、夏の山にいて、カシの二枚葉やキラキラ光るミミュラスの双子ラッパの花に出会わなくても、きっと楽しい夏を過ごせます。このときのマシュー少年は、銀モミについてもっと知る必要があるとは思っていませんでしたが、この木の秘密に気づいてから、あれこれ考えるようになっていました。少年は十二才の年までモミの木とともに成長し、その年令にふさわしい元気な男の子になりました。そして父親の炭焼きは、息子の学校をどうするか心配を始めました。
|

|
クリスマスツリー(4)
|
|
|
そうこうするうちに、パイン・マウンテンのふもとに、よそものたちがひっきりなしに訪れるようになり、溶鉱炉は煙を吐き出しては真っ赤に燃えさかり、町はざわざわと騒がしくなりました。炭焼きは息子が町をこわがっていることを知っていました。たまにいっしょに町に行っても、マシューは炭袋のところにじっとすわったきりで、父親がいっしょでないかぎりそこから離れようとしませんでした。その後もしばらくは二人の静かな暮らしが続きましたが、庭の花々が育つころになって、本をかかえた子供たちが道を歩いていくのを見かけるようになりました。
「父さん、あの子たちどこに行くの?」
「学校だよ」
「ぼくも行けるの?」とマシュー。
「まだだ、マシュー」
ある日、マシューの父は町に建設中の新しい建物をさして言いました。
「教会だよ。あれができたら、母さんみたいな女のひとたちが町にやって来て、それでおまえは学校へ行くようになる」
マシューはモミの木のところへ走っていって、この話をしました。
「でも、きみのことを忘れたりはしないよ。ぜったいに」。こう言って、木の幹にキスをしました。山の見晴しのいいところから、マシューは日に日にできあがっていく教会を見ていました。人けのない美しい山の中から眺める教会の姿は、なんとすばらしく見えたことでしょう。これほど好奇心をかきたてられる建物を少年は見たことがありませんでした。壁ができあがり、屋根がつき、空にむかってとんがり屋根がのびていて、そのてっぺんにはなにかきらきらと光るものが見えました。それから壁が白く塗られ、塔には鐘が吊り下げられました。マシューは、日曜になるとその鐘が鳴るのを、点々と人々が教会への道を歩いていくのを心に描きました。
「来週だな」と父親が言いました。「学校がはじまる。前に約束したとおり、おまえも学校にいくんだよ。一月に一度は、会いに行くよ。学期が終われば、山に帰ってくればいい」。マシューはモミの木にお別れを言いにいきました。学校はうれしいのに、目には涙がいっぱいでした。「きみのこと、いつもいつも考えるよ」。そう言ってから「ぼくのいない間、きみはどうする?帰ってきたら、学校のこと、ぜんぶ話すからね。ぼくは教会にいくんだよ。きっと好きになると思う。だってね、そこはてっぺんのところに、きみと同じように十字があるんだよ。黄色くて光ってはいるけど。あそこに行ったら、どうしてきみがてっぺんに十字をもっているのかわかるんじゃないかと思うんだ」。そしていよいよ、父親の手をしっかりとにぎって、ちょっときんちょうしながら町の教会に行く日がやってきました。
|

|
クリスマスツリー(5)
|
|
|
町には人がいっぱいで、マシューはそれに慣れることができなくて、いつもびくびくしていました。町で育ったものが山の中に一人置いていかれるのと、同じような気持ちなのでしょう。夜になって、山の方で炭焼きの火が真っ赤に燃えはじめ、暗闇の中で山々が溶けていくのを見ては、ふとんに入って涙を流す日々がありました。でも勉強がすすんでいくうちに、そんなこともなくなりました。この子にとって赤い火は、暗い部屋の中のろうそくの光くらいの存在になったのです。日曜に教会に行くと、そこにはろうそくの光と音楽があり、牧師さんの話す聖書のおはなしがあって、マシューはそれを信じるようになりました。それまで山で起こることはなんでも真実であったし、山で育った人々は信じることがすべてでしたから。マシューは牧師さんの言うことはすべて正しいと思い、それは神さまへの気持ちと重なりました。夜、ベッドの中で眠れないときなど、もしここに来ることがなかったら、自分はどうなっていたんだろうと考えたりしました。そして山に帰らなければならない日のことを思い、それを恐れるようになりました。こんなに大切なことを少年に教えてくれる者がいなかったのです。父親でさえ、気づいてはいませんでした。このことは少年を苦しめました。それなのに誰ひとり少年の心のうちを知らず、家が恋しくてお父さんに会いたいせいだと思っていたのです。
季節は冬に向い、夏雪の丘が一年中頭にのせている白い帽子を下へ下へと広げはじめ、雪が炭焼きの家のところまでとどくようになりました。教会ではクリスマスツリーを置くことがきまり、こどもたちはワクワクどきどきしてそれを待つようになりました。日曜日のたびにキリスト生誕のはなしがくりかえされ、それはどんどん身近になって、クリスマスの星のように輝きはじめました。マシューにとってそのおはなしは初めて聞くもので、クリスマスについて知っていることと言えば、冬のある日、父親がおもちゃを買ってくれることくらいでした。でもそれは、外が嵐で家の中にいなくてはいけないからだと思っていました。それがいまは、そのおはなしに夢中になり、すっかり信じこんで、聞けば聞くほどその想いは大きくなって、晴れて風のない夜に空を見上げては、パイン・マウンテンの上にベツレヘムの星があらわれるかもしれない、小さなキリストが雪の上を歩いてくるのが見えるかもしれないと思うのでした。ほんとうにそれを信じていたわけではありませんが、それくらいそのおはなしはマシューにとって真実味があったのです。山の中で長く暮らした人々というのは、うつくしいものの存在をすぐに信じてしまう傾向があります。マシューはここにずっといたいと心の中で願いました。教会で聞く牧師さんのおはなしひとつひとつが、深く深くマシューの心にしみこんでいきました。
いよいよ教会のクリスマスツリーを探すときがきて、マシューのお父さんが炭焼きであることから、その木の選定をまかされることになりました。マシューは大喜びで、父も息子の喜びように心が熱くなりました。クリスマス前の土曜日、その年のクリスマスは火曜日でしたが、いよいよクリスマスツリーを探しにいくことになりました。マシューは心の中で、ぼくのあの銀モミにしよう、と思っていました。マシューにとって、このすばらしい喜びをあのモミの木とわけあうにはこれしかない、あの木に自分ができることは他にないと信じていました。これまでの教会のおはなしをすっかり信じていたし、こうすることが最愛のものに対する、最高の気持ちの表わし方と思ったからです。このころには、神さまのおはなしを聞けないところでは生きていけないとまで、マシューは思うようになっていました。そこでマシューは、ロープとおのの準備ができると、あのモミの木のところへ父親を連れて行きました。
「ほー、かわいらしいモミだ」と炭焼き。「それに大きさもちょうどいい」。
ふたりは大喜びしながらシャベルで木の根元の雪をかきました。木を切っているとき、マシューは飛んでくる木くずをよけて顔をそむけました。ついにモミの木は、身をふるわせ、ため息をもらしながら雪の上に倒れこみました。すきとおった樹脂の玉が、おので切った傷口からこぼれました。それはモミの木の涙のようでした。それでも、教会に立てられて、贈り物を待っているこのモミの木のうつくしさは格別でした。マシューはそう思おうとしていました。
|

|
クリスマスツリー(6)
|
|
|
クリスマスイヴの日、炭焼きは何十年ぶりに教会を訪れました。息子といっしょに、こうして教会の行事に参列するのはまた特別の気持ちです。礼拝堂とモミの木が、ろうそくの灯でかがやいていました。少年にとって、夢の地とはこんなところ、と想像されるような光景でした。モミのてっぺんには大きなろうそくがともり、天上の星のように、長い光の矢をふりそそいでいました。炭焼きの子は、ベツレヘムを思いました。それから牧師さんのはなしが始まり、十字架と星があたりにあふれました。でもマシューは、モミの木ばかりを見ていました。モミの木はふるえているように見えました。少年は自分がモミの木を裏ぎったように思えてきました。聖歌隊の歌がはじまり、モミの木のてっぺんのろうそくの火が小さくなったとき、いちばん上の細い十字の枝が、暗がりの中に浮かび上がりました。そのとき突然、少年の心に、小さい頃からのなぞの数々がよみがえりました。小さな若枝がどうやってつぎつぎ十字になっていくのか、なぜ毎年毎年、枝が星形をつくるのか、このモミの木でおきることはどのモミの木でもおこっていることなのか。もうそれを確かめることはできないんだ、という思いから少年の目に涙があふれました。教会の柱は木の幹のように天にむかって伸び上がり、オルガンの音は風にゆれる木々のざわめきのようでした。星を抱いたモミの木たちが、頭に十字をのせて、教会のとんがり屋根よりずっと空高く、上へ上へと塔のようにそびえ立ちました。目の前ではモミの若木がふるえながら、その腕を動かして話しかけてくるようでした。少年はそれを神さまの声だと思いました。心に聞こえた声をそのように信じました。すると恐れは立ち去り、山に帰る日のことを恐れる気持ちも消えていきました。それは、山のすばらしい思い出も、神さまの星も、銀モミの木の十字架も、どれも捨てさる必要はないんだと知ったからです。前に思っていたよりもっともっと、これからは森でさまざまなものに出会えるかもしれないと、心が明るくなりました。森でなにをみつけたらいいのかが、わかったのです。神さまというのはどこにでもいて、それぞれの話し方をするもので、そのことばをどのように自分が理解するかが大切なのだ、そう思ったのです。
クリスマスの夜、小さな教会の中は喜びにあふれ、笑い声とお菓子のボンボンがとびかい、子どもたちはキャンディーのつつみや持ちきれないほどのプレゼントを腕におおはしゃぎでした。炭焼きもプレゼントのおもちゃで、服のポケットをぱんぱんにふくらませていました。マシューは家へ帰る道々、炭焼き場の燃えさかる炎のように目を輝かせていました。寒さきびしい、静かな夜でした。
「マシュー」と炭焼きが言いました。「もう父さんのいる山の家には帰りたくなくなったんじゃないのかな」
「ううん、そんなことないよ、うれしいよ」とマシューは楽しそうに答えました。「ぼく思うんだけど、山は、町の人たちと同じくらい大切なことを知ってるって」
「そのとおりだ」炭焼きは息子の手を両手の平にはさむと、トントンと軽くたたきました。「うれしいよ。おまえがこんな風にものがわかる子になってくれて」。でもこの父は、息子の心の中でなにが起こったのか、そのすべてを理解していたわけではなかったのですけれどね。
(2003.12.5.改稿)
|
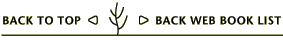
|
|
|