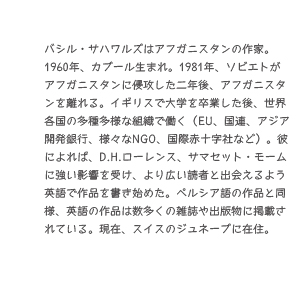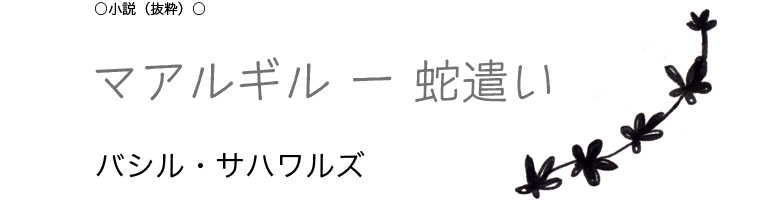
|
第一章
弟のラマトが食欲をなくし、目が黄色味を帯び始めてからしばらくたっていた。肝炎にかかっているのは間違いなかった。ハーミドは両親から、通りのはずれで店を開いている蛇遣いのところに、弟を連れていくよう頼まれた。その蛇遣いは赤コブラのような危険きわまりない蛇をつかまえることで知られているだけでなく、あらゆる病人を直すことでも有名だった。蛇にかまれた人の命も救ったし、妊娠したい女性たちの手助けもしていた。肝炎も含め、何千もの病気を治してきた、という噂だった。 ハーミドの両親は信仰深い人たちだった。儀式や祭礼を信じており、ヒーラーでもある蛇遣いは病気を治すときの第一選択肢だった。神さまの手助けと信心の力からか、多くの患者が蛇遣いのところに来たあと、病気から回復していた。巨大な体躯に浅黒い肌、分厚い唇に長いあごひげ、その強烈な容姿で、蛇遣いの男はあらゆる階層の人々を惹きつけていた。店は男が飼っている危険な蛇を入れた箱で溢れていた。折りに触れ、蛇遣いは箱の一つをあけて、蛇を操って患者たちにその顔を見せた。ときに蛇を駆立てて見せたりもしたが、患者がびっくりするとおとなしくさせた。蛇遣いはこのような遊びを楽しんでおり、患者が心を奪われ、自分の目の中にある不思議な力(危険な蛇を操る力)を信じこむのを見て気をよくした。それでも、ハーミドは弟の病状を見て、ちゃんとした医者のところに連れていくことに決めた。その医者は、二ヵ月前にある結婚式で会った人だった。 「この方がいいって、本当に思うのかい?」とラマトが訊ねた。 ハーミドは弟をじっと見て言った。「この医者はおまえの病気を治してくれると思う」 ラマトは手の甲で、汗が吹き出した額をぬぐった。「ぼくはただ、、、なんだか恐い気がして、、、」 ラマトの声はしぼんでいった。 「直ったらそんな風には思わないさ」 ハーミドは弟の肩をつかんだ。「おまえを見捨てたりしないから」 ハーミドは自信ありげにそう言ったけれど、絶対的な自信があったわけではないようだ。結婚式の前にも、ハーミドは住んでいる地域の路地で、ドクター・ナスラットと顔を合わせることはあった。アンドラビの礼儀を知る人々の慣習から、ハーミドはドクターと挨拶は何度かかわしていた。誰かが地元の蛇遣いのことを言い出したのは、その結婚式でのことだった。蛇遣いは、ほとんど治療不可能と言われた病気も直すと言ったのだ。会場にいた人々は心から賛成し、神はあの男に治癒能力を与え、死にかけた人でさえ生き返らせると言って誉め讃えた。モスクワの大学病院の卒業生であるドクター・ナスラットは、人々が熱狂するこの話を口をはさまずに聞いていた。しかしとうとう黙っていることができなくなって、蛇遣いはただのペテン師だと言った。ドクターは人々に向って強い口調で、今の時代、迷信など信じている国はないと説いた。このもの言いは結婚式のお客たちを驚かせた。その人たちは蛇遣いの力を信じていて、インチキ扱いされることに不快感をもった。この二十五年間、アンドラビの住人を手当てし治してきたのは、医者ではなく、この蛇遣いなのだから。蛇遣いより医者の方が優れていると思う者などいなかった。そして人々は心の中で、この医者は蛇遣いの人気に焼きもちを焼いているにちがいないと思った。蛇遣いの店の待ち合い室は、あらゆるところからやって来た患者でいっぱいなのだ。それに対して、ドクター・ナスラットのクリニックがどこにあるのかさえ、人々は知らなかった。 ハーミドは教育に対して信頼をもっていたので、ドクターの言うことを注意深く聞いていた。ハーミドの学校では、科学的な授業をしており、蛇遣いのような者が存在できる場はなかった。科学の教師は最近の世界の発展や、近代的技術、薬品についても語っていた。そういうものは、多くの人が聖職者や僧侶の言うことに耳を傾け、ヒーラーや蛇遣いを信じるような国の人々にとっては耳新しいものだった。イスラムのムッラー(聖職者)がニール・アームストロングが月面着陸したことを信じず、「月は神聖な場所、そこを敬わない者が足を踏み入れてはいけない」と言っているような国のことだ。ハーミドはドクター・ナスラットに親近感を感じた。結婚式のパーティで二人は長々と話をし、親しくなれそうだと互いに思った。ドクターはクリニックにお茶でも飲みに来てください、わたしの人生観についてお話ししましょう、とハーミドを誘った。ハーミドはそれを喜んで受け入れたけれど、訪ねることを延ばし延ばしにしていた。 ハーミドとラマトがドクター・ナスラットのクリニックに着いたのは午後も遅い時間で、ドクターは一人、肘掛け椅子にすわっていた。読んでいた新聞から目をあげて、「おや、これは驚いた」と言った。 ハーミドは今まで来れなかったことをきまり悪く思った。「もっと早くに来ようと思っていたんですが、学校がとても忙しくて。大学入試の準備をしているので、時間が取れませんでした」 考えつく最もよいと思われる言い訳を述べた。 「何を勉強しているのですか?」 「文学です。たいがいの時間は、公立図書館で本を読んでいます。文学を勉強して、作家になりたいんです」 「それはいいですね。この国にいい作家が必要なことは確かですよ。人々を理解し、賢い言葉でその人たちを導くことができるような作家がね」 「いい作家になれるかどうか、ぼくにはわかりませんけれど、読むことと書くことが好きなんです」 「一生懸命勉強して、読むべきものを読めば、きっと良い作家になれると思いますよ」 ドクターはラマトの青い顔に目を向けた。「しかし、君は今日ここへ将来の話をしに来たのではないのでは?」 ハーミドは、ここへ来た理由をやっと説明させてもらえそうで、ホッとした。 「弟のラマトが具合が悪いのです。ここ何日か食欲がなく、からだがだるいのです」 ドクター・ナスラットはまだ三十代初めだったが、髪にはかなり白いものが混じっていた。背が高くほっそりしていて、流行を追いかけたりしない、控え目な服装をしていた。グレーのスーツを着ていて、グレーの髪の色とよく似合い、ハンサムに見えた。 「ここにすわって」とラマトに椅子を指し示し、ドクターは診察を始めた。目、のど、耳を丹念に調べ、胸に聴診器を当て、検査機関で血液検査をしたほうがいいと言った。 「うん、やはり、肝炎でしょう。でも何か合併症があるかもしれません」 ハーミドは困惑した。みんなが蛇遣いを好んで訪ねる理由がわかった。あまりお金がかからないからだ。自家製の薬は安く、患者に検査を要求することもない。ドクターはハーミドの心配を読みとったように、こう言葉を添えた。「検査機関の責任者は、わたしの同志の一人でね。君からお金を取ることはないでしょう。薬代のことを心配する必要はないですよ。わたしが援助しましょう。薬を出しますが、それで少しよくなるでしょう。お金はいりません」 「でもドクター・ナスラット、そんなご親切を受けるわけにはいきません。お金を払わなくては」 ハーミドは困惑して答えた。 「あなたの書いたものを読むのに、貧しい人からお金を取りますか? いいですか同志、我々はここで商売するためにいるわけじゃない。困っている人を助けるためにいるんです」 ドクターは錠剤を数えて小さな瓶に入れ、ラマトに手渡した。「ロシアから届いた新薬です。よく効きますよ」 二人がクリニックを出ようとしたとき、ドクターが一冊の本をハーミドに渡した。マクシム・ゴーリキーの「母」という小説だった。 「読んで次の金曜日にでも、感想を聞かせてください。同志の家で集会があります。行くとき、君を拾っていきますよ」 家に帰る途中、ラマトは道で立ち止まりハーミドに顔を向けた。「ありがとう」 そう静かに言った。「家では何も言わないから」 ハーミドは両親に何というかについて、それほど心にかけていたわけではなかった。むしろドクターが言ったことの方に気をとられていた。「どうしてドクターはあんな風に親切なのだろう。なぜ自分のことを同志と呼んだのか。同志という言葉は何を意味するものなのか」 それに金曜日の集会とは何なのか、いたく興味をそそられた。 その夜は何事もなく過ぎた。ラマトはハーミドより二つ年下で、兄に敬意を抱いており、逆らったことがなかった。また信頼もしていた。ハーミドが病気を治すのに蛇遣いは向かないと言ったとき、それに従ったのは、そういう理由からだった。ラマトを医者に連れていったのは、ハーミドが迷信を信じないということだけでなく、他にも理由があった。弟のことを大事に思っていて、適切な方法でちゃんと病気を治してやりたかったからだ。ハーミドにとって、近代医学はラマトを救う唯一の方法だった。クリニックにいる間、ラマトは静かにすわっているだけで、ドクターにからだについて問われたときだけ答えていた。ラマトはおとなしい性格で、率直にものを言うハーミドとは違い、自分の意見を口に出すことはまれだった。ラマトも西洋的な学校に行っていたが、科学は一種の道具で、イスラム教を説明するためのものと思っていた。信仰心は厚かったが、それでも兄と同じように、蛇遣いがイスラムや病気の治療には役立たずだとわかった。
<ここに自らの命をアッラーに捧げた、イスラムの王が眠る。その魂は、天上からの光に囲まれている。> 兄弟の母、ハリマは息子たちが蛇遣いの元に行き、それでラマトの救いがたい病が治ったことに感謝していた。そして今、ハリマは息子たちに新たな任務を言い渡した。アッラーに感謝するため、近くの聖地「シャー・エ・ドー・シャムシャイラ(二つの剣をもつ指揮官)」に行って、自分が作ったハルワ(中東や南アジアで宗教儀礼などで供される菓子)をそこにいる貧しい人々に配ってくるのだ。 「ラマト、ぼくらはこの聖地のことを何も知らない」 ハーミドがラマトの背後からこう言った。「どういう意味?」 「この前図書館で、たまたまアンドラビの聖地の歴史についての本を読んだんだ」 「それで、何て書いてあったの?」 「それがさ、ピア・エ・ボーランドの聖地はイスラムとは何の関係もないとか」 「母さんが毎週水曜に、アッラーに感謝するためにぼくらを連れていっていったあそこのこと?」 「そうだよ、あそこには誰も埋められてなんかいない」 「そんな! あり得ないよ」 「いや、これは真面目な話。1842年にイギリスが負けてカブールから撤退したとき、彼らは重い兵器を持ち帰ることはできないと思った。それで丘の上にそれを埋めて、旗を立ててピア・エ・ボーランドの聖地、頂上の聖職者って名づけた。そこを守るためにね」 「兄さんの言うこと、信じられないよ」 「信じないなら信じなくてもいいさ。あの場所は、イギリスがカブールを再び侵略するまで当時のままだった。イギリス軍は穴を掘って、すべての兵器を取り出した。でも聖地として残したんだ、誰にも疑われないようにしてね」 「じゃあ、貧しい女の人たちがあそこで、今も聖地の灰をありがたく吸っているってこと?」 「そうだ。あの人たちは愚かだ。イギリスによってつくられた灰を吸っているんだ」 「じゃあ、シャー・エ・ドー・シャムシャイラもウソの人なの?」 「いいや、ありがたいことに、あれはウソじゃない。そうじゃなきゃ、ぼくらが一緒にハルワをやったのは、母さんのハルワを捨てたくないからってことになってしまう」 「じゃあ、この聖地にはどんないわれがあるの?」 「ここの聖人はアラブ人だったんだ」 「ほんと? アフガニスタン人だと思ってた」 「アフガニスタン人とは何か。ぼくらは当時、みんなヒンドゥー教徒だった。アラブ人がやって来て、ぼくらをイスラム化しようとしたとき、大変な戦いがあったんだ。すべての兵士とその司令官、シャー・エ・ドー・シャムシャイラ(二つの剣をもつ指揮官)は虐殺された。一団は殺された場所に埋められ、のちに墓地に家が建てられたとき、住人たちが聖地として残したんだ」 「ぼくらがヒンドゥーだって言ったよね」 「そう、ぼくらはヒンドゥーだった。シャブ・エ・バラアトの今日、殉死したムスリムたちの死を思い出すんだ。ぼくが読んでいる本には、聖夜であるシャブ・エ・バラアトは解放の夜で、一晩じゅう寝ずの祈りを捧げると書いてある。だから毎週金曜の夜、ぼくらはロウソクに灯をともすんだ。アンドラビは聖地の町として、殉教者の墓地がある場所として知られている」 二人は車の多い大通りをさけて、横道を通って家に向った。中央広場のところにやって来た。子どもたちがトプダンダ(野球のような遊び)をやっていて、他の子どもたちは追いかけっこをして走りまわっていた。その広場は近隣のどの家から歩いても、五分から十分の距離にあり、様々な遊びや活動に使われていた。そこは駐車場としても、年間を通じて使用されていた。大人たちはときに、サッカーやバレーボールをやっていた。イド(イスラム教の祝日)の日は、子どもたちがゆで卵をもってきて、卵当てに興じていた。自分の卵を他の子どもの卵に当てるのだが、自分のものは傷つかないように注意する。先に卵の殻が割れた方が負け。勝った者は、負けた者の卵を手に入れられる。冬には、広場は他のスポーツや遊びのグラウンドになる。男の子たちは雪合戦に夢中になったり、アイススケートをして遊ぶ。 モスクの前を通り過ぎるとき、美しい音楽が二人の耳を捉えた。早朝の祈りのあと、そして夕方、コーランを朗唱する声が通りに響いた。子どもたちが朝と夕、モスクにやって来て、コーランを学んでいるのだ。ムッラーがコーランの朗唱の節まわしを教え、子どもたちがその詩を繰り返す。アンドラビは神聖な空気に包まれていた。 北門を通過するとき、ハーミドが弟を振り返り、こう言った。「読んでる本の中にこんなことも書いてあったんだ」 「ぼくの信仰をこき下ろさないでね」 「いやそうじゃなくて、この門を見ると、アンドラビの歴史を考えたくなるんだ。アンドラビは旧市街の一部で、百三十年前に、アフガニスタン独立のために、ゲリラたちがイギリスと戦った場所なんだ。二つの主要な門があった。北部にあるこの門は川の端に、南部にあるもう一つの門は山に面していた。ここはアフガニスタンにとって、イギリスを攻撃するのに最適な場所で、攻撃の後、ゲリラは南部の山の中に隠れた。今ではそのときの門は、どちらもなくなったけどね」 「残念だね」 「うーん、もう門は目的を果たしたからね。カブールの安全を守っていたわけで。今は政府や警察がその責任を負っているから、門は必要ないんだ。町への出入りは、夜の間も人々に解放されているからね」 人々がそれほど意識していなくとも、アンドラビは変わってきていた。泥と石と木で造られた家は、長いこと持ちこたえ今も健在だ。変わったのが風景でないとしたら、それは何か。それは人間だ。モスクが教育の中心だった日々は去り、今は、親たちは子どもを学校へ送り出し、その中から大学へ行く者も出てきた。このような社会の変化は、伝統を尊ぶ人々やモスクのムッラーに従ってきた、信仰に厚い者たちの抵抗をかった。ムッラーはこのような変化をあまり気持ちよく思っていなかった。変遷期を経て、1973年に君主制から共和制に政府が変わると、人々の考えや態度の変化はさらに明らかになった。人々は自分の子どもたちの将来にとって、何よりも適切な教育が望ましいと感じ、新政府は新しい時代に則した正式の学校を支援するべきだと思った。つまり変わったのはアンドラビの心のありよう、人々の変化だ。古い価値観にしがみつく者があり、また近代化を主張する者がいる。 その他の変化としては、アンドラビへの移住者の流入があった。主にアフガニスタン北部の村からやって来た人々が、カブールの旧市街に入りこみ、アンドラビを気に入って住みついた。アンドラビはカブールの中心地だった。新しくやってきた人々は、市民の間に、以前はなかった階層意識を生み出した。アンドラビ土着の人々は、自らを真性カブール人だと言い、実際にそうであったわけだが、新来者を移民と呼んでいた。アンドラビの町について何か決めるとき、カブール人は優位に立っていた。 ハーミドの家族は、富裕クラスに属し、真性カブール人だった。父親のアブダルはモスクの近くに小さな食料品店を営み、家と店、モスクを行き来する日々を送っていた。二人の息子は、学校に行く前の小さな頃、モスクにやられイスラム教を学んだ。父親は息子たちに、厳格な宗教的教育を施すとともに、将来政府の役人になること目指すよう勧めていた。ハーミドは初等教育を、インドのデオバンドの修了生である著名なムッラーの徒弟の元で学び、その後正規の学校に行った。それに対して弟のラマトは、正規の学校とともに、イスラム教の勉強も続けていた。ハーミドの両親は二人の子どもを幸せな気持ちで見守り、学校の選択に口を挟むことはなかった。イスラム教の勉強を続ける弟のラマトは、信仰心の厚い若者になった。ハーミドの方は、夢みがちな人間になり、図書館で長い時間を過ごし、詩を書く人間になった。 カブールの公立図書館は、アンドラビからさほど遠くなく、ハーミドはいつでも気軽に歩いてそこまで行けた。閲覧室は小声で話をする研究者や政治的な活動家たちで溢れていた。ハーミドは知識に飢えており、研究者たちの話し声を盗み聞いては、文学作品の情報を得ていた。政治には、さほど関心がなかった。しかしながら、ある日、二人の若者が話しているとき、互いを同志と呼び合っているのを小耳にはさんだ。名前で呼び合わないのは、あまりあることではなく、ハーミドは興味をそそられた。 ハーミドはドクターに誘われた集会で、何を見つけようとしているのだろうか。 この作品は、バシル・サハワルズの小説 "MAARGIR - The Snake Charmer" (Platinum Press / Leadstart Publishingより2013年に出版)からの抜粋です。 |
||||