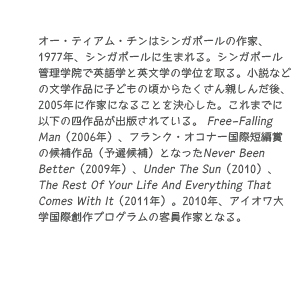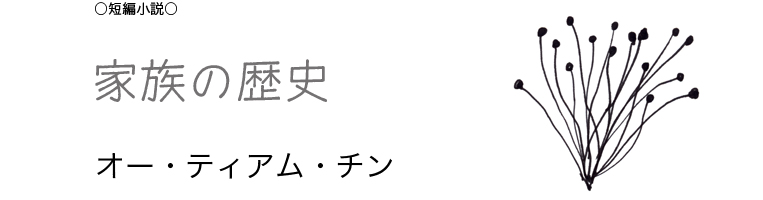
|
そっけなく短い一節だったが、繁体字中国語で書かれていたため、読むのに長い時間を要した。 <リー・チンをKK婦人病院に連れていった。今朝、彼女は大変な痛みを訴え、数時間の間、病院で監視下におかれた。医師の言うことには、お腹のなかで赤ん坊は死んでいるとのこと。医者は何のせいなのか、どうしてこうなったか言わなかった。赤ん坊を取り除くために、簡単な処置をすると言われた。それほど負担になることではありませんよ、と医者。わたしたちは医師にまかせた。病院はリー・チンに鎮痛剤を飲ませ、彼女はありがたいことに、ぐっすりと眠りについた。あとで医者はわたしに、男の子でしたと言った。わたしの息子だ。> このことを兄のトミーに話した。トミーは三年つきあったボーイフレンドのエリックと別れたところで、家に戻ってきていた。家を出ていく前の部屋をまた使っていたが、その部屋は父親の本や雑誌、新聞の切り抜きを入れたダンボール箱を置く倉庫になっていた。父は地元新聞の中国語局で、原稿整理の編集者として働いていた。二年前に退職するまで、ここで二十九年間仕事をしていた。父はものを貯め込む人で、母からよく文句を言われていたが、家族は何年もの間、貯め込んだものが増えていくのに耐えていた。四部屋のアパートの小さな納戸はもので溢れ、間を置かず、いくつかのものを居間の隅に移動させることになった。そして今父は去り、兄さんは恋愛に失敗して心取り乱しており、父親の残したものを整理するのはぼくの役目になった。 「俺たちガガ(哥哥:長男)がいたかもしれないって、知ってた?」 その晩夕食の席で、ぼくが訊いた。兄さんは夕飯に、卵とランチョンミートの炒飯を作っていた。エリックと住んでいた頃、兄さんは食事を作っていた。失恋については、何も訊いていない。それを話すには早すぎる、兄の心の傷はまだ生々しい。 「えっ、何。かもしれないって、どういう意味?」 トミーが読んでいた中国語新聞から目をあげて訊いてきた。戸惑ったような顔に、好奇心が炎のように広がっていた。そして下がった眼鏡を鼻の上に押し戻した。父親と同様、兄さんも眼鏡をかけていた。中学生のときからかけていて、それは夜遅く、ベッドの中でふとんをかぶって小さな灯りで本を読んでいたせいだろう。トミーは子どもの頃いつも本を読んでいた。父は兄さんが読みたがるものは何でも与えたし、おおっぴらに自分の(お気に入りの)息子が、読書好きなことを、自分と同様に知的であることを喜んでいた。トミーが父親にエリックとの関係を話し、そのために二人が仲たがいし、長い沈黙のときを過ごしたとしても、トミーが父のお気に入りであったことに変わりはなかった。 「パーの日記を今朝、見つけたんだ。パーのものを整理してたときにね。書いたものを少し読んだんだ。からかってるんじゃないよ。ぼくらには本当に兄さんがいたんだ。でも流産で死んだんだけどね」 そう言って、皿から炒飯の残りをすくった。兄さんは眉をしかめた。 「それ見せるよ」と言って、ぼくは自室に行って日記をもってきた。その部分を見せると、トミーはびっくりしたように頭を振った。 「おまえ信じるか? 兄さんかぁ、いることを知らなかった兄さんのことを、、、」 トミーはそう言うと、さらに読み進み、ページをめくり、ぼくらの知らない過去を探っていた。トミーは妙な魔術みたいなものを使って、分厚い沈黙の幕で自分をおおい、まわりのものすべてを遮断しはじめた。最近よくトミーが見せる態度のひとつだ。 「なんでパーとマーはこのことをぼくらに隠してたんだと思う?」 ぼくは不快な魔力を破ろうとして言った。 トミーはぼくの方に向き、読んでいる文のところに指を置いて、こう言った。「わかんない。ぼくらに言いたくない理由があったんじゃないのかな」 兄さんは日記に戻り、ぼくに汚れた皿をテーブルから片づけさせた。 家族の死のことをぼくらに言わないという、どんな理由が両親にあったかわからないが、二人はそれをお墓に持ち込んだんだ。母はぼくが学校を卒業して少しして死んだ。母については、つるつる滑るウナギみたいに、とらえどころのないあやふやな記憶しかない。でもそうであっても、ぼくはもっと知りたい、見失い宙に浮いた家族の過去について何か見つけたい、というとめようのない強烈な衝動に駆られていた。それでぼくは父の日記のすべてを読む決心をした。 * 「おい、知ってたか、赤ん坊が生まれる前、パーはすごく心配してたみたいだぞ。マーが流産する前に、奇妙な夢を見たらしい」 ある日の午後、トミーがそう言ってぼくの部屋に飛び込んできた。 父親が前立腺がんで死ぬ一ヵ月前に戻ってくるまでは、トミーの顔を家でみることはほとんどなかった。父親の誕生日とか、旧正月の家族の夕食会とか。一度、兄さんは家族の夕食会にエリックを連れてきたことがあった。食事の間、父親が見せたエリックに対するあからさまな嫌悪感のせいで、以降兄さんは家族の集まりにエリックを呼ぶことをやめた。こうして今、兄さんが家に戻ってからは、顔をつきあわさずに家の中を歩きまわることは難しくなった。兄さんがぼくを探して何か話そうとするとき、ノックもせずにぼくの部屋に入り込んでくることがある。ぼくは自分に少し我慢しろと言い聞かせた。兄さんは今、人生で一番つらい時期を過ごしているんだからと。ぼくが少し我慢してあげればいいのだ。だから兄さんが突然部屋に入ってきても大目に見て、今のこのぼくらの暮らしを思いやりの気持ちで続けよう。 「ああ、知ってたよ。パーの日記読んだからね」とぼく。声にいらつく気持ちが混ざる。「いいか、パーは初めて父親になろうかという時だったんだ。心配する権利はあるだろうな」 「だけどさ、パーの見た夢はどうだ?」 ぼくが兄さんの言ったことなど聞いてなかったみたいに、途中で口を挟んできた。「赤ん坊が見えない糸に吊られて、操り人形みたいに動きまわっていたっていう、気味の悪い夢をパーは見たんだぞ。覚えてるか、どんな風に書いてたか」 ぼくはうなずいた。「パーのことはわかってるだろう、心配性なんだ。何であれ、あらゆることを心配してた。あれはパーが見た悪い夢ってだけだ」 トミーは手にパーの日記を抱えてぼくのベッドに腰かけ、皮肉な口調でこう言いながら頭を振った。「物書きとして、もっと想像力というものがないのか。ただの悪い夢だった? おい、ここにはきっと何かあるぞ」 ぼくは兄さんと言い争わなかった。一緒に育つ間に兄さんのことで学んだことは、ひとたび何かを確信したら(考えであれ、理屈であれ、直観であれ)、何があろうとそれにしがみついて、最後まで言い張るってこと。放っておくのが一番、信念であれ思いつきであれ。あいつはまったく頑固で愚かなやつ、ただし何かに対する粘り強さとか忍耐強さという面がないわけじゃない。 多くのことで兄さんの性格はいい方に作用していたが、人との関係となると、それが問題を起こしてしまうことがよくあった。宿命的と言ってもいい。兄さんは一つの見方しかできない、自分の見方だ。それ以外の見方は二の次、自分の見解以下のものになる。自分が見たいように、信じたいようにしか、ものを見なかった。だからエリックが海外出張中に起こした、一度だけの裏切り行為を告白したとき、兄さんはエリックの後悔の念も、謝罪も、懇願も、仲直りしたい気持ちも、すべて拒否して、エリックはいつもこうだ、要するに浮気性なんだと結論づけた。 兄さんは呼び覚まされた自分の執拗さと荒れ狂う怒りの中で、服や洗面道具をいくつものバッグに詰めて、家の鍵を郵便受けに残して、告白の次の日にエリックの元を離れた。
その夜、夕食のあとで、父親が青い表紙の日記帳を取り出して、何か書きはじめたのを見た。ぼくは食卓にすわって、兄さんとエリックのことを、父と話したいと思っていたが、拒否のまなざしを向けられてしまった。ぼくは父親の寡黙さのことをよく考えた。生まれながらのものに加えて、融通のきかない古い考えによる、厳しいしつけがもたらした性格とでも言おうか。でも時がたつにつれ、それは父親が盆栽を心を砕いて注意深く育て世話していたように、もの静かで内向的な性格がもたらす必然的な特質だったのかもしれない、と思うようになった。奇妙なことだが、トミーはぼくよりずっと、父親に似ていた。 ぼくが父から受け継いだものは、書くことだった。とはいえ、それは何か書いてみようと思い始めた二十代の初めになって現れたことだが。最初の仕事、テレコミュニケーションの会社での修理技術者をやめて(地元の技術専門学校で、電子機械工学の学位をとっていた。平均以上の成績ではあったが、全く興味がもてなかった)、職業大学で四年間の定時制の英文学コースをとった。父親はこれについて、ぼくに何か言うことはなかった。最初の二年間の学費を父が払ってくれ、残りは自分の稼ぎでなんとか賄った。マイナーなアート雑誌にときどき何か書いたり、イベントやマーケティング・コミュニケーションの仕事で臨時的にコピーを書いたりしていた。父の世話で、英字新聞の生活欄の編集者から書く仕事を得たりもしたが、少しして、ぼくの書いた記事が容赦なく批判されたり、編集者によって大幅に改稿されたりして、この収入の道も先細りとなった。このことを父と話したことはないが、何か聞いているだろうとは思っていた。そのことがあってから、父親からの書く仕事はいっさい断っていた。 父はときどき会社から仕事を持ち帰り、夜、食卓にすわって太い赤ペンと定規を手に、中国語の記事や論説の草稿に修正を加えていた。何回か直しを入れたあと、最終稿を声に出して読み上げていた。直しに満足すると、会社にそれをファックスで送り、同僚に自分に代わって寄稿するよう電話で頼んでいた。一度、何か飲もうとキッチンに行ったとき、赤丸と取り消し線と漢字の列で埋まった、中国の政治政策改革に関する記事を目にした。その三行目まで読んで、放棄せざるを得ない自分に気づいた。単語三つの内一つは読み飛ばさなければならかったとはいえ、そこにある文章の意味がほとんど理解できなかった。 前に何かで読んだことがあるのだが、心からの言葉というのは、人が考え、感じ、読み、分析し、夢をみるときに使う言葉だ、と。ぼくにとって、それは英語ということになる。英語は、ぼくが覚えているかぎり、第一番目の心の言葉であり、それで生き、仕事をしてきた言葉だ。ぼくとトミーが成長する間、父はぼくらに中国語を強要することはなかったが、自分自身は日々の生活の中で、中国語の新聞や本、テレビ番組などを通して、しっかりと中国語との関係を保っていた。父はぼくらに一度たりとも、英語で話しかけたり、返事をしたりすることはなかったが、ぼくらが言っていることは充分に理解していた。父の心は隅々まで、中国語でできていた。それに比べて息子であるぼくらは、忠誠心と対抗派閥がいがみあう、分裂した言葉の世界を生きていた。 父の日記を読みはじめたとき、どれくらい父親のことを自分が知っていたのか、父の心のリンガ・フランカ(共通の母語を持たない者同士が使う共通語)である中国語を通して、どれくらい父のことがわかっていたのか、疑問をもたざるを得なくなった。
ぼくはアパートに入るときに、咳払いをした。すると興奮した声が静まった。ぼくが中に入ると、エリックだけぼくの方を見た。トミーは窓ガラスの外に目をやっていて、胸の前で腕を組んでいた。エリックが困ったような笑みをぼくに送り、ぼくは肩をすくめて同意した。エリックは兄さんがすわっていたソファから離れ、そのあとどうしたらいいか困っているようだった。 二組の目が自分の一挙一動に注がれているのを感じながら、ぼくは靴を脱ぎ、玄関の脇にある戸棚にしまった。トミーの方を見てみた。トミーがすわるソファに、父親の日記があった。トミーの頭の上には、家族の記念写真が掛けられていた。ぼくの卒業直後に撮られたもので、両親は口を閉じたまま笑みをつくり、堅苦しい髪型をしていた。家族の中に二人目の大学卒業者が生まれ、満足しているという父の自負が現われた写真だった。父自身は初等の四つの教育しか受けていなかった。家族の記念写真をまず撮りたいという人物、それが父だった。その四ヵ月後、母が車の事故で死んだ。ぼくは記念写真を取りはずして納戸にしまおう、と心に決めた。父の目が部屋の中をさまよい、何か探しているように見えたからだ。 兄さんが突然こう言ったとき、ぼくは目を床に落とし、自分の部屋に行こうとしていた。「これについて、ちゃんと言いあったことがあったかな」 エリックがトミーをにらみつけ、信じられないという顔つきで、ぼくに目を移した。くちびるが少し開き、何か言いかけたように見えたが、すぐにやめて、不機嫌そうにあごを動かした。 「なんでこんなことしてるんだ?」 エリックがとうとう口を開き、ぼくはふと、ぼくに言ってるのだと思った。ぼくは前にも後ろにも動けなくなった。部屋の空気が緊迫した。言葉が取り除くことができない有毒なガスのように、息苦しく漂っていた。 「くだんないバカみたいなこと訊くなって」 兄さんが声を荒げて言った。「何でかって、どうしてかって? 自分に訊いてみろよ。自分のやったことが何か、わからないみたいに振る舞うな!」 「落ちついて、言うことを聞いてくれないかな」 エリックが歯ぎしりして言った。 兄さんがソファから立ち上がり、部屋から出ていこうとしたとき、エリックが腕をつかもうとした。兄さんはその手を振り払った。エリックが再度手をかけようとした。「こういうバカげだことを聞くのは、もうごめんなんだよ」 トミーがぼくにそう言って、自分の部屋に行き、部屋をロックした。 ぼくは肩掛けカバンのストラップを握り、頭を振った。エリックは目を閉じ、大きなため息をついた。兄さんがあんな風に振る舞ったときはできることなどなかった。 エリックがアパートを出ていくと、ぼくはトミーの部屋のドアをノックした。トミーがベッドから起き上がり、こちらにやって来るのが聞こえた。「エリックが言うことに少しは耳を貸して、何を言おうとしたのか聞いたっていいじゃないか。まったくそんなに意地をはってばかりいて」とそこまで言って、言いよどんだけれど口に出した。「パーみたいだ」 こんな言葉が吹き出したことに自分でも驚いていた。トミーは、ものも言えないアホかというような目でぼくを見た。部屋の中に引っ込んで、小さな扇風機をつけ、ベッドに倒れ込んだ。 「ここから出ていけよ。おまえの言うことなど聞きたくない」 トミーはぼくをにらみつけてそう言った。ぼくはそれでも部屋の中に入って、勉強机のところにある回転椅子にすわった。机の上いっぱいに請求書や銀行口座の明細書が散らばっていた。 「流産のあと、マーが長いこと落ち込んでいたこと、知ってるか?」 トミーが言った。「パーが日記にそう書いていた」 「うん、それ読んだよ」とぼく。医者は産後のうつだと言っていた。父の日記によれば、マーはそこから立ち直ることがなかった。日記の中に、母親のちょっとした反応や今どんな様子かを逐一書いていて、それは微に入り細に入りの記述だった。「おい、おまえ大丈夫か? おれにそんなこと言うな、、、」 トミーがすばやくぼくを遮った。「うるさいな。オレはなんともない・ラー*」 「言ってみただけだよ。いずれにしてもパーはあのことで大変な時期があったんだよ」 そうぼくは言った。 トミーはベッドから起き上がると、指をポキポキと鳴らした。そしてベッドカバーの上にあった日記に手を置いた。 「流産したあとで、なんでオレらを生もうと思ったと思う?」とトミー。 「パーはもう一度子どもをもちたいと思ったって書いてる。あのことを乗り越えるためにも。あとの方の日記にあったよ」とぼく。兄さんが死んでから三年たってトミーが生まれ、それから二年後にぼくが生まれた。 「どうしてこのことをぼくらに言わなかったか、いまだにわかんない」とトミー。それについて日記には一切書かれていなかった。ページからページをじっくりと探して、一行ずつ確かめ、心の中でそれを英語に置き換えたりもしたが、何も出てこなかった。しかしある記述を見つけて、殴られたみたいな気持ちになった。それは1977年の11月に書かれたもので、トミーが生まれる一ヵ月前のものだった。 <リー・チンが悪い夢を見て起きだした。寝室から彼女が叫ぶ声を聞いた。わたしが部屋に入ると、彼女は腹部をつかんでいて、顔に筋が立っていた。からだじゅうに汗をかき、何かを恐れている風で、実際理性をなくしていた。わたしが抱きしめると、彼女はわたしの胸で泣きはじめ、何かわからないことをつぶやいていた。もし赤ん坊がまた連れ去られるのなら、もう生きていたくない、というようなことを。彼女はとめどなく泣きつづけた。わたしは彼女を引き寄せた。わたしから逃れようとして暴れる、死にゆく鳥のようだった。どのくらいの時間そうしていたかわからないが、彼女のからだの緊張が溶けていき、息もだいぶ正常に戻った。彼女を眠りにつかせた。断続的な眠りのせいで、まぶたの下で目が動いているのがわかった。窓の外で空がゆっくりと光を帯びてきた。明るくなってきた。そろそろ終わりにしよう。長い一日が始まる。> 「わかんないな。パーは日記の中で何も書いていない」とぼくが言う。 「ところでいくつ日記を見つけたんだ?」とトミーが訊いた。 「かなりあるよ。書いたもの全部を見つけたかわからない。でも見つけたものはみんな兄さんに渡すよ」 「わかった、おまえが読んでからでいいよ」と言ってから、「パーもマーも死んでから、このことがわかるなんて、変じゃないか? つまり知ったからといって、どうなる? 役立たずだよ、そうじゃないか?」とつけ加えた。 「まあね。でも知ることは大切だよ」 そう言って部屋を出るため立ち上がった。「たぶん、知ってることに意味がある、そうすればすべて置き去ることができる。そこを封鎖するみたいにね」 「へっ、正真正銘の作家みたいなこと言うな」 ぼくはトミーを見た。そして二人で笑った。
ある日、ぼくはトミーに自分の考えを話した。ここのところ考えていたことで、もしトミーがエリックのところに戻るなら、使わない部屋を誰かに貸して収入を得るか、アパートを売ってもっと狭いところに移るかしようと思っている、と。トミーはぼくの部屋にやって来て、箱からまだ読んでない父の日記を取り出していた。ぼくは日記の表紙に、年代順に番号を振ったラベルを貼っていた。十二番目の日記をぼくは読み終えるところで、トミーは八番目を読んでいた。気をもむような表情で、トミーがぼくを見た。 「なんでぼくがエリックのところに帰るなんて思うんだ?」 そう言うと、少し間をとった。「もしぼくが戻ることを考えるとしても、まだ話しあわなくちゃいけないことが山ほどある」 「いずれにしても、時間の問題だろう。自分がしたいことを決めるのに、それを待っていることはできないよ。何があるかわかんないし、もう考え始めなきゃ」とぼく。 「でも、ぼくはまだ考えちゅうだよ。ここを出る気は今のところない。このアパートを売るべきだとは思わないね。パーが二十五年間かかって払い終えたものなんだから、なあ」 ぼくらは他の可能性や考え方も検討してみたが、最終的な答えには至らなかったので、とりあえず問題を棚に上げた。いつか解決すべきときが来たら、手をつけなければならないが。そう自分に言い聞かせた。 「でもどうしてだ? 今のところなんとかやっていけてるんじゃないのか?」 そうトミーが訊いてきた。「もしそうじゃないなら、いくらか金をやってもいいけど」 「大丈夫、なんとかやってるから。生活にそれほどお金はかからないんだ」 ぼくはそう答えた。「自分でやっていくのに問題はない。フリーランスの仕事がある限り、ぼくは大丈夫」 「でももし金が必要なら、遠慮せずに言えよな。まあすごい金持ちってわけじゃないけど、一ドルや二ドルくらいなら都合つけられるからさ」 「一ドルか二ドル? ったく、けちなやつだ・ロー*」 ぼくはにやっと笑ってエラそうに言った。 「いやなら結構。人に金借りて文句いうとはな」 トミーは日記帳でぼくの肩を叩いて笑った。 兄さんに言わずにおいたこと、それは書く仕事のいくつかをふいにしたせいで、短編小説に集中することができたということ。日記を見つけて以来、間を置かずに小説を書いてきたし、以前よりずっと熱心でもある。物語はどんどん先に進み、広がり、それ自身が生きもののようになってきた。父親の隠された過去という種から育ったものが、現実の父と想像上の父を一つにしながら、違った生きものとなって現われた。話がどんな結末を迎えるのか、それが知りたい一心で、ぼくは駆立てられるようにして書いていた。 あと三ヵ月分くらいは、なんとか貯蓄でやっていけそうなので、お金のことはあまり心配していなかった。そのときまでに小説を終えることだけを願っていて、その後はまた、請け負い仕事をすればいい。
1983年4月21日の父の日記から。 アー・センというのは父親がトミーを呼ぶときの愛称だった。トミーの中国名はポー・ライ・センで、それは父が死んだ兄につけようと思っていた名前だった。トミーというのは、十代の頃に兄が自分で使いはじめた名前だった。父は日記の中で、トミーが生まれたときのことに少し触れていたが、母親がこの名前に賛成したかどうかついては何も書かれていない。トミーはこれを読んで、驚き信じられない風だった。 「想像できるか? ぼくの名前が兄さんのものだったとは」と口にした。「兄さんと名前を分けあってるんだ」 「実際には死んだ兄さんの名前じゃないよ。生まれてもないんだから、名前なんてなかったんだ」とぼく。 「でもさ、パーとマーはその名前を死んだ兄さんにつけたかったんだよ。考えてみろよ、ぼくは代わりに兄さんの人生を生きてるってことか」 「名前をもらっただけだよ。人の人生を生きてるわけじゃない。最初からいなかったんだから。兄さんは自分の人生を生きてるだけ」 ぼくはそう言った。 「どうかな、わからないぞ。こういうことは、何とも言いがたい。人の名前はその人間の運命だ。両親から受け継いだ唯一のものだ」 「まったく、なんの運命だよ、どんな遺産だよ。何言ってんだって」 ぼくはふざけて舌をならしながら、目をまわしてみせた。「日記の読み過ぎで、頭おかしくなってんじゃないの」 「ここ見ろよ」 そうトミーは言って椅子をぼくに近づけた。日記をぺらぺらとめくって、あるページの言葉の上に指を置いた。「パーがこう書いてる」 <人の最後にあるのは、その名だ、名前そのものだ、そしてすべては名前が約束している。人の人生はその名前に満たされたものだ。> ぼくはこの文を何度も読み返した。どうしてここを抜かして読んでいたか、まったくわからない。この日記の日付けをメモした。トミーが生まれた一週間後に書かれたものだった。ぼくが見過ごしていたとき、トミーはしっかりとこの文をつかまえていたというわけだ。日記を読んでいる間、どれくらい気づかずに読み飛ばしているところがあったのか。おそらく不明瞭だった場所は、盲点みたいに、ぼくの前をするりと抜けていったに違いない。 「ここ初めて読むよ。ここを読んだ覚えがない。読んだけど、忘れちゃったのかな。でもパーが言ってることは正しいのかも。きっと正しいと思うよ」とぼくは言った。「パーが名前をどんな風に扱っていたか、知ってるよな。この手のことに関してパーは、古風だからな」 「確かに」 兄さんは少し悲しげな様子で、ふっと彼方に消えいるように静かになった。見知らぬ土地に心をさまよわせているみたいに。見た目に変わりはなかったが、心の中で何かが動いたように見えた。ぼくには見えない何か。かすかで、つかまえにくい、心の揺れ、瞬きする間だけ見えて、すぐ消えてしまうような。ぼくが感じたのは見えない波動のようなもの、消えさり、広がってはまた消えさる。
ぼくらは日記を半分ずつ分けることにした。兄さんが十冊、ぼくが九冊。兄さんは、父の人生の前半を、ぼくは後半を手にすることになった。万年筆と結婚記念写真とシャツは、ぼくが持っているようにとトミーが言った。「小説を書くときに、なんかインスピレーションがわくかもしれないし」と言った。ぼくは眉をあげて、えっと思ったけれど、黙っていた。 父と死んだ兄についての短編小説を書き終えたのは、トミーが家を出ていく日で、エリックが迎えにきていた。トミーが玄関を開ける音を聞いて、居間に行くと、ソファにすわっているエリックがいて、その表情は明らかに満足げだった。ぼくはにっこりと笑いかけ、エリックが「ハイ」と言った。ぼくらはトミーが自室からトランクや持ち物を詰めた箱を、玄関の脇まで何度も運ぶのを見ていた。兄さんの荷物を見ていて、刺すような悲しみがぼくの心の奥深くに達するのを感じた。 「二人がもと通りになって、ほんと嬉しいよ。この何ヵ月もの間、もうダメなのかなと希望をなくしたこともあったから」とぼく。 エリックが歯をみせてにっこり笑い、手を髪にやって子どもっぽく掻いた。「二人の男がいっしょに住むってことは、簡単なことじゃない、ほんとにね。でもぼくらはそれをやろうとしてるんだ」 「わかってるよ。ぼくは兄さんが家を出ていくまで、二十年以上もいっしょに暮らしたからね」 そうぼくは言った。「長いこと、がまんしたよ。だからわかるよ、きみがどんな苦労してるか。これから耐えるのはきみだよな」 エリックが声をたてて笑った。ぼくはエリックの喜びにつられて、声をそろえた。 「それに耐えて暮らすんだろうな、他に道はないよ」 「がんばれよ。二人がうまくいくのを祈ってるよ」とぼく。 「そうだね。ありがとう」 兄さんは最後の荷物を持ちだすと、居間をさっと見まわした。父の日記の箱を持ち上げると、エリックにトランクと他の箱を持つよう頼んだ。そしてぼくを見て、こう言った。「何かあったら、オレに電話しろよ」 「ああ、わかった」とぼく。「兄さんもね。何かぼくに頼みたいことあったら、電話して」 二人が出ていって、ぼくは部屋に戻り、書き上げた短編小説を取り上げた。もう一度それを読み返し、すべてをからだに染み込ませた。家は静まりかえり、柔らかな風が吹き抜けていった。カーテンがはためき、針金のハンガーに掛けられたシャツが波うった。静かなアパートの中に漂う足音やささやく声に耳を澄ました。ぼくらがともに生きた、家族の歴史の跡を、壁の間に、部屋の隅々に見ていた。ぼくは父親を、母親を、そして会う前に失った兄のことを考えた。 手に短編小説を持ち、引き出しの中からライターを探しだした。 「ありがとう、パー」 オレンジ色の炎を紙の端にもっていって、紙が丸まり一掴みの灰になっていくのを見ていた。火がぼくの指をなめた。と、突風が起きて、灰になった短編小説をアパートの隅々まで撒き散らした。 初出:QLRS Vol. 8 No. 2 (2009年4月) |
||||