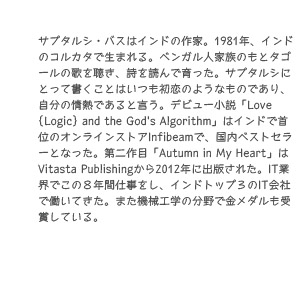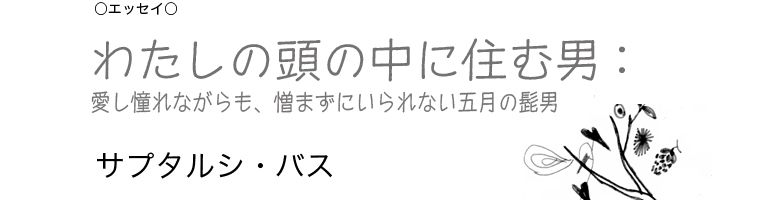
|
それから時間が経ち、わたしが成長すると、頭の中の男の存在がより堅固なものになった。わたしは彼の口に出されていない言葉を聴いた。グゥルゥデーウの詩はわたしが悩みを通過するときの助けになった。でもこのことは秘密だった。わたしはタゴールゆかりのシャンチニケタン(西ベンガルの小さな町)やビスババラティ大学で、教育を受けたわけではないことから、グゥルゥデーウに接するときはいつも遠慮がちになった。わたしはあご髭を伸ばし、ボサボサの髪で、ナンダン(コルカタにある西ベンガル映画センター)をうろつきまわるという、出来損ないの自分を認めねばならない。アカデミーで映画上映に出席したり、アートカレッジで授業を受けたりしていた。隠しだてすることなく言えば、こういう創造性に富んだ豊かな土壌に、わたしはまったく不適格な人間だった。シャンチニケタン出身の珍重すべきガールフレンドがいる友人たちも、わたしにずけずけと忠告した。グゥルゥデーウの作品を真似しようなんてことはするな。あれはすごく高度な感性によるものだと。 それからまた日々が過ぎ、わたしは機械工学のバレル分野で奮闘していた。でも世界に名だたるわたしたちの「ベンガル人」が、わたしの魂をなだめてくれることがよくあった。わたしは リトウィク・ガタク(ベンガル人映画監督、1925-1976)、サクティ・チャットパダイ(ベンガル人作家、1933-1995)といった名声ある天才たちを知って感嘆し、さらにわたしたちのよく知るスニル・ガングリー(ベンガル語の作家、1933-2012)も、日常の「高み」を保つ助けになった。わたしの「ベンガル人」への愛が、これらの人々に導かれたことに、大いなる誇りの気持ちをもっていた。実際のところ、自分の日常がこのような偉大な人たちと繋がっていると思うと、素晴らしい気持ちになる。この人々はわたしの心を奪い、わたしはたくさんの夕べを、幾多の夜を、貴重な「ベンガル人」と過ごすことに捧げた。そんなある夕日に染まる美しい夕べに、好きな酒を幸せな気分で飲んでいたとき、わたしはグゥルゥデーウとまた出会った。アヌプ・ダのセク(アッダとも言う。仲間が集まって知的会話をするコルカタなど南アジアに残る伝統的習慣、楽しみ)でのこと。わたしは、農夫とリキシャー引きと地元のマタドール(トラック)運転手と一緒に、土床にすわっていた。話題はあれこれ面白く変わっていった。そこにいた中で一番教育を受けていたわたしが、だれの話が最も素晴らしいか、決める役になった。なかなか難しい選択で、すでに何杯か飲んで酔っていたわたしは、決めかねて悩んでいた。がそれでも、農夫が突然泣き出すまでは、すべてはうまくいっていた。その農夫は酒を素早く二杯飲み干すと、息子がいたんだ、あんたくらいの年齢の息子が、今はもういない、と言った。切なくも、その場の空気が暗くなった。年老いたその農夫は、息子を救うことができなかった痛みで、泣きつづけた。そして、わたしの頭の中のあの男が現われたのだ。「ベンガル人」を腹にたくわえるわたしは、老農夫が粗い声でグゥルゥデーウを歌うのを聴いて驚いた。「ジラーテムーリドワー ....」 そうしているうちに、痛みは安物のグラスの中に溶けていった。わたしは目を閉じ、農夫の歌と一体になった。 それからまた何年かが過ぎた。わたしはロンドンに住み、保険会社で働いていた。その日は雨が降っていたと思う。ご存知のように、女王様の国はいつも曇りがちで雨が降っている。その日、雨粒が窓ガラスを落ちていくのを見ていて、また彼のことを思い出した。「パグラハウワー、バードルディーニ .....」 グゥルゥデーウの詩がわたしの心の内で響いた。窓の下を見おろし、甥っ子の紙の舟がモンスーンの中で、震えながらくるくるまわっているのを想像した。わたしの奥深く、心の真っただ中で、言葉にされたことのない苦痛が声をあげていた。突然、外の世界に染みや割れ目が広がり、目の前の色が消え去り、虫に食われたような空虚感に襲われ、わたしは引き裂かれた。あの男が、何度も言うようだが、いつもそこにいた。今は大人になったわたしの頭の中に。 粉々になった紙の上に言葉を注ごうとすることは、ひどく苦痛だった。言葉が流れ出したとき、わたしは解放された。心が楽になった。彼に感謝し、そして書き続けた。しかし少しして、すべてが無意味に感じられた。二、三日後、マクミランのポケット版タゴールの詩集「ギタンジャリ(神への捧げ歌)」をめくっていて、同じ感覚にとらわれた。同じ気持ちに。わたしの書くものの何千倍も優れている。それはわたしに憎しみを与えた。わたしは何行かさらに書き加えてから、書くことを放棄した。わたしの言葉に、何ひとつ新しいものはなかった。あらゆることが、髭の男によってすでに、もっと素晴らしく感動的な書法で書かれていた。男のことを憎んだ。わたしの気持ちをすべてわかっていることに、わたしを中途半端な創作者におとしめ、何度も何度もあざ笑うことに、わたしはそのことでさらに彼を憎んだ。それは確か五月のことで、ハイドパークはまだ緑生い茂る季節を待っていた。 秋がやって来た。相変わらずわたしは苦闘していた。コルカタに引き上げるという決心が、わたしを落ちつかない気分にさせていた。そして、もう西海岸のベイエリアがそれほど魅力的ではないと思えた、ある憂鬱な気分の夜、わたしの頭の中に、あの男の声がまた聞こえた。ゴールデンゲイトブリッジを見ていて、わたしの故郷のハウラー橋と比べていた。アメリカに今も住む友人たちは、わたしの決心を「まったくバカげたこと」と決めつけた。かの女王の地に住む友人たちは、「信じられない」と言った。外国に行ったことのない故郷の者たちはこう訊いた。「こっちで何かやりことでもあるのか?」 わたしがそれはどういう意味かと訊くと、こう言った。「NGOを始めて、こっちの人たちの手助けをするとか? あるいは、、、それとも、、、」 わたしがこう答えるとみんな驚いていた。「いいや、自分のためだ。ぼくの気持ちの問題、故郷の街に住みたいからだ」 そしてまた、わたしは「まったくバカげたこと」という言葉がささやかれるのを耳にした。 当初わたしが苦労したことは認めよう。確かに大変だった。銀行の残高は急激に目減りした。わたしは考えてみた。アメリカやイギリスの友人たちが言ったことは、正しかったのだろうか。わたしはさらに考えた。そしてその思いを全部、KMC(コルカタ地方自治体)の下水に流して、古い蓄音機をつけてみた。蓄音機はまだ生きていて、昔の記憶をよみがえらせた。わたしは微笑んだ。解放された気持ちになった。そして頭の中のあの男が、またやって来た。わたしはコルカタの自分のお気に入りの道を歩いた。コルカタ競馬場の脇の道だ。グゥルゥデーウを口ずさんだ。夕日に染まる空がゆっくりと闇に変わっていった。空を見上げれば、鳥たちが巣に戻っていく。わたしは目を閉じて、頭の中の男に言った。「あなたの言葉が心から好きだ」 ここでわたしは、今も奮闘している。わたしの愛する街で。喜びの街、コルカタで。朝から汗をかく暑さ、異常なほどの湿度、交通渋滞の列、ひどくなるばかりの大気汚染、そこを「マンチーナ ....... マンボーナ」が行進する。わたしはこれが大好きだ。こんなにも汚染された空気の中でも、街はあの髭の男の魔法の言葉を孕(はら)む。これからも、永遠に。ありがとう。 *グゥルゥデーウ(詩聖)とは、インドの詩人、思想家ラビンドラナート・タゴールのこと。1913年に「ギーターンジャリ」でアジア人初のノーベル文学賞を受賞。(1861年 - 1941年)
|
||||