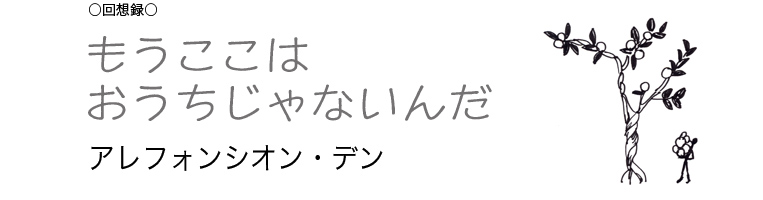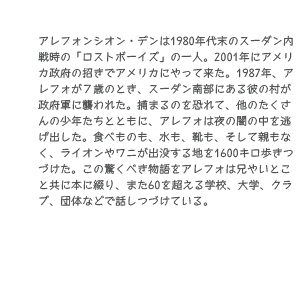<ロストボーイズと呼ばれたスーダン難民少年たちの回想録>
ベンソンがいなくなりアチョルが殺されたあの襲撃の一ヵ月前、ベラベラベラと音をたててやって来たヘリコプターが、ボクらを家の外に呼び出した。ヘリコプターは頭の上で、疲れてしまったみたいに低く降りてきて、黒い煙をおしりから出して空を飛んでいった。
一年たって、また同じことが起きた。今度はヘリコプターは小さくて、頭のすぐ上を飛んでいった。家の中にいた人たちは、外をのぞいた。ボクはヘリコプターが何を探しているのか、わからなかった。
ヘリコプターのいったすぐあと、侵略部隊が村にやって来た。何の前ぶれもなかった。北部人がやって来たら、ボクらは村を出て牛もよそへ連れだすことになる、という話を大人たちは聞いていた。でも今度の襲撃は、突然で激しいものだった。爆音が鳴り響き、馬やラクダが人のあとを追いまわし、弾がとびかい、泣き声と叫び声があふれた。この世の終わりみたいだった。
ボクは自分のヤギを捨てて、ほかの人たちと草むらに走りこんで身を隠した。煙が村じゅうに充満し、雲でおおわれたようになった。あちこちの屋根で火があがり、たいまつみたいだった。村の人たちはみんな、銃弾を逃れて走りまわった。ボクは侵略者たちが、捕虜にした人たちの腕と足をしばって、首に長いロープをかけているのを見ていた。捕まった人たちは目隠しされて、列になって村から連れ出されたので、自分がどこに向っているのかわからないままだった。「きっと川に沈めるんだ」とそばにいた誰かが叫んだ。「あいつら、弾を無駄にしたくないんだ」
その夜、ボクの大好きな村、ヤシとココナツの木でいっぱいのジュオル村は、見知らぬ場所に変わり果てた。
生き残った村人たちは、ジュオル村に戻ってはいけない、あそこで生きてる者はもういない、敵だけだ、と言った。ボクらは暗闇のなかを、ヘビのことも気にせずに、背の高い草に沿って移動した。痛いほどの恐怖を感じていた。ボクが考えていたのは家族のことだけ。家に帰りたい、でも大人たちは、子どもを家に帰してくれない。「安全じゃないんだ。つかまってしまう」 そう言われた。
食べものもなくわずかばかりの水で、ボクらはスーダン政府の軍隊があるトーチに近づかないようにして、百キロを超える道のりを歩いた。四日間歩いて、トンジ地方に入った。そこは反政府軍が守っていたので、逃げてきた人たちが集まっていた。大人たちはボクら子どもに「さあ歩いて、歩いて歩いて」と指示を与えた。そのとき道の向こうで、腹違いの弟のピーターがすわって泣いているのに気づいた。ピーターの母さんはボクの父さんの四番目の奥さんで、おばあちゃんといっしょに別の村に住んでいた。ピーターの村もきっと襲われたんだ。
ピーターはボクがそばに行くとさらに声を高めた。この子はまだ五歳で、服も毛布もなかった。何にももっていなかった。ボクはボロ布の肩掛けを斜めがけしていて、寝るときにそれを毛布にしていた。ボクは運がよかった。そのあとピーターはボクにぴったりくっついて離れず、ぼくの毛布もふたりでいっしょに使った。ボクらは町から町へ、大人たちに連れられて歩いた。大人たちはこう話していた。「この子たちには親がいない。スーダンの子だから、飢え死にさせるわけにはいかない」 でも子どもたちは病気になったり、ノドの渇きや飢えでたくさん死んでいた。中でもピーターみたいに朝から晩まで泣いている小さな子は。
そこからまた何日か歩いて、スィエトという町に着いた。そこで運のいいことにいとこのジョセフを見つけた。ボクはジョセフに泣いて頼んだ。「うちに帰んなきゃ。うちに連れてってよー」
「家に帰る道なんかわからないよ」 そうジョセフは言った。「そんなことしたら道に迷ってしまうか、動物にくわれるか、オオカミと出くわすぞ。この子たちといっしょに行くんだ。安全な場所にきっとたどり着けるよ」
ジョセフは九歳で、ボクより二歳年上だった。ジョセフはジュオルの近くの村に住んでいたけれど、いつも牛の世話をしていたからあまり会うことはなかった。ジョセフはサンチノ・アクエトクとディイン・ンゴルという友だちといっしょだった。ボクらは五人グループになった。ジョセフが一番年上で、背も一番高かった。
スィエトの町で、大人たちはボクらを二、三百人ずつのグループにわけた。ボクらは外で寝かされた。ジョセフがゴミ溜めから蚊帳(かや)を見つけてもってきた。それはすり切れてきたなく、穴がいっぱい開いていた。ジョセフはアカシアの木からトゲを抜いてきて、皮をはぎ、とがってないお尻の方に穴を開けた。拾ってきた白いソックスから糸を引き出し、蚊帳の網の穴を全部つくろった。ボクらはゴミ溜めから服を拾ってきて、洗った。
スィエトにいるとき、ボクの兄さんイエルとばったり出会った。ジョセフはイエルの顔を覚えていた。ボクはほんの二、三回村で会ったことがあるだけ、それはイエルがワウにある大学に行っていたからだ。政府軍がそこの学生を皆殺しにするまで、イエルがいた大学だ。いまイエルは反政府軍といっしょで、兵士たちが町にやって来たとき、ジョセフがイエルを見つけた。子どもたちがいっしょに逃げていると聞いて、スィエトまでボクらを探しに来た、とイエルは言った。ピーターとジョセフとボクは家族の一員と会えたことに心から感謝した。なかでもイエルのように年長者は、ボクらの世話をしたり、こうした方がいいと言ってくれる。心の中では、父さん母さんがいてくれて、ボクを守り、愛し、こうするようにと言ってくれたらと願っていた。ボクは父さんのことを毎日想っていた。イエルが突然呼ばれて、他の兵士たちといっしょに戦うために北へ向ったときは、ボクの胸はぽっかりと穴が開いたみたいだった。家族はボクにとってかけがえのないもの。それなしにはボクは、砂漠に生えるひとりぼっちの木と同じだ。
-----------------------------------
ボクらは別の兵士のグループといっしょに、また南へと向った。新しい場所に着くたびに、そして初めて出会うグループと顔をあわせるたびに、ボクは家族の誰かがいないか、なかでもベンソンがいないか探した。ボクはピーター、ジョセフ、さらにはイエルにだって会えた。ベンソンは二年前にいなくなったとはいっても、どうして見つけられないって言える?
ずっと歩きづめなので、ボクの足には傷がたくさんあった。そうなっているのはボクだけじゃない。昼間は安全ではないので、移動ができない。ボクらは裸足で夜に歩く。でも暗がりの中では、自分が何を踏んづけてもわからない。夜にはヘビが草原に出てくるから、それでみんなは噛まれてしまう。ボクの足は腫れていて、でもどうしてなのかわからない。歩くのが難しい。歩きつづけるために、ボクは足を引きずらなければならなかった。ボクは自分が生き延びて、家族が生き延びるのを助けると心に決めていた。一週間して、大人の人が言った。「見てごらん、この小さな穴を、膿みが出ている。ヘビに噛まれたんだ。毒蛇じゃなくて、よかったな」
ジョセフはボクたちを守ってくれた。いつもボクらがそばにいるようにしていた。何か危険なことが起きたときは、たとえばハイエナが現われて、みんなが逃げ出したときとか、ジョセフはどうしたらいいか知っている。ジョセフは木の枝のこん棒をもっていた。誰も彼もを守ることはできなくても、いっしょにいるボクらのことは守ってくれた。
ときどき、ボクらが手のつけられない状態になると、ジョセフでさえどうしようもなくなった。ボクらは泣きやまなかった。ジョセフでさえ泣いていた。何週間も歩きつづけることに耐えられなくなっていた。子どもたちはヘビに噛まれたり、飢えのために死んでいった。ボクらの中には、辛さ悲しさに耐えられず、口をきかなくなる子がいた。食べものを口にしなくなる子もいた。ピーターは食べものがあっても、食べないことがよくあった。ボクが食べものを見つけてきたときも、ピーターは食べようとしない。ピーターが泣いていると、ボクも、他の子たちも泣きはじめた。泣いてる子のところにいって、やめさせるのは、たいていボクだった。みんな泣くのがいいとは思ってなかった。泣いてばかりいて食べることをしない子が、死んでいくのをボクらは見ていた。
家を出てからはじめて、ボクらは安全と思える町に着いた。そこの人たちはまだ牛を飼っていた。そしてボクらに五頭の牛をくれた。でもボクらの集団はすごい数なので、一人にあたる肉切れはほんのわずかだった。町の人が牛乳をもってきてくれたときも、小さな子たちだけが、コップ半分ずつもらった。ボクくらいの子にとっては、とても足りる量じゃない。その夜、みんなで川のそばで寝ていたら、ハイエナが一人の子に襲いかかり、その子の顔を喰いちぎっていった。次の朝、その子のほっぺたが口まで裂けているのを目にした。とても恐くなって、その晩は一睡もできなかった。
ジュオルを出てから一ヵ月のあいだ、ボクらは外で眠り、食べものもほとんどなかった。ユロルの町に着いて、ボクらはやっと蚊帳を新たに与えられ、二百人の男の子たちは、細長い建物のコンクリート敷きの場所に連れてこられた。
次の朝、爆発の音でボクらは目覚めた。音のすさまじさに震え上がったけれど、すぐに音は消え去った。ボクらは川のところに行った。そこに前の日あった何本ものマンゴーの木がすっかりなくなっていた。アントノフが、土手にいる白い鳥たちを見て、人間が洗濯をしているのだと思って、爆弾を落としていったんだ、と兵士たちが言った。
大人たちがアントノフのことを話しているのを聞いたことがあった。「アントノフってなに?」とボクら。
「アントノフっていうのは政府がロシアから買った飛行機だ。やつらは下から見えないくらい高いところから、爆弾を落とす。音が聞こえるだけだ」
ロシアってなんだ? ボクは思った。
隊長の一人がボクらをすわらせ、アラビア語で話しかけた。それをそこにいたヌエル族の子たちがディンカ語に訳してくれた。「きみらは未来だ。スーダンの明日をになっている」 そんな風に話しはじめた。「わたしたちはきみらに安全な場所を見つけるつもりだ。学校を見つけ、反政府軍の元で保護する。きみらはまだ小さくて、一人で生きられない。わたしたちはきみらを助けたい。きみらの誰ひとり、死なせるようなことはしたくない」
兵士たちは爆弾について教えてくれた。「走っちゃだめだ。その場にふせるんだ。小さな飛行機はとっても速い。音を聞いたときには、もう通り過ぎて爆弾を落としたあとだ。大きな飛行機はアントノフだ。ものすごい爆音がするが、爆弾はそのときにはもう落ちたあとだ。逃げるには遅い」
毎晩、ボクらはヤシの葉で床をきれいに掃除し、毎朝、アントノフが爆弾を落とした。一日も休まずにやって来た。ボクらは毎朝、日が出る前に起き、身を守るために深い穴の中に隠れた。国際連合の飛行機が薬を運んで来たときも、誰かがこう叫んだ。「アントノフだ、アントノフだ」と。ボクらは穴に逃げ込んだ。アントノフはすごく高いところを飛ぶので、ボクらから姿は見えない。でも向こうからこっちは見えている。風向きを調べて、それから十六個、二十個の爆弾を落とすのだ。その一つ一つから噴煙が上がるのが見えるだろう。毎日ユロルの町に爆弾が降ったので、メタル片が町じゅうに散らばっていた。爆発の最中、逃げまわった人の中に、手や足に傷を負った人たちがいた。頭にメタルがささった人もいた。その人たちは恐くて走り出すんだ。ボクは、その場に伏せることがアントノフの爆弾から身を守る方法だ、ということを学んだ。
運がない時は、爆弾がみんなが隠れている穴に落ちることもあった。そのときは誰も生き残れない。そこにいた全員が、爆弾のメタル破片に切り刻まれて死ぬ。
ある夜、空のはるか高いところから、大きな振動音が聞こえた。目を少しあけたら、他の人たちはみんな眠っていた。だからボクは夢を見ていたんだろうと思い、また目を閉じた。
深い眠りの中にいたとき、地震のような大きな衝撃が建物を襲い揺れつづけた。外で爆発があったのだ。まだ暗かったけれど、あちこちから泣き声や叫び声が聞こえてきた。子どもたちが埃と煙の中から、咳き込みなかがら出てきた。ボクも起きてあとにつづいた。
日が昇ってからボクらは、爆弾がボクらの建物の屋根を通過して、爆発しないまま隣りの建物との間に着地しているのを見つけた。太った男の人くらいの大きさで、とても大きかった。上にはプロペラがついていて、下の端は先が地面に突き刺さっていた。もし爆発していたら、みんな死んでいただろう。
ユロルの反政府軍の兵士たちは、戦いのために北に送られることがよくあった。兵士たちの長はこう言った。「三百から四百人の子どもたちがここにいて、アントノフで殺されようとしている。ここは安全とは言えない。移動しなければならない」
ボクらが通ったユロルの南部は、人食い族がいると言われている場所だった。男の子たちが、中でも小さな子たちがいなくなった。草原の動物がその子たちを食べてしまったのだろう。そのあたりには、ニャンジュアンと呼ばれる小さなライオンが住んでいた。ボクの故郷の村にはいない種類のライオンだった。もし年が大きければ(十歳以上とか)、このライオンは鋭い目を向けるくらいだろうけど、五歳とか七歳とかなら捕まえて食べてしまう。その小さなライオンは、ボクら子どもたちを食べあさった。
ある晩そのライオン、ニャンジュアンが、ボクらが寝ているときにやって来た。ボクのすぐそばの子を、ニャンジュアンが連れていった。「助けて、助けて!」 ボクは泣き叫んだ。
ボクが目にしたのは連れていかれるその子の影と、暗闇に消えていく直前に聞いた泣き叫ぶ声。次の朝、ボクらは血の跡と手、足、頭といったその子のからだの一部を目にした。目はすっかりえぐられていた。ニャンジュアンが人を食べるとき、目をえぐり出し、内蔵や腹を食べ、足や手だけ残していくので、誰だかわからない。目がない人間というのは、おそろしい見映えだ。
神様がボクを守ってくれたんだ、そうでなければボクもニャンジュアンに食べられていた、と思った。
-----------------------------------
ボクらが通る村々には、子どもを亡くした人たちがいて、小さな可愛い子を見つけると、自分の子どもにしたがった。ある村で、ボクはナッツをもっている女の人と出会った。ボクはそのナッツがものすごく欲しくて、少しください、とその人に頼んだ。
その人はこんな風に言った。「ぼうや、あなた、かわいいわね。わたしのぼうやが死んじゃったの。あなた、わたしのぼうやにそっくり。ぼうやを見たとき、うちの子かと思ったわ。お父さんお母さんはどこにいるの?」
「知らない」とボク。
「どこに行くの?」
「知らない」
ボクが質問にぜんぶ答えているのに、その人はボクにナッツをくれない。
「わたしと暮らさない? 幸せになれるわよ」 その人が言った。
「そのナッツを少しください」 ボクがせがんだ。
ナッツをやっとくれたので、ボクはそれを食べた。
「わたしといっしょに暮らしてくれる?」 その人が聞いた。
「できません。自分の家族といます」 そう答えた。
その人は悲しそうな顔をした。ボクはそこを立ち去った。
-----------------------------------
ピーターのように小さな子には、歩きつづけるのは大変なことだ。ピーターはボクにくっついて離れない。それはボクが腹違いの兄だからだ。ボクらは道からはずれて三日間、食べものなしの水だけで歩きつづけた。小さな町に着いたとき、ボクらはものすごくお腹が減っていた。でも村の人たちはボクらに食べものを分けてくれなかった。これまで人に物乞いをしたことなどなかったけれど、死ぬほどお腹が減っていたので、ボクは女の人にピーナツをねだった。その人はダメとことわったあとで、こう言った。「しつこく言うと、ぶつよ」
ボクは口をとざし、そこを立ち去った。地面にほんのわずかな穀物のつぶが落ちていた。ボクらの中の何人かが、砂の中からそれを集めはじめた。ボクが頭をあげると、ピーターがぼんやりすわっているのが見えた。「ピーター」とボクは声をかけ、「おいで、穀物を拾うんだ」
ピーターが答えた。「ボクはメンドリじゃない。地面から食べものなんか拾わない」
拾い終わって見ると、手の平に小山ができていた。ボクにはとても貴重なものだった。みんなの集めたものを一つにして、小枝を拾ってきて火をおこし、缶の中で料理した。みんな一口ずつ食べることができた。ピーターも一口食べた。一口の穀物を口にしたおかげで、ボクらはしばし陽気になっておしゃべりをした。
食べ終わって、ボクはピーターがすわっているところに行った。「おまえはもう、ママのおうちにいるんじゃないんだ」 ボクはそう始めた。「どうしてこんなことになったのか、考えなきゃだめだ。メンドリみたいだなんて、文句を言うんじゃない。生きるためになんだってやらなきゃ。おまえくらいの子たちが、死んでいっているのを見ただろう。その子たちはいつも泣いてばかりで、いつも沈みこんでいる。ボクが大人だって言ってるわけじゃない、だけどこれが今の状態なんだ。生きるために、ボクが信じることなんだ。どう思おうと、おまえ次第だ。死にたいなら、今のままでいて死んでしまえばいい。ボクはかまわない。ボクらはみんな死ぬんだ。だからどうしようと勝手だ」 本当は、かまわなくはない。ボクはピーターに死んでほしくない。ピーターはボクのたった一人の、生きているのがわかっている兄弟なんだから。
ピーターは静かに聞いていた。この子はお母さんお父さんが恋しくてたまらないのだ。でもピーターは、ボクの言うことを大きい子がするようにじっと聞いていた。もしボクやジョセフがいなかったら、自分が生きていくのが難しいと、知っているのだ。
ボクらはまた歩きはじめ、ナイル川上流へやってきた。そこには船がいて、ボクらを赤道地域へと運ぶのだった。ボクはベンソンもここを通っただろうか、と思った。たくさんの子どもたちがここを通り、エチオピアに向って東へ進んだと聞いていた。ボクらはそこで二日間、まったく食べものなしで過ごした。ボクは救いようのないくらいお腹が減って、口をきくことすらできなかった。ガソリンの切れた車のように動けなくなった。
大きなモーター付きの船で、ボクらはナイルを渡った。悲しくみじめな旅だった。ボクの頭には、家族と村と離れていくディンカランドのことしかなかった。大人の人たちは、安全な場所を見つけなければ、そこで戦争が終わるのを待つんだ、と言う。だけどボクが願っているのは、家に戻ること、それだけ。
ナイルの東岸に着くと、アリアブ・ディンカ族の人たちが、ボクらに牛をくれた。指揮官が十人の子どもに一人の兵士をあてがった。牛が殺されると、その兵士たちが肉を受けとり、ボクらのために料理してくれた。ここ何週間の間で、初めての満足なご飯だった。ところがその晩、ボクらは蚊の襲撃にあった。牛の群れが鳴いているような大きな音をたてて、すごい数の蚊が集まってきた。誰ひとり眠ることができなかった。十人でひとつの蚊帳を分けあったけれど、ひとりがこっちに引っぱれば、別の者があっちに引っぱるという具合だった。蚊に好きなだけくわせるしかなく、手で触れば、からだじゅう血だらけだった。ここの人たちはどうやって暮らしているのだろう、とボクらは思った。
朝になって、ボクらは疲れきって、家が恋しく、みじめな気持ちになって、みんなで泣きはじめた。大人たちがボクらに静かにするように言った。
「うちに帰りたい」
「家には帰れない。あそこは戦場になっている、戻っても何もない」
「ボクらはどこに行くの?」
「きみらを連れていくのは、子どもたちが集まっている場所だ」
「エチオピアに行くの?」
「いや、南に行く。パラタカというところだ」
「パラタカ? パラタカはどんなところなの?」
「そこにはキリスト教の学校がある。きみらは安全にいられる」
パラタカというのは、いい場所のように聞こえた。「どれくらいかかるの?」 ボクらが聞いた。
「もうそんなには遠くない。トリートを超えれば、ほんの二、三日だ。トリートには二、三週間で着けるだろう」
大人の人たちは、もうボクらは六百キロを超える距離を歩いてきた、と言った。トリートはあとたった三百キロほどだ。そしてパラタカまではそこから二日間で行ける。百キロちょっとの距離だ。どれだけの距離をここまで歩いてきたのか聞いて、ボクらはおおいに励まされた。ボクらは涙をふいて、もっと強くなろうと決心した。
でもボクらはちっとも強くなんかなかった。おかしな行動をとる子どもたちがいた。その子たちは、普通の人がしないような、気違いじみたことをやった。ある子はおしっこをそばにいる子たちに撒き散らした。そして言った。「雨だぞー」 まったく口をきかなくなる子たちもいた。話すことができなくなったのだ。人のことをただじっと見るだけ。ボクも時々、口がきけなくなることがあった。ばかなこともした。何でもないことに怒り、けんかした。それが自分の置かれている状況に対する折り合いの付け方だった。そのあとでボクは、わかってきた。もし互いにけんかするだけの力があるのなら、父さん母さんからボクらを引き離した人たちとどうして戦わない? ボクはみんなに言った。「ボクらはこれから起こるいろんなことと戦わなくちゃならない。一つになれば、十人の子どもは一人の大人と同じだ。ひとりひとりに頭があるんだから、何であれそれに打ち勝つためのいい考えを思いつくことができるはずだよ」 それは生き延びるためのもう一つの方法だった。一つの集団として強さを保つのだ。
自分勝手な子たちもいた。食べものを見つけると、自分だけで食べて人に分けようとしなかった。人とものを分けることから、ボクは多くを学んだ。何かちょっとした食べものを見つけたとき、他の子が目にはいると、分けてあげないことには気が落ち着かなかった。ボクはそれを割って、一切れその子にあげる。そして一切れを食べる。そしてボクが食べものが必要になったとき、今度は誰かがボクにその一切れをくれた。
ボクらはナイル川に沿って南下し、ガメイズに向った。そこで夜を過ごすためだ。夕日が沈んでいくとき、燃えさしみたいな真っ赤な光線があとを引いていった。ボクはきれいに澄んだ青い空を見て、他の子たちに声をかけた。「見てごらんよ、今日の空は、どうしてこんなに澄んでるんだろう」
「雨が降るんじゃないの」とディインが言った。
ディインはボクと同じことを考えていた。
他の子たちがばかにするように笑った。一人の子が「おまえは予言者か?」と言った。
みんなゲラゲラと笑いはじめ、涙が出るまで笑いころげた。ディインとボクは引き下がり、口をとじた。夜になって、ボクらはグループごとに分かれ、子犬が母犬のところに身を寄せあうようにして、蚊帳の下に固まった。ほとんどの子はすぐに眠ってしまった。ボクは星がまたたく空を見上げて、母さんや故郷のことを考えていた。その頃は、寒くないように暖かな毛布や気持ちのいい上掛けにくるまれて、小さな赤ちゃんみたいにすやすやと眠っていたんだ。誰かが雨期のカエルみたいないびきをかきはじめた。くすくすと笑いだす子がいて、ボクの思いを中断させた。
ボクは頭をもちあげて、子どもたちがずらりと寝ているところを見た。「だれなの?」
「ボクだよ、サンティノだよ」
ボクらはちょっとの間おしゃべりをして、それからサンティノはすぐに眠りについた。ボクが寝はじめたと思ったら、突然の強風で目を覚まされた。熱い炭を踏んだ小さな子みたいに、ボクは飛び上がった。すぐにもっと強い風が吹いて木をしならせ、突風がゴーゴーとうなり、枯れ枝を激しく鳴らし、落ち葉をさらい、さびた缶カラを吹き飛ばした。寝ぼけ眼でボクは暗がりを行き、みんなの上でつまずいた。ボクが足を一歩外に踏み出すと、雨が落ちはじめた。それは大きな黒い粒になってすごい勢いで落ちてきた。胸が張り裂けるような雨となり、太陽に焼かれてひび割れた地面を容赦なく叩きつけ、割れ目のところに大きな水たまりをつくった。子どもたちがソプラノ歌手のような、悲鳴をあげて泣き出した。雨はさらに激しく地を打ち、それはアドウゴ太鼓のようだった。こんな雨は見たことなかった。ボクは水たまりの暗い地面の上を、シャブシャブと音をたてながら歩いていった。
サンティノが「あー!」と声をあげた。
「ニャリク(神さま)」とボクはつぶやいた。あごがガクガクと震え、歯がカチカチ鳴った。稲光が起きると、光の舌がとサッと走った。子どもたちはみんな、散り散りになって逃げた。ボクは黄ゾウ草でふいた屋根の家並の方に向って走った。凍る寒さから身を守るため、小屋の一つに頭をつっこんだ。そこはもう人でいっぱいだった。年長の男の子が大きな手をボクの頭に置いて、外に押し出した。みんながわめいた。「ここはいっぱいだ」
ボクはじっとドアの前に立っていた。それから別の小屋に移動した。死ぬかと思うほど、からだが震えているのがわかった。ボクの命はこれで終わってしまうのだろうか。
いやだ! ボクは気持ちを強くもった。小屋の中に飛び込んで、人垣の上にからだを投げ出した。
そんな雨だったけれど、次の朝、蚊が少なくなっていたのはよかった。その日、ガメイズに大きなトラックが次々にやって来た。家くらいの大きさの幌のあるトレーラーを三つ引いていて、ボアへ食料を配って戻るところだったので中は空だった。
トラックの運転手たちが車をとめて、料理を始めた。ボクらの兵士たちがそこに行って、運転手たちと話をした。「この子たちが歩いてるのを見てくれ。俺たち兵隊は歩ける、大人だからな、でもこの子たちはひどく疲れているんだ。トリートまでこの子たちを連れていくのを、助けてくれないか」
一人の運転手がよその言葉で何か叫んで、トラックに飛び乗った。エンジンをかけ、車が走り出すと、兵士たちが銃を撃って全部のタイヤをへこませた。運転手が飛び降りて、大声で怒鳴った。兵士たちは運転手を端からつかまえて叩き、トラックの運転席に追いやった。運転手はみんな、びくびくしていた。
兵士たちがボクらを大声で呼んだ。「トラックに乗るんだ」 エンジンがかかった。ボクはトラックの荷台に乗ろうとしたけれど、タイヤはボクの背より高かった。すると男の人が来て、ボクらみんなを荷台がいっぱいになるまで積み上げてくれ、一台目が埋まると、次の荷台に積み込んでいった。
三十人の子どもたちが、一台のトレーラーの床にすわった。ボクはワクワクしていた。車に乗るのは初めてだった。トラックが動きだし、ボクは幌のすき間から外を見ていた。タイヤが撃たれてパンクした一台をのぞいて、トラック全部が列をなして走った。外の木が飛び去るように消えていくので、ボクは恐くなってすわった。外は暗くなり、ボクらは振動であちこちに転がった。そばにいる子がボクをつかみ、しがみついた。ボクらは揺すられ、端から端へと転がった。トラックの排煙が立ち込めていた。ボクは大丈夫だったけれど、他の子たちはみんな気持ちが悪くなっていた。たくさんの子が吐きはじめた。そこらじゅうがへどだらけ。ますます外は暗くなり、灯り一つなく、アアアーはひどい臭いだった。
雨の季節のあいだ、車が移動するするのはスーダン南部ではとても大変だ。ボクらの運転手は、道が泥水でおおわれていて、トラックや車が立ち往生しているのを見つけた。運転手は動けなくなっている車をさけて通ろうとしたけれど、ボクらのトラックも泥にはまってしまった。兵士全員が車から飛び降りた。ボクは興味津々で、荷台から外に顔を突き出して、何をやろうとしているのかを見ていた。壊れた車があちこちにあって、そのまわりには人間の骨が散らばっていた。頭蓋骨がこっちを見て笑っているように見えた。ボクらのトラックが泥から抜け出すまで、兵士たちは一時間くらい奮闘していた。
政府の軍隊は今も、ナイル川の向こう岸の町を制圧していた。トラックがとまり、兵士たちは車を降りて火を焚いた。そしてボクらに静かにするように言った。ボクらはものすごくお腹が減っていた。兵士たちは自分たちのことにかまけて、ボクらのことを気にかけてくれなかった。「いいか、きみらはもう、ママのおうちにいるんじゃないんだ」
ジョセフが穀物を少し持ってきてくれた。ボクらは火を起こしたけれど、何分もしないうちに兵士たちから出発すると言われた。ボクらはその日、一晩じゅう、丘や森の見える美しい緑地を走った。そして一週間前にアントノフが落ちたという村にたどり着いた。たくさんの人が殺され、生き残った人も救いようのないひどい怪我を負っていた。
そこでボクらは一休みした。兵士たちは町の外に出てはいけないと言った。地雷があるからだ。ジョセフが料理を始めた。二、三分後、兵士たちがこう言った。「さあみんな、行くぞ」 またボクらは食べ逃してしまった。
いくつもの町を通り抜けた。どこもメチャクチャにやられていた。崩れた建物、壊れた車。戦場のようだった。血の臭いもした。
ひどい状態の町を次々に見ているうちに、ボクらの気分は沈んでいった。もう村とは呼べないものになっていた。どうしてムラヒリーンがボクらの村を襲ったのか、わかったと思った。ムラヒリーンはボクらの牛をねらったのだ。ボクらの持ち物や子どもをねらったのだ。でもこのよくわからない戦争を、ボクが理解していたわけではない。どうしてこんなにもひどく、ボクらの土地をむさぼり喰い、骸骨の山にしていったのか。大人たちはいつも戦争の話をしていた。奴隷制やアパルトヘイト、人種差別や人種隔離、部族主義などについて話していた。大人たちはこの戦争を、宗教戦争と呼んでいた。聖戦だ。ボクは大人たちの話をじっと聞いていたけれど、よく理解できなかった。子どもは大人とは違う風にものを見る、そう思った。ボクが感じたのは、戦争というのは、男であろうと女であろうと、子どもでも大人でも、若い人に年長者、金持ちに貧乏人、誰もを同じに、ただの人にしてしまうということ。
この間ずっと、ジョセフはボクらのことを心配し、気づかい、いつも何かと面倒をみてくれた。ピーターはずっとひどい状態だった。食べることをせず、ちょっとしたことに泣きわめいた。誰かがピーターから何かをとったりすると、すぐに大泣きをはじめる。そしてこう言う。「ママがここにいたら、こんなじゃなかったのに」 ボクらはピーターに言った。「いいか、そんなことを言うな。もうここはおうちじゃないんだ」 何回この言葉を口にしたことか。七歳とか八歳の子どもは、世界というものを知らない。自分たちはもう、ママのおうちにいるわけじゃない、わかっているのはそのことだけだ。
*ムラハリーン:政府側準軍事組織の人民防衛軍やバッガラの民(チャド湖と白ナイルの間に住む牛牧民)からなる民兵組織
* * * * *
パラタカ
トリートの町にボクらのトラックの列が着いたのは夜だった。ボクたちは、そこに最初に到着したグループだった。反政府軍が、何ヵ月かの戦闘のあと、政府の軍隊からトリートを取り戻していた。町じゅうにいやな臭いが立ち込めていた。
ボクらは次の朝、壊れた建物や銃弾、薬きょう、骨や頭蓋骨があちこちに散らばる中で目覚めた。町には近代的なビルがあって、舗装された道路もあった。戦争の前はきっと、すてきな場所だったんだろうな、と思う。背の高い建物がある伝導所や天にとどきそうなカトリック教会があった。そこは小高い丘にあって、マンゴーやグァバ、レモンなどの木々が緑にゆれていた。車や乗りものがたくさんあったけれど、どれも壊されて血に染まり、死体の臭いがした。三ヵ月、四ヵ月ではなく、何年ものあいだ戦争があったみたいだった。ボクらは半分爆撃を受けた学校の建物に連れてこられた。水道管もこわれていた。水洗トイレがあって、それはボクには初めて見るものだった。ただし水は流れなかった。兵士たちはどうであれ、そのトイレを使っていた。町じゅうのトイレは、普通の家のトイレでさえ、クソだらけだった。その臭いときたらひどいものだった。町は大きかったけれど、地雷に囲まれていたので、ボクらは遠くへは行けなかった。気分転換にどこかへ行くことが許されてなかった。
ボクらは毛布をかぶって外で寝ていた。ボクの毛布はとても丈夫で、すごくきれいだった。今までの自分の持ち物の中で最高のもの。その毛布は、黄色と青と赤とグレーの縞模様がいっぱいに広がっていた。毛布を洗ったら、ボクは一日じゅう、それが木の枝の上で乾くまで、誰にも盗まれないように見張っている。その毛布が大好きだった。厚みがあって丈夫で、濡れるととてもいい匂いがした。故郷の村で、ヒツジのそばにいたときみたいな感じだった。
ボクらは許されている範囲で、あちこち歩きまわった。町の中には食べもののある市場があったけれど、爆弾や地雷があるので、兵士たちはそこが一掃されるまでは入ってはいけないと言った。兵士たちはいつもボクらに言っていた。「ここは地雷をのけてある。ここから遠くへ行ってはいけない。向こうに行ってはだめだ」 ボクらが行ってもいい範囲を、兵士たちは教えた。「ここの外にはたくさんの地雷がある。毎日、誰かが吹き飛ばされている。その人たちは何かしに外に出たんだ。でもきみらはだめだ。安全のために、ここから出るな」
ボクたちは聞きはしなかった。地雷があったとしても、外に行って食べものや薪を見つけなければ。それがどんなに危険だったとしても。一人の子が爆弾を持って帰って、地面に置いた。バアーーン! そんな風に爆発した。「やめろよ、やめろ」 ボクらはその子に言った。「人が死ぬぞ」「でも面白いじゃん」 そうその子は言った。その子はそのあとまた同じことをして、吹き飛ばされた。他の子たちも巻きこんで殺すところだった。
面白がってボクらは、そこらじゅうに散らばっている薬きょうで遊んだ。一人ずつ薬きょうをいくつかもち、並べる。「いいか、ボクらはアラブできみらは反政府軍だ。バン! ボクが自分の薬きょうでおまえの薬きょうを撃ち落としたら、そっちの兵士がやられたんだ」 毎朝、ボクらは兵士たちが本物の銃を撃っているのを見ていた。
野外の市場が活気を取り戻していた。人々はそこでお金、食べもの、ちょっとした雑貨などをやりとりしていた。ジョセフとボクも商売をはじめた。トリートの川が氾濫すると、誰もそこに行ってマンゴーを取ってこようとしなくなる。それはカミアリのせいだ。マンゴーの木に登ると、カミアリはパッと寄ってきてからだを這いまわり、かまれるとものすごく痛い。それでみんな木から落ちてしまう。でもボクは木登りが大好き、ジョセフも大好き。ジョセフがどうやって知ったのかわからないけれど、手や足におしっこを塗ってからマンゴーに木に登れば、アリは逃げ出すんだ。
そんな風にして、ボクはマンゴーの木に登り、食べたいだけ食べて、それからいくつかを市場にもっていって、調理した食べものを買うためにお金にかえた。すごくおいしかった。
トリートでの最初のひと月の間に、アントノフが二度市場に落ちて、たくさんの子どもが死んだ。二ヵ月目、ヌバ山からいっせいに、たくさんの男の子たちがやって来た。その子たちは飢えていた。すごく痩せて、疲れ果てていた。何ヵ月も水浴びもしていなかったので、ひどい臭いがした。男の子たちはシラミにたかられていて、隣りにすわろうものなら、シラミの隊列がこっちに乗り移ってくる。ヌバの子たちは、トカゲを殺して焼いていた。ひどい臭いがしたけれど、ヌバの子たちは気にしていなかった。口に入るものなら、何でもよかったのだ。からだというのは、エンジンと同じ。エンジンが切れたら、自分の世話さえできなくなる。食べものを口にすれば、いろんなことに心を向けられるようになる。
トリートでも、ジョセフはボクらを守ってくれた。十歳とか十一歳の年長の子たちがボクらを殴ったりすると、ジョセフが来てやめさせた。ジョセフは一度、みんなをいじめてる三人の悪ガキとやりあった。三人はジョセフを攻撃して、殴りかかった。ボクはいてもたってもたまらず、悪ガキの一人に向かっていった。その子はボクに「おまえ、殺してやるからな」と言った。
大人の人がやって来て、木の棒でその子をたたいた。その人は銃をもっていて、こう言った。「人がたくさん死んでるところから、きみたちはやって来た。きみらが仲間同士でやりあっているのを、わたしは見たくない。互いを好きになれ。きみらには、すべきことがたくさんあるはずだ。きみらは飢えと戦っている。きみらの命を狙っているやつらと戦ってもいる。きみらが命を守るため、逃げてきた者たちのことだ。それなのに、きみらはここで互いをやっつけようとしている。他の子をいじめようとしたり、けんかをふっかける子を見つけたら、わたしがその子の頭を撃ち抜くからな」
ボクらは銃などさわったこともなかった。誰かが銃を手にして発射させるのを見て、撃たれたものは死ぬとわかった。ボクらは銃のことを危険な棒、と呼んでいた。もし誰かがその棒を自分に向けたら、死んでしまうということを知った。
十歳くらいの男の子たちの中には、言うことをきかない者がいた。その子たちは人が殺されるところをたくさん見てきた。そして自分たちも人を殺したいと思っていた。戦士になりたいと思っていた。優しさや哀れみなんてもちたくないと思っていた。たぶん、その子たちはあまりにたくさんの死を見て、心がすり切れてしまったんだ。
-----------------------------------
二ヵ月後、ボクらはパラタカに向けて出発する、と大人たちに言われた。戦争が終わるまで、そこにいることになるらしい。そこはスーダンの一番南の端に当たり、政府軍が攻撃しているところから離れた場所だという。ボクらは従うしかなかった。もう家には戻れないのだ。パラタカがいいところでありますように、と思ってついていった。
兵士たちがボクらを連れて橋をわたったとき、まだ雨の季節のさいちゅうで、トリートの川はすごい勢いで流れていた。曇り空のもと、ボクらは頭より背の高い草が生えている草原を通って、丘を越えて南に向った。何もかもがボクの背より大きかった。ヌバ山から来た男の子たちを入れると、ボクらは千人を超えて、たぶん二千人くらいの集団になっていた。たった五人の兵士がボクらを先導していた。
二日目に、ボクらはハルツームという小さな町に着いた。北の方にあるスーダンの首都と同じ名前の町だ。ボクらは豆をもらった。出発してからずっと何も食べていなかった。ガソリンタンクの上部を切り取って、豆を入れて料理した。ガソリン臭くても、ボクらは指をその中に突っ込んで豆をつかんで食べた。ヌバ山の子たちは手を押し込んで、熱い豆をすくい取った。ボクは手が熱くて、たった二つまみしか豆を取れず、そうしている間に豆は消え去った。がっかりするのと同時に、腹をたててヌバの子たちとやりあった。
その晩たくさんの子どもたちが、大人たちはウソをついている、と言い出した。「パラタカは見捨てられたような場所で、ツツガムシでいっぱいだそうだ。よその子どもたちはパニャドに向ったらしい。パニャドの方がずっといい」 その子たちはここを出て、エチオピアに向った。
もしかしたら、ベンソンや他のいとこたち、ベンジャミンやエマニュエル、リノもそこに行っていて、会えるのではないかと思ったけれど、ジョセフとピーターとボクはここにとどまった。あの子たちが何を知ってるというのか。うわさ話はいつもあちこちにあった。大人たちはボクらは安全な場所に向っていると言った。キリスト教の学校だ。そこは戦争が終わるまでいられる場所だ。ボクらはもう歩くのに疲れた。毎晩寝るときに、恐い思いをするのにも疲れてしまった。食べものも水もなく次の日も生きられるのか、心配することにも疲れた。
離れた丘のところから、ボクらは、パラタカの赤れんがのビル群をやっと目にした。目的地を見おろして、ボクはなんだかいい気分になっていた。何ヵ月もの間で、一番家に近いと感じられるものが、あともう少しなのだ。ボクは毒蛇にもかまれず、人食いにも襲われず、病気もしないで、飢えもせず死にもしなかった。このひどい旅をなんとか耐えた。これからボクの行く道に何が訪れようとも、ボクは生き延びられる、そう思った。
パラタカに最初に着いたのは、ボクらではなかった。もう少し小さなグループがすでにそこにいた。その子たちは汚れて痩せていた。ひどく痩せっぽちだった。みんな、かかとで歩いて、すわると自分の足をいじっていた。ツツガムシだ!
最初の週、ボクらは年齢ごとに、別々の建物に分けられた。ボクはピーターといっしょだったけれど、ジョセフはよそに行った。ジョセフが行ってしまった最初の日、ボクはボアやヌバなど他の地域からやってきた子たちと、十五回もけんかをした。他にも、けんかをする子たちがたくさんいた。ボクがけんかばかりしていると、大人たちが言った。「規律を守れ」 そしてボクを年長の男の子たちの中に入れて、その子たちがやっていることをさせた。木を切ったり、掃除したり、指揮官の家を建てたり。ボクはけんかをやめた。ジョセフといっしょにいられて、嬉しかった。ボクは規律を理解した。
家を出て、パラタカに着くまでは、ボクはいつも悲しく、怒ってばかりいた。ただ生きていただけ。でも、いる場所が決まり、たくさんの子たちといっしょに暮らすようになって、ボクは自分の中に変化が起きたことがわかった。ボクはみんなと馴染もうとした。ボクらはいっしょに出かけていって、サッカーをして遊び、こんな風に叫んだ。「ボクらのチームがいちばんだ! いちばん強いチームだぞ!」
でもピーターはそうはならなかった。泣いてばかりで、ひとりですわっていた。ここでも食べものを欲しがらず、他の誰とも遊ぼうとしなかった。ピーターは変わらなかった。ピーターは、小さな子たちのグループで、他の子たちから離れていた。そういうピーターを見ていると、可哀想でしかたがなかった。
夜になると、ボクは床の上でずだ袋に横になった。ボクの足は今もひび割れていて、ずっと歩きっぱなしだったので傷がたくさんあった。その場所はとてもきたなく汚れていたので、ボクはすぐにツツガムシにやられた。ツツガムシはとても小さくて、赤黒い虫。夜眠っているとき、ひびのあるところから皮膚の中に入ってくる。人間の血を吸って太り、まあるく白くなる。そうするとむずがゆくなる。かきむしると、ツツガムシはおしっこをする。一匹取りのけても、次の晩には別のやつがそばの傷口から入り込んでくる。それを取りのけようとすると、傷は広がって、足全体がやられてしまう。
ペニスや肛門にツツガムシがついてしまった子たちもいた。目を向けるのもためらわれた。お医者はツツガムシを取りのけなければならず、ペニスはすごく腫れてしまった。次の日には、別のツツガムシがやわらかな傷から、中に入るのだ。
ボクは小さな川まで行って、足を水の中につけるのがいいと思った。ボクには靴がなく、足じゅうがひび割れていて、ツツガムシはこういう割れている場所や、傷のある皮膚が好きなのだ。自分の足をなめらかに柔らかにしておけば、ツツガムシは皮膚の割れ目を見つけることができなくなる。それでボクは、毎朝、流れのところに行った。水はすごく冷たかったけれど、足を清潔にしなければと思った。少ししてツツガムシは、ボクの足からいなくなった。
毎週、ほんの少しの穀物が配給された。それを粉に挽いて、料理して、二日に一回の食事をした。それで飢え死にすることはなかった。食事のない日は、時を刻むものがなかった。
もっと飢えた子どもたちが、ヌバ山からやってきた。食料の割当てがとても少なくなり、ボクらは何も食べてないのと同じだった。食べたことのないものを食べて、病気になって死んでしまう子たちをボクは見てきた。食べても死なないものだけを、ボクは食べるようにしていた。黒い果物のなる、クニュクという大きな木があった。食べればお腹はいっぱいになったけれど、栄養はなかった。それを食べると便秘になることがあった。この木に登って果物を取ろうとした子たちの中には、手足や首を折ってしまった者も多かった。ミツバチの巣を見つけたりすれば、ボクらは大喜び。蜜を取ろうとして蜂にさされてもお構いなし。ヌバの子たちは、アジャアマーという根っこを教えてくれた。パイナップルみたいな形で、大きさはそれより小さく、中に果汁のようなものがある。サワーミルクのような味で、毒もなかった。ボクらは、パブースと呼ばれているアフリカタケネズミをワナにかけた。リスくらいの大きさの小さな動物で、それを焼いて食べた。
食べものが来ないときは、ボクはパブースを捕まえたけれど、ジョセフがそばにいないと、年長の男の子たちがそれを横取りしようとした。ときどきエチオピアの話を聞いて、ボクらは自分たちがパラタカにいることを悲しんだ。国連はエチオピアにいる子どもたちのことがわかっていて、食料や服を与えているので、みんな太って楽しそうにやっている、と言うのだ。それなのに国連は、パラタカにはやって来なかった。服もなく、ボロきれだけ。パラタカはどこも、生き残り競争みたいだった。
子どもたちの中には、心がこわれてしまって、地面にただすわり、言われなければ何一つしない者たちがいた。その子たちはもう長いことからだを洗うこともしていなかったので、年長の男の子による委員会ができて、どの子も川に行ってからだを洗うよう指導された。それでも聞かない子たちは、川に突っ込まれるはめになった。川の水はすごく冷たかった。割礼をしている子、していない子に分かれていたので、みんな互いをからかいあった。ヌバとボアの子たちは割礼していなかった。ボクらは互いをからかって遊んだ。
大人たちは、生き延びたかったら、働くことが何より大事だと言った。だからボクらは一生懸命働いた。地面に穴を掘り、板でトイレをつくり、ハエがわいてこないように、灰を上にまいた。木を切るために森にやられ、男の子二人で、重い丸太を何キロも歩いて運んだ。指揮官のクオル・マニャンの家をボクらは建てた。大きくなったらどのように仕事したらいいか、大人たちは教えてくれた。
夜ボクらは疲れていたけれど、ナンキン虫のせいで眠ることができなかった。毎朝起きると、ボクらのからだはかまれて膨れた跡がいっぱいで、掻いたせいで血だらけだった。ナンキン虫は黒くて小さく、小さなダニのような虫。親指くらいある大きなダニとは違う。赤いのもいて、どれも脚が六本ある。ボクらはこの虫を殺すこともできない。もし殺せば、建物じゅうにひどい臭いが充満するから。スカンクよりひどい臭いだ。誰かが押しつぶすようなことがあれば、子どもたちが集まってきて、「もうーなんてことしたんだ、ナンキン虫殺しただろう」と言う。
二年目に、学校ができて、白人の女の人が二人、勉強道具を携えてやって来た。ボクらは鉛筆を二つに折り、教科書も二つに分けた。それで全員にいき渡った。 ABCを習いはじめたけれど、千人の子どもに対して、たった六人しか先生がいなかった。よその言葉を習うのは本当に難しい。先生が言葉を教えて、次の日、ボクらがそれを言えなかったら、定規でボクらの手をたたいた。ボクはそのせいで、いつも手を腫らしていた。先生が手をたたいたときから、ボクは何一つ学校で学ぼうとはしなかった。たたかれるのはいやだった。学校でボクはどうしようもなくダメな子だった。もしこれが学校だと言うなら、こんなもの大嫌いだ。
先生たちはボクらには規律が必要だと言った。たとえ雨がものすごく降っていても、外に行けと先生たちは言った。それは体育と呼ばれていて、走ったり行進したりする。服が濡れて、ボクらはびしょびしょになり、ものすごく寒かった。走るのをやめると、チュルタと呼ばれる、人をたたくのが好きな子たちを使った。これが規律とは思えない、罰か何かの仕返しみたいだった。
大人たちはボクらに言った。「わたしたちは長いこと戦いつづけてきた。自分たちはもう若くない。きみらは若い、だからきみらに教育を身につけてほしいし、未来を継ぐ人になってほしいんだ。きみらがこの国をつくり、先頭に立っていくんだ。きみらをたたいたり、何かを強制しようとしたからといって、わたしたちを嫌うな。きみら自身の未来のためにそうしてるんだ、わたしたちのためじゃない。わたしらには未来はないからな」
パラタカでの二年が過ぎ、ボクは九歳、ジョセフは十一歳になった。ある晩ジョセフがボクにこうささやいた。「ここから逃げなくちゃ」
これを聞いてボクの心臓はドキドキしはじめた。これまでに、逃げようとした子たちが打たれているのをたくさん見てきた。
「年長の子たちをグルマレと呼ばれるキャンプに送りこんで、兵士にする訓練をしているんだ」
ボクは何も言わなかった。銃をもちたがる子たちもいたけれど、ボクには恐いことだった。この話が本当のことなのかボクにはわからなかったけれど、大人たちが子どもを前線に送っていると聞いたことはあった。
「トリートに行こう。イエルは兵士だ。郵便局に聞けば、どこにイエルがいるか教えてくれるだろう。イエルならボクらがどうしたらいいかわかると思う」
イエル! スィエト以来、もう二年も会っていない。今、一番年上の兄さんに会えると思うと心がわくわくする。頼りになって、ボクらの世話をしてくれて、どうしたらいいか知っている、年上の家族といっしょにいられるんだ。「イエルならボクらを家に連れていってくれる?」
「それはわからない」
「ピーターはどうする?」
「ピーターはまだ六歳だから、無理だ」
「ピーターをおいてはいけないよ」
「あの子は大丈夫だ。兵士の訓練を受けるには小さすぎる。ここの学校に置いてもらえる。あの子をいっしょに連れていくわけにはいかない」
それでも、ピーターをおいていくのは、納得できなかった。「いつ出発するの?」
「誰にも言うんじゃないぞ」
そうするのがいいのは、ボクも知っていた。数人の子が集まってすわって何か話していれば、それは逃げ出す計画をたてていると思われた。その子たちは罰を受けた。
「でも、いつなの?」
「あとで教える」
日本語訳:だいこくかずえ
2014年4月27日改稿
★このテキストが含まれる原著が翻訳されて本になりました。
「空 か ら 火 の 玉 が ・・・<南スーダンのロストボーイズ 1987 - 2001>」(2014年7月葉っぱの坑夫刊)
著者:ベンソン・デン、アレフォンシオン・デン、ベンジャミン・アジャク、
紹介と結び:ジュディ A・バーンスタイン
翻訳:だいこくかずえ
"They Poured Fire on Us From the Sky: The Story of Three Lost Boys from Sudan " by Benjamin Ajak, Benson Deng, Alephonsian Deng, Judy Bernstein(2006年6月PublicAffairs 刊)より
ウェブサイト:http://www.theypouredfire.com