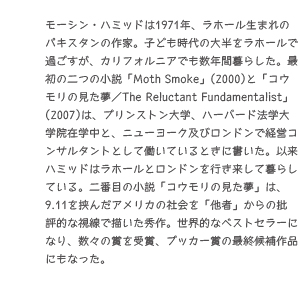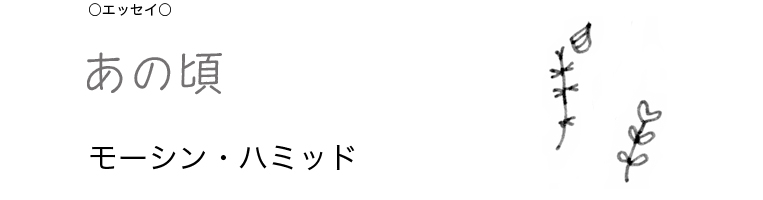
|
ラホールに飛行機が着陸すると、あの頃はまだセキュリティー感覚が薄かったから、親戚や家族の人々が滑走路をうろうろと出迎えにやって来た。ちょうどアメリカは、ロナルド・レーガンが大統領選でジミー・カーターを打ち負かし、ソビエトはアフガニスタン侵攻から一周年を迎え、アライグマの目をしたジアウル・ハク将軍が、パキスタンの独裁者としてイスラマバードに収まったときだった。そしてわたしはウルドゥー語を失った。 自分の母語をなくすというのは、奇妙な感覚だ。わたしは口の早い子で、2歳のときには筋の通った話ができ、ペラペラとよくしゃべっていた。それを証明する傷も残っている。1973年の夏のこと、Z.A.ブットーがパキスタン首相になるための選挙運動をしているときで、わたしはよく食卓の上にのぼって、パキスタンテレビで見た演説の真似ごとをやっていた。「わたくしが首相になった暁には、、、」 ある日誰かがわたしを抱きかかえて、床に下ろそうとした。わたしはサッとその手を逃れて、闇雲に飛び出して落下、頭をぶつけて怪我をし、目に血をしたたらせ、額を何針か縫うはめになった。(Z.A.ブットーの運命も、悲しいかな、似たようなことになった。) 次の年、わたしは両親とともにラホールを離れ、香港経由で太平洋を越えて、サンフランシスコにたどり着いた。カリフォルニアでは、スタンフォード大学キャンパス内にある、ずらずらと同じ建物が並ぶ大学院生用の集合住宅に移り住んだ。子どもたちが群れになって走りまわり、蝶を追いかけ、回っているスプリンクラーの水しぶきの中を駆け抜け、みんな裸足で、大人に見とがめられることもなかった。わたしも家を抜け出してそこに加わった。 母が泣き声を聞きつけて外に出てきた。そしてわたしが、うちの隣りの家の前で泣いているのを見つけた。わたしをからかう子どもたちに囲まれ、困り顔の隣りの家の人を見上げていたのだ。母はわたしの手を取って家に帰ろうとした。 「この子、知恵おくれなの?」 そこにいた子どもの一人が訊いてきた。 「いいえ」 母が答える。 「じゃあ、どうしてちゃんと話せないの?」 「話せるわよ。英語がわからないだけ」 その後1ヶ月間、わたしは口をきかなかった。両親は心配したが、この場所に慣れるのに時間が必要なだけだろう、と考えることにした。二人はわたしをテレビの前にすわらせ、絵を描かせ、積み木で高い塔をつくらせたりした。次にわたしが口を開いたとき、両親を驚かせたのは、それが英語だったから。ちゃんと意味をなす、アメリカなまりの英語だった。 それから6年以上、わたしはウルドゥー語をひとことも話さなかった。友だちをつくり、泊まりがけで遊びに行き、ジャムのビンにオタマジャクシやカエルを持ち帰り、風のごとく走りまわり、サッカーで遊び、大学院生のパーティではその辺の空きベッドで眠りこけた。国立公園でテントを張ってキャンプをし、マリファナ臭いボブ・マーリーの野外コンサートで、この変な臭いは何かと訊いたり、冷たい太平洋で泳いだり、モカシンの靴をはいてビーズ飾りのチョッキを着たり、最初の小説を書いたりした。それはスターウォーズやスタートレック、宇宙空母ギャラクティカ、キャプテン・ロジャース、宇宙怪人ゴースト、スターブレザーズ、惑星戦争といった、当時のSF映画やドラマに影響された、銀河系宇宙を舞台にしたSF小説だった。 そんななか、父は博士号を取り、母は創成期だったシリコンバレーの電子機器会社で経理として働き、妹が生まれ、うちのポンコツ中古ダットサンのメーターは何千キロにも達した。 あれだけウルドゥー語をよく話したわたしが、パキスタンに戻ったとき、どうしてここまですっかり忘れてしまったのか、両親にはまったく理解できなかった。 わたしは、見知らぬ新しい(また昔のでもある)世界に放りこまれた。叔母たち、叔父たち、20人を超えるいとこたちといった大所帯の親戚、クリケット、妙な味のパン、さらにもっと変な味のミルク、チャンネルが一つしかないテレビ(しかも一日の何時間しかやってない)、知っている商品ブランドはどこにもない。ここラホールには、フロステド・フレークスも、トゥインキーも、スレクイックも、トラッパー・キーパーも、ナーフボールも、バクティンも、ノーモア・ティアーズのシャンプーもないのだ。 パキスタンでの初日、わたしはいとこの一人に訊いた。「この人たち奴隷なの?」 「違うよ。使用人だよ」 そういとこは説明した。 カリフォルニアの友だちに手紙を書きたいとずっと思っていたのに、できなかった。どう書いたらいいんだ? 何ヶ月かたって、もう手遅れだと思った。ある夜、星を見上げてこう思った。この星はあっちでみんなが見ている星と同じなんだ。そうしたら泣けてきた。そのとき一回だけのこと。お涙頂戴みたいな話だけど。でもそれで終わった。 いや、終わってなかったかも。でも弱まったことは確か。それにわたしはこちらで友だちをつくったし、新しいスポーツに挑戦もし、街を自転車で走りまわり、飛行機のプラモデルを売ってるところを見つけ、アクアリウムと熱帯魚を売ってる店を見つけ、そして打ち身をいくつかつくった後でわかったこともあった。いとこたちは兄弟みたいなものなんだ、一クラス分くらいの親戚はいつでもおしゃべりしたり一緒に遊ぶ用意ができていて、外の世界からわたしを守るためにいかなる時もやってくる、ということが。 わたしは自分の新しい居場所が好きになったけれど、同時に以前の場所も好きなことには変わりなかった。そして二つが一つになる場所というものを想像した。わたしは地図マニアで、10歳の誕生日に両親は精緻な地図帳を買ってくれた。鉛筆を手に、わたしは新しい国々を地図に書きこんでいった。実在しない太平洋の島々、そこには雪帽子をかぶった火山があって、きっちり等高線も入れた。フランスのアルプマリティム県は独立共和国(形が好きだった)になり、インドのカティアワル半島は深い運河で本土と切り離された。そして中くらい規模の同盟を結ぶ都市国家が、あちこちの大陸にばらまかれている。 これらの場所について、わたしは年鑑のような項目を書き入れていた。歴史だとか、天然資源だとか、気候、軍隊、動植物について。さらに重要事項として、その土地の人口を入れた。どこも人種や民族が混ざりあっていて、目立った支配民族はなく、ラホール人とサンフランシスコ人の移民系の存在が際立っていた。 これは当初、パキスタンへの帰国によって引き出された創作だった。(トルーキンの中の詩やギリシア・ローマ神話を手本にした詩もいくつかあった。「処女とは何のことかおまえは知ってるのか?」と父がそれを読んで訊いてきた。「乙女みたいなもの?」とわたしは答えたものだ。) ラホールでは親戚たちや同級生が英語を話したので、今回は黙りこむ必要がなかった。わたしはウルドゥー語を行く先々で拾い集めた。結果、ちょっとした冗談や歌を歌ったりできるようになったし、ふざけたり、けんかしたり、物語を読んだり、試験を受けたりもした。わたしは外国人風にではなく話すことができた。それでも以降、わたしの第一言語は、第二言語となっていった。 英語の方も、カリフォルニア風とパキスタン風が混じり合って、壊れていた。(後に大人になってからは、アメリカの中部大西洋地域風、イギリス英語がそれに加わった。) 2回の太平洋横断を経験した9歳の子にとって、耳にした言葉が予期しない方向へと自分を連れていくこともあった。晴天の午後の日々のぼんやりした思い出のように、記憶にはっきりとどまることもないから、人に言うこともできないもの。 思えば、こうやってものを書いているのも、いくらかはこういった体験のせいかもしれない。 初出:Observer、2011年
|
||||