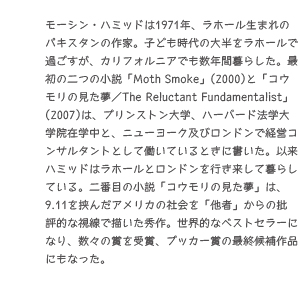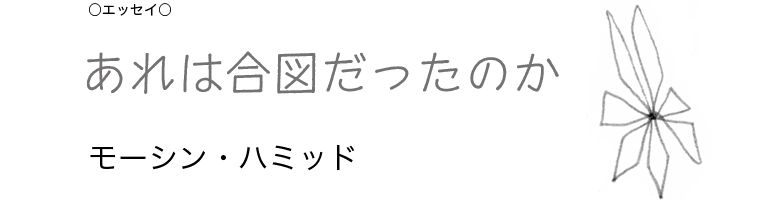
|
8月14日はパキスタンの独立記念日。今年はわたしたちの娘、ダイナが生まれた日でもある。(どっちに転ぶかという日だった。19時間遅ければ、ダイナはインドの独立記念日に生まれることになったのだから。小説家にとって、これが象徴するものはある種の巧妙な仕掛けみたいだった。ダイナがぐずぐずすることなく生まれてきたのは幸いだった。) 出産はわたしの妻に対する見方を変えた。今や妻は、流血の特別部隊の戦士であり、家族のために闘い、命をかけていた。わたしは彼女の偉業を誉め讃え、帰宅を祝い、回復を助ける役目を負った、配偶者支援隊といったところだった。だからわたしは、2、3時間しかるべき間をおいてから、ここを離れて何千キロ遠くの街へ、大陸を超えてあちらに帰ろうと提案したのだ。 もし僕らが宇宙からの合図を待っているとしたら、今がそのときだよ、僕らの故郷ラホールに帰るときだよ、そうわたしは言った。ダイナの誕生こそがその合図だった。 ザーラは病院のベッドの上でわたしをじっと見つめた。彼女は自分たちがそんな合図を待っているとは、思いもしなかったと言った。1ヶ月くらいたってから話しましょう、そう言う彼女の提案にわたしは素直に同意した。 その間、わたしはいろいろ考える時間を与えられた。ロンドンはわたしにとって住むのにいい場所だった。30歳の誕生日のすぐ後、1年間の滞在の予定で、ニューヨークからこの地にやってきた。そして8年たった今も、ここに住んでいる。妻に出会ったのもロンドンだった(正確に言うと、西ロンドンのお屋敷町マイダヴェイルでのパーティで)。わたしは2番目の小説をロンドンで書いて、出版した。最初の子どももロンドンで授かった。ロンドンはわたしに、友だちや家族、そして(20年の副業作家の後に)書くことで生きていく才を与えてくれた。 ブッシュ時代のアメリカからの自主的亡命者たちがそうであるように、わたしはロンドンから、自分が最初にニューヨークに魅せられたときのような自由さを感じていた。9.11以降のアメリカは、その自由を被害妄想の日々の間にすっかり失ったように見えた。ヒースロー空港の入管は、JFK空港より通過するのが楽に感じられた。ロンドンの新聞各紙は、反対意見に対してそれなりに開かれており、愛国的な自己検閲に対する抵抗力も、アメリカの新聞よりずっとあった。またバッキンガム宮殿の地での市民権獲得の過程は、意外なことに、自由の女神の地よりずっと簡潔なものだった。 もちろんイギリスにも問題はある。人種間の摩擦はその一つ。わたしと同様、アメリカからやって来たパキスタン人の友だちは、こう指摘していた。「あのさ、ここでは僕らはアフリカ系アメリカ人なんだよ」 もうひとつは制度化された貴族社会への奇妙な支援。そこには(わたしの目からは)、君主制のような関係事象や、「非定住」金持ち住民への不公平な恩恵がある税制、金融業界に隷属した経済モデル(業界関係者が公的に生まれた保険金からの利益を私物化している)、といったものが含まれる。 しかしながら全体としては、イギリスはわたしが成功を手にした居場所であり、ロンドンは素晴らしく、なんとも面白みのある街だった。 そうであっても、わたしの心はしぶとくパキスタンから離れることがなかった。昨夏ロンドンのローズ・クリケット・グラウンドで行なわれたワールド・トゥウェンティ20決勝(パキスタンがスリランカに勝って優勝)には、わたしはグリーンのウィグを付けて行ったものだ。それに留学のため18歳でラホールを離れはしたが、生まれた街がわたしの心から消えることはなかった。ラホールにはたびたび行っていた。毎年2、3ヶ月の滞在をしていたし、10年に2、3回は1年に及ぶ長期滞在もしていた。 それにわたしは、ニュース番組でのパキスタンの悪役ぶりを全く信じていなかった。わたしの知っているパキスタンは、それとは違うパキスタン、メイクも付け牙もないパキスタン。すり切れた靴をはいて、家族みんな仲がよく、心から笑いあえるそんな役回りのパキスタンだった。 もちろん、今、国にとって大変な時期ではある。ラホールの友人たちは、ベスランで起きたテロリストによる学校占拠事件のような残虐行為が恐くて、3週間も子どもを学校にやっていないと言っている。わたしの姉が教えている大学は、飛散防止フィルムを窓に張って備えていた。アフガニスタンとの国境地帯にあるワジリスタンで先月、軍が軍事行動を開始してからは、パキスタンのあちこちの街が攻撃されて、数百人が死んでいる。 それでも希望がもてそうな要因はある。宗教的過激派を支援してきた長い歴史を経て、政府も軍もやっとこの事態に本気で取り組むようになっているのではないか。アフガニスタン国境付近のスワートはこの夏、タリバンの支配から奪還された。ワジリスタンの攻撃も順調だと聞いている。パキスタンの世論は、過激派に対する反感が増しているし、増大する独立系メディアや司法は、貧困層へ資産の再配分という予てからの要求を拡大させる力となっている。現在の不安定さや流血事象から脱出して、もっと公平で懐の深いパキスタンが生まれることは不可能ではないと思う。 というわけで、ダイナの誕生後1ヶ月して、妻のザーラとわたしは再びパキスタン行きを話し合い、戻ることを決めた。天性とも言えるここまでのあちこち歩きまわるわたしの人生からすれば、今後どれくらいパキスタンにいるかはわからない。1年かもしれないし、10年、あるいはずっとかもしれない。 でもわかっていることはある。パキスタンがどっちに進むか考えるときが来たなら、わたしたちは自分の意志を身をもって示すということだ。 「コウモリの見た夢」武田ランダムハウスジャパン (2011/6/23)
Reprinted by permission of William Morris Endeavor Entertainment, LLC on behalf of the Author through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
|
||||