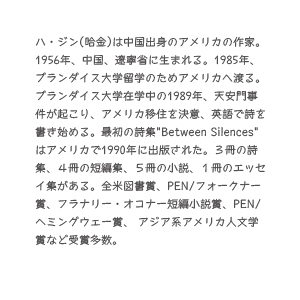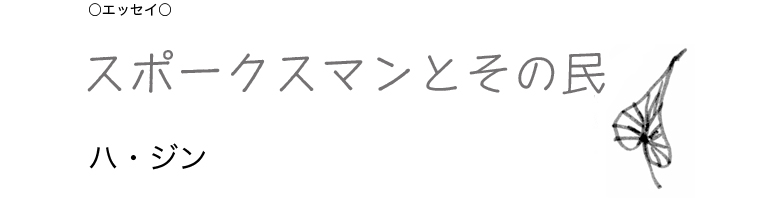
|
こういった疑問へのわたしの答えは、当初、きわめて単純なものでした。最初の詩集「Between Silences」の前書きで、こうわたしは書きました。「わたしは運に恵まれた者として、運に恵まれなかった人々のために口を開く。それは苦しみに耐え、我慢を重ね、どん底の中で死に絶えた人たちであり、歴史をつくってきた人々でありながら、その歴史にだまされ、葬られた人たちだ」 わたしは自分のことを、虐げられた中国人の代理となって、英語で作品を書こうとする作家であると見なしていました。わたしは自分がもくろんだこの立ち場が、いかに複雑で実行不可能なものであるかということに気づいていなかったのです。とりわけわたしのような状況にいる者にとって難しいということが。実際のところ、過ぎた誠実さというのは危険なものです。それは人の脳を過熱させます。 概して、発展途上の国からやって来た作家たちは、自分を社会的役割という観点から見ようとする傾向があります。その理由のひとつは、自分が物質的に豊かな西洋に来ていることへのやましさであり、もうひとつは自国で受けた教育のためで、そこでは普通、個人よりも集団や共同体の方が尊ばれているからです。実際、「個人主義」という言葉は、中国語では、今も否定的な響きをもっています。作品を書き始めたころ、わたしは中国へ帰りたいという思いをもっていました。アメリカに自分がいることを、単なる滞在であると見なしていたので、自分が不運な中国の人々の代弁者か何かであると思うことは、自然なことだったかもしれません。そんな言い分には何の根拠もないとは、思いもしなかったのです。どんなときも、国というのは作家に対して非難を浴びせたり、自国の民に向けてなされた不正や裏切り、その他の悪事で告発することができます。作家が救おうとしている人々自らが、疑問を投げかけてくることだってあるでしょう。「誰がおまえに、我々の代弁者となる権利を与えたのだ」と。難問をふっかける人もいるかもしれません。「一緒に耐えたこともないくせに、我々の苦境を自分の利益のためにただ利用してるだけじゃないのか。おまえは自分の国や同胞を国外に売ってるだけだ」 作家を尋問するこれらの人々が、ホメロスはその偉業を讃えるために、ギリシア兵たちとともにトロイアまで行く必要はなかった、という自明の理に気づくことはまずないでしょう。とは言え、ホメロスは偉大な詩人です。それに対して我々は何者でしょうか。わたしたち作家を志す者は、自分の書く行為を正当化してはいないだろうか、と思い悩むことがあります。作家としての才能さえあれば、人々の代弁者であることが正当化されるでしょうか。論理的な話としては、才能があれば資格はある、と言えるでしょう。なぜなら多くの集団的体験や個人の物語は、芸術に変換され保存されないかぎり、意味を保ち続けることができないからです。しかしながらこの世界は、作家の才能をくじいたり、もみ消したり、まるで画策されているみたいに、全く別の論理で動いています。 代弁者を名乗るための最高の資格は何かと言えば、母国ですでに認められた作家としての発言権を有していることです。海外に渡る前に、すでに母国で読者を持っているということです。この地位を元にして、作家は外国で再び書き始めることができます。違う読者に向けて、違う内容を書くことになるかもしれませんが。これは有利な基礎財産にはなりますが、他の基礎財産同様、永遠に保持することはできません。そういう作家は、期間限定の文学大使のようなもので、いつか他の者に席を譲ることになります。 亡命した多くの重要な作家たちが、自身を母国の代弁者であると見なしていたことは理にかなっています。なぜならそのように考えることは、作家としての役割を取り戻すのに好都合だからです。典型的な例が、ロシアの小説家アレクサンドル・ソルジェニーツィンと中国の作家リン・ユータン(林語堂)です。両者とも亡命者であり、自らを母国の代弁者と見ていました。二人のものの見方は、郷愁と、長期に渡るアメリカ暮らしの後にまた、母国の人々と共にありたいという強い気持ちによって形づくられたものです。 ソルジェニーツィンは虚偽の反逆罪によってソビエト市民権を剥奪されました。1973年12月、パリの出版社が「収容所群島」の第一巻を刊行、ソルジェニーツィンは1974年2月、ロシアから追放されました。自信に満ちあふれ、道徳的信念の強い人間でありましたが、彼にとってどこか別の場所で生きることも、国外の読者にむかって書くことも想像を超えたものだったので、この追放にはいたく動揺しました。ソルジェニーツィンはスペインの記者からの取材に対して、こう言っています。「西洋の作家になろうなどと、考えたこともありませんでした。。。意志に反して、わたしは西洋社会にやって来たのです。わたしは母国のためだけに書きます」 またスイスの報道記者に対して、このように嘆いています。「わたしはスイスに住んでいるのではありません。。。わたしはロシアに住んでいます。わたしの興味、わたしの気にかけていること、そのすべてはロシアにあります」 2年間ヨーロッパで過ごした後、1976年の夏に、ソルジェニーツィンと家族はアメリカに渡りました。ヴァーモント州ブラックリバーの谷間の村、キャヴェンディッシュの外れに引きこもりました。ソルジェニーツィンは、ニューイングランド地方の寒い気候、ピリッと冷たい空気、自然林に愛着をもっていたと言われていますが、それはその全てがロシアを思い起こさせるからでした。 去年の夏、わたしはたまたまヴァーモントへ行くことになりました。その帰り道、マサチューセッツへの途上、ソルジェニーツィンの家を見てみようとキャヴェンディッシュに車を向けました。驚いたことに、鉄柵に囲まれた50エーカーの地所には、今もソルジェニーツィンの親族の人が住んでいるのでした。鉄の門は閉め切られ、インターフォンと電子監視機に制御されていました。そばの木に看板がありました。「私有地につき、侵入禁止」 住居へ続く小道も、こんもりと木に囲まれた車庫へ通じる道も舗装されていませんでした。小山の上にある二階建ての木造の住居は、風雨にさらされて傷んでいるようで、家のまわりの木や草は伸び放題の見映えでした。家のある小山の下には、深い溝をブクブクと音をたてて水が流れ、軍事的観点から、外の世界からの防御ができていました。キャヴェンディッシュに居てもなお、ソルジェニーツィン家の人々が時折、殺害の脅しを受けていたことは知られています。鉄柵の向こうにあるすべてが、ここの住人には永住する気持ちがなかったこと、極度に安全への注意を払っていたこと、意図して外界からも近隣からも自らを隔絶させていたことを表しているように見えました。その一方で、キャヴェンディッシュの食料雑貨店の中年の女店主は、作家の家までの正確な行き方を教えてくれ、ソルジェニーツィンを「アレクサンドル」と親しみを込めて呼んでいました。ソルジェニーツィンの住居の印象は、生まれ故郷にいつも帰ろうとしていたという彼の声明と一致していました。 ソルジェニーツィンと妻、3人の息子はこの場所に18年住んだ後、1994年3月、ついにロシアへと帰ることができました。ロシアの市民権を取り戻し、反逆罪の告訴も取り下げられ、ロシアで彼の本が出版されることになったのです。この作家が朝の8時から夜の10時まで、1日に12時間、14時間と、週に7日間、書き続けた場所はここでした。ここで、最高傑作と言われる「The Red Wheel」シリーズを中心とする、多くの著作を生み出したのです。ソルジェニーツィンは「わたしは母国のためだけに書く」と主張し、母語で作品を書いていたにもかかわらず、長い年月に渡って、ロシアの人々に直接語りかけることはできませんでした。ソルジェニーツィンは翻訳を通して、西洋の読者に向けて書くしかなかったのです。ここでも作家は、ソビエトの歴史の裏側を暴露する任務を自分に与え、人間性の破壊についての証言をし、声をもたないロシアの人々の記憶を守ろうとしました。このときのものの見方が、文学的意味から歴史的な意味へと、後の作品を方向づけました。ヴァーモントで書いた本が皆、亡命前に書いていた小説より文学性が低いことがわかります。たとえば、彼の初期の小説「イワン・デニーソヴィチの一日」「煉獄のなかで」「ガン病棟」を見れば、それが非情に卓越した作品であることがわかります。これら初期の写実主義的な作品に対して、古くさくて堅苦しく、退屈で、それに有名すぎると思う人もいるでしょうが、どの作品も時代を超えた作品としての自律性を保っています。こういう作品は受け継がれます。それに比べると、後期の作品群は芸術としてのしっかりとした規範がなく、作品の妥当性は、歴史観の転換によって浸食を受けてしまう可能性があります。 1994年3月にロシアに発つ前、ソルジェニーツィンはめったに足を向けたことのないキャヴェンディッシュの村に出向き、200人を超える村人の前でお別れを言いました。感謝の念を表してこんな風に言ったのです。「亡命生活というのは困難なものです。故郷に帰る日を待ちわびて暮らしましたが、ここヴァーモントのキャヴェンディッシュの他には、そうやって暮らせる場所は思い浮かびませんでした」 明らかに、彼にとってのアメリカでの18年間は、暮らすというより待機の日々でした。その間、ペンをもってソビエト政権と闘い、それを打ち倒す触媒の役割を演じたのです。 とはいえ、ソルジェニーツィンは、現在のロシアが、自分が離れたときのものとは大きく異なっていることを敏感に察知していました。ロシアはゴルバチョフのペレストロイカを通して、西欧の民主主義の影響や資本主義の浸食を受けやすくなっていました。文学作品が母国で広く受け入れられてはいましたが、帰国に対しては用心深く、躊躇がありました。ボリス・エリツィンからの「国外ではなく、ロシア国内でロシア国民のために仕事をしませんか」という誘いがあってから、ヴァーモントを引き払うまでに2年の月日を要しました。ソルジェニーツィンは故郷で死ぬために帰るのであって、戻ってそこで長く生きて過ごすつもりはありませんでした。しかしながら、ソルジェニーツィンの帰国はまさしく英雄的、奇跡的なものとなり、文学史において数少ない追放された巨匠の母国への帰還となったのです。あらゆる点で、彼の帰国はオデッセイの再現でした。 ただ、オデッセウスが家に戻り、都市国家で王位を取り戻したのとは違い、ソルジェニーツィンは母国で苦難の時期を過ごしました。この作家のキリスト教正統派的で愛国的なものの見方は、人々の関心を引かず、同様に政治的な著書「Russia in Collapse 」(1998)、「Two Hundred Years Together」 (2001)も冷淡にあしらわれ、時代遅れの今のロシアの現実に即さない作家であると見なされました。ソルジェニーツィンのラジオトーク番組は、人気の低さのせいで放送がなくなり、かつては抑圧されたロシア国民にとっての、西洋社会からの強力な代弁者であり、ソビエト政権への熱烈な批判者であったソルジェニーツィンも、発言力を失い、ロシア社会で意味ある役割を演じることはもう不可能に見えました。その昔キャリアとその職務で幅を利かせていた外交官が、退職したときのように。ところがソルジェニーツィンはソルジェニーツィンでした。天才が天才であるように。2006年1月末、国営放送がソルジェニーツィンの小説「煉獄のなかで」をドラマ化した10回シリーズを放映しました。番組はロシアのテレビで最も視聴率の高い作品のひとつになりました。ソルジェニーツィンは現在87歳(訳注)、その脚本を書き、一節を朗々と読み上げたりもしています。一説によると、編集された番組を見て、この作家は涙ぐんだそうです。 ソルジェニーツィンが母国に戻って10年の時を経て、作家はついにロシアに帰ってきたのだ、やっとロシアの人々から受け入れられたのだ、と言えるようになったのです。とはいえ、この帰国は主として文学を通じて可能なことだったということを、わたしたちは覚えておく必要があるでしょう。確かに、今日のロシアの政治状況によって、彼の文学作品は、国家のあり方や文化的遺産の刷新に手を貸すことを許されましたが、もし真に意味ある文学作品を書かなかったなら、ロシア国民の心に再び到達することはできなかったと思われます。「煉獄の中で」と同様、「巨匠とマルガリータ」「金の子牛」「ドクトル・ジバゴ」などソビエト時代の名作を脚本化したものがテレビで放映されました。このことは、ロシア国民に歓迎されて帰還を果たすために、作家自身がロシアの土を踏む必要がなかったことを証明しています。ソルジェニーツィンが母国に帰ることがなかったとしても、彼の作品は母国の人々のところに届く道を見つけていたと思われます。 ソルジェニーツィンの帰国が英雄的で輝かしいものだったからといって、亡命の日々の辛さや苦しみを軽く見ることはできません。1985年6月24日、キャヴェンディッシュから北に30kmほど行ったところにある町、ヴァーモント州ラトランドの裁判所で、裁判所員と三列に並んだ報道記者、カメラマンが、アレキサンドル・ソルジェニーツィンがアメリカ市民権の宣誓をするために現われるのを待っていました。妻のナタリヤ・ソルジェニーツィンと息子のヤーモライはすでに来ていて、皆がソルジェニーツィンの到着を待っていました。しかし作家は結局現われなかったのです。ソルジェニーツィン夫人は、「夫は具合がよくないので来られなかった」と説明しましたが、一家と仲のいい友人はソルジェニーツィンはどこも悪いところはない、元気だ、と明らかにしています。その1ヶ月前、一家はアメリカ市民権の申請をし、6月24日にはそのためのお祝いの式典が準備されていました。その日、ソルジェニーツィン夫人は、アメリカ市民権証書を一人で受けとりました。そして三人の息子のために自分は帰化の申請をし、こうしてアメリカ市民になったと記者たちに述べました。 明らかに、ソルジェニーツィンは最後の瞬間に心変わりし、祝典に出向くことができなかったのです。ではなぜ、最初のところで市民権を申請しようとしたのでしょうか。一家のことをよく知ると思われるジョセフ・ピアスは、次のように説明しています。
どんな人にも認められているように、ソルジェニーツィンも信念を変えたり、必要があれば母国を捨て去る権利を有していました。それでも、名声や社会的役割をもった作家として、よその国の市民となるわけにいかなかったのです。もし彼がアメリカ市民となっていたら、ロシアへの帰国はもっと複雑で面倒なものになっていたことでしょう。彼に敵対する者たち(普通のロシア国民であっても)は、アメリカ人として彼を扱ったでしょうし、作家のロシアへの忠誠心を疑ったかもしれません。(2) 彼の中で核となる価値であった、ロシア国民であることの必要性を言い続けながら、アメリカ人となって帰国すれば、彼の信頼はおとしめられていたことでしょう。幸いにして、ソルジェニーツィンは冷静に考えることができたので、市民権取得の祝典に行くことをしませんでした。 ソルジェニーツィンが選んだ道についてのエピソードは、彼が自分の国の人々との関係に心を砕いていたにも関わらず、この作家の役割が違うものに変わってしまってもおかしくなかったことを表しています。偶然の出来事やときに避けがたいことが起きて、築いたものは簡単に土台を失い、大幅な変更を余儀なくされることもあり得ました。ソルジェニーツィンが企てた帰化についてここで書くことで、この偉大な人物が陥りそうになった愚行を指摘しようとしているのではありません。言おうとしているのは、この作家が、自分の民の代弁者であろうとするときの、そのアイデンティティの危うさです。 わたしは心から、ソルジェニーツィンの勇敢さや自分の作品が孤独な状況におかれていることを受け入れる姿勢に動かされています。「わたしの人生はたった一つのことから成り立っています。それは作品です」 ソルジェニーツィンはこう言ったことがありました。伝記を書いたD.M.トーマスによれば、キャヴェンディッシュの村には当時、ひとりの医者さえいなかったそうで、座骨神経痛を患う、年老いたソルジェニーツィンは、ものを書くとき演台の前に立って過ごしたと聞きます。作家をここまで粘り強くさせていたのは、わたしの考えでは、単なる作品への献身ではなく、キリスト教への信心があったからだと思います。それにより、この世の生を超えた連続的な生というものを信じていたのです。来世の存在を信じることは、この世を恐れなく生きることを可能にします。ロシアへの帰国の前のインタビューで、ソルジェニーツィンは死を恐れるかと訊かれて、満面笑みを浮かべてこう答えました。「全くありませんよ! 死というのは、のどかで平和な転移なんです。クリスチャンのわたしは、死の後にまた生があると信じています。ここでの死が終わりとは思ってないんです。魂は続きます。魂は生き続けます。死は単なる段階に過ぎません。それは解放だ、という人もいます。いずれにしても、わたしは死への恐れをもっていません」 また別の文章の中でこうも言っています。「人間の到達目標は幸福にはない。精神の成長にこそある」 この発言には、ソルジェニーツィンが亡命生活の中で作品を書き続けてきた、精神の強さがよく表れています。 彼の言葉から、2001年の夏にあった、ウィスコンシン州のリヴァー・フォールズでの中国人詩人グループの集まりに思いが飛びます。詩人たちの中に昔の同級生が一人いました。その人は集まりのあった中西部の小さな町をとても称賛していました。それは気候や風景が、わたしたちの出身地である中国の北東部を思い出させるからでした。わたしは彼に訊いてみました。「もし許されるなら、この町に一人で住んでみてはどうだろう。詩作に集中できると思うけれど」 友人は答えました。「友だちがひとりはいなくちゃな」 典型的な中国人の答えでした。中国人というのは、人の暖かみなしには生きていけないのです。このことは、なぜ北米にいる中国人亡命者は孤立して生きることが少ないのか、なぜ都市生活者が多いのかを説明しています。社交好きというのは表面的なことに過ぎず、その奥底にあるのは、生というものを違った側面から見ることを促す、宗教や信仰の欠如だと思われます。 作家のリン・ユータン(林語堂、1895—1976)は小説「My Country and My People」 (1935)の中で、中国人の生き方の理想について長々と論じています。中国人にとって、理想の人生の本質はこの世での楽しみだと指摘しています。来世の存在を信じないため、現世に深い執着をもち、それをなんとか最高のものにしようとするのです。そのせいで、彼らは死と、寂しさの元となる孤立を恐れます。中国人の人生の理想は、「素晴らしく単純」で、「この世の幸せに心を傾ける」ことにある、とリン・ユータンは言います。中国文化に大きな影響を与えた孔子は、死について問われてこう答えたことがあります。「人生が何か私にはよくわからない。その私が死について何を知ろうか」 この世の楽しみを取り逃すことを恐れ、最低の人生であっても最高の死よりはずっとまし、と思っている中国人の現世についての考えをよく表しています。小説家ユー・ホア(余華)も、映画化された「活きる/To Live」(1993年)の中で雄弁に語っている主題です。 幸運であったソルジェニーツィンとは違い、異境に暮らすリン・ユータンは母国に二度と帰ることが叶いませんでした。30年に渡ってアメリカに住みましたが、彼もまたアメリカ市民となることを拒みました。(3) リン・ユータンは博学で、切れのいい機知に溢れ、現実的な視野をもった人物で、自分を文化大使と見なしていました。ハーバード大学で学士号(1922年)を、ライプツィヒ大学で博士号(1923年)を取得するより前に、中国語辞書における前途有望な学者として、中国で知られるようになっていました。また清華大学で教鞭をとってもいました。リン・ユータンの生き方は、作家の役割というものが、代弁者としてであれ背徳者としてであれ、国の内外の政治によっていかに形づくられるか、歪められるか、を実証していました。最初の英語による本「My Country and My People」(1935年)は、彼がまだ中国にいるときに書かれたものです。友人であったパール・バックの励ましを受け、出版の手助けもしてもらいました。本はアメリカでベストセラーになりました。1年後の1936年、41歳のとき、リン・ユータンは英語での執筆に専念するためにアメリカに移住します。1937年末に出版予定だった最も著名な本「The Importance of Living」を書いていたとき、盧溝橋事件が起こり、中国抗日戦争(日中戦争)が勃発しました。母国の苦闘を支えるため、リンはニューヨーク・タイムス、ニュー・リパブリック、ネイション、アトランティックに、中国を併合しようとする日本を糾弾する記事を掲載し、アメリカ国民に中国の大義を支持するよう促しました。また「My Country and My People」の最終章を、13版の印刷を前に大幅に書き換え、日本の侵略に抵抗する中国人の団結と闘いをより際立つようにしました。 当時、アメリカ在住の中国官僚たちはアメリカの公共メディアとの関係が、ほとんどありませんでした。それでリン・ユータンは文字通り、中国のスポークスマン(代弁者)となったのです。彼の公的な役割は、1944年に半年間中国を訪れた際、蒋介石とその夫人に少なくとも六回は迎えられたことによって、人々の知るところとなりました。国民党政府はリン・ユータンのメディアでのプロパガンダ(それはアメリカから公的支援を得る手助けとなりました)に感謝していましたが、彼の断固とした反共主義的な視点も気に入っていたのです。 リン・ユータンのような作家にとって、母国が戦いの最中にあるときに、そこから距離をおいていることは愚かで自分勝手な態度だったかもしれません。しかしながら、自身を文化大使とみなす視点は、多かれ少なかれ、作家の人間性やさらには作品の質をも決定づけました。「わたしの優位性は、中国文化について外国人に話したり、中国人に外国の文化について話したりできるところにあります」と認めてもいました。リン・ユータンは生涯に60冊を超える本を出版しました。英語で書いたものだけでも、40冊に及ぶ著作があり、七つの小説を除いて後はすべてノンフィクションでした。ノンフィクションの中には、長短含めた個人的なエッセイ、古代中国の偉人の評伝、老子や孔子など古代中国の本の翻訳、中国芸術理論集、中国の出版史、中国古典名作「紅楼夢」の参考図書目録、政治論文、講演録などがありました。明らかに多面体の人でありましたが、そのエネルギーは拡散しがちで、五十代を迎えた1940年代末には作家としての経歴はかなり低下しており、中国への帰国を考えていました。しかしその帰国は、1949年の共産党の支配で、不可能なものとなったのです。 リン・ユータンは学識ある文学の学者であり、文学の論理と本質を理解していました。英語で書かれた最初の本の序章でこう述べています。
しかしながら、リン・ユータンは中国について書き続けていく中で、類似性の原理から逸脱していきました。彼のその不注意さは、自国の文化を西洋の読者に通訳する者として自身を見る、その見方と関係していました。この作家は、英語で書いたエッセイの目覚ましい成果に満足していませんでした。文学における序列を理解もしていて、このように書いています。「わたしの野心は、書いた小説のすべてが時を経て生き長らえることです」 リン・ユータンは文学がもっている序列(私的なエッセイはマイナーなジャンルであり、最下層に属するという)を認知しながらも、創作に力を入れることをまったくしませんでした。中でも、年に一冊の本を書くことも多かった晩年において、経済的な理由がない限り、はっきりとした文学的使命をもって書くことはなかったのです。書いた小説の中で、リンは「Moment in Peking(北京好日)」(1939)を最も誇りに思っていました。それは一年で書き上げた長大な小説で、「紅楼夢」の様式を手本にしていました。「Chinatown Family」を除く他の小説の運命と同じく、英語版では長い間この本は絶版になっていましたが、翻訳された中国語版では読み継がれ、中でも離散中国人によく読まれていました。この小説には大きな野望と広大な意図があったにもかかわらず、マイナーな作品と見なされ、また本質的な弱さも備えていました。最も特徴的なのは、この小説家が細部への目をもたないことでした。そのことが小説家として王道を行くことを阻んでいました。実際のところ、小説には宝石や服、家具や庭、食べものなどたくさんの細部が描かれてはいましたが、それは作家が知る他の本から喚起されたもののように見え、著者自身の観察眼や想像力から生まれたものではないように感じられました。別の言い方をすれば、それは机上の、模倣の細部であって、登場人物の心理やそこにある日常の感触を表してはいませんでした。結果、文章はものごとの表面をなでるだけにとどまり、身体的な知覚を刺激するだけの充分な手触りをもてませんでした。 リン・ユータンが、中国の文化的代弁者として自分を見る見方に起因する弱さが、他に二つあります。一つは、語り手があまりに露骨な形で、中国文化を西洋の読者に差し出していることです。中国の女性の教育や中国の薬、結婚における五つの要素の調和といった中国人の心得などが、ミニエッセイのように書かれた部分がいくつかあります。これらの文節は印象的な文脈をつくることなく、語りの流れをとめてしまい、結果、全体として荒削りで未完成な印象を与えています。この荒削りな感じは、単に技術上の問題にあるのではありません。この小説家の不十分なものの見方を露呈しているのです。作品の書き手が単なる仲介者ではなく、文化の創造者となることを目指すべきであるのと同様、偉大な小説もただ文化を提示するのではなく、文化をつくるものなのです。そういう作品はこの世界で起きたことをただ伝えるのではなく、読者の共感を呼び起こし、読む人に自身の存在のあり方について考えさせるものなのです。もし一つの小説が野心ある著者の浮き沈みを左右するなら、作家はその本に含めるどのような文化的な指令で、それを達成するか考えるべきでしょう。リン・ユータンは明らかにそのような視点はもっておらず、中国を説明することに終始しています。「Moment in Peking(北京好日)」では全編を通じて、語り口調に、この本が西洋の読者のためだけに書かれたことが表われています。 この作家の「スポークスマン精神」に関するもう一つの弱さとは、国が戦争や政変でぼろぼろになり、人々の暮らしが不安定で崩壊しかかっている時期の現代中国の暮らしについて、無害な説明しかしていないことです。80を超える膨大な登場人物の中に、一人の悪者もおらず、それは人間の生活ではまずあり得ないことです。確かに、著者は儒教や人間の善良性を信じていたのだと思いますが、このような甘すぎる物語は、通俗小説のように作品を味の薄いものにしてしまいます。 「Moment in Peking」の翻訳版は、今でも中国人の間で読まれています。その主な理由は、三つの家族の物語を通して、現代中国の全景を描こうとした作品だからです。似たような理由で、アメリカ移住者の体験を描いた「Chinatown Family」も、ラトガーズ大学出版によって、再び印刷出版されています。作家にとってはこの作品は重要なものではありませんが、アメリカ移住者の体験であるという理由で、今もアメリカで読まれているのです。英語で書かれた本のうち、この小説とノンフィクションの代表作「The Importance of Living」のみが、英語での出版物として今も続いています。このことは、本の生命を決めるのは、どんな言語で書かれたかではなく、テーマと内容であることを示しています。 リン・ユータンは七十代のとき、5年の歳月をかけて(1967年から1972年)、大部の「現代的用法による中国語英語辞典」を編纂しており、それが自身の文学上の経歴の頂点であると信じていました。面白いことに、ソルジェニーツィンも、単語帳のようなものを書きたいと望んでいて、それは共産党革命によって侵害され、西洋からの言語的、文化的影響に脅かされていたロシア語の純正を守る、という視点から発していました。そして1990年代初頭、ソビエトの批評誌「Russian Speech」に用語集の寄稿を始めました。多くの国外に出た作家たちがそうであるように、ソルジェニーツィンもリン・ユータンもともに言葉への執着がありました。しかしリンはその意図において、ソルジェニーツィンと違ったものをもっていました。それは英語と中国語の橋渡しをしたい、という気持ちです。当初、リン・ユータンは辞書編纂を、二つの既刊の辞書(マシューズ版とジャイルズ版)に取って代わるものとして着手しました。彼の考えでは、この二つは、現代の読者の使用に耐えないものだと判断したからです。リン・ユータンの辞書は1972年に出版され、その目的はたやすく達成されました。しかしながら、その六年後、北京外国語協会が「中国語英語辞典」(1978年)を出版、それはリンの辞書を更新しているわけでも、携帯に便利なものでもありませんでした。この公式辞書の編纂は、毛沢東の指示によるもので、周恩来の管理の元進められました。50人を超える編集スタッフは、中国人と非中国人で構成され、8年の歳月がかけられました。出版の後も、この辞書は標準中国語英語辞書として存続し、修正や更新が定期的に行なわれました。リン・ユータンの辞書編集プロジェクトは、3人の編集員によるものでした。リンの辞書が北京外国語協会の辞書に簡単に押しのけられたのは、当然の成りゆきでした。 実際、ここ何十年間というもの、中国において、参考図書は出版社の得意分野でした。労働力が安く、創造性を必要としない人員をプロジェクトのために簡単に集めることができたからです。たとえば、ワン・トンイー編纂の「中国語大辞典」(1990年)は、正社員、アルバイト合わせて200人を超える大所帯でした。他に先駆けて、リン・ユータンが自分の辞書プロジェクトを始めたのは間違いでした。また、自分が中国本土の何と競争しているのかに気づきもせず、辞書編纂が自分の文学的キャリアの頂点であると宣言したことは、近視眼的だったと言えます。国外に出た作家は、個人としての取り組みを集団的な活動に対抗させるようなことは避けるべきです。なぜなら、作家の主要な資産はその創造的才能とエネルギーであり、それは創作にこそまず使われるべきだからです。素晴らしい文学は、集団的作業からは生まれません。 家に引きこもり、必要がなければ旅することもなかったソルジェニーツィンと違い、リン・ユータンはニューヨークを本拠としながらも、変化に富んだ、あちこち歩きまわるような生活をしていました。ヨーロッパ中をよく旅し、南フランスの気候やライフスタイルを好んでいました。1940年代の半ばには、全財産の12万ドルをつかって、初の中国語のポータブル・タイプライターを作りだしました。機械の発明には成功したものの、中国本土で起きた国共戦争のせいで、それを作りたがる製造業者はいませんでした。タイプライターのひな形は、ただのがらくたとなりました。発明は画期的で利益を生む可能性はあったものの、結果として、リン・ユータンは破産に追いやられました。1949年、リンは国際連合の芸術と文学を担当する上級職員となりましたが、すぐに作家生活を全うするため退職します。1954年、リン・ユータンは南洋大学の初代校長に就任するため、シンガポールへ向かいましたが、半年後、共産主義者の妨害を受け、辞任しました。この時代を通して、リンは母国に帰りたいと願っていました。しかし反共産主義の立ち場をとる彼にとって、それは不可能なことでした。晩年に、リンはよく香港を訪れ、丘の上に立って国境越しに母国を眺めました。川や山を目にすることはできましたが、そこに足を踏み入れることはできませんでした。 1966年、リン・ユータンがそこで暮らすために台湾にやって来た際、蒋介石は国民党政府として彼の貢献に感謝する意味で、あたかもこの作家が、長い任務を終えてやっと母国に戻ってきた政府高官であるかのように、住むための家を建てて提供しました。リン・ユータン自身が、著名な建築家の助けを借りて、この家の設計をしました。白壁に青いタイルの屋根を乗せた美しい見映えの家で、庭には池があり、中国とスペイン二つの様式を組み合わせて建てられました。リン・ユータンはこの家を愛し、わが家に住んでいるように見えましたが、実際は公費で建てられたものでした。1976年の死後は、この家はリン・ユータンの生涯と仕事を展示する博物館になりました。 ソルジェニーツィンのような幸運に恵まれず、母国の地に足を踏み入れることはなかったものの、リン・ユータンは文学を通して中国本土に帰国しました。1987年、ついに「北京好日」が中国で出版されました。この本の出版に続いて、彼自身や彼の作品に関するいくつかの本が世に出ましたが、そこに書かれている批評は、革命家たちの言いそうなきまり文句や愛国者的な陳腐な言葉にあふれていました。30巻におよぶリン・ユータンの全集も1994年に出版されました。これまでに、何百万部もの本が中国で印刷され、リンは中国で非情に人気の高い作家となりました。「北京好日」をドラマ化したテレビ番組が、台湾と中国本土でそれぞれつくられました。生まれ故郷の福建省章州の人々は、海外のファンの寄付を助けに、リン・ユータンの博物館を建てもしました。このような注目の背後には、彼の文学作品が新たなる中国文化の幕開けに必要とされており、それによって帰国への道がつけられた、ということが再認識できます。文学を通した帰国だけが、この亡命作家には可能だったということです。 実際のところ、作家の郷愁が満たされることを除けば、作家の肉体的な母国への帰国は、大きな意味をもちません。文学史のページには、亡命作家の巨匠たちの名がちりばめられており、作家自身は母国に足を踏み入れる資格がなくとも、作品は最終的に母国の民に受け入れられています。歴史的な出来事の中で、流浪の生活を余儀なくされたダンテは、フィレンツェに生涯戻ることがありませんでした。その灰さえも、仲間の市民たちが何度も試みたにもかかわらず、帰国を許されませんでした。それでも、時がたち、イタリアによって詩の月桂冠の栄誉が与えられています。アイルランドから離れることが創作行為だとでも言うようなジョイスは、作家活動のための流浪生活を基本原理にしていましたが、死後、遺体はチューリッヒに埋葬されたものの、作品は誇りをもってアイルランドに持ち帰られ、近代小説に大革命を起こしました。中国の作家、アイリーン・チャン(張愛玲)は、ロスアンジェルスで人知れずひっそりと死に(1995年)、10年以上の間、中国の人々は作品に触れることがありませんでしたが、小説のいくつかは、今では近代文学の古典として広く読まれています。文学は、歴史的、政治的、言語的な壁を突き抜けて、読者の元に到達できます。その中には作家の母国の人々も含まれています。 わたしたちの時代においては、母国への激しい愛着はときに不必要なものとして、あるいは移民者を衰弱させる時代錯誤な感覚と見られます。多くの追放された人々のために、あえてそれに抵抗して言うのであれば、郷愁というのは恐れの入り混じったものです。確信のなさへの恐れ、より広い世界から突きつけられる挑戦に立ち向かうことへの恐れ、過去の経験からもたらされるはずの自信や確信がないことへの恐れ。突きつめれば郷愁は、あるタイプの移民たち、つまり亡命者であることの体験と関係しています。多くの移民者にとっては、この愛着は筋の通らないもの、不当なものとさえ言えるものです。サルマン・ラシュディの小説「恥(Shame)」で、語り手はこのように反論しています。「われわれは重力を知っていますが、どうして存在するのかは知りません。なぜ人が生まれ故郷に執着するのかを説明すれば、われわれは木のふりをし、根っこを主張するからです。自分の足元を見てみてください。足の裏からごつごつと出てくる根っこなど見つけられません。ルーツなどというのは、わたしが思うに、われわれをある場所にとどめておくために考案された、単なる昔話です」 木の例え話のうそを暴くなら、人間は木とは違う存在であり、根などなく動きまわるものだとわかります。これは大変過激な思想ですが、ラシュディの小説の中では、主人公ウマル・ハイヤームが故郷に戻った後に打ち砕かれる場面として、劇的に表現されています。しかし人間というのはいつも合理的に考える生きものではありません。「恥」の中の同じ語り手が、ときに恥じ入ってこう言うのです。「そして『根っこ』という考えに戻れば、完全にその考えから自由にはなれませんでした。ときにわたしは自分を木だと見なしたのです。さらには、巨大な木、北欧伝説に出てくる世界を体現する木、灰のユグドラシルにさえ」 ここにある原理は、灰のユグドラシルという比喩で示されたある種の滑稽さです。ユグドラシルは北欧神話に出てくる木で、語り手の故郷とはほとんど関係がなく、芸術の想像力によって彼の中に移植されるのです。このようにして、芸術は彼の心を融かし乗り越える方法となったのです。 その人の存在のあり方として、根無し草であることを受け入れることは(中でも旧イギリス植民地出身で、イギリスのパスポートを持ち、第一言語として英語をつかっている作家たちにとって)、多くの移民作家が直面する状況を典型的に表しています。ソルジェニーツィンやリン・ユータンのように、母国を離れる前にすでに地位を獲得していた作家は、彼らの中にはほとんどいません。今日の移民作家の多くにとって、母国を出ることは自身の存在を脆弱にし、行き当たりばったりの境遇に自分を追い込みます。それは意味を持つ過去を当てにすることもできず、新しい土地で生き残るための闘いをしなければならないからです。V.S.ナイポールは小説「The Enigma of Arrival」の中で、そのような作家の窮地を、キリコによって描かれた、表題の元となる絵を引きながら痛烈な筆致で書いています。地中海沿岸の港町に着いた新参者は、荒れ果てた道路や町のバザールをさまよい、見知らぬ人々の間を通り抜けて、寺院の内部に通じる神秘の門に入っていきます。ところが主人公は終いに、その冒険にあきてしまい、自分の当初の目的を忘れて、「船の待つ波止場に戻ろう」としますが、「その行き方を知らない」のです。ナイポールは書いています。「わたしは宗教的な儀式のようなものを頭に描きました。その儀式で、親切な人々に導かれて、いつの間にかそこに参加し、自分が被害者の一員であることに気づくのです。危機に直面してドアに向かい、そのドアを開け、自分が着いた波止場に戻ろうとしていると気づきます。彼は助かりました。世界は覚えているものと同じでした。一つだけ失ったものがあります。堤防と建物の向こうには、マストも帆も見えなかったのです。帆船は行ってしまっていました。旅人はそこで骨を埋めるべく生きました。」 ナイポールは足止めをくった旅人を自分のイギリスおよび英文学への到着になぞらえて、あらゆる移民に対して、それが偶然の結果であれ強制的なものであれ、出てきた場所にはもう戻れないことを寓話にして語りかけているのです。乗ってきた船は行ってしまいました。新しい場所に残された者は、自分の今後の生き方を決めて、過去とは違う人生を歩まねばなりません。自由とともに手に入れた不確かさ、裏切りの苦い味、困惑と自信喪失によって増幅された孤独感、それらと共に生き延びる道を見つけるしかないのです。もし運があれば、人生の充実がいくらかは得られるかもしれません。 作家の窮状を描写したナイポールの文章は、鬱々とした声の調子にもかかわらず、とても詩的です。実際のもがき苦しみはもっと痛切で耐えがたいものです。妹のカムラへの手紙で、ナイポールはこう言います。「僕がイギリスにとどまっている理由は、作品を書くためだということが君にもわかるだろう。そしてそのことに君が共感をもって、僕を励ましてくれるんじゃないか、と思うんだ。トリニダードに帰って借金を返すという目先の解決法は、長い目で見れば、僕らみんなを不自由にすると思う。だけどもし僕がもっと大きなことを(努力の果てに)成せたなら、僕ら全員のプラスに繋がるんじゃないか。一緒に耐えてくれないか、頼むよ。のんきにやってるわけじゃない。飢えてるわけでもないけど、君に対する自分の責任感ですごく心を痛めているんだ。自分のことを恥じてもいる。」 ナイポールはここで、妹に向かって、家に戻って経済的に家族の助けをしてほしいと願う母親に、同調しないでほしいと頼んでいるのです。それに加えて、ナイポールは妹にお金を送ってくれ、そうすれば密かに本を書き上げられると頼みこんでいます。ナイポールは以前に、自分の母親にこう言いました。「自分はトリニダードの生活に合わないと思うんだ。もしこのまま残りの人生をトリニダードで過ごしたら、死んでしまうよ。」 彼は「母国での知性の死」ということを意味していたのでしょうが、皮肉なことに、オックスフォードへの奨学金を提供したのはその母国でした。妹に援助を乞うていた時期、ナイポールは最初の2冊の本を書いていましたが、どちらも受け入れてくれる出版社の一つも見つかっていませんでした。まだ駆け出しの作家であり、一番身近な人々に対しても、文学を追究することを正当化しなければなりませんでした。その他の大半の人々については、求めても得られない恋のようなものだったのではないでしょうか。 ナイポールの状況は、亡命して姿を消したときにはノーベル賞を受賞していたソルジェニーツィンのものとも、アメリカに行く前に英語でベストセラーの本を書き、当時の中国で最高額の著作料を得ていたリン・ユータンのものとも、何と違うものだったでしょう。(4) ナイポールにとっては、母国に対しては元より、自分の家族にでさえ、書くことの正当性を示すことが難しかったのです。彼にとっては、自分を母国の代弁者だと思うことは正気の沙汰ではなく、英国への移住は、明らかに自国の民から疎まれる要因となりました。駆け出しのナイポールのような作家は、いかに良いものを書くか、経済を支えながらどうやって本を出版するかを考える必要があります。それ以上の野望は贅沢すぎるものでした。 初めて、ナイポールの小説「暗い河(A Bend in the River)」を読んだときのことは今でもよく覚えています。この本でわたしの人生は変わりました。それは1992年12月のことで、初めて出版した本の前書きで、不運な中国の人々のために書くと宣言した3年後のことでした。そのとき教師の職を得ようと、米国現代語学文学協会の集会に参加し、ニューヨークにいました。この旅に先立つ2年間、わたしは仕事を探し続けましたが、うまくいきませんでした。面接官と会うために、ホテルからホテルへと渡り歩いていたとき、いつも次の文章がわたしの心の内にありました。
ナイポールの小説にいたく動かされたわたしは、その返答として二つの詩を書きました。一つは「The Past」という詩で、もう一つは以下のものです。
金色の雨降るなか 言葉は、わたしの背を 英知は輝かない
ナイポールは、エッセイ「Two Worlds」で、社会的存在としての作家と芸術家としての作家の区別を認識する必要があると書いています。プルーストの初期の作品「オーギュスタン・サント=ブーヴ」からの引用をあげて、本を書く自己と日常生活の中に存在するそれは同じではない、と反論するのです。一見して、作家の社会的役割についてのこの言い分は、無意味とまでは言わないでも、虚偽のように見えます。重要と言われる作家たちのどれだけ多くが、ペンをもって正義に働きかけてきたことか。その中のどれほどの人が、国民の良心であると見なされてきたことか。さらには、国の魂をなんとか救おうとした作家もいました。前提になるのは、良い作家になるためには、良い人間になる必要があるということであり、作品を書く人間と社会的存在は一つのものだということです。しかし論点をさらに検証してみれば、プルースト、ナイポール、どちらも正しいことが見えてきます。社会的に非情に誠実であったソルジェニーツィンやリン・ユータンのような作家でさえ、自国の民に受け入れられたのは、彼らが後世に残る作品を書いたからです。二人が生きていた間の社会的役割は、ほぼ忘れ去られました。何が残されかと言えば、書く存在である作家から排出された本、それだけです。陳腐な言い方のようですが、ここにはある種の真実があります。作家に一番優先される責任とは、良いものを書くことです。社会的役割はその後に来るもの、多くは周囲の押しつけによって与えられたものであり、作家としての価値には、さほど意味をもつものではありません。 何度か、わたしは現代中国について書くことはもうしないと言ってきました。人々はわたしに、「なぜ故郷につながる橋を燃やしてしまうのか」とか「どうして成功の種を捨てるのだ」と訊きます。わたしの答えは「もうあの場所に想いはないんです」というものです。思ってみれば、作品に現代中国のことを書かないという決断は、代弁者と見なしていた自分の役割を、否定することではないかと思います。わたしは作家として、一人で立つことを学ばなければなりません。 ここでわたしが言おうとしているのは、作家は象牙の塔に住むべきだということではなく、自身の芸術にのみ責任があるということです。ナディン・ゴーディマのエッセイ「いつか月曜日に、きっと(The Essential Gesture/本質的な身振り)」には、作家と活動家の両方の機能を果たそうとし、社会の緊急事態に作品で応えているような書き手たちが描かれていますが、そのような作家たちに、わたしは感嘆の気持ちさえもちます。32歳になって書くことを真剣に捉えるようになるまで、わたしは作家になろうと思ったことはありませんでした。カレッジで教えていた最初の八年の間、授業のとき「芸術」という言葉を使いませんでした。詩と小説をずっと書いてはいましたが、芸術としての作品というものに疑いの気持ちがあり、社会を形成していく上で作品がもちえる価値や高潔さ、自律性や有効性に触れることはなかったのです。ゴーディマの言う、作家とは「作家以上の存在」であり、共に生きる市民の幸福に対して責任がある、という考えに心から賛同します。長いことわたしは、デレク・ウォルコットの「The Schooner Flight」の一節に深い感動を持ち続けてきました。「わたしは何者でもないか、国民か、そのどちらかである」 しかしながら、作品を書き続ける中で、社会的存在としての作家の「本質的な身振り」の問題は、わたしにとってますますわからなくなってきました。作家がいい社会をつくることはないですし、今日の文学は社会の変革に対して無力です。すべての作家が追い求められるのは、個人としての声です。 しかし、作家は誰に向かって語るのでしょう。もちろん自分のためにだけ語るのではありません。ではある集団のために? 自分の言うことを聞いていない人に向かって? 作家が道徳的な態度をとり、抑圧や偏見、不公正に抵抗しなければならないのは議論の余地がありませんが、そのような態度を示すのは二次的なことで、本当に大切なことは、社会闘争という面では、自分の芸術には限界があると気づくことです。作家の戦場は他のどこでもなく、本のページの中にあります。作品は芸術として理解されなければ、ほとんど無意味なものになります。現代史を見渡せば、東洋でも西洋でも、文学の中に記されていない多くの空白地帯があることに気づきます。大虐殺、戦争、政治の大変動、人災による大惨事。中国で1950年代後半に起きた反右派運動を例にしてみましょう。何百万もの人々が迫害に耐え、何万もの知識人が奥地に送られ、そこで死に絶えましたが、未だ、この歴史的苦難を題材にした、価値ある不朽の文学作品は一篇も現われていません。犠牲者たちは中国社会で高い教育を受けた人々ですが、意味ある作品を生み出すにはすでに年老いてしまっています。被疑者となった右派の人々の多くは、作家であり活動家でもあり、何人かは今も嘆願書や記事を書き、集会をしたりしています。しかし読み継がれる文学作品の一つもない状況では、彼らの苦難や喪失したものは、集団的記憶としては、すべてと言わないまでも、その多くが薄れていってしまうでしょう。それは大きな喪失である、と言えないでしょうか? 何が必要とされていたかと言えば、それは一人の芸術家の存在であり、その人が差し迫った社会の必要に応え、抑圧された人々のことを記憶に留めるための、本物の文学作品を書き残すことでした。そうです、書き残すことは、文学における主要な機能です。起きたことの記憶をなくさないために、文学は時の流れにも侵されない、自律性や高潔さを基本とする存在としてあるべきなのです。アンドレイ・マキーヌの「フランスの遺言書(Dreams of My Russian Summers)」の中で、語り手はどのように歴史を証言するかについて考えを巡らせます。「そして個人の記憶を書くことに忙しいロシア人たちは、歴史は無数の小さな矯正労働収容所のことをまともに扱わなかった、ということを理解しなかった。たった一つ、古典になる記念碑的な作品があれば、それで充分だったのに。」 この文が暗に述べているように、作家は単なる年代記編者ではなく、歴史的体験を形づくる人であり、錬金術師でもあるのです。 作家は主として、自分の作品という通路を通って歴史の中に足を踏み入れるべきです。もし作家がある大義のために、ある集団のために、さらには国家のために尽くすことがあるなら、そのような尽力は自らの選択によるもので、社会から押しつけられたものであってはいけません。方法においても、時期や場所の選択においても、それを自分で考えたやり方で提示するべきでしょう。どんな役割を演じようと、作家は自分の成功も失敗も、テキストに書いたことで判断される、と心に留めておくべきです。作家にとってテキストこそが、自分が存在するために、力をそそぐ場所なのです。 (1)たとえば、「ガン病棟」の中で、主人公のオレークは病棟を後にしてから、動物園に向かい、巻き角の山羊を長いこと観察した。そしてその姿に感動する。「オレークはそこに5分近く立っていて、それから感嘆の気持ちを抱いて立ち去った。山羊はぴくりとも動くことがなかった。このようなことこそ、人間が生きていく上で必要とされる何かではないか。(「ガン病棟」) また、「煉獄のなかで」では、インノケンティが義理の妹の夫で著名な作家(重要な作家ではないが)、ガラコフにこう言う。「偉大な作家というのは、ごめんなさいね、多分こんなこと言うべきじゃないんでしょうけど、小声でいいましょうね、偉大な作家というのは、いわば第二の政府なんですよ。だからどこの政府であれ、偉大な作家が好かれることはないんです。二流の作家だけが好まれるの。」(「煉獄のなかで」) 戻る (2)ソルジェニーツィンはロシア国民のままであるにもかかわらず、ロシア人の中には今もこの作家の「アメリカ的な」ところを見つけて言いたてる人がいる。ある町の議会で、参加者の一人がソルジェニーツィンをこう非難している。「すべての始まりはあなたでありあなたの作品なんですよ、この国を崩壊と荒廃の縁に追いやったのはね。ロシアはあなたを必要としていない。だから、あなたの愛するアメリカへ帰ったらどうですか。」(2002年出版のPerennial Classics版、エドワード・E・エリクソン・Jr.による「収容所群島」序文からの引用) 戻る (3)リンはかつてこのように説明した。「多くの人がわたしにアメリカに帰化するよう勧めましたが、わたしは言ったんです、ここはずっと住む場所ではないとね、だから家も買うんじゃなくて借りてるわけです。」(シーピン・ワン「リン・ユータンについて」1987年出版、からの引用) 戻る (4)1920年代後半から1930年代前半にかけて、リン・ユータンは「印税王」と呼ばれており、出版物からの収入は中国のどの作家にも勝るものだった。 戻る
|
||||