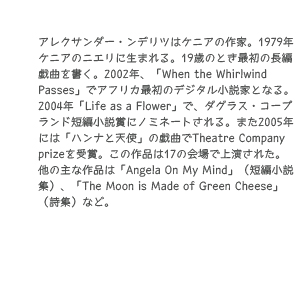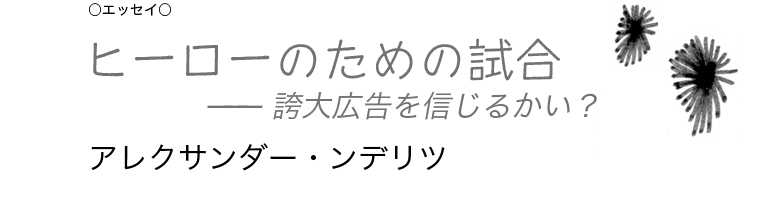
|
この文章は回想録の中のサッカーに関しての部分。ぼくの出身地では「フットボール」って呼んでるけど、あの妙な形のボールを男たちが投げ合うまったく別の競技「アメリカン・フットボール」と混同されたくないんでサッカーと呼ぶことにする。 サッカーっていうのは、世界で一番人気のあるスポーツ、と言われてきた。確かに北米では、サッカーは野球みたいに大衆を惹きつけてやまない熱いスポーツじゃないけど。何年か前に、CNN(シンデモ止まらない・ネガな・ニュース?)の「みんなの声」で、その辺のアメリカ人がマラドーナを知っているかと聞かれてるのを見たんだ。ほとんどの人はマラドーナを知らなかったんだけど、面白かったのは一人の回答者がこう言ったこと。「ええ、知ってますよ。彼女の歌は好きですから」 明らかにこの人はサッカーのレジェンドをポップシンガーのマドンナと間違えてたんだね。 北米から離れれば、サッカーが宗教みたいな場所もある。ヨーロッパのUEFAカップ戦みたいな明らかな地域戦では、世界中に及ぼす影響力は絶大。サッカーのスーパースター、カカーとかロナウジーニョとかフェルナンド・トーレス、デイヴィッド・ベッカム、ロナウドなんかは、何百万ドルもの金を賞金や毎年売り出されるチームロゴが入ったTシャツやらキーホルダーでかき集める。 アフリカでは、サッカーは議論の余地なく、スポーツの王様として君臨している。たくさんのトーナメントも行なわれている。でも運のないことに、ぼくの国(ケニア)に関しては、サッカーの神さまは冷淡だったんだな。ぼくの国のサッカーっていうのは、国民の大きな期待に応えられず、優れた才能も捨て置かれた、そういうもんだった。国際試合やトーナメントでのぼくらの国の不甲斐ないプレーということだけじゃなく、2004年にはぼくらはFIFA(サッカーの運営機関)から完璧な追放をくらった。そのときまで、ぼくらの代表チーム(ハランビー・スターズ)がよその国と試合するときは、ぼくは相手チームを応援してた。ぼくが愛国者じゃないからじゃないよ。ハランビー・スターズが負けるのは火を見るより明かだからさ。ぼくは勝った側にいたいんだ。そういう逆風のなかでも、サッカー熱はここではすごく高くて、ぼくら男の子はごく小さい頃からその熱狂にひたされる。ぼくもちっちゃかった頃、家のまわりをゴムボールを蹴って遊んでたのをよく覚えているよ。 小学校では、休み時間といえばサッカータイム。学校の用具が自由に使えるわけじゃなかったから、自分たちでボールも調達してた。柔らかい紙を丸めて押しつぶしナイロン布でおおって、クモの糸みたいなナイロン糸を上に巻きつけてボール状にするんだ。ゴールポストは上着か靴を置いて間に合わせ、レフェリーなんてレゲエコンサートでヨーロッパ王室の人を目にするよりマレ。試合の名目は楽しい時間を過ごすこと、ルールは甚だしく無視される。オフサイドやマイナーな反則はよく素通りされた。チームワークなんてものは軽視されてた。誰もがゴールすることだけに燃えていた。それに女の子たちがタッチラインの横で試合を見てたから、「ゴール」はぼくら年ごろの男の子にとっては、すごいでかいこと意味する言葉だったんだな。 足の速い子たちは一般にからだのぶつかり合いを避けて、ボールを前に蹴り出して、フィールドの端を矢のごとく駈けていく。一方足の遅い子たちは、ボールさばきやフェイクの動きを覚えて、敵のコーナーにきたらパスをする。ぼくはドリブルが得意じゃなかったんで、フィールドの端を走っていく方の部類で、敵に捕まらないようにしてゴールエリアに入り込もうとする。もうひとつのぼくのお気に入りのポジションは、ディフェンダーだった。ディフェンダーの仕事は、いつもゴールキーパーの前に陣どって、やって来た敵を邪魔すること。そうすればゴールキーパーが直接たいへんな目に会わなくて済む。ゴールエリアを離れることはないから、ボールが遥か遠くにある間は、草の上でゆっくり座ってくつろぐことができる。それに敵のボールがネットを揺らさないかぎり(もちろんネットが揺れることはない、ネットなんかないんだからね。でも言ってる意味はわかるよね)、そうしてても誰からも文句は言われない。さらに、ボールが紙でつくったものである場合、あり得ない問題が起きたりもする。ゴルファーやサーファーならよく知ってるけど、風というのは気まぐれな女王様、ボールはまったく当てにならない動きをする。 相手ゴールのネットを揺らすことはぼくにとって重要だった。それで「ドイツのサッカー」などいろいろなサッカーのテレビ番組をたくさん見て、どうやってゴール技術を上げるかを学んだものだ。ゴールからどれくらい離れたところから、決定的瞬間を捉えたらいいのか。ゴール際にいる場合、ボールを浮かせてゴールキーパーを出し抜けばいいのか、それとも強く打ってキーパーが反応するより先にゴールしてしまえばいいのか。こういう疑問がぼくの心にはいつもあった。中でもぼくが特別に興味があったのは、ペナルティーキックのとき、ストライカーたちがよくやっているテクニックだ。ペナルティーエリアに立ち、心を静め集中し、そしてボールを蹴る。ゴールキーパーが飛んだのと反対側にボールが着地するように蹴る。多くのペナルティキックはこの方法で達成されている。この動きがたまらなく好きで、ぼくは学校で試さずにはいられなかった。 ぼくが十四歳のとき、そのチャンスがめぐってきた。ぼくらはサッカー用のフィールドではなく、ホッケーのピッチを使っていた。サッカーより小さなゴールマウスで、ゴールチャンスは少なそうに見えた。で、敵陣の一人がゲーム中にボールを手で触ってしまった。これはサッカーでは基本の罰則で、相手チームは自陣のゴールエリアでペナルティーキックを被ることになった。蹴るのはこのぼく。自信満々のゴールキーパーの前二、三メートルのところに位置をとり、ぼくはにんまりとほくそ笑んだ。 最初に知っておいてほしいのは、ペナルティーのときプロのキーパーは、ボールではなくキッカーに目を据えるということ。というのはごく近くから蹴られたボールはすごく速いから、人間には反応できない。キーパーがキッカーの動きを予測できれば、ボールが吸い込まれる前に飛びだしてゴールを防ぐことができ、セーブの確率を高められる。キッカーの方は、トリックをつかう、どっちに蹴るかを知られないようにする。蹴ろうと思っている方向とは逆の方に、目も足も向ける。それでスパイク(なんであれ履いてる靴のこと)の横でボールを擦って、見かけとは違う方向に蹴り入れる。強く蹴る。もし思った通りにキックできれば、ボールは予想外の方向に、蹴ったのとは反対の方に飛んでいきゴールのネットを揺らす。 さあ、ぼくらはそのときを迎えた。場所は代用のホッケーピッチ。アフリカの曇り空からは輝くばかりの太陽光線が降り注ぐ。みんながペナルティーシュートを見ようとゴールエリアに集まってきた。そしてぼくは、ネットの右隅を狙っているのをキーパーに知られないよう心した。二歩、三歩、ぼくはボールから離れる。ぼくはからだをカーブさせ前に傾ける。ボールがネットを揺らした。 とても美しいゴールだった。 絶対に忘れられないゴールだ、将来ぼくの孫たちにも記憶させるようにしようと思う。ゴールキーパーは反対方向に飛んだ。チームメートが大騒ぎした。自分が予測したよりもずっとうまくいった。ゴールキーパーが屈辱の表情を浮かべて反対側のコーナーに座り込み、ボールの落ちた先を見ているのをきみにも見せたかったな。 それから先、またペナルティを蹴ることはなかった。高校に入ってからはサッカーへの情熱は薄れ、もっと人生の大事なこと(経歴とか人間関係とか)が目の前にあらわれたから。ほんとのところ、今のサッカー・トーナメントへの執着は理解できない。たしかに、いいサッカーの試合は、人の注意を引くに足ると思う。だけど相手チームのファンに対して、フーリガンがやるみたいに非難を浴びせてはいないか? 一つ二つゴールを決めただけで、選手をあがめなきゃならない? スター選手たちは今では、「ヒーロー」として大騒ぎされている。日本に住む少年はベッカム御用達のサングラスを買い、アフリカの若いのはロナウドみたいに頭を刈っている。でもそれでいいサッカー選手が生まれるとでも? ぼくはそうは思わないね。 サッカーおよび偉大なサッカー選手たちのまわりを取り囲む誇大広告にじっと目をやるなら、選手を抱え、試合を制御している組織であるサッカークラブが、その熱狂のチアリーダーであることに気づくだろう。別の言葉で言えば、試合はコマーシャリズムというモンスターによって、むさぼり喰われているっていうこと。「金は狂気だ。われわれの巨大にして集合的な狂気だ」D.H.ローレンスはこう言った(あれ、マーク・トウェインだっけ。いい話の中に不正確な記述はダメだぞ!)。そしてケニアでさえ、金の狂気はサッカーの窮状に大きな責任を負っている。 たぶん、ぼくには偏見があるんだろうね。ぼくが思っているより、フットボール選手たちはもっと信頼に値する人たちだろう。とはいえ、ぼくの不信を払うには多大なものが必要だ。ぼくが子どものころ、好きな選手はディエゴ・マラドーナだった(ぼくが生まれたのは70年代が幕を引きかけていたころ。だからペレみたいなレジェンドをリアルタイムで見る機会はなかった)。だけどマラドーナが自分の人生のヒーローか、というとそうじゃない。ヒーローとは、ぼくの定義では、何かの苦難から自分を救ってくれる人のことだと思う。マラドーナがぼくにいったい何をしてくれた? ぼくがずっと若くていい加減だったころ、銀行から金を引き出し過ぎて、返すことも不可能な事態に陥ってしまった。母親が自分の銀行を空にしてぼくを救ってくれた。そのおかげでぼくは人生をオークションにかけられることなく済んだ。ぼくがヒーローと呼ぶのはそう人のことなんだな。 © 2012 Alex N Nderitu ンデリツのウェブサイトは、www. alexandernderitu.com
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
||||