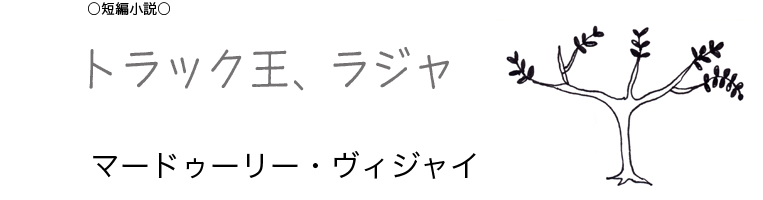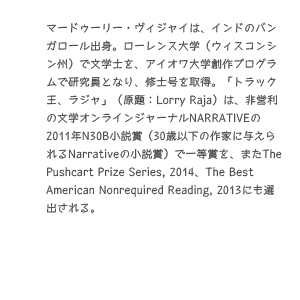何が起きたのかと言えば、兄さんのシジュが鉱山でトラックの運転手の職を得て以来、大物みたいにふるまいだしたことだ。今までやっていたように、ムンナを砂袋みたいに宙に放りあげて、キャッキャと笑わせて遊ばなくなった。アンマ(母さん)が何を聞いても、憐れむような目で見るだけで、答えようとしない。ガールフレンドのマンジュとは、まったく話すのをやめてしまった。ボクが鉄鉱石のかたまりをハンマーで砕いていると、泥遊びでもしてるのかとあざ笑った。アッパ(父さん)に関しては、兄さんは特に無謀なふるまいをした。軽蔑を隠す様子もなく、地面を掘り、酒を飲むことしか能のない落ちぶれた運転手野郎となじった。アッパは兄さんを地面にねじ伏せ、鉄分豊富な赤土を口いっぱい押し込み、こう叫んだ。これがうちの今の食いぶちなんだ、死ぬほどありがたく思わんとバチが当たるぞ。シジュは鉱山の現場監督のスッブに文句を言ったけれど、家族のもめごとと片づけられ、仲裁には入らないと言われた。以来、シジュはアッパの前では、仏頂面をして口をきかなくなった。アッパが近くにいないと、竹の棒にブルーシートの切れ端を掛けたうちのテントにやってきて、悪口を言いたてた。トラックのもち主から、普通の運転手の半分しか賃金を支払われなくても気にしなかった。パーン(キンマの葉)噛みのアーンドラから来たやつは、ラジャッパと呼んでいたけれど、それはシジュがまだ十四歳で、掛け合うことも知らなかったから。
ラジャッパのトラックの認可証が偽のものであっても、心配には及ばない。期限の記述もなく、半分は判読不可能な薄っぺらな紙切れであっても、鉱石をホスペットの鉄道駅までなら、シジュが運んでもいいという証書になった。州境の警備員につかまるリスクがあるため、他の運転手のように、マンガロールやチェンナイのような港町まで行くことは許されていなかったにしても。鉱山のトラック清掃の子たち(多くはボクと同じくらいの年の子)が、シジュのいないところで「トラック王、ラジャ」と呼んで、気取った歩き方を真似していても、気にすることはない。なんであれ、兄さんが気にすることはなかった。それに、あまり認めたくはないけれど、兄さんはあのトラックの運転席の王様で、加えて、そういう風にも見えた。真っ黒のふさふさした髪、それが束ねられて首筋に落ちて、カラスのつやつやした尻尾みたいだった。まっすぐの鼻筋、汚れのないきれいな目、鉱山の空気を吸っていてもなお真っ白な歯。トラックの運転席にいるとき、シジュは信じがたいような、重要な存在に見え、まるでボクの知らない人のようだった。
鉱石は港町に運ばれて、それからビルみたいに大きな船に積まれた。ボクは見たことがないけれど、現場監督のスッブが話してくれた。話では、船は海を越えていき、何週間もかかる旅をするそうだ。オーストラリアや日本に向かうものもあるけれど、中国に行くのが一番多いらしい。中国ではスタジアムを建てていて、それはリンピック競技会と呼ばれるもののためだそうだ。スッブさんの説明では、リンピック競技会というのはワールドカップみたいなものだけど、クリケットだけとか、水泳だけ、テニスだけ、射撃だけ、陸上だけというのでなく、あらゆる競技が一斉に行なわれる。そこで勝てば、金メダルがもらえる、とスッブさんは言っていた。インドはこの前の大会で、ボクシングで金メダルをとった。
中国のスタジアムは、クリケット競技場みたいに円形だけど、十倍くらい大きいらしい。この話をするとき、スッブさんは腕を大きく広げたから、ボクらはきれいにアイロンがけされたシャツの、脇の下の汗のしみが見えた。
世界じゅうの人が鉱山で働いている。そんな風に、そのときは思えた。カルナータカとその隣りのアーンドラ・プラデーシュでかんばつがあって、あまりに飢えていたので、そこの人たちは汚い野良犬にまで目を向けるようになった。ボクらの隣りの人は自分と娘三人に灯油をかけて、火を放った。奥さんは顔をやけどして逃げ出した。そして鉱山のニュースが入ってきた。ベラリに何百という鉱山が開かれ、労働者を探しているというのだ。それを聞いて、人々はそこへ向かった。人の列は一晩じゅう続くように見えた。その人たちは、親戚の誰かに畑や家の世話をたのんだり、売り払ったりした。子どもを学校から呼び戻した。村全体がとつぜん、打ち捨てられ、作物のできない畑は荒れるままになった。たくさんの家族が、鍋やビニール靴、ぼろの服を詰めた大きな包みをかかえ、色あせた映画ポスターが貼られたままのバス停でバスを待っていた。バスは満杯になって、傾くほどだった。ぎゅうぎゅう詰めの状態。積み残された人々はバスの横を走って追い、もっと愚かな人たちは動き出したバスに飛び乗ろうとした。その人たちはみんな振り落とされて、砂ぼこりの上に転がり、雨の降らない空を見つめてしばらく横たわっていた。それから起き上がり、服のほこりを払って、次のバスを待つためバス停に戻った。何ヶ月かの間、ボクの家族はこの状態を見てきた。とくに気にすることはなかった。アッパにはライチュール火力発電所の副監査官の運転手の仕事があった。だからボクらの家族は大丈夫だと思った。そのあと、アッパが事故にあい、仕事をなくした。それからの数週間、アッパは酒場に入りびたり、家に戻ってからはボクや兄さんのシジュ、アンマを好きなだけ叩きまくった。そしてそのあと、ずっと泣いていた。それから少したったある日、アッパはボクらの家族は鉱山に行って働くと発表した。家族全員で行くと。そのとき七年生だったシジュは抵抗しようとしたけれど、アッパに腕にあざができるほどつねられて、不平を言うのをやめた。ボクは五年生で、なんだか大冒険に出るような気分だった。アンマは何も言わなかった。そのときムンナがお腹にいて、足がパパイヤくらいの大きさに腫れあがっていた。アンマは足を引きずって家に戻り、荷物をつめた。
一週間のうちに、ボクらの家族は、お尻から黒いオイルをポタポタ垂らして走るバスに、なんとか潜りこんで乗った。この旅のために、アッパは一人に一つ、巻いた新聞紙に入った熱々のピーナッツを買ってくれた。ボクは焼きピーナッツを口に放りこみ、風景がゆっくりと乾いた赤土に変わっていくのを見ていた。身を寄せ合う村々の建物が赤くなり、木の幹も、バスの車掌の指も同じ色に染まるまでバスは走り、アッパの手から乗車券をとった車掌が「次のバス停です」と言うまで続いた。ボクらは人でごった返す、床にひびの入ったバスの駅によろよろと降りたった。ボクはアッパになんで地面が赤いのか訊いた。土に鉄分が含まれているからだ、とアッパは答えた。アッパが働き手を探している近くの鉱山を訊いてまわり、アンマがみんなの昼食用にタイガービスケット一箱とセブンアップ一瓶を買おうと、ブラウスからお金を取り出しているとき、シジュがやってきて、ここの土が赤いのは血が混じっているからだ、とささやいた。地面に埋められた鉱夫たちのからだからしみ出てきたものだ、と。何ヶ月かの間、ボクはそれを信じて、べたべたした血がひっつかないか、ばりばりとした骨やぐちゃぐちゃの内臓を踏まないかと怯えながら歩いていた。ボクが真実に気づいてシジュをぶとうとしたら、手首を痛いほどぎゅっとつかまれ、ニーッと歯をむいて笑われた。
この鉱山に来て一年くらいたったある日の午後のこと、ボクは高速道路のそばの採掘場で、ほかの子どもたちや女の人たちと作業していた。ボクは道のすぐそばにしゃがんでいた。通る車の生暖かい排気ガスが、色あせたTシャツをふくらませ、短パンの中にまで入ってきた。アンマが今朝くれた、ひもじさを忘れるための噛みタバコは、もうとっくに味がなくなっていた。今は口の中に張りついた、ただの生暖かいかたまり。太陽の熱が肌にささり、あたりには強い金属臭が漂っていて、なにか胸騒ぎがした。いつも笑ってふざけあっている女の人たちも、背をまるめて、黙ってハンマーを打ちおろしていた。子どもたちも今日は散漫に見えた。ときどき誰かが親指をハンマーでたたいてしまい、小さな悲鳴をあげていたからだ。西の地平線では、黒い雲のかたまりが低く胸を垂れていたけれど、頭の上では太陽が紗のかかった空から、ギラギラと照りつけていた。モンスーンの到来は遅れていた。作物にとって遅すぎる到来。でもいつ来てもおかしくない状態だ、とボクは思った。ここ一週間の間に、小さな雨嵐が激しく赤土を打つ日があり、あちこちの採掘穴で水が溢れ、採掘がほぼ不可能になった。去年のモンスーンのとき、酔っぱらいの男がある夜、ふらふらと歩いていて、水がたまった採掘穴に落ちたことを思い出した。発見されたときには、死体はふくらんで黒くなっていた。
高速道路を走るトラックは、上りも下りも流れをノロノロと進んでいた。ベラリから出ていくものは、重い鉱石を山ほど積んで、グレーやグリーンの防水シートがかけられ、ボクの足首くらいの太さのロープでくくられていた。あちこちの港町から帰ってきた空のトラックは、こぼれた石が荷台で飛び跳ね、ガラガラと音をたてていた。トラックの運転手たちは汗で顔をぎらつかせ、そうすれば詰まった道が少しは動くとでもいうように、クラクションを鳴らしていた。ときおり鉱山の主の乗る外車が、渋滞の道を音もなく駆け抜けていった。ボクは口の中のタバコを噛み噛み、外車の名前を挙げていった。マセラティ、ジャガー、メルセデス、ジャガー。その車体は太陽をとらえ、キラキラと輝きを放っていた。光が滑るように車体を横ぎり、テールライトがチカチカとまたたいた。鉱山の主たちは、高速道路のそばのピンクと白の巨大な家に住んでいて、庭には噴水があり、バルコニーから石のライオンが恐い顔で見おろしていた。ボクは黒い流線型のマセラティが通りすぎるのを見上げ、スモークの窓ガラスに自分が映っているのを見た。短パンにだぶだぶのTシャツを着て、泥の上にしゃがみこんでいる子ども。そしてボクの後ろに立っている、女の子のゆがんだ影を見た。ボクはすくっと立ち上がり、手にしていたハンマーを振りまわした。
マンジュはボクがそれでたたくとでも言うように、身を引いた。二、三日前に、二人の子が同時に見つけたティタンの時計を奪い合って、ハンマー片手にけんかしているのを見た。一人がもう一人の手を砕いた。あとで、けんかしていた場所に、小さなツメのかけらが埋まっているのを見つけた。
「きみを打ったりしないって」とボク。
マンジュがゆっくりと笑みを浮かべると、褐色の小さな丘のふくらみにえくぼの影ができた。そしてワンピースの前をなでおろした。それは本当は学校の制服だった。前は白かったけれど、今は赤鉄色に染まっている。マンジュの細いからだを包むワンピースは、のど元高くとめられたボタンのところで始まり、ひざのところで終わっていた。もつれた髪が背中で波うっていた。マンジュとマンジュの母さんがこの鉱山に来たのは、ボクらとちょうど同じ頃だった。マンジュの母さんは病気で、テントから出てくることはなかった。どこが悪いのか、ボクは知らなかった。しばらくの間、マンジュはシジュのガールフレンドだった。シジュのために自分のタバコの残りをとっておき、話を聞いているときは真面目な顔でうなずき、どこへでもついていった。そしてある日、シジュはマンジュに話しかけるのをやめた。それについて訊いたとき、シジュは頭を傾け、口をゆがめて、ぬかるみにチュッとつばを吐いた。
「やあ、マンジュ」 ボクらはほぼ同じ背の高さ、でも何歳かボクより年上、たぶん十五歳。
「うん、グナ」とマンジュは言って、ボクの足元にすわり込んだ。ボクもしゃがみ、マンジュが何かするのを待った。マンジュはボクが割っていた鉱石の一つをとり、つまらなさそうに自分のハンマーで二回たたいた。それからやる気が失せたようでやめた。石をぽろりと落とすとこう言った。「あいつはもう来たの?」
「まだ」とボク。
ボクはマンジュが好きだった。ジャーナリストやNGOの人が鉱山の見学にくると、マンジュとボクはハンマーを置き、ぐるぐると跳びはねてこう叫んだ。「ここには子どもの労働者はいません!」 鉱山の所有者によれば、ボクらの親がここで働いている、と言うわけだ。ボクらは親とただここに住んで、鉱山の近くで遊んでいるだけ、と。ハンマーとたらいはボクらのおもちゃなんです。ジャーナリストがノートにメモをとり、NGOの職員はこそこそと耳打ちしている。するとマンジュが思いきりの笑顔をボクに向ける。そしてリンピック競技会のことを知ったあとでは、ボクらは自前の競技会を開いた。徒競走、石投げ、石積み競争。勝者は金メダルをもらい、二位の者は手を打ち、足を踏み鳴らして喝采した。マンジュと競争するのは面白かった。それはほとんどボクが勝つから。それにマンジュは他の男の子みたいに、負けても絶対怒らなかった。
「マンジュ」とボクが言った。「競争する? 金メダルはボクがとるって賭けてよ」
でもマンジュは頭をふって、トラックの列を見上げていた。マンジュはやせていて、首の下の骨が飛び出ていて、制服の下に小石でも隠してるみたいだった。ボクはそれをハンマーで、やさしくトントンとたたいてやりたかった。濃い口ひげをはやしたトラックの運転手が、マンジュを見て、ストローに吸いつくみたいに、チュウッとくちびるを鳴らした。つき出した男の舌は、分厚くてむらさき色だった。そしてこう叫んだ。「よう、セクシーガール! 陽気なセクシー娘!」 ボクはマンジュのことを思って顔が赤くなり、そばにいた女たちの視線を強く感じた。なのにマンジュときたら、雨がやってくるとでも言われたみたいに、男のことを見ていた。ボクはプットゥを一杯にするのに励んだ。洗面器一杯を計量所にもっていくと、五ルピー半になった。親指のつけ根にマメができるのを気にしなかったら、働きのいい日は、七プットゥか八プットゥはいけた。
そこで働く他の子どもたちが、遠慮のない視線でボクらを見ていると感じた。ボクはほっぺたの裏にあるタバコを右から左にそっと移した。
「あんた、そういうバカげた遊びをやってる場合じゃないと思うよ」とマンジュ。
「ダメなの?」とボクはおそるおそる訊いた。「なんで?」
マンジュが言った。「学校に行きなさいよ」
ボクはなんと答えていいかわからなかった。教室にいたときから、二年がたっていた。ぼんやりとした記憶しか残っていない。冷たい土の床。ひまし油の臭いがするディーラジという名の男の子の隣りにすわっていたこと。スレートの壁と割れたプラスチックの建具。黒板に書かれた計算ができないと、アタマジラミとボクらを呼んだ算数の先生。意味の全然わからない英語の詩を、みんなで声をそろえて読み上げたこと。『少年は、燃えさかる船のデッキに立っていました』 消毒液臭い女子トイレから流れる、カビみたいな別の臭い。トイレの外でくすくす笑ってたディーラジ。木のものさしで、三回、四回、五回と手の平をぶたれて、痛くないふりをしたこと。『少年は、燃えさかる船のデッキに立っていましたが、逃げおおせました』
「あんた教室に朝早く行ってたよね、違う?」とマンジュ。車の排気ガスが顔にかかり、マンジュの髪が口元になびいた。マンジュはそれを噛んだ。顔には赤土のほおひげがあった。
「なんで知ってるの?」
「シジュに聞いた」 そうマンジュが言ったので、ボクは驚いた。「あんたどの科目でも百点だって、シジュが言ってた。算数みたいな難しい科目でもね。あんたはここで無駄に過ごしてたらいけない、って」
兄さんがそんなこと言ってるの、聞いたことがない。NGOの人たちが言いそうなことだ。シジュはどこでそんなもの言いを仕入れてきたのか。
「でもマンジュ、ボクはここが好きだけど」 ボクは言った。
「どうして?」
ボクは理由を説明しようとした。どうしてかって言うと、毎日マンジュと遊べるからだよ、それに鉱山は広くて、開けていて、好きなところどこへでも行ける。確かに仕事はきついけど、トラックが重い荷を積んで、ゴロゴロ音をたてて走っていくのを見てるとワクワクするし。と、そのとき、マンジュがハンマーをぽとりと落とした。
張りつめた声でマンジュが言った。「シジュが来る」
シジュのトラックは他のものと何一つ変わったところはない。ただきれいに磨かれているところが違っていた。運転台のところはオレンジで、長い荷台のアオリ部分は茶色に塗られていた。鉱石をいっぱいに積んでいて、荷台は太った男の腹みたいだった。シジュはこれからホスペットの鉄道駅に行くところなのだ。荷台のうしろのアオリには動物の絵が描かれていた。ライオンと二匹のシカ。ライオンは立派なたてがみをなびかせ、青々とした森にたたずんでいた。二匹のシカがその両脇で、オレンジのきれいな顔をあげて、それぞれ遠くを見ていた。シジュは動物の絵をなにより自慢にしていた。毎朝、トラック清掃の子たちのそばに立ち、動物の顔から赤土がきれいにぬぐい去られるよう、見張るようにしていることをボクは知っていた。清掃の子たちがシジュをからかうのは、新品みたいにきれいにしろ、というシジュの指示を笑っているのだ。
シジュはボクらが高速のそばでしゃがんでいるのを見たと思うけれど、こっちを向かず前を見ていた。ボクは手をあげて振った。それでも無視するので、ボクは「オイー、シジュ! こっちだよ」と言った。
シジュはちらとこっちに顔を向けた。
マンジュの大きな目がシジュを追った。
するとそばにいた女の一人(片方の目の玉がなくて、まぶたがそこに垂れ下がっている)が、タバコをペッと吐き捨てながらマンジュに言った。「いいかげんにしな。どっかよそに行って仕事しな。あの子たちの仕事をじゃますんじゃない」
マンジュは答えなかったので、女は声を荒げて言った。「聞いてんの、あたしが言ったこと。あっちに行って、、」
マンジュが小石をひろって女に向かって投げた。小石は肩に当たり、女が悲鳴をあげた。
「スーレ!」 女が威嚇した。
マンジュが痩けた顔を女に向けた。「スーレ?」 マンジュの声は震えていた。「あたしがスーレだって? この老いぼれ片目の汚いサルが」
ボクは口がきけなくて、マンジュをただ見つめた。マンジュはボクの鉱石をひろってハンマーでたたきはじめた。
「マンジュ、、、」とボク。マンジュは泣き出すんじゃないかと思ったが、上を向いて言った。「あんたがトラックもってたらいいのに。そしたら、あんたとあたしで中国までドライブできる」
少ししてボクはいっぱいになったプットゥを計量所に運んだ。その途中、斜面の下のところで、アンマが女たちの中で働いているのに出会った。ボクは立ちどまってアンマを見た。アンマはふるいを使っていて、からだに赤土がつかないよう、からだから離して振っていた。黒い小石が大きな浅い器の中で跳ねまわり、飛び散っていた。そのすぐそばで、ムンナがボクのお古のシャツを裸の上にかぶっただけの格好で、這いまわっていた。遠くへ行こうとしたり、土をつかんで口に入れようとしたら、アンマかそこにいる女の誰かが腕か足を伸ばして、ムンナを引き寄せた。ムンナはボクを見つけると、小さな腕をダブダブの袖から突きだして、嬉しそうに声をあげた。アンマが顔をあげ、ふるいを置いて背をのばした。アンマは子どもみたいに小さくて、手もぼくのものとたいして変わらない。そばにいた女たちはボクをちらりと見て、仕事を続けた。女たちの伸ばした腕が、線路みたいに並んでいた。
「いくつやったの?」とアンマが訊いてきた。
「三つ」とボク。持っていたプットゥを持ち上げて「これが四杯目」 まだ日が傾くまでに二、三時間はあった。ベラリの赤い山が黒く染まるまで二、三時間、そうしたらその日の総量が集計され、汗かきの現場監督のスッブが発表する。それがいくつであっても、多かろうが少なかろうが、みんな言葉を何かかけてもらうのを期待した。
アンマは目をボクにすえたまま、手をブラウスの中に入れてそこにあるベルベットの宝石入れにさわった。そこに入っていた宝石はすべて、ずっと前から質に入っていた。今はそこに二、三百ルピー入っていると、ボクは知っていた。それはアンマが何ヶ月かの間、隠れて貯めていたものだった。アッパが見過ごしていたり、飲み過ぎて数えられなかったときに取っておいたものだ。それはボクのためのもの、学校の費用だった。アンマはいつもそうやって、そこにあるもののことをボクに知らせようとした。アンマは口を半開きにして、ボクを見た。ボクに言おうかと迷っているんだ。
「グナ」 アンマはついに口を開いた。「今晩、アッパが戻ったら、、、」
「行かなくちゃ」とボク。「仕事がいっぱいあるから。雨も降ってきそうだし」
アンマはため息をついた。「学校に戻りたくないのかい?」 そう訊いてきた。「いっしょうけんめい勉強して、いい仕事につきたくないのかい?」 アンマは声をひそめた。「あんたは賢いんだから、グナ。いつもいい成績だっただろう。自分の賢い頭を無駄にしたいのかい? プットゥの鉄くずでいっぱいにしたいのかい?」
ボクは答えなかった。マンジュがボクの学力について言ったことを思い出していた。プットゥの中身をあらいざらいアンマの顔に投げつけて、石があちこちに散乱するところを想像した。
アンマは目の端でムンナがふるいの中に入ろうとしているのを見ていた。「シジュは今日、トラックで出ていったのかい?」と訊いてきた。
「トラック王のこと言ってるの?」とボク。
「トラック清掃の子たちみたいなことを言ってんじゃないよ。あの子はいい運転手だよ」
ボクはお盆のバランスをとるみたいに、ピョンピョンと足の重心を交互に変えて、プットゥを揺らした。「トラック王は方向指示器を使おうとして、ワイパーを動かしたんだ」
「グナ!」 アンマが怒った。
「トラック王はいつもバックミラーを見て、髪をとかしてる」
アンマの隣りで働いていた女が笑った。黄色い大きな歯に、ピアスをつけた広がった鼻。アンマはちらりと女を見て、それから目を落とした。
女の笑いに勢いづいて、ボクはさらに言った。「トラック王のトラックは、まっすぐに進むこともできない」 そういうとボクは、どんな風にトラックが進むか、手を揺らして示した。
ふるいをひっくり返さないよう、アンマはムンナを抱き上げた。サリーのパルの端っこを唾でぬらし、ムンナのほおの赤い鉄くずをこすり落とした。それはアンマの顔にも、鉱石の表面にもこびりついているものだ。汗と混じりあって、鉄くずはゴム状になり、肌につくと、石けんと水でもないかぎり取り去るのが難しい。そんなものはここにめったにあるわけもなく、せいぜい雨が降ってたまった水たまりが、ときたまあるくらい。鉱山で働く者を見分けるのは簡単だった。みんな血を流しているみたいな見映えだったから。
アンマがムンナを下に置くと、ボクを見て斜面を這いあがってきた。アンマが小さなからだをまっすぐに伸ばし、胸を張るようにしてそこにいる女たちを見た。「シジュはここで一番若い運転手なの」 声を張り上げてアンマは言った。女たちは、さっき笑った者も含めて、誰も見向きもしない。
「たったの十四歳なんだよ。それでもうトラックを運転してる」 アンマは大きく息を吐いた。赤い鉄くずの仮面の下で、興奮で顔を赤くさせていた。
ムンナが斜面を這い降りてきて、お尻をついた。ムンナは歯のない口をあけて、怒って泣きだした。
「あんたの弟でしょ」とアンマ。
アンマとボクはムンナを見た。どちらもムンナを抱き上げようとしなかった。
「わかってるよ」とボク。
ボクは計量所で四杯目の登録をして、一列に並んで待っているトラックの最初の荷台にプットゥをあけた。計量所のすぐ脇は鉄くずの低い壁で、隣りの許可区域と仕切られていた。捨てられたり、外れたりした短い鉄パイプ、錆びたキャブレターやホイールキャップががあたりに散らばり、やって来た人がスッブさんのアルミの小屋をたたくときに、ガラガラと足元で鳴った。この四角いテカテカした小屋は、ボクらの住むテントの三倍はあって、労務事務所として使われていた。ここで不平不満が申し立てられ、労務者の記録が分厚い冊子に書き留められた。一日に何人が仕事をしたか。何杯のプットゥが運ばれたか。鉱山のキャンプに何人の労働者が住んでいるか。流れてきた男や女(バスに乗って毎朝やってきて、列をなして仕事を待っている者)は何人か。スッブさんが事務所から出てきて、適当に人を選び、選ばれなかった人たちは高速道路のバス停に足を引きずって戻り、運を願って次のバスに乗り、次の鉱山に向かう。選ばれた者は、ハンマーとプットゥを与えられた。多くの人は、仕事に慣れると、自分のハンマーをもった。昼の間は、スッブさんの小屋は、鉱山のどこにいても見えた。ハンマーを打つ手をとめて見上げれば、錆色の丘の上にチカチカ光るものが見えた。スッブさんの栗色のスズキカルタスは、小屋の外に止めてあった。木の形をした緑の芳香剤が、ゆっくり回っているのがバックミラーに映っていた。ボクは芳香剤の緑に目を引きつけられた。それはこの鉱山の近くには、緑の木など一本たりともなく、どの木も赤い葉っぱをつけているからだ。
スッブさんはショベルカーの日陰に立って、ペプシを飲んでいた。長袖シャツを着て、一番上のボタンをはずしていた。シャツの下にVネックの下着が透けて、胸元からちりちりとした黒い毛がのぞいているのが見えた。スッブさんは汗をいっぱいかいていて、大きな汗のしみが胸と背中にできていた。左右の脇の下にも三日月のしみがあって、腕をあげると満月になった。
ボクはそこに立って、スッブさんを見ていた。おさげ髪の若い女の作業員がやって来て、スッブさんに何か話そうとしていた。スッブさんは頭をかたむけて、話を聞いていた。それから手を女の子の肩に置いて、何か言った。女の子はおさげを揺らすことなく、じっとに立ちつくしていた。スッブさんは話が終わると手をおろし、女の子は背を向けて歩いていった。キャンプでは、生まれたばかりのある赤ん坊のことで、噂がたっていた。その子の鼻がスッブさんにそっくりだと言われていて、赤ん坊の母親(サビスリという名のガリガリにやせた女)は、夫がベルトのムチを手にやって来る前に、夜こっそりキャンプから追いやられた。アッパがスッブさんを、恥知らず、スーレ・マガネと呼んでいたのをボクは聞いた。でも上等のシャツを着て、ひとり立つスッブさんは寂しげで、それなりの人に見えた。立ってスッブさんを見ているとき、ふと、ボクに手を貸してくれるかもしれない、という考えが浮かんだ。心臓がドキドキいいはじめ、自分がスッブさんと日陰に立っているところを想像した。ボクが話しかけ、スッブさんが微笑み、うなずくのだ。
スッブさんの隣りに立って話すために、ボクは空のプットゥを腿にパタパタ当てながら歩いていった。スッブさんはペプシを飲みおえ、瓶をショベルカーの下に投げ込んだ。その間、ボクには目もくれなかった。スッブさんはハンカチで口をぬぐった。
「休憩か?」と訊いてきた。鉱山でボクを見たことはあるだろうが、もちろん名前など知らない。ここでは何百人もの子どもたちが走りまわっているし、赤い色に染まったボクらは見分けがつかないにきまってる。
「はい、ほんの五分だけです」とボク。なまけていると思われないよう、そう言った。
「そうかい」とスッブさん。
スッブさんは目をつむり、ゆっくりとうなずいた。ボクはペプシをすすめてくれないかと待ったが、そんなことはなく、それでもそこに立っていた。こういう人というのは、どんなことを考えているのだろう。大きな赤い口をあけている鉱山の向こうを見た。鉱山とちがって、向こうの土地は色がなく、やぶのように背の低い木が生えていて、茎のような幹に茶色の葉をつけている。遠くには、まだ掘られていない丘が見え、信じられないくらい青々としていて、大空の下、大きく波うつように緑の丘がつづいていた。そして太陽は、あらゆるものに襲いかかる白い玉、水ぶくれのできたボクの手の甲に、ショベルカーの車体に、鉱山の赤くあいた口に向かってくる。
ボクは咳払いをした。スッブさんの口が開いては閉じ、開いては閉じた。長いつばが伸びて、口のところで縮まった。
「監督さん」とボクが言った。
スッブさんが目をぱちりとあけた。「ん?」
「監督さん、お訊きしたいことがあります」
スッブさんがボクを見た。ボクは大きく息をして、スッブさんの目を見た。不親切なものではなかったけれど、どこかぼんやりとして他のことを考えているみたいだった。
「あの、ボクは運転手になりたいんです、トラック運転手です」 ボクは早口で言った。
スッブさんはボクがさらに何か言うのを待っているように見えたので、こうつづけた。「運転の仕方は知っています。父さんに教わりました。ライチュール火力発電所の副監査官の運転手だったんです。スッブさんのように、スズキカルタスを運転してました」 そう言いながら、小屋の外に止められている栗色の車を指した。
ボクは嘘をついているとは思っていなかった。アッパが副監査官のために運転をしていたとき、会議の間や監査中、ときに奥さんじゃない女の人のアパートの前で、ひざの上にすわっていたのだから。座席の革から漂ってくるじゃこうの臭いに目をまわしながら、ボクはカルタスのハンドルを握っていた。アッパがゆっくりとライチュールの道を走らせ、アクセルにはほとんど触れず、ボクの耳にこうささやいた。「左だ、さあ。用意はいいか。ゆっくりハンドルを回すんだ」 アッパの手がボクの手を包みこんですっぽりとおおい、ボクはアッパの手を感じながら、その動きに応えて、その手がやることに従った。アッパの口からいつも臭ってくる安物の自家醸造のダルの臭いをかぎながら、アッパのくちびるがボクの頭のうしろをかすめ、いっしょに栗色のでかい鳥を滑るようにカーブさせ、またまっすぐに走らせるその瞬間を待っていた。「おまえは天才だ!」 嬉しさを隠して眉をよせるボクの髪に、アッパは生暖かい息をたっぷり吹きかけてささやいた。「こんなに小さいのに、ベテラン顔負けの運転だな」
ボクは事故のことは言わなかった。アッパがあの日どんだけひどく酔っていて、どんな風に女のひざを砕いたか、どんだけアッパがあとで泣いたか。あの女がたてた声、崩れ落ちるまえに出したアー、という声が耳について離れないと。
スッブさんは指をこねくりまわしていた。
「監督さん、お願いです」とボク。
「何歳なんだ?」 そう訊いてきた。
ボクはちょっと間をおいた。「十三です」 ボクはサバを読んだ。
「十三歳か」とスッブさん。太陽を見て目を細め、それから波うつ赤い丘の上を行ったり来たりしている労働者の中の、一人の少年を指した。太陽の光がその子を小さな黒い点のように見せていた。ボクが自分のプットゥに集めている鉱石と同じくらいの大きさだ。「あの子が見えるか?」とスッブさん。
「はい、見えます」とボク。そして少しの間、二人でその子を見ていた。
それからスッブさんは、算数の問題でも出すようにこう言った。「あの子は何してる?」
「働いてます」とボク。
「その通り」とスッブさん。「かしこい子だ。よく働いてる」
ボクは一台のトラックが、斜面を切り開いたでこぼこ道をくねくね下り、高速道路に向かうのを見ていた。そのうしろには、赤い砂煙があがっていた。
「しっかり働け。そうすれば欲しいもの何でも、手に入れられる」 そうスッブさんが声をあげた。話しを聞くために人が集まっているみたいに、やたら大きな声だった。「わたしからのアドバイスだ、ぼうず。おまえのお父さんも同じことを言うだろうな」 そう言って父親みたいに肩に手を乗せて、軽く押したので、ボクはいつの間にかまた、太陽の真下に立っていた。
高速道路のそばの仕事場に戻るかわりに、ボクはアッパを探しにいった。掘り返した土の山に半分隠れて、裸の胸にロープを縛りつけたアッパが、穴に屈みこんでいるのを見つけた。ズボンを脱いで、すりきれた縞のボクサーショーツだけはいていた。アッパは手の延長みたいな、長い柄のハンマーをもっていた。ロープの端を三人の男がもち、アッパの体重を足で踏んで支えていた。それからアッパは、地中に飲みこまれた。
ボクはときどき、アッパがこんな風に働いているのを見にきた。アッパはボクが見ているのを知らない。アッパが地下で打ち鳴らす、こもったハンマーの怒号を聞きながら、穴に入っている秒数をボクは数えた。非常事態を知らせるかすかな音か声、わずかなロープの張りに神経を集めて、ボクは待った。何回これを無事にやりおおせたとしても、次のとき最悪の事態が起きるかもしれないことを知っていた。そしてただ待つのは耐えがたいことだったから、ボクは穴の口に走っていって、正体をあらわした。アッパは赤い顔をさらして、ぶら下がってあらわれ、水から引き上げられた人のように喘いでいた。
男たちがローブをほどき、アッパはからだにくいこんだローブの跡をこすった。一人の男が言った。「下はいい天気だったかい?」 アッパが答える。「いい天気だ。あんたの奥さんのアソコみたいにな」 男が笑った。アッパが言った。「いつかあの野郎、スッブを縄でしばって、下に送りこんでやりたいな」 他の男が言った。「まずあいつは穴に挟まって出てこれなくなるな。それに女の子たちをブクブクした手でなでまわすのに忙しい。それ以外に、あいつが事務所で一日じゅう何してるかってことだ」
「デブ野郎が」とアッパ。ハンマーを持ち上げ、それから強く振り下ろした。それからまた振り上げ、ガシャンと振り下ろした。それを繰り返し、その一連の動作はとても滑らかだった。アッパの腕からボクの足へと伝わる一振り一振りの衝撃、地面を通してボクらを繋いでいる、ボクとアッパのからだに響くものを感じていた。
「息子しかいないのは、神に感謝だ」とアッパが言い、男がまた笑った。
高速道路の脇の採掘場に戻ると、マンジュがいなくなっていた。マンジュがすわっていた地面に、跡がついていた。ボクはその上にしゃがみ、マンジュの裸足の足の跡を確かめようとした。何人かの女はまだそこでからだを丸め、トントンとハンマーを打っていた。片目のない女が灰色の塊からタバコをひとつまみ取って、ボクにくれた。ボクはそれをもらい、ゆっくりと噛んだ。タバコの苦みが口にひろがった。
タバコを噛むボクを女が見ていた。「あの子がどこに行ったか、知りたいかい?」と訊いてきた。
この女の目はどうしてこうなったのか、考えてみた。マンジュが女に石を投げたことをすまなく思った。でもマンジュのことをスーレと呼んだことに、ボクは腹をたてていた。
「自分のテントに戻ったんじゃない」とボク。
「もっと考えてごらん」と女。「教えてやろうか?」
「いい」とボク。
「できた子だよ」と女が言った。
そしてボクの方にからだを傾け、声を落として言った。「よく聞くんだよ。あの子はよくない。わかった? よくないんだよ。あの子に近寄らない方がいいよ」
「わるいけど、ボク忙しいんで」と言った。
そこから二、三時間の間、ボクは休むことなく働いた。ハンマーで鉱石を打ちつづけた。ふらつくことなく、正確に打ちおろす。金属と金属がぶつかって快音が響く。汗がとめどなく手首に落ち、ボクはパンツでそれをぬぐう。ひっきりなしに高速を走るトラックが、時間の経過を知らせる。
シジュのトラックはあれから通らない。少しして、女たちが立ち上がり、背を伸ばした。指をほぐし、足の先を砂の中で丸めた。タバコをくれた女がにっこりしたけれど、一つ目での笑みは不可解なものだった。女たちはいっぱいになったプットゥとハンマーを手に、計量所の方へ歩いていった。女たちが歩いていくとき、その角張った背中、サリーからのぞく頑丈な太もも、がに股の歩き方、土がこびりついたゴツゴツした足を見ていた。どの女も靴など履いたことがなく、持っているのはゴムかビニールの安っぽいサンダルだけ。マンジュが言ったことは正しかった、そう思った。あの人たちは女というより、サルだ、ライチュール周辺の村に群がる、ごつごつした茶色のサルと同じ。恐れを知らない凶暴なサル、子どもの手からピーナッツをかすめ、小さくて鋭い歯で人に襲いかかるあのサルたち。崩れ落ちた低い塀の上に群れてすわり、おしゃべりしながら互いの毛のノミをとりあう。ここの女たちが脇をかきかき、低いしゃがれ声で笑う姿はそっくりだ。
太陽が熟して紫を帯び、闇に向かって朽ち果てた。あたりをおおう臭いは、太陽がすべてを焼き払っていたときには、気づかなかったものだ。よどんだ水たまりからの悪臭とそこにたまる蚊、あたりから流れてくる甘ったるいし尿の臭い、こそこそとあるいは太々しく、ここの人たちが(女の人も女の子も)残したものだ。ボクは最後の鉄くずを計量し、アンマが夕飯のために火を起こしているテントへと帰った。雲がビニールテントの町に低く垂れさがり、男たちが丘の上から降りてくる声が聞こえた。毎夕、男たちは仕事のあと、そこに集まって酒を飲んでいた。アッパの声が他の男たちの声にかぶさるように聞こえた。誰よりも大きな笑い声。アンマがときどき見あげる顔は不安げで、炭火に赤く照らされていた。ボクがムンナをひざに乗せると、炭火のほうに眠そうな目を向けしばたたかせた。アッパが丘を降りて家に向かうとき口ずさむ歌声が聞こてくると、アンマはボクをちらっと見て、炭火を吹きはじめた。ボクはムンナの首に鼻をおしつけ、赤ん坊のすっぱい匂いをかいだ。息を吹きかけるたびに、炭火が赤く燃え、アンマの頬が何度もふくらんだ。
「グナ、パアンを」 アンマが小声で言い、ボクはビニール袋の中にあるひしゃげた靴墨の缶を探した。缶の中にはビンロウの実を砕いたものと、キンマの葉が何枚かしまわれていた。
「ムンナの鼻をふいてやって」 そう言われて、ボクはムンナの鼻から垂れさがる光る鼻水を、ムンナの服の袖で拭いた。
「グナ、、」 アンマが言いかけたとき、アッパが頭をテントにつっこんで、手足をもつれさせながら、ボクらのいるところに崩れおちてきた。アンマはするりとアッパのからだをよけ、両手で生地をこね始め、平たい丸になるまで生地の端っこを折り返し、それから炭火の上に乗せて焼いた。そして生地が飛んでいってしまうとでもいうように、一心に見ていた。アッパは肩肘をついていた。もう裸ではなく、カルバンクラインと書かれた破れたTシャツを着て、色あせたズボンをひざまでまくりあげていた。一月にアッパは、左足の親指をハンマーでたたいてしまい、そこは鳥のくちばしのように曲がったままになっていた。
「スープリーヤ」。「スプリヤ」という名を呼ぶとき、アッパは長く引き延ばして言った。
アンマは答えない。
「こわい顔してんな」とアッパは言って、鼻にしわを寄せた。ダル臭い息が、テントを満たした。「オレの顔を見るのが嫌なんか? ダンナに笑顔ひとつ見せられないってか? 可哀想なダンナが一日じゅう、犬のように働いているのにな」
アンマが顔がゆがむほど、くちびるをきつく噛んだ。焼けたロティを一つ素手で火からとると、新聞紙の上に置いた。アッパがしゃっくりした。
ボクは靴墨の缶を差し出した。アッパがそれをとり、ポンと開けるとキンマの葉の上にビンロウの実をふりかけた。葉の端をきれいに折って四角にすると、くちゃくちゃと噛みはじめた。口の端から赤い汁が垂れた。ぼくは汁がアッパの頬に流れ落ちるのを見ていた。
「グナ」 アッパは口を赤い汁で汚したまま言った。「今日プットゥは何杯だった、グナ」
八杯と言おうとして、炭火で顔を赤く染め、祈りでも捧げているようなアンマの顔を見た。アンマはロティから目を離さず、手をブラウスの中に入れ、ベルベットの宝石入れがある胸のところを触った。
ボクは「六杯」と言った。
「六杯」とアッパが復唱し、「それだけか?」
「うん」とボク。「ごめんなさい、アッパ」 ボクは平手打ちを待った。
ところがアッパは、たたくかわりにボクの顔に手をのばし、ゆっくりとなでた。アッパは手をボクの頭から頬へ、そしてあごへと滑らせ、首のうしろのへこんだところで止めた。ボクの脈がドクドクと早鐘をうちだした。アッパの手はかさぶたと水ぶくれにおおわれて、ヤスリのようだった。いくつかの傷は破れて口があき、いくつかはまだ膨れたままだった。顔や首のいたるところに、アッパの手の突起やミミズ腫れを、くぼみや穴を感じた。ボクの顔に、生の手の刻印を残しているかのようだった。
「いや、ちがう」 アッパが張りのある、歌うときの声で言った。「ごめんなんて言わなくていい。オレこそ悪いんだ。あやまらなくちゃいけないのは、このオレのほうだ。おまえたちがここにいるのは、オレのせいだ。家族みんながな。オレがすべて悪い」 アッパの声が言葉の端で震え、目が暗く沈んでいった。
ボクは目の奥がチクチクして、顔がピクピクし、手足が重くなった。アッパが酔っぱらったとき、こんな感じなのだろうか、と思った。
「オレが悪いんだ」とアッパ。「オレはしょうもない父親だ」
アッパが手を伸ばし、ボクはそこに稼ぎを乗せた。稼ぎの全部を。ウソをついた十一ルピーもいっしょに。アッパはお金を握り、ポケットに入れた。ボクはムンナをしっかりと抱きしめた。アンマを見る勇気はなかった。
アンマがこちらに向く気配を感じた。こらえていた息を一気に吐き出すのを聞いた。
「この子の学校のお金なの」とアンマが言った。
アッパはそっちを見ようともしなかった。
「この子の学校のお金なの」 アンマがもう一回言った。「今年学校に戻れるようにするって、言ったでしょ。授業料としてそこから少し、とっておかなきゃならないの」
アッパが言う。「このオレに、どうこうしろと言ってるんだな。オレの家で、おまえはオレにそう言うんだな」
ロティの上にポツポツと焼けこげがあらわれ、シューシューいいはじめた。
「ただの男だよ、あんたは」とアンマがロティのポツポツを見ながら言った。「どんだけダルを飲もうってわけ?」と言ってアンマは口をつぐむ。「娘がいたほうがよかった」
「クソッタレ娘が欲しいのか?」とアッパ。「なんで娘が欲しい? オレに持参金を払わせたいのか? どこぞのはな垂れ野郎がきて、娘さんと結婚したいんです、ってぬかして、オレはポケットをさぐり、そいつにおべんちゃらか? 冗談じゃない」
「女の子はね、母親の手助けをするの。でもあんたは持参金を飲みつくしてしまうんだろうね」 アンマがぶつぶつと言った。
ボクはその手の出し方で、アッパはアンマのこともなでるのかと思ったが、ボクが見たのはつねるところだった。胴まわりのいちばん柔らかなところ、腰骨の上の、ペチコートとブラウスの間の肌が出ているところを絞りあげた。アンマは声を出さずに口をあけ、激しくからだを揺らせた。アンマの片手がムンナの頭に当たり、こぼれた炭火がボクの足のすぐ近くに蹴りとばされたので、足先を焦がすところだった。足を引っ込め、ムンナが泣くだろうと思ったが、泣かなかった。
アッパが手を離すと、アンマの腰に赤い半円が二つできていて、そこの皮膚がへこんでいた。アンマはうめき声を上げたけれど、ロティを焦がすことはなかった。火からおろして、新聞紙の上に置いた。大きな息をふっーとついた。
「スプリヤ、おまえの欠点はなんだと思う? ちっとも笑わないだろ」 そうアッパが言った。「もっと笑え。笑わん女はな、不細工だ」
アンマの視線が炭火を越え、屈みこんでいるアッパを越えていった。ボクはシジュがテントの入口に立っているのを目にした。シジュは清々しい感じでそこにいた。なんと、髪もきちんととかれていた。シジュはそこに立ってボクらを見ていた。と、突然ボクの目に、シジュを通した風景が見えてきた。足先を丸めているボク、ボクの腕で揺られて眠るムンナ、ひじに寄りかかるアッパ、炭火に屈みこむアンマ。シジュの見たものをボクは見た。そして見なければよかったと思った。
「こっちみて何してる?」 アッパはそう言い「すわれ」と声をかけた。
シジュはアッパとボクの間のすきまにやって来た。シジュがすわると、テントがぎゅうぎゅう詰めのように感じられた。全員が身を寄せ合っているような狭さ、そこを怒りと恐れがロケットのように行き交った。
「今日はどこに行ったんだい?」 アンマがシジュに訊ねた。びっくりしたことに、シジュはいつもやるようにそっぽを向いたりせず、見知らぬ人に親切にしてやろうと決心したみたいな、とりつくろった態度でアンマを見た。
「ホスペットに行った」とシジュ。
「ホスペットに」 アンマは嬉しそうだ。「そこはいい所なの?」
シジュは変わらずていねいな口調で答えた。「実際、あんな汚い場所、見たことないな」
「おまえ、いったい何を期待してんだ?」 アッパがあおるように言った。「どこの街も汚いさ。街なかじゃないとこで食いぶち見つけたいのか、ええ、何だ?」
シジュが無視すると、アッパは身を固くした。
「何回くらいそこまで遠出したのかい?」とアンマが訊いた。
「遠出!」 アッパが鼻で笑った。「あのくそトラックで駅まで、たった十キロだ。十キロばかりを遠出とはな」
シジュが足をもみはじめた。アンマがもう一つロティを炭火に置いた。アッパは二人をにらんだ。自分を無視する二人に対して、我慢できない気持ちがどんどんたまっていった。
「それで? 何回なんだ?」 アッパはそう言って、顔をシジュの方にゆっくりまわした。「何回遠出した? おまえの母さんが訊いてるだろ。聞こえないのか? 耳でも不自由なのか?」
「三回」 シジュがぶっきらぼうに答えた。
「クソの始末をする召使いに言うみたいに言うな。ちゃんと言え」
「三回」 シジュがもう一回言った。
「聞いてるのか、スプリヤ」 ゆっくりと脅すように言った。「おまえ、にっこりできるようなことが聞きたいんだろ? 息子がくそトラックでくそったれ駅まで三回遠出したんだとよ。三回だと。娘がいたらどうだ? 息子といっしょにこれをやるか?」
アッパの死んだような目が、シジュの顔に張りついたまま動かなかった。アンマが最後のロティを炭火に置いた。
「くそトラック運転手が自分をくそったれ王だと思ってる」 アッパがつぶやいた。
ここで泣き声をあげてほしいと、みんなの気をそらしてほしいと、腕のなかでムンナをつねった。が、泣かなかった。ボクはもう一回強くつねった。ムンナはじっとすわったまま、やわらかな、でも意外なほど重量のあるからだをボクのひざに乗せていた。炭火がポンとはねて、心臓がどきんとした。火力発電所の所長が、アッパの事故のあと家にやって来たときのことを思い出した。声をあげたときに唾がアッパの顔に飛び、アッパがそれを拭おうとしなかったことを覚えている。アッパがどんな風に言ったかも覚えている。「そんな、所長、すみません、所長。そんな、所長、すみません。所長」 自分が言っている言葉がわからない人のように。覚えた詩を暗唱でもするように。その晩、アッパは道に出て、そこで寝ようとした。アンマが連れ戻しにいくと、こう言った。「スプリヤ、ほっといてくれ! オレはこうでもした方がいい男なんだ」 アンマに頭を抱かれ優しく話しかけられて、最後にはそのあとについて、足を引きずって家に戻ったアッパのことを、ボクは覚えていた。
アッパはいま、シジュが何をするか待ちかまえていた。
シジュがアッパをなぐる、ボクはそう思った。でも肩をすくめただけ。「くそトラック運転手は、一日中くそったれ石くれをたたいてるよりましだ」 言いながらシジュはボクを見ていた。ボクは目をそらした。
アンマがライムピクルスをロティに乗せ、筒に巻いてはボクらに渡していった。そしてムンナを胸に抱きあげ、ブラウスを肩まで落とし、垂れた胸を、紫の乳首をさらした。ムンナが吸いつき、薄暗がりの中で、パチリと黒い目をあけて、ボクらを見つめていた。ロティはあったかく、こうばしく、ライムピクルスは酸っぱくて固かった。ボクは食べてるもののことだけ考えた。それが口を満たし、ノドで飲みくだされ、何かが解放されるのを感じていた。いつもこうだった。食べものはそこにいる誰もを解き放つ。固く巻かれたバネをほどく。ボクは気持ちがゆるんでいくのを感じた。食べものにはこんな力がある、人を暖め、眠りに誘う。静けさが流れる。誰も口をきかない、炭火の音とパタパタいうビニールテントの音と、隣りから漏れてくる話し声だけがある。そして闇が降りてくる。
するとシジュがボクの方に身をかたむけ、こう言ってすべてを台無しにした。「おまえに言いたいことがあるんだけど」
ボクは口の中のものをごくりと飲み込んだ。「聞きたくない」とボクは言った。アッパがうとうとしはじめたので、声を落とした。アッパは軽くいびきをかいていた。
「聞けよ、ほんのちょっとだから」
「へぇー、トラック王ラジャが何か言いたいって」とボク。
「おい、、」
ボクは耳をふさいで唱えた。「トラック王、トラック王」 バカなこととは知っていた。でもボクはこのいっときの平和を壊したくなかった。宝石のように手の中にしっかりと握っていたかった。
「グナ、聞けよ」とシジュ。思ったより大きな声になってしまったみたいだった。
「なんの騒ぎだ」 アッパが目を覚まして言った。
「なんでもない」とシジュ。
「なんでもないよ」とボクも言う。
アッパはまた目を閉じた。アンマはムンナの授乳をつづけていて、静かに乳を吸う息子に頭を傾けていた。
「あのサル女がマンジュをスーレと呼んだんだ」 ボクは小さな声で言った。
シジュはひざのかさぶたを引っぱった。
「あんたたち何の話をしてるの?」 アンマが訊いてきた。
シジュが答えるより早く、ボクが言った。「マンジュのこと、シジュのガールフレンド」
「母さんが病気の子?」
ボクがうなずいた。
「気の毒に」 アンマはそう言うとさらに「何かできることがあるか、行ってみようかしら」
その時ムンナが乳首を半分吸いながら眠りに落ち、アンマの目が優しく溶けた。ムンナの赤く染みのついた額に手をやり、髪をなでつけた。
「よけいなことすんな」 シジュが吐き出した。「どうすりゃいいかくらい、自分でわかってるさ」
「どんな具合か、見てくるよ」 ボクはそう言って立ち上がった。驚いたことに、シジュも立ち上がった。
「いっしょに行くよ」とシジュ。
「いいってば」 ボクは声をあげた。
「そうね、いっしょに行くといいわ」 アンマが言った。
「シジュ」 アッパが言った。まだひじにもたれたままの姿勢だった。まくり上げたズボンの下のふくらはぎは、磨き上げられた砲弾のようだった。その日の昼、裸の胸をさらし、腰を折り、長いハンマーを滑らかに打ちおろして、地面を掘っていたアッパのことを思い出した。大男ではない、背も高くない、でも来る日も来る日も、日に十時間鉄を打ちつづけることのできる男、それがアッパだ。
シジュはアッパをじっと見つめていた。それからうなずくと、ポケットに手を入れた。折り畳んだ札を取り出し、アッパの伸ばした手の中に押しつけた。アッパはそれをポケットにしまいこんだ。ボクの給料がしまわれているポケットに。調子っぱずれの歌を口ずさむと、アッパは目を閉じた。
アンマがボクとシジュを見ていた。「ほらこれを」とアンマ。「あの人たちに持っていってやって」 そう言うと、ボクにロティを二つ渡し、新聞紙にくるませた。「雨が降る前に戻っておいで」
「来たくないなら来なくていいよ」 テントの迷路を歩いていきながら、ボクはシジュに言った。「言わないから」
シジュは口を閉ざし何も言わなかったので、ボクは不安になった。ボクの足くらいあるネズミが行く手を横切って、右手の暗闇に消えた。ネズミはキャンプで問題を起こしていた。食べものに手をつけ、毛布に穴をあけ、眠っている赤ん坊に噛みついた。去年、赤ちゃんが一人、ネズミに噛まれて死んだ。ボクはムンナが眠っているところを思い浮かべた。キャンプじゅうが静まりかえり、青いビニールシートの船が、黒い毛並みの群れの上を漂う。シートの下で黒いものはカサカサと音をたてて動きまわり、海のように休むことなく、始終腹を空かせている。
マンジュはテントにいなかった。中からマンジュの母さんの荒い息が聞こえてきた。シジュがボクを見て眉をあげ、あごでテントの入口の方を指した。ボクは頭をふった。人間とは思えない大きさの毛布につつまれたものが、ぼんやりと見えた。マンジュの母さんが咳をした。生気なくぜーぜーと咳をし、それはうら寂しい狭い通路を風が通り抜けていくような音だった。ボクは思わず、後ずさりした。
「マンジュはいないな」とボクはささやいた。
「こ狡いやつだ」とシジュが言い返した。
「じゃあ、どうする?」
「テントに戻ろうぜ」
「戻れば。ボクはここで待ってるよ。トイレにでも行ったんだろう」 ボクが言った。
シジュがじっとボクのことを探るような目つきで見た。「グナ、あいつのことは忘れろ」 そう言った。
「いやだ!」 ボクは叫ぶように言っていた。鼻の奥が熱くなって、涙がこぼれだすのを感じた。自分を止める間もなくこう言っていた。「マンジュはボクが中国に連れていくのを待ってるんだ」
「なんだ、それ」 気の抜けた声でシジュが言った。
「ボクのトラックで」 そうつけ加えた。ボクは秘密をしゃべってしまってる。ロティを強く握ると、温かな汁が新聞からしみ出てきた。「ボクがトラックを運転できたら、中国に連れていってもらえるのにって、マンジュが言ったんだ。リンピック競技会を見にいけるって。スッブさんに頼んだんだ。でもダメだって。一生懸命働けば、いつか欲しいものが手に入れられるって言われた」
シジュがふーっとため息をついた。「おまえ、スッブに訊いたんだ。あの太っちょ野郎に。あいつに訊いたんだ」
「うん」とボク。
「なんてこった」 兄さんは頭をふってこう言った。「オレといっしょに来いよ」
スッブさんのカルタスは、アルミの小屋の外にまだ止まっていた。小屋は外灯の真下にあって、銀色の光にすっぽりおおわれていた。外灯は発電機につながっていて、犬のいびきみたいなうなり声をあげていた。ボクらは少しずつショベルカーに近づいた。それは光の水たまりの縁から、ほんの少し外に置かれていた。
シジュがボクの肩に手を置いて言った。「近づきすぎるな」
「なんでここに来たの?」 ボクが訊ねると、シジュはくちびるに指を当てた。
ボクらは巨大なショベルカーに身を隠して待った。ボクはショベルカーに寄りかかった。冷たいメタルの車体にびくっとする。シジュはボクのうしろ、すぐのところに立っていた。奇妙な静けさがあたりを包んでいた。光を放つ小屋、うなる発電機、動かない空気。
すると、驚く方がバカに見えるほど、自然なそぶりでマンジュがスッブさんの小屋から出てきた。マンジュはそこで立ちどまった。制服と細い脚がくっきりと、外灯で照らされていた。シジュのトラックに描かれているシカのように、空を見上げていた。そして振り向くと、ボクらの方をじっと見た。ボクは飛び上がらんばかり、シジュの手がまた肩に置かれた。
「静かにしてろ」 シジュが小さな声で言った。
でもマンジュはボクらをみつけた。制服がひどくぶかぶかに見え、その日の昼に見たとき以上だった。こっちにやって来るとき、マンジュは服の中で泳いでいた。泥道を足音をたてずに歩いてきた。ショベルカーのところに達するなり、シジュが飛びでてマンジュを引き込んだ。マンジュは両手を腰にあて、黙って長いこと、ボクらを見つめていた。マンジュのうしろで外灯がパチンと消え、すべてが闇につつまれた。と、スッブさんのカルタスのヘッドライトがつき、まるで川の上に浮いているみたいに、車の姿が現われた。
「それで」とマンジュが言った。ゆっくりと目を向けると、マンジュの目がはれあがっているのに気づいた。泣いていたのだ。ボクは小屋の中を、スッブさんのこねあわせる手を、冷たいペプシの瓶を、おさげ髪のマンジュの肩に置かれた手を思った。片目の女が言っていた言葉を思い出した。あの子はよくない子だ。
「いつからここにいたの?」 マンジュが訊いた。
「おちつけよ」 シジュがさとすように言った。「グナが散歩したい気分だったからだよ」
「散歩」とマンジュが復唱した。そしてボクの方をなじるようにチラッと見たので、胸がチクリと痛んだ。「で、こっちに歩いてきたんだ」 マンジュがつづける。
シジュが肩をすくめた。「そういうこと」
ボクはこう言った。「ロティをあげようと思って来たんだけど」 新聞にくるまれたロティをマンジュの手に押しつけた。マンジュは、無意味なことをボクがしたとでもいうように、それを見た。
「テントに戻ろう」 ボクがシジュに言った。マンジュの腫れた、生々しい顔から逃げ出したかった。マンジュの赤く汚れた頬に、涙の跡がくっきりとついていた。
「ちょっと待てよ」とシジュ。シジュがマンジュの方に身を傾けたので、二人の顔がすぐそばまで近づいた。シジュがにやりと、意地悪そうな笑顔をみせた。
「おまえが中国に行きたいって、グナが言ってた」 シジュが言う。
マンジュがボクを当惑顔で見た。ボクは目を閉じた。「なんなの?」 マンジュはわけがわからない。
「今でも行きたいか?」
シジュはトラックの鍵の予備をつくっていた。ホスペットで。店主が鍵をつくっている間、トラックの中で待っていた。鍵は真新しく銀色に輝いていた。ボクはそれを見て、落ちつかない気持ちになった。
トラックのたまり場は、油とディーゼルの強い臭いに満ちていた。ボクはささやいた。「スッブさんが見つけたら、放り出されるよ。アッパに殺される」
「うるさいぞ」 シジュが声を荒だてることなく言った。「スッブさん? アッパ? オレがかまうと思うか? オレらと来るか、黙ってここに残るか。どっちだ」
シジュはトラックの高い運転台にのぼった。そしてマンジュの方に手を伸ばした。マンジュは棒をつかむように言われたみたいに、無表情にそれにつかまった。ボクがひとりで登ろうと苦戦しているのを、シジュはただ見ていた。ボクがドアを閉めると、シジュは鍵をイグニッションに入れた。
「音が聞こえないかな」とボク。
「いや、聞こえない」 シジュは険しい顔で言うと、鍵をまわし、エンジンをかけた。
草原をかけめぐる雷のような音がした。ボクは目を閉じた。怒鳴り声を浴び、ライトで顔を照らされ、見つかって緊張から解き放たれるのを待ち構えた。でも誰も来なかった。テントの町は闇の中にあり、保安灯の炭火の明かりしか見えない。空で雷鳴が応えた。
シジュはヘッドライトをつけず、トラックは敷地からそろそろと走り出した。計量所を過ぎ、許可区域を過ぎ、周囲をぐるりとすると、キャンプが黒い球体のように静かに回転し、泥道が視界から消えた。
「位置について」 シジュが低い声で言った。「用意、スタート」
と、ボクはからだが前に投げ出されるのを感じ、トラックがスピードをあげた。ボクらは下り坂を降りていた。窓から風が押し寄せて、ボクの肺をいっぱいにした。マンジュの肩がボクの肩にふれるのを感じた。シジュの手がハンドルの上で回転した。車の床が、足の下で跳ねた。そしてボクはびくりと目覚めた。夜の冷たい空気に、ぱっちり目が覚めた。
シジュがヘッドライトをかちりとつけ、もうボクらが鉱山の敷地にはいないことに気づいた。鉱山ははるかうしろ、枝に脇腹をこすられながら、トラックは木々の間を飛ぶように走った。何も考えることができないくらいのスピード。自分のからだのバランスをとって、ドアに肩をぶつけないようにするのが精一杯。ボクらは大きな岩を飛び越えんばかりに通過した。シジュは前屈みになって、何があろうとスピードを緩めることなく走り、トラックは跳ね上がってはドスンとおり、バネがキーキーと音をたて、ヘッドライトの黄色い光線の中で、地面が大きく隆起したのを目にしたとたん、ドンとその向こうに飲み込まれた。遠くの山が近づいてきて、ボクはシジュが頂上まで行き、さらにそこを超えようとしているのだろうかと思った。ボクはそうしてほしかった。シジュにずっと永遠に運転していてほしかった。シジュが運転をつづけるかぎり、ボクらは安全だと思えた。
でもそこで車はとまり、エンジン音が静まった。ボクらは草原の真っただ中にいて、よその国にいるみたいに、鉱山からはるか離れてしまっていた。大地は四方八方に広がっていた。木で方角をはかることはできなかった。闇の中で、黒い影をつくっているだけだった。シジュはハンドルから両手を離し、髪をすいた。マンジュの胸が制服の中で上下していた。みんな黙ってそこにすわっていた。マンジュはそのあとも、汚れたフロントガラスの向こうをじっと見つめたままだった。
「金メダルか」 そうシジュがささやくのをボクは聞いた。
ボクは口をパクパクして何か言おうとしたけれど、そのたびにコトバは粉々にくだけ、からまりあって出てこなかった。
「グナを連れてこなきゃよかったのに」とマンジュがシジュに言った。自分の名前が口にされて、ボクは震えた。名指しで責任を押しつけられたみたいな気分だった。ボクら三人ここにいるのは、ボクのせいだと。ここで起きたことは、すべてボクのせいだとでもいうように。
「なんでダメなんだ?」 シジュが訊いた。「こいつは来るだけの価値があるんじゃないか? あのな、こいつは今日、スッブのところに行って、トラックの運転手になれないか、って訊いたんだぜ。おまえのためなんだよ。嬉しくないか? あのバカはもちろんダメだとよ。時間の無駄だとこいつに教えてやりゃよかったな。スッブは手を広げておまえの、、、」
「あんた、あたしが好きでやってるとでも?」 草原が広がるフロントガラスに向かって、マンジュが言った。「金をせがんだのか。お願いです、薬を買うお金をください。お願いです、手術の費用がいるんです。母さんの咳がひどくて。先生が肺が弱ってるって。お願いです、お医者に見せるお金をください。じっとして、あいつがやるがままにさせればいいって、思ってるんだ。だけどあいつはほんのちょっとしか金をくれない。だからまたすぐ行かなきゃならない。それがいい獲物なのか?」
シジュは面食らったんだ、とボクは思う。「おまえ働けば、、、」
「一日五十ルピーで?」とマンジュ。「朝から晩まで働いても、食べることさえままならない。あんたはバカよ。グナだってあんたよりは賢い」 こう言うと、マンジュはがくんと肩を落とした。ボクの肩にもたれてきたのを感じた。
「マンジュ」 ボクは理由なく名前を呼んでいた。
シジュは黙ってしばらくすわっていた。そして嫌なことをやっと決心したとでもいうように、押し殺したような声を出した。シジュはドアをあけて飛び降りた。
「来いよ」とマンジュに言った。
ボクは車から降りようと、からだを動かした。
「いや、おまえはここにいろ」 シジュが言った。
「だけど、、、」 ボクはなにか言おうとした。
「グナ、ここにいて」 マンジュが諭すように言った。
ボクはくちびるを噛んだ。マンジュが腕をボクの肩にまわして、引き寄せた。金属の臭いが髪から漂った。こんな鮮烈な臭いを嗅いだことがなかった。形も輪郭もくっきりした臭い。するとどうしてか、隣りの家の奥さんのことが浮かんだ。だんなさんが家族みんなを焼き殺そうとしたけれど、助かった人。その事件のあと、奥さんは寺の境内に住んでいて、僧侶がめんどうをみていた。牛のふんを乾かしたものをもって、帽子みたいに頭に乗せていたことがあった。通りがかるひとをじっと見て、頬をピンクに染めていた。なんで今、あの女のことを思い出したのかわからない。でも思い出した。ボクがそんなことを考えてる間に、マンジュはボクの脇をすりぬけて、運転席に行き、足を伸ばして地面に降りた。小さな声をあげて着地した。
二人がトラックのまわりを歩いている音が聞こえた。チェーンを外す音がして、荷台をあけるギーという音が聞こえた。二人の動く振動が、荷台から伝わってきた。こするような音で、防水シートをシジュが広げたのがわかった。鉄の車体から、合成革の座席から、あちこちのバネや部品が軋む音から、二人の動きがわかった、二人が上になり下になりしているのがわかった。シジュが低い声で何か言ったのを耳にした。マンジュがそれに答えたか、覚えていない。
それ以上何も聞きたくなくて、ボクは薮から聞こえてくる虫の声に、灯りが見える遠くの村から響く犬の遠吠えに、地面に吹きつけて落ち葉をかきあつめる風の音に、集中した。闇がそこを巨大な空間に見せていた、昼間ただっぴろく見える鉱山よりもっと広大な場所に。何もかもが、キャンプとは違っていた。音といえば、もちあげて、積んで、降ろして、掘ってという機械音か、食べたり、いびきをかいたり、泣いたり、眠るために誰かに向かって黙れとののしる人の声か、キャンプではそのどちらかだった。
小さな風がボクの顔をなで、雨の匂いを運んできた。明日の仕事は厳しいものになるだろう。地面はじゃぶじゃぶして掘れないし、鉱石はすべってツルツルするし、水たまりは池になる。男たちはひざまで水につかって歩きまわり、悪態をつくだろう。子どもたちは押し合いへし合いして、「泥仕合」に興じる。トラックはぬかるみにはまり、タイヤを空まわりさせ、あちこちに泥を撒き散らし、タイヤをそこから押し出すのに時間を費やすだろう。ぼくらのひじのところに、ツメの中に、耳にも赤い泥がこびりつく。夜、炭火がつかなくて困るだろう。
これからやって来る毎日、毎週、毎月、毎年がボクの上に鉱山の石のようにのしかかり、ボクを闇の中に押し込めるのではないか、という恐怖からその場に凍りついた。気づくと運転席にすべりこみ、イグニッションから突きでている光る鍵をつかんでいた。それは握ってくれと突きだされた冷たい手のようだった。どうやったらいいか、他の人がどうやっていたか、思い出そうとした。クラッチをそっと押した。そうするのに、座席の前の方にからだを移動する必要があった。ボクが鍵をまわすと、トラックが息を吹き返した。ボクはちょっとそのままの姿勢で待ち、息をとめた。それから急いでクラッチを離し、アクセルを踏んだ。トラックがガクンと動き、ボンと跳ねた。運転席側の半分降ろした窓ガラスに額を打ちつけた。手を額にやると、血が出ていた。エンジンがこもった音を出し、切れた。静けさが戻った。
シジュがドアを乱暴に開け、ボクを運転台から引きずり降ろした。ボクのシャツをむんずとつかんで揺すった。
「おまえ何したんだ」 シジュが言った。「このアホが」
返事をしないでいると、シャツを乱暴に離した。シジュのズボンはジッパーがあいていた。ボクはV字に垂れさがったフラップを見つめた。シジュがボクを見て言った。「なんだよ」
「なんにも」
シジュはジッパーを閉めた。
「乗れよ。家に帰る」 シジュが言った。
「マンジュは?」
「荷台にすわっていたいんだ」
「雨が降ってくるよ。濡れちゃうよ」
「いいからくそトラックに乗れって、グナ。口出しすんな」
運転席の隣りで、ボクはからだを抱え眠ってしまわないようにした。冷たい風が入ってきて、窓を閉めたかったけれど、シジュは自分の側の窓を開けていて、ひじをそこに乗せ、頭を手にもたせかけ、片手でトラックを運転していた。シジュはゆっくり車を走らせ、でこぼこした地面のくぼみに気をつけて、車が跳ねまわらないようにしていた。車は幽霊のような白い岩を通過した。来るときには気づかなかったものだ。目の端でボクは、不機嫌そうなシジュを盗み見た。王なんかじゃない、ただの十四歳のベラリ鉱山のトラック運転手だ。
「これからどうなるの?」 ボクが訊いた。
シジュは手を中に引っこめた。「何が?」
いろんなことがだよ、と言いたかった。でもこう言った。「マンジュの母さんのこと」
シジュは答える前に少し間を置いた。口を開いて言ったのはこうだ。「いいかげんにしろ、グナ。おまえは賢い。そうだろ」
「ボクの授業料のお金をあげることができると思う」
「何のために」 シジュは大人みたいな口のききかたをした。「そうすりゃ、二ヵ月で死ぬところが三ヵ月になるってか」
そのあと、ボクとシジュは黙りこんだ。木々が消えて、地面が少しなめらかになった。キャンプが見えてきたけれど、ほとんど真っ暗闇、わずかに保安灯がついているだけ。シジュがトラックの駐車場に車を止め、飛び降りた。ボクは中ですわっていた。雨がポツポツとフロントガラスを打ち、流れて線を描いた。キャンプは水に浮いているのに気づいて目を覚ます。ネズミは乾いた地面を探して出てくるだろう。ムンナはアンマを探すだろう。アンマはムンナの柔らかな毛でおおわれた頭のうしろに手をやり、なだめるだろう。アッパはテントの屋根にたまった水をかいだすだろう。アンマはアッパの古いルンギーを、二本の竹の支柱に結んで、ムンナのためにハンモックをつくり、ネズミから守ろうとするだろう。マンジュの母さんは楽になれるよう寝返りをうち、雨がやむのを待つだろう。そこには何によらず、その場しのぎの行為しかない、ボクが納得できるものがない。同じことの繰り返しと習慣と避けようのない出来事があるだけ。明日、スッブさんはペプシを飲み、ボクらは石を掘る。
ボクはシジュが名前を呼ぶの耳にした。その声は慌てているようだった。雨は激しくなっていた。フロントガラスが白く洗われていた。ボクはドアを押しあけて、転がるように飛び降りた。足が泥に埋まった。シジュが荷台のうしろで、アオリを開けて立っていた。髪が顔に張りつき、髪の先に雨粒が滴っていた。シジュが黙って荷台を指した。ボクは荷台に目をやり、マンジュを探したけれどいなかった。
ボクらは一時間くらい、そこに立っていたような気がしたけれど、実際は一分もたっていなかっただろう。ボクはマンジュが草原を歩いていくところを頭に描いた。どこか知らない町に顔を向けて。マンジュは何時間も歩くんだ、そして疲れたら、足をとめたその場所で眠りにつく。雨に濡れないよう、腕で顔をおおって。地面の上で丸くなるマンジュを想像した。その髪が頬に張りつくところを頭に描いた。制服が洗われて真っ白になっているのを想像した。探しにくる誰かのための目印になるように。でもそうする人はいない。
それから数ヶ月、シジュはトラックからディーゼルを吸い上げ、それを運転手たちにガソリンスタンドより二十パーセント安く売ることを始めた。モンスーンが終わるまでに、シジュはボクの一年分の授業料を稼いでいた。ボクにはひとことも言わずに、シジュはアンマにそれを手渡した。だからボクはシジュに面と向かってありがとうを言っていない。あのトラック旅行の夜以来、ボクらはほとんど口をきいていなかった。ボクはしばらくの間、シジュもいなくなってしまうのではないかと恐れて、見張るようにシジュを見ていた。でもシジュは毎晩毎晩、家に帰ってきた。ときにみんなが眠ったあとに。シジュは笑わなかった。シジュはしゃべらなかった。ボクは、ときどきシジュがトラックでどこかに出ていくのを知っていた。でも二度とボクを連れていってはくれなかった。シジュがえらそうに歩かなくなったので、トラック清掃の子たちは、がっかりしているように見えた。ボクは毎朝学校に行き、そのあと鉱山に行った。
次の年の八月、水のたまったくぼ地が干上がる季節がまたやって来た。スッブさんがある日の午後遅く、採掘場にやって来て、今日の仕事はこれでおしまいだ、とみんなに告げた。そしてみんなの喝采ににっこりした。カルタスから、小さなカラーテレビと白いパラボラアンテナを取り出し、発電機につなぎ、そこにいた男の手を借りて、ガタガタするテーブルの上に設置した。スッブさんは画面に映像が映し出されるまで、アンテナをいじっていた。
ボクらはみんなでそのまわりに集まって、中国の堂々たる円形スタジアムが、色と光と音楽と踊りに埋めつくされるのを見つめた。しなやかに動く曲芸師や羽をつけた女性たち、顔を色とりどりにペイントした子どもたちを見つめた。ボクらは輝く花火を、光るウェアを着た引き締まったからだつきのアスリートたちが、世界各国の国旗をひるがえして歩くところを見つめた。スタジアムがゆっくりと赤いライトで満たされていくところを、何千人もの人が優雅に動いて、中央で形を変えていくのを見つめた。ものすごい数の人々が観客席で、ボクらが感じているのと同じ感動を、その顔に表わしていた。ボクらみんなが、ここの全員が、じっと黙って、その美しさにぼうぜんと見とれていた。ボクらがつくったそのスタジアムに。
日本語訳:だいこくかずえ
初出:Narrative Magazine