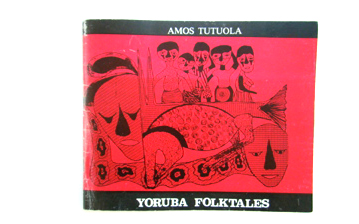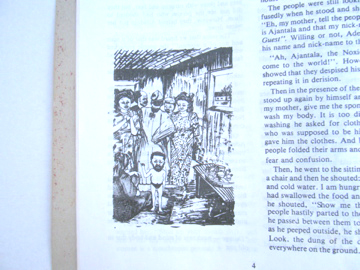父の小説はどれも、ユーモアのセンスを表明しているんです
ワイアード・フィクション:子どもの頃のことで、お父さんについてどんなことを覚えていますか?
インカ・チュツオーラ:父は率直で謙虚な人で、非常に働き者の紳士でしたよ。家族やまわりの人、村を愛していました。父は人の手助けをいつもしていました。情熱家でもありましたね。
ただ父はいつも物語を書いてばかりいました。お客もなく、家の仕事もないときは、自分の机で書いたりタイプしたり、夜中の2時くらいまでやっていて、時に午前3時なんていうこともありました。作品を書いたりタイプするのに飽きるということがなかったですね。
父が政府の仕事をやめる前は、年次休暇といえば、古いオープンリールのテープレコーダーをもって故郷の村を旅していました。学校が休みのときは、わたしたち子どもも一緒についていきましたが、そこで父はありとあらゆる物語を集めたのです。夜には、村でヤシ酒を買って客をもてなし、人々は自分の知る面白い話を披露するためにやって来ました。父は村の人々の話を夜遅くまで録音していました。これが父が休暇のときにいつもやっていたことです。村で過ごすのを父はとても楽しんでいました。もし政府の仕事をしていなかったら、そうやって村人たちと暮らすことを選んでいたでしょう。それはおそらく、村の生活がシンプルだからです。
ただ父はこうして集めた話を、自分の本の中では少ししか使っていませんでした。自分で何かから、ちょっとした出来事などから話を展開する方が普通でした。それでも話を集めて録音することは大好きでした。村から帰ると、自分が楽しんだり、お客を楽しませるために、それをかけて聞いていました。父の暮らしは話を集めること、話をつくり書くこと、それを語ること、それによって成り立っていました。思い出すのは、小学生だった頃、わたしは自分のことで忙しく、でも父がお話を聞かせたがっているとき、わたしがそんな気分じゃないと言うと、父は腹を立てましたね。わたしだけでなく、家族のみんなが同じことを経験していました。父はいつも聞き手を探していたのです。お話が父に与えた喜びはとても大きかったので、社交的な催しやパーティに行くなど、他のことにはほとんど興味がないみたいでした。父が踊っているのを見たことがありません。歌は好きです。でも好きなのは民謡なんです。その中にある話が好きなんです。つまり父のすべてが、お話、お話、またお話、というわけです。父は誰かをじっと見て、あるいは何か出来事を見て、それをお話に変えるのです。
オープンリールの録音機が時代遅れになって、カセットテープが使われはじめたとき、問題が起きました。収集した話が非常にたくさんだったので、それを全部カセットに移すことができませんでした。父は膨大なコレクションの多くを失いました。カセットに移せたのはほんの少しです。わたしには、父は二つの違った世界を生きているように見えました。一つは実際の生活、もう一つは物語や民話、神話の世界です。父に大きな喜びをもたらしたのは神話の世界の方でした、それは疑いようのないことです。
ワイアード・フィクション: お父さんはユーモアのセンスをお持ちでしたか? 内向的、それとも社交的、どちらでした? リーディングをどこかでやったりしていたのでしょうか。覚えておられますか?
インカ・チュツオーラ:生前父に会ったことがある人なら、父が内向的ではまったくなかったということに同意するでしょうね。父はユーモアのセンスに溢れた人でした。ユーモアは父の言葉であり表現の方法とさえ言えます。ものごとを深刻に捉えるのが好きではなかったのです。父はどんなときも、ユーモアのセンスをもって生きることが大切と信じていました。そうすることで、生きていくことに勇気がもて、どのように行動したらいいか考える際、より良い選択ができます。家でも職場でも、父はユーモアの体現者でした。教えるとき、助言するとき、人を楽しませるとき、正すとき、父はユーモアを使いました。父の小説はどれも、ユーモアのセンスの実演であり、そこから発展したものです。父は自分を作家というよりは、エンターテイナー(ストーリーテラー)と思っていたふしがあります。職場では聞き手が見つけられないので、しかたなく紙に綴ったと言ってもいいです。ユーモアは父個人の美徳ではありませんでした。ヨルバ族のものと言っていいと思います。話の仕方、人々への伝え方、モラルや教訓を教えるその方法といったね。
もうずいぶん前のことですが、よく覚えているのは、わたしがあまりに音楽とお酒にお金を費やしすぎていると、父が思っていた頃のことです。そのことを直接指摘するかわりに、こうわたしに訊きました。今お金を持っているか、と。あるよと答えると、じゃあそれを出して、と。いくらでもいいからと。わたしが一枚お札を出すと、次に「これは誰のものだ」と訊くのです。わたしが「もちろん、ぼくのだよ」 すると父はじゃあそれを証明してくれと、お札に名前がないからな、と。わたしはどうやって証明したものかわからかなったので、「じゃあ、これは誰のもの?」と訊き返しました。父はこう言いました。「誰のものでもない」とね。わたしはそれでわかりました。父は彼独特のユーモアで何かを伝えようとしていたのです。それでこう訊きました。「自分のポケットから出したものが、なぜ自分のものじゃないか説明してよ」 しばしの沈黙をおいてから(父はドラマチックに演出するのが大好きなもので)、こう言いました。「お金というのは大きな羽をつけた鳥で、望めばいつでもどこへでも好きなところへ飛んでいける、ということを覚えておくんだな。価値あるものに使われるまでは、お金は幻のようなものだ。商業的に価値のある有用なものに、実際に使うことによって初めて、誰かのものになるんだ。お金でやっていること、それがお金なんだということを覚えておきなさい」とね。この教えを、わたしは生涯忘れないでしょう。
でも父は子どもたちや十代の若者といるとき、さらにユーモアを発揮してました(彼らは父の一番の友だちで、たくさんの若い友だちがいました。それは彼らがいつも父のお話を聞くのが大好きだったからです)。子どもや若い衆に民話を語るのが父の幸せでした。そしてお話の中から面白い名前を見つけて聞き手の誰彼につけていました。ときにおやつを買ってご馳走してましたね。みんな父のことが大好きで、いつも一緒にいたがりましたよ。大人たちもお話が聞きたくて、そこに加わることもありました。父はどこかよその町に住んでる村長みたいでした。親しみやすく、すぐに仲良くなれる、そういう人でした。
でも父はあまり社交的ではなかったですね、字義どおりの意味でね。このことについて言えば、父は選り好みがありました。形式的な集まりや堅苦しい会議など、嫌っていました。人が自分がいいと思ったように振舞えないような場所にいることが嫌いでした。なかでも盛装をしなければならないとか、厳格な作法に従う必要があるとか、理事会の集会のようなね。わたしが思うに、父の友人に学者が多かったのも、彼らは形式などにあまりこだわらない人たちだったからでしょう。それで友人たちのパーティやレクチャー、議論の場には喜んで参加していました。父はあまり旅には出ませんでした。何日か向こうで過ごす場合は特に。これは父の希望でそうするというより、大人になってからの父はずっと、十二指腸潰瘍に苦しんでいたためで、特別な食事が必要だったからです。これがために、食べられるものが手に入りにくい場所への旅は避けていました。それでもいくつかの国内や海外の招待には応じていました。聴衆の前でリーディングをしたり、ヨルバ族の習慣や伝統について話したり、ストーリーテリングをしたりしました。父はアメリカ、フランス、イタリア、イギリスに旅しています。実際に訪れた場所より、招待を断った場所の方がずっと多かったです。
ワイアード・フィクション:子どもの頃、お父さんの作品を読んだ記憶は? 読んでどんなことを考えましたか?
インカ・チュツオーラ:学校時代、わたしたちは英語圏とアフリカ両方の物語を英語で読みました。どんな本もわたしは楽しんで読みました(英文学の「ハックルベリー・フィンの冒険」のようなものも、アフリカの「太鼓たたきの少年」のようなものも)。ただわたしが自分自身を感じられるのは、アフリカの物語の方でした。しかしながらわたしにとっても、共に読んだ友人たちにとっても、一番特別に感じたのはわたしの父の本でした。不思議の国のアリスのように、わたしたちはいつも、父の本の中の英雄たちの冒険を遊びの中で演じていました。自分たちが英雄となり、苦難や試練や窮地に直面しているところを想像していました。父の書いた本はどれも面白かったし、よく本のことで父と議論もしました。いろいろ質問もしました。小さかった頃には、父の文法をとりあげて、こうしたらと提案したこともありました。でもそれから何年かして、父はヨルバの言葉、思想、使用法をそのまま英語に移し替えることを好んでいたんだなとわかりました。英語で同じ意味をもつ言い方を見つけたり、イギリス人がするような表現を選ぶよりも。父によれば、これによって「物語に香りがつけられる」というのです。たとえば「秒」という言葉は、ヨルバでは「目がキラリとする瞬間」のように言います。そういう表現を父は本の中で使っているのです。そのような表現はたくさんあり、多くの人は父が言葉をねつ造したり、文法の欠如からそうしているのだと考えましたが、このような表現は日々のヨルバの表現法であり、考え方や行動から来ているのです。オグンディペ・レスリー教授はこのことに気づいていて、こんな風に指摘しています。「チュツオーラは率直に、堂々と(そして無邪気に)ヨルバ語のもつ表現形態や文学的な特徴を、英語の文章に流し込んだのです。英語によるお返しの形をとってね。この作家はヨルバ語を話して暮らしつつ、英語を使って本を書いたのです」 わたしが思うには、このことが多くのアフリカの作家の中で、父が際だっている点ではないでしょうか。民話というのは、その土地のもつ意味や考えを余すところなく表現するために、一つ一つの言葉がきちんと選ばれて話されるべきだと、信じていたのです。たとえ正しいとされる英語の文法を犠牲にしてもね。この点で父に反対する人々はいます。それでも父は自分の考えを曲げませんでしたし、多くの人がその点に愛着も感じていました。
ワイアード・フィクション:チュツオーラの作品へのイギリスやその他の国の反応を、お父さんは驚いたとお考えですか?
インカ・チュツオーラ:非常に驚いていました。実際のところ、驚いたでは足りないくらいです。ものすごい衝撃を受けた、と言った方がいいかもしれません。大きな遥かなる夢が実現したということです。父は出来る限りたくさんの人々から多くの喝采を得て、お話で楽しませたいと望んできました。そうしたら突然、予想もしなかった、おそらく当時としては前代未聞の海外からの注目と称賛を受け、他ならぬイギリスからも反響があったのです。夢の実現でした。父は驚いたなんてものじゃありませんでした。アメリカでも出版されたんですからね。でもその喜びは水をかけられたようになりました。西アフリカ、中でもナイジェリアの識者たちによって。その人たちは、イギリス人やアメリカ人以上に、正しい英語の擁護に責任を感じていました。そして(西洋基準から見て)充分でない英語力の作家の努力に何もいいところを見ようとせず、(ヨルバの基準から見て)正真正銘の熟練した話し手であるという見方をしました。その人々にとっては、どんなことも、あらゆることが、西洋の審査や基準を通ったものだけが評価され、良いと判断され、推賞されるのです。当時は、人々が西洋の植民地主義や帝国主義、文化や影響を及ぼすもの、ありとあらゆるものに対して、小説や詩などを通して闘っていた時代でした。こういう西アフリカの人々も同様に驚きました。父の側に立って、応援してくれた人々には感謝しています。イバダン大学や後には地元にあるイフェ(ヨルバの聖地)の多くの人々がいつも父を応援してくれ、その調子でもっと書いたらいいと言ってくれました。父はよくストーリーテリングや朗読をしたり、ディスカッションやパーティーのときに大学のキャンパスに招かれました。西アフリカの外の多くの人々も応援してくれました。アメリカでは、バーンス・リンドフォース教授や後に教授になったロバート・レン氏がいつも表舞台に立って、父の仕事を研究し、励みになる評価をしてくれていました。
ワイアード・フィクション:イギリスで本が出版される前、ナイジェリアでお父さんの作品は知られていたのですか? もしそうなら、反応にはどんな違いがありましたか?
インカ・チュツオーラ:1952年にイギリスのフェイバーアンドフェイバーから、「やし酒飲み」が出るまで、ナイジェリアでは知られていませんでした。斬新さゆえに名前が知られ、称賛されたのはイギリスが最初です。しかし父の作品は、すぐに(ほとんど同時的に)ナイジェリアはもちろんのこと、アフリカ全土に広がりました。
ワイアード・フィクション:初期の西洋からの称賛が、ある意味人種差別的であるという主張についてはどう思われていますか?
インカ・チュツオーラ:わたしは「やし酒飲み」の出版とその称賛のどちらにも、人種差別的な要素があったとは思えません。わたしたちは(ときには)変わったもの、気味の悪いもの、風変わりなものを読みたいと思っている、と信じています。ディラン・トーマスが1952年のレビューで誰よりも早く書いたように、「なにやらいろいろ出てきて、身の毛のよだつ、人を惹きつけるものがある」そういうものです。「やし酒飲み」はアフリカの外の文学界の興味を(どんな興味であれ)喚起した、ということだと思っています。反響は本物でした。そうでなければ、出版してすぐに本は酷評されたでしょう。最初の反響がアフリカ文学のレベルを差別するのが目的であったり、ただ市場に本を押し出すためだったなら、そうなっていたと思います。
(後略)
この続きはこちらでお読みいただけます。(英語)
訳者註;
エイモス・チュツオーラは1920年生まれのナイジェリアの作家。1950年代とかなり早い時期に西洋社会から「認められた」ナイジェリアの、あるいはアフリカの作家として有名です。その10年後に生まれたチアヌ・アチェベとともに、英語圏を中心にヨーロッパやアメリカで名前が知られています。
日本でも、チュツオーラの「やし酒飲み」は今でも出版されていて、去年新たに文庫版も出ました。アチェベの方は、どの本も日本語訳ではアマゾンでも手に入らなくなっているようです。アチェベは去年、新作"There Was A Country: A Personal History of Biafra"というビアフラの歴史を重ねた回想録を発表し、英語圏でかなり評判になっていました。また友人のパラグアイの作家が、最近アチェベの昔の小説"Things Fall Apart: A Novel"を読んで、大変感動したと言っていました。本人もまだ生きていますし、若い作家への影響力を今も備えているのでしょう。
それに比べると、チュツオーラはやや忘れ去られた作家のようにも見えます。ただ日本では、アチェベより、断然チュオーラの方が好まれているように見えます。わたしがチュツオーラを知ったのは、多和田葉子さんのエッセイ集でだったと思います。
今回訳したAjantalaの物語は、10年くらい前にアメリカのアマゾンで買った絵本のような体裁の本に収録されています。ナイジェリアのイバダン大学で出版されたもので、タイトルは"Yoruba Folktakes"。紙といい印刷といい、素朴すぎるくらいの仕上がり、造本です。中の絵がまたすごい。でもそういったザラザラとした「粗末な」手触り感が、この民話集には合っている気もします。
今回訳してみて思ったのは、10年前に訳したときほど違和感を感じなかったということ。チュツオーラの英語は奇妙でおかしい、ということになっていますが、そう言うほどのこともないな、と。どちらかというと、生真面目な学校英語のような印象も。確かにいわゆる文学的表現というものはないし、でもそれは民話という性質からくるものでもあり、稚拙に見える表現も、民話や童話の手法と思えば特に言い立てるほどのこともない。
また何か、不思議な面白さも、今回あらためて感じました。単純な話のようでいて、変な感じがあとに残るといった。また善悪の表現も、一面的ではないように思えました。森の中の悪霊だったり、動物になる前の人間だったりが出てきますが、意外に現代的な印象も受けました。
そんなとき、チュツオーラの息子、インカ・チュツオーラさんが、アメリカのオンライン誌「ワイアード・フィクション・レビュー」で、インタビューを受けているのを見つけました。主宰・編集者のジェフ・ヴァンダーミーアの質問に答えています。それで連絡をとり、インタビューの一部を日本語に訳して掲載させてもらうことになりました。
著者のページの写真は、インカさんが直接葉っぱの坑夫に送ってくれたものです。「父の作品に興味をもってくれてありがとう!」とメールには書かれていました。
だいこくかずえ
「有害なお客・アジャンタラ、生まれる」が収録されているYoruba Folktales(1986年、イバダン大学出版刊)
「有害なお客・アジャンタラ、生まれる」に使われているイラスト(Yoruba Folktales)