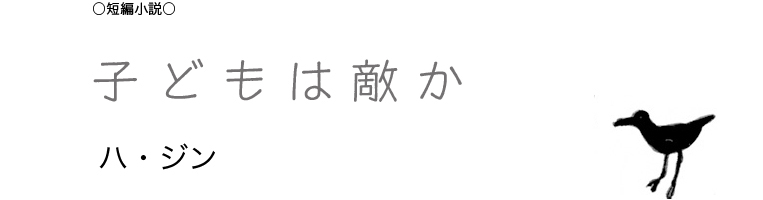
|
|
||||
うちの二人の孫はわたしたち祖父母を嫌っている。男の子が十一歳、女の子が九歳、二人そろって身勝手でいいかげんなガキどもで、年長者を敬うことを知らない。二人の我々への敵意は三ヶ月前、二人が名前を変えたときに芽生えた。
ある夜、男の子の方が自分の名前をクラスメートが発音できないと不平を言った。だから変えたい、と。「みんな僕のことを『チキン』って呼ぶんだよ。もっとみんなみたいな普通の名前にしたい」 こう孫息子は言った。この子の名前はQigan Xiといって、発音は『cheegan hsee(チーガン シー)』のようにする。中国語を話さない人には難しいに違いない。
「あたしも名前変えたい」 妹のホアが割りこんできた。「誰もちゃんと言えないんだよ、『ワウ』とか言うんだから」 頬をプッーと膨らませ、くちびるをとがらせた。
子どもたちの親が何か言う前に、わたしの妻が口を挟んだ。「お友達にどう発音するか、教えてあげればいいのよ」
「チーガンなんて情けない名前、みんな笑ってるよ。僕が中国人じゃなかったら、僕だってチキンって呼ぶさ」と孫息子。
わたしは二人の孫にこう言った。「名前を変えるなんてのは慎重にやるべきことだ。おまえたちの名前はな、名の知られた易者に見てもらって決めたんだよ」
「えーっ、だれもそんなもん信じないよ」 孫は不満げに言う。
父親が割って入って、息子にこう言う。「ちょっと考えてみよう、いいな」
息子の嫁のマンディが細い目をこちらに向けて割り込んできた。「子どもたちはアメリカの名前をもったほうがいいのよ。世の中に出たときに、発音できない名前ではいろいろ面倒が起きるんじゃない。もっと前に変えておくべきだったのかもね」
わたしたちの前では何も言わなかったが、息子のグビンも同意している風だった。
妻もわたしも嫌な気分になったが、あえて反対の言葉は返さなかった。それでマンディとグビンは、息子と娘の新しい名前を考え始めた。孫娘のほうは簡単だった。中国名のホアは花を意味するところから、『フローラ』という名前を選んだ。ところが孫息子のほうは簡単にはいかなかった。英語の名前というのは一般に単純で、言葉の元の意味を失っているものが多い。チーガンは『素晴らしい勇敢さ』という意味がある。英語の名前に、この意味と響きの両方を兼ね備えたものを見つけられるだろうか? わたしがこの点を指摘すると、孫息子はいきりたって言った。「へんちくりんでわかりにくいのは、いやだからね。普通の名前がいいんだよ。チャーリーとかラリーとかジョニーとか」
わたしには許しがたいことだ。名前というのは運勢や運命にかかわることだ。だから易占いは名前の字画を見て、その人の運勢の浮き沈みを言い当てることができる。やたらめったに名前を変えてはならないのは、そういうことだ。
マンディは公立図書館に出向いて、子どもの名前に関する本を調べた。一冊の小さな本に目を通しているうちに、『マティ』という名が思い浮かんだ。マンディはこう説明した。「『マティ』は『マティルド』の短縮形で古いドイツ語から来ているの、意味は『戦闘における力強さ』だから中国語の『Qigan』とは意味的にとても近いわ。それに音の響きが英語の『マイティ』に似ているし」
「あまりよくはないな」とわたしは言った。心のうちでは『マティ』はわが家の姓である『シー』とうまく合わないと思っていた。
「それいいね」と孫息子は嬉しそうだ。
この子はわたしに異を唱えるために、そう言っているように見えた。だからそれ以上何も言わなかった。息子がこの名前に反対してはくれまいかと願ったが、グビンは何も言わず、ロッキングチェアにすわってアイスティーを飲んでいるだけだ。これで事は決まった。孫は学校へ行って先生に新しい名前「マティ」を告げた。
一週間のあいだ、孫は嬉しそうにしていたが、それは長く続かなかった。ある夜、両親にこう言った。「マティって名前は女の子の名前だって、カールが言ってた」
「ありえないわよ」 母親が言う。
「本当だってば。いろんな人に聞いたけど、みんな女の子っぽいって言ってた」
わたしの妻がエプロンで手を拭きながら、「本を見てみたら」と息子のグビンに言う。
子どもの名前についての本はまだ家にあったので、グビンが本を繰って、名前の横に「女、または男」と書いてあるのを見つける。マンディが、女の子にも男の子にも使える名前だということを見逃していたのは明らかだった。なんにせよ母親の不注意と無知がもたらしたことだった。
さて、どうしたものか。十一歳になる孫は、男か女かわからない名前をつけた母親に文句を言いながら、涙に暮れている。
すると息子がひざをぽんとたたいてこう言った。「こういうのはどうだ。『マティ』は『マット』からきているとも言える。Mattyの「y」を落とせばマットだ、どうだマットで」
孫息子の顔が輝いて、うん、それがいいと言った。でもわたしは反対した。「見てごらん、この本には『マット』は『マシュー』の短縮形だって書いてある。そうなればもう、中国語のチーガン『素晴らしい勇敢さ』とは何の関係もなくなる」
「ったく、くだんねぇ」 吐き捨てるように孫息子は言った。「ぼくはこれからマットでいくからね」
返す言葉もない。わたしは自分の顔がこわばるの感じた。席を立つとパイプたばこを吸いにバルコニーに出た。妻が後ろから来て、「あなた、孫の言ったことをまともに取らないで。あの子はちょっとおかしくなってるんだから。中へ入って食べましょう」と言う。
「一服したら行く」 わたしは返した。
「長居しないでね」 妻は家の中に戻っていった。小さな背中が以前にも増してまるまっている。
バルコニーの下では、雨に濡れた通りを車が、色とりどりのクジラが行き来するように滑っていく。ターリエン(大連)の町ですべてを売り払って、息子の家族と住むためにここへやって来ることなどしていなかったなら。グビンは一人っ子、だから一緒に住むのがいいと思ってやって来たのに。今では来なければよかったとさえ思える。妻が六十三、わたしが六十七、我々の年齢では、それにこの時代では、ここの暮らしに慣れるのは難しい。アメリカにいると、年をとればとるほど、地位が低くなる気がする。
妻もわたしも孫たちの生き方に口出しするべきじゃないことはわかっていた。でもときにちょっとした忠告をしたくなってしまうのだ。妻は息子の嫁が孫たちを甘やかして、わたしたちを嫌うように仕向けたのだと信じて疑わない。マンディが甘い母親かどうかは別にして、わたしはそこまで悪くは思わない。フローラもマットもいくつかの好きな食べものを除いて、中国のものは何であれ見下している。二人は漢字の読み書きを習いに、週末学級に通うのを嫌がっていた。マットは「あんなクソみたいなもの必要ない」と言い放っていた。
孫がそんなことを言うのを聞くたびに、自分の怒りを抑えるのに苦労した。両親は孫たちに週末学級に行かせていたが、マットもフローラもすでに漢字を覚えるのをやめてしまっていた。二人は台湾の老画家から、筆をつかって絵を描くことを学ぶために通っていた。女の子の方は芸術的センスをもち、からだが弱かったけれど、男の子の方は得意なものが何もなく、夢ばかり見ていた。わたしはこの子が行く末は浮浪者になってしまうのではないかという想いから逃れられなかった。孫息子は竹とか金魚とか風景を描こうとはせず、かわりに紙の上にただの線や帯を墨で描いて、それを抽象画と呼んでいた。彼は墨の濃淡をつかって、水彩画を描くような試みをしていた。ときに家でそれをやっていることもあった。ぽっちゃりとした頬に細い目をしたこの子が、大真面目で絵を描いているのを見て、わたしは笑わずにはいられなかった。孫は一度、学校の先生に、墨で描いた縦の線の絵を見せたことがある。たまげたことに、その女の先生はその絵を誉めた。この線は降りこめる雨、それとも滝を表しているのかもしれないわね、絵を横にすれば、雲の重なりにも見えるし、どこかしらの風景のようでもあるわ。
なんたるたわごと。わたしはグビンを呼んで文句を言った。子どもたちにもっとちゃんとした教育をさせたらどうだ、科学とか古典とか、地理や歴史、文法、書道とかいろいろあるだろう、と。マットがこういうことを取得できないなら、将来は車や機械の修理をしたり、シェフになるために料理を学ぶことを考えなきゃな。自動車整備士はアメリカではいい稼ぎになる。修理屋で働くやつを一人知っているが、まったく英語をしゃべれなくても、一時間二十四ドルを稼ぎだす、加えて年末にはそれなりのボーナスまであるんだ。『芸術』なんていうつまらない手わざでは、子どもたちの将来はどうにもならない、筆でペタペタやるのはやめせさた方がいい。グビンは言う。まだマットもフローラも小さい、あまり押しつけるようなことはしないほうがいい。でも子どもたちに話はしてみると息子は言った。グビンとは違い、マンディの方は子どもたちの肩をもち、わたしたちは彼らを個人として尊重して、思うように伸ばしてやらなきゃ、中国にいたときみたいにがんじがらめにしてはだめ、と言うのだ。妻もわたしも、嫁のこの態度には不満だった。われわれが嫁を批判したりすれば、孫たちは必ず、母親を弁護しようと、わたしと妻に刃向かいわめきたてる。
アメリカの小学校教育については、かなりの懸念があるとわたしは思っている。先生は生徒に真剣に勉強するようにしむけないのだ。マットはかけ算も割り算も三年生で学んでいた。でもニヶ月前に、わたしが1586ドルの74%はいくらだ、と聞くと、どうやっていいのかわからないようだった。計算機を渡して「これを使ってみろ」と言った。それにもかかわらず、0.74を総額に掛けるということがマットにはできなかった。
「かけ算と割り算は習ったんだろう?」 わたしは聞いた。
「やったけど、去年のことだよ」
「そうかもしれないけど、やり方がわからなくてどうする」
「割り算もかけ算も今年はやってないんだよ。だからもうよく覚えてない」 マットはそう言いわけをした。一度習ったということは、それができるようになって自分のものになったということだ、とこの子にわからせるのは難しそうだった。だからこそ知識はその人の財になるというのに。そうやって蓄積することで豊かになっていくわけだから。
アメリカの先生というのは生徒にいわゆる宿題というものを与えない。かわりにやらせるのは様々なプロジェクトで、中にはばかばかしいとしか言いようがないものもあり、子どもを自意識過剰にさせかねない。息子は子どもたちのプロジェクトを手伝うはめになり、それはまるで親のための宿題のようだ。大人でも答えるのが難しいテーマがあったりもする。「文化とは何ですか? どのようにしてそれは作られましたか?」「イラク戦争に賛成か反対か議論しなさい」「人種差別はアメリカ社会をどのように分裂させていますか?」「地球規模の貿易は必要だと思いますか? それは何故でしょう」 息子はネットや公立図書館に行って、こういったテーマを語れるような情報を集めてこなければならなかった。確かにそういうテーマに取り組むことは生徒に世界への目を開かせたり、自信を与えたりするかもしれないが、年端のいかない子どもたちは、政治家や学者のようにものを考えはしない。子どもたちは規則に従うことを学ぶべきだ。まずは責任ある市民、国民になるために必要なことだからだ。
わたしがフローラに、勉強はクラスのどの辺にいるんだと聞くと、いつも肩をすくめて「わかんない」と答える。
「わからないとは、どういうことだ?」 兄よりはましなはずだが、クラスの平均を下回るのかもしれない。
「ギレン先生は順位をつけたりしないってこと」と返事が返ってきた。
もしそれが本当なら、なおのこと学校にはがっかりだ。競争で他の者に勝とうとする気持ちや一番になってやろうとする意欲を教えこまないで、いったいどうやってこの子たちはグローバル経済の中を生き抜けるのか。アジア系の親たちが、フラッシングの公立学校をよく思っていないのも無理はない。正直な気持ちを言えば、アメリカの小学校教育は、子どもたちを堕落させるようなことをしている。
五週間ほど前、マットが夕食の席で苗字を変えなくっちゃと宣言した。その日の朝、代用教員が苗字の『シー(Xi)』を『イレブン』と読み間違えた。それでクラス中から大笑いの的となり、マットのことをその後も『マット・イレブン』と呼んでからかう者もいた。フローラも我が意を得たりと「そうなのよ、わたしも違う苗字がいい。友だちのレタも苗字をウーに変えたんだから。『Ng(エング)』が発音できない人がけっこういて、『レタ・ノー・グッド』って呼ばれてたの」
子どもたちの親は吹き出した。しかしわたしには何がおかしいのかわからない。妻がフローラに言った。「大きくなって結婚したら、だんなさんの苗字になるのよ」
「男の人なんていらない」 フローラは言い返した。
「ぼくらは新しい苗字がいるんだよ」 マットも言いつのる。
わたしは激高した。「そんなことはさせない。おまえの苗字は家族のものだ。おまえは自分を先祖から切り離すことはできない」
「ナンセンス」 マットは顔をゆがめた。
「おじいちゃんにそんな言い方はだめよ」 祖母が口を挟んだ。
マンディと息子は目を見合わせた。この二人がわたしと妻のようにこのことを考えてはいないことはわかっている。どうせ二人は子どもたちの苗字を変えるつもりだったんだろう。カッとなったわたしは、茶碗をテーブルに置くとマンディを指差して言った。「あんたが子どもたちを甘やかせてばかりいたからだ。子どもたちをうちの家系から追い出して、さぞいい気分だろうな。あんたはいったいどういう嫁なんだ。あんたをうちの家族に迎えるんじゃなかった」
「そんなに腹を立てないでくださいよ、お父さん」 息子が言った。
マンディは言い返さなかった。かわりにひょうたんのような鼻にしわを寄せて泣き始めた。子どもたちが怒って、わたしに文句を言った。お母さんをいじめないでよ。子どもたちが言いつのればつのるほど、わたしの怒りは激しくなった。とうとうわたしは堪忍袋の緒が切れて、こう叫んだ。「苗字を変えるというなら、二人とも出ていけ。この家から出ていくんだ。違う苗字を使っている間は、この家族の一員ではない」
「アナタは誰なの?」 マットが静かに言った。「ここはおじいちゃんの家じゃない」
「ただのお客、ここに泊まってるだけでしょ」 フローラが付け加えた。
これにはわたしも妻も激怒した。妻が孫娘に向かって叫んだ。「じゃあ、わたしたちが、中国の家もお菓子屋も何もかも売り払って、この家のお客になるためにやって来たっていうわけ? 薄情な。ここがわたしたちの家じゃないって誰が言ったの?」
孫娘は口を閉ざしたが、目は祖母を睨みつけたままだった。息子が誰にともなくこう言った。「頼むから、静かに晩めしを食べようじゃないか」 息子はもぐもぐと揚げエビを食べつづけた。
おまえは飯のことしか頭にない米樽か、と息子にむかって怒鳴りつけたかったが、我慢した。こんなしょうもない息子をわたしたちは育ててしまったのか。
公平に見れば、息子は仕事においては文句なしの働きぶりだ。橋工事の技術者として、年に六桁の稼ぎがあるくらいだ。だが妻の尻に敷かれ、子どもを甘やかしている。アメリカに来てからどんどんそれがひどくなっている。気概も言い分もない男に成り下がったみたいだ。もっと男らしく生きろ、以前のおまえを取り戻せ、ズバリと息子に言ってやりたいと、どれだけ思ってきたことか。わたしと妻はしばしば、息子はひょっとして不能なのだろうかと話し合う。そうでなければ、なんでいつも息子はマンディの言うことばかり聞く。
諍いの後、妻とわたしは家を出た。グビンとマンディが、市が提供している年配者用アパートの申し込みを書くのを手伝ってくれた。入居できるまでずいぶんと長いこと待たされそうだ。もしわたしたちがまだ若く、健康に不安がなかったら、息子たちのところからずっと離れた場所で、自分たちのやりたいようにして住んだだろうが、息子たちはこの国でわたしたちのただ一つの家族、だから近くに住むことになったのだ。当分のあいだ、グビンが借りてくれた五十四丁目にあるワンベッドルームのアパートに暮らすことになった。ときどき息子が、すべて順調か、何か必要なものはないか見にやって来た。孫たちが今何と言う苗字を使っているのか、聞いたことはない。多分、アメリカ人の名前から選んだのだろう。孫の名前がどこかに書いてあっても、それが誰だかわからないとは、何と悲しいことか。家族の糸が、その他大勢の人々の中にまぎれて消えてしまったようだ。それを考えると、いつも胸を針でさされたような痛みを感じる。あのとき、中国を離れる決心をひるがえしていたなら。今ではもう戻ることはできないのだ。残りの人生をこの場所で過ごすしかない。たとえ孫たちから敵であるかのように扱われたとしても。
マットとフローラはわたしたちを避けている。町でばったり会ったときなど、二人はわたしたちに、自分たちの母親を二度と「いじめない」ようにと、噛みついてくる。もしわたしたちが許可なく家に入ったりしたら、警察を呼ぶなどと脅しさえした。妻とわたしには、そんなことを言われる由縁はない。あそこを出てからというもの、あの家に一度も足を踏み入れたことはない。わたしたちは息子に、孫たちが違う苗字を使っているかぎり、家族の一員であることを認めないと言ってある。
グビンは二度とこの話題を口にしない。わたしの方はずっと返事を待ち続けているのだが。今の状況はそんなところだ。この前、妻が業を煮やして、マンディの勤めるフォーチューンクッキー工場に行って、プラカードをあげると言いだした。「わたしの、家の、嫁、マンディ、チェンは、地球で、いちばんの、親不孝者」と書いて。わたしが長年の伴侶を思いとどまらせた。いったい何になる? 夫の両親を幸せにできないからといって、会社がマンディを解雇するとは思えない。これがアメリカだ。ここではわたしたちも、自分で自分の責任をとること、他人のことに口出ししないことを学ばねば。
"A GOOD FALL" (Vintage International, 2010)より
日本語訳:だいこくかずえ
*日本語で読めるハ・ジンの本:長編小説「自由生活」(2010)、「狂気」(2004)、「待ち暮らし」(2000)、短編小説「すばらしい墜落」(2011.3.18/白水社、立石光子訳)はこのページの短編を含む"A GOOD FALL"の日本語版です。amazon.co.jp