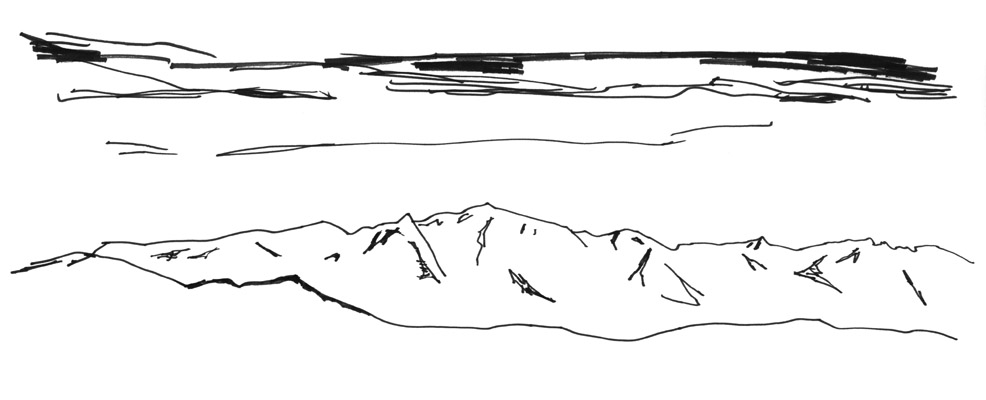オッパパゴーはワバンの丘を、ワバンはコソの丘とビター・レイクを見下ろし、この三者をパイユートの集落が眺めている。さらに、集落はコソの麓を通り過ぎる風の始まりを、高い峰の後ろに湧きたつ雲を、泉のほとばしりを、メサの上にやさしく広がる野生のアーモンドの花々を見ている。これらのものは、いうなれば、パイユートの部屋の壁のようなものであり、調度品のようなもの。枝編み小屋だけが我が家じゃない、土地が、風が我が家であり、山の姿、川の流れが我が家なのだ。これらのものは、家の中だけが我が家という人たちがするように、お店で調達することもできず、たとえ財布が許しても、同じ家をアラスカのシトカやウズベキスタンのサマルカンドに再現することもできない。インディアンがときにホームシックから死を選ぶことが、どういうことなのかわかるだろう。苦痛を和らげてくれるものがないのだから。見知らぬ土地では、風も、草も、地平線も、山の姿も、よそよそしいものとなる。それで政府がパイユートの土地に手を伸ばしたとき、人々は他に解決法を見つけられない哀れで無力な部族となって、北部居留地へと集まった。そして川の流域とショショーニとの境界がある南の端までが、かつてここを我が地としていたパイユート一族が、今は惨めな居候として住む土地となった。とはいえ、一日の仕事が終わって我が家に帰りつき、肉を焼く匂いや鍋からの湯気が夕日に立ちのぼるとき、人々の笑い声を耳にすることもあるだろう。その間子どもたちは足先を温かい灰の中に突っ込んで寝そべり、お話の数々を聞く。子供たちは浮かれ、お腹もいっぱいになって、家族たちと楽しいひとときを過ごす。少なくとも、人々には山がある。たとえ自らの運命を切り開いていく気力を無用のものとされても。さあここからは籠編みセヤビの最後の話。
#もくじ