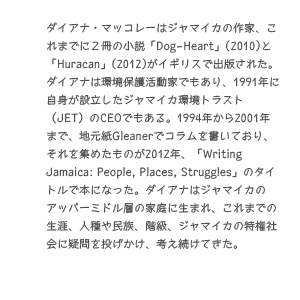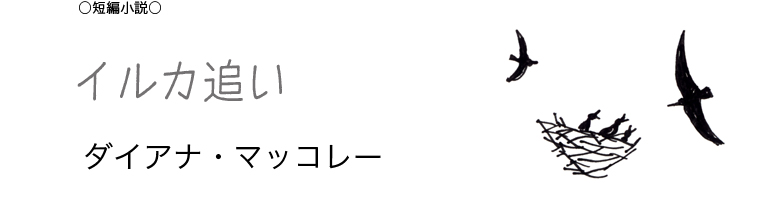
|
男の子は崩れかけた崖の風下にすわり、海をじっと見つめていた。あたりはすっかり闇につつまれ、雨が海面に音をたてて落ちていたが、男の子がすわっている場所は土砂降りの雨から守られていた。男の子は海の上でリン光が渦巻いて、さっと消えるのを見た。想像していたよりあっけないものだった。もっとよく見たいと思っていたのに。それは祖父のマアス・コンラッドが海の中に小さな生きものが住んでいて、夜になると船を追って水面を輝かせ、大きな魚のシルエットになると、かつて話してくれたからだ。祖父によれば、キングストン港には、昔はそれがたくさんいて、夜、漁に出てあの輝く不思議なものを見ないことはなかったという。「それはどこいっちゃったの、じい」と男の子は訊ねたものだ。 「あいつらには、この海はきたなすぎる」 「なんで海はきたなくなったの?」 うーん、じいはうなっただけだった。じいは海の男、言葉の男ではなかった。じいは海で行方不明になっていなくなった。 「ロイド、えー、なでピクニ(坊や)ここいる? じいは運わるかた。神さまだけが何あたかシッてるさ」 そう言ったのは男の子の母だった。ロイドは立ち上がって母親の方を向いた。「風邪でもシキたいんか、ピクニ? こな雨ノなか、夜ダいうに」 母親は、誰かがバスに置き忘れていった、鮮やかな色の傘をさしていた。「おいで。じいは大ジョブだ。おまえは海がじいを殺した思てのか?」 ロイドは母親の方に歩いていき、傘の下にはいった。下水の臭いをおおい、街の汚物を海に流しながら、汚れた雨水が流れていくキングストンの暗い通りを、二人はいっしょに歩いていった。ロイドはじいの声を聞いた。わしはな、漁師の血筋なんだ。 男の子はキングストン港の湾岸にある、古びた西下水処理場の近くに、母親と住んでいた。マアス・コンラッドの息子、男の子の父親はいっしょに住んでいなかったが、ときどき訪ねてきて、二部屋のアパートを不平不満でいっぱいにしていった。ロイドは父親はいっぱいしゃべるけれど、肝心なことを言わないと思っていた。家の中は耐えがたく暑かった。扇風機が必要だった。プリンセス通りには、安ものが売られていた。父親はまたしても解雇されていたが、それは足しにもならないバカバカしい仕事だった。父親にはかつて将来の計画や野心に満ちた夢があって、何者かになれそうだったが、一家の主が反対した。父親は車を手配してくれる男を知っていて、それは高級車とは言えないが、それでタクシー業をやることができた。それから大きなお金を動かす仕事も、裏の仕事ではあったがやって来た。生活が困難なときは、仲間の一人といっしょに海に出て、漁師になることもあったが、漁師は昔のやつらがやる仕事と言っていた。父親がロイドに最もよく放つ言葉といえば、ぼおずラムもてこい。すると母親が言い返す。あんたいつ、ラム、家にもてきた? あんたラムもてくれば、ラム飲めるいうこと。 ロイドは、母親が玄関の南京錠と格闘している間、傘をかかげていた。 家の前の街灯はもう何年も前に、吹き飛ばされて壊れていた。母親はチッと歯を鳴らす。「おまえのヤクタタズのとーさんに、新しい鍵かてくれ言うもうんざりだわ」と母親。やっと鍵ははずれて、二人は中に入った。中の空気は湿気がいっぱいで、小さな家はじめじめしていた。「もう寝れ、ピクニ(坊や)。神さんみてるかぎり、おまえわ漁師になンない。神さんみてるかぎり」 ロイドは二つあるうちの小さい方の部屋で、巾の狭い折りたたみベッドに寝ていた。濡れた服を脱いで、たわんだ紐に掛かっている制服を端に寄せ、湿ったベストと半ズボンの隙間をつくり、そこに掛けた。ロイドはどうしてじいは、ペドロの岸に行ったのだろう、あそこの漁師じゃなかったのに、と思った。ペドロの岸を探して、屋根もない小舟で、航法機器もなく、無線機もなく、自分の目と経験と体力だけで、百キロもの航海をしなければならなかった男がいた。マアス・コンラッドは、バウディッチやカリフォルニア沿岸やジャマイカ大陸棚の端に沿った、海の深いところで漁をしていた。沿岸部には近年魚がいなかった。たしかに、キングストン港に吐き出される下水パイプの近くで、釣り糸を投げ、罠や網で魚を獲る漁師たちはいた。海鳥が飛びまわって水面に突っ込み、街なかの水路からのゴミが浮いているような、そんな場所でも魚を獲る人はいたが、ロイドの祖父はそういう男ではなかった。 マアスは、死んだ魚が新鮮に見えるように防腐処理液をかけるような女たちに、魚を売る男ではなかった。いい釣り場で塩素の袋を投げて、魚が浮いてくるのを待つような男でもなかった。警察からダイナマイトを買い、海を破壊の連鎖に巻きこむようなことをする男でもなかった。ロブスターの季節が近づいたことや、割れたホラ貝の殻がある海底には女王ホラ貝は住まないこと、ブダイがサンゴ礁をはぎとって藻を食べるのは放置していい、というようなことをマアス・コンラッドは誰から教わる必要もなかった。 ロイドは一歳になる前から、祖父とともに海に行っていたと母親は言った。港をぐるっと一巡りして、薄緑色の浅瀬を超えて、ポートロイヤルのマングローブの静かな水辺まで行っていたんだよ、と。祖父は深海の漁師で、はえ縄漁をやっていた。網や罠は使わなかった。ロイドが大きくなってから、祖父が言っていたのは、魚を無駄にとるからだと。一定量以上に何でも獲ってしまう、雑魚や稚魚、ウナギやカメなども。ロイドはマアス・コンラッドに質問を浴びせた。 「なんで一人で海にいくの、じい」 「なんで釣り糸を垂れるときと、流し釣りすることがあるの」 「どこにいったらいいか、どうやって知るの」 わしはな、漁師の血筋なんだ、これが祖父の答えのすべてだった。そしてロイドは、その漁師の血筋が海に突き刺さるのを見ることになる。血筋というのは人を生かしも殺しもする。 漁に一番なのは週末、祖父が朝の四時に投錨地に向けて発つとき。街で清掃車が動き始める前の、そしてダンスホールが音量をおとす前の、最も静かな夜の時間。マアス・コンラッドは自分の小舟の後部にすわり、手をエンジンにかけた。携帯用灯油ランプの小さなぼんやりした明かりに影が落ちる。ロイドは船首に立って、アンカーロープをしっかり握り、前を向いて船が水を切って進むのをじっと見ていた。何の方向指示もない(少なくともロイドにとっては)海を、二人で渡っていった。そして錨を下ろし、いっしょに釣りをした。太陽が昇ってきて、アイスクーラーも満杯になり、魚がおとなしくなったころ、そしてもし天気が穏やかであれば、二人は南岸のサンゴ礁の一つに足を伸ばした。 ニードルス岩礁はロイドのお気に入りだった。サンゴ礁に囲まれた場所で、そこを通れる船は少ない。粗い白砂で、チョウバエも少なかった。ぽつんと生えているマングローブの木の下で、マアス・コンラッドはレッドスナッパーをうろこを取らずに亜鉛の四角い炉の上で焼いた。スナッパーの表面を塩でおおい、小さな熱い火で魚の皮がはげ落ちるまで焼けば、きれいな白い中の身を、祖父と孫が海水とタマネギとライムと唐辛子のさっぱりしたソースで食べることができた。マアス・コンラッドは指と自分の愛用のナイフで食べる。象牙の柄でできた鋲のとれたナイフで、波が打ち寄せる砂の中に突っ込んで、きれいにしていた。 食べ終わり、お腹もいっぱいになり眠気を催す心地よさに包まれ、二人は木陰の中で休んだ。マアス・コンラッドがイルカの話をロイドに話して聞かせるのは、そんなときだった。「坊よ、いいか、動物はかしこい。あいつらはイッチョに狩りをし、イッチョに暮らし、夜には人間を仲間にチてくれたりもする。イルカを見る前に、声を聞くこともある。わしらと同じニ、息シュルために顔だすとき、聞こえるんだ。あいつらは遠くまで泳ぎ、深くまでもぐる。レックリーフのところで、大きな波がわしをリーフの中に押し流したとき、出口を教えてくれたのはな、イルカだった」 ロイドは大きくなるにつれて、このような話の信憑性に疑いをもつようになったが、キングストン港の入り江近くに住むイルカの群れをよく目にしていたし、その流線型の美しいからだや、船のあとを高官の車を先導する警備隊みたいに、小さくなったり大きくなったりしながら追走していく姿が好きだった。昔にはな、と祖父は言っていた、イルカを痛めつける漁師などいなかったと。そんなことをすれば、それをやった家族に大変な惨事が起こると言われていたからだ、と言う。最近の記憶にも、ネグリルの漁師が、三匹のイルカが自分のワナを傾けて、魚を海に逃がしてしまったのを見て腹を立て、水中槍銃で一匹を撃ったという事件があった。イルカは血を流しながら海の中に潜っていった。漁師の水中槍銃はイルカと共に海に沈んでいった。その晩、漁師が乗ったタクシーは、運転手が居眠りしていて道を踏み外した。漁師はなんの傷跡もなく死んだ。街の人々は漁師が傷つけ、死に至る苦しみを与えたイルカを知っていたので納得した。イルカたちにかまうな。 マアス・コンラッドは一ヵ月、姿を消していた。ロイドは岩壁のところで、金曜の夕方になると祖父を待った。土曜の朝には、いつものように母と出かけて、魚を山の手の人たちに売る手伝いをした。母親は漁港の浜や市場では、魚を売らなかった。母親はマアス・コンラッドの釣った高品質の魚を、古い冷蔵庫をアイスボックスとして使い、リグアネアスーパーマーケットのそばの道端で売っていた。「魚売りのおいしいおばちゃん」と呼ばれていて、白人や肌色の薄い黒人たちに魚の品質で信頼されていた。「来週ロブスターは買えるかしら?」 大きな車の窓から顔を出して、そんな風に女性客たちは訊いたものだ。「あなたのところからしか、魚は買わないのよ、おいしいおばちゃん」とよく言っていた。 「たビん、来週はね」 そんな風に母親は答えていた。「でもどしてこのおいしおいしシルクスナッパー食べんね?」 こんな風に言うので、母親は「おいしいおばちゃん」と呼ばれているのだ。このおばちゃんの売る魚は、いつもおいしおいしなのだ。「じゃあ来週またね」 山の手の女性たちはそう言って車の流れの中に戻っていった。ロイドは山の手の人々というのは、海を徘徊するサメのようなものだと思っていた。食物連鎖の頂上にいて、生きる場をわけあう他のたくさんの生物を恐れることはなく、その存在を気にもしていない。いつでもサメは、小さな魚たちを怖じ気づかせることができ、力強いしっぽの一振りやバリバリ噛み砕く大きなあごで、優位を保っている。それで一巻の終わり。ロイドは山の手の人々と目を合わせたことがなかった。 その土曜日も、魚はよく売れていた。その日の魚は高品質とは言えなかったけれど、ロイドはお客のために氷の山から、ちょうどいい形と大きさのものを掘り当てて、魚を新聞紙に包み、ビニール袋に入れるのに忙しく働いた。母親はときに、ロイドに大きなスナッパーを持たせて、道の端に立たせた。ロイドの腕は重くなり、指先も冷たくて痛くなった。そして朝の太陽に目を細めた。祖父はロイドにそのやり方を、どうやってぎらつく海面から目を守るかをやってみせたし、サメを頂上とする食物連鎖について話して聞かせた。ロイドはマアス・コンラッドの道具のことを考えた。釣り糸、釣り針、重り、錨、ナイフ、かぎ竿、そして指先のもの(それは自転車のチューブから切り取って右の人差し指をおおったもので、大きな魚と格闘するとき、釣り糸で指を切り落とさないためのものだった)、ビニールと潮と魚のうろこの臭いがする黄色いカッパ、携帯用灯油ランプ、クーラー、餌箱。祖父は一つだけ今風の道具を持っていた。それは携帯電話で、ロイドの母親から渡されたものだった。でも祖父はこちらからの電話に出なかった。ペドロにそれを持っていっていることは、母もロイドも知っていた。「わしだ、着いた」と電話してきたからだ。 「神さまはいい方だ」とロイドの母は言っていた。 通りの車が少なくなり、クーラーの中には小さなイエローテールスナッパーが少し残っているだけだった。ロイドの母、おいしいおばちゃんは臭いを嗅いで言った。「もて帰ても、しょうない」 母親は自分では魚を食べなかった。ロイドには不思議だった。魚に養われているのに、一度もそれを味わわないなんて。海のことも、魚のことも知らないし、知ろうともしないなんて。どこで魚が産卵しているかとか、何を食べているのかとか、どこに住んでいるいるのかとか。母親はスーパーの裏に住んでいる野良犬に、魚の残りをやった。 その夜、ロイドの父親が帰ってきた。マアス・コンラッドがペドロに発ってから、初めての訪問だった。父親は息子に、いつものように声をかけた。「どしてた、元気か」と言い、ロイドの母には「何か聞いてるか」と訊いた。 母親は頭を振った。「そっちは何か聞いた」そう訊き返した。その声には何か隠しごとがあるような響きがあった。母親が手を差し出すと、ロイドの父親が折った札束を手渡した。それが二人の暮らしの元、どうやって食べているかの元だった。父親がもってくる金、それとマアス・コンラッドの魚。その夜遅く、ロイドは母と父がぼそぼそと話す声を聞いた。ロイドは二人がイルカの話をしているのを知っていた。カリブ海のそこらじゅうで、観光客が海辺の囲いの中やプールに入れられたイルカを見たがっているから、イルカを捕まえてくる必要がある、という話。ロイドはこれが父親の秘密の、大きな仕事だと知っていた。 安定した仕事ではなかった。海外のイルカ商人がロイドの父に電話してきて、手に入れて欲しいもののことを話すのに、数ヶ月、ときに一年の間があった。最初にそれがあったとき、ロイドは電話口で父が、いっしょにドミノで遊びラム酒を飲んでいる仲間の一人と話すのを耳にした。「若い娘ッコが見たがテル」 そう父親は言っていた。「かわいピンクの腹のな、そいつらが言うんだ。シミひとつないきれい肌だ」 その日ロイドは、父親が準備をしているのを見守っていた。父親が出発すると、ロイドは岩壁のところに行って、その深い影の下で待った。夜になり、高速船はイルカを連れずに戻ってきた。そして次の日も。一週間後、父親と仲間を乗せた高速船は、脇に縛りつけた網の中に、生きものを入れて戻ってきた。岸辺では男たちが、ビーチに止められたシートを敷いたトラックの荷台に、のたうつイルカを運び込む手伝いをするため待っていた。男たちが濡れたタオルでイルカをおおい、金勘定が始まった。たいした金額だった。それぞれがラム酒とニューキングストンの娼婦を買って、ケイマナス競馬場へ行ってもまだ、赤ん坊の母親に少しお釣りを渡せるくらい。そして男たちの車は、荷台にイルカと二人の男を乗せて走り去った。 三度ほど父親がこれをするのをロイドは見た。そして三番目のとき、それは六週間前のことだったが、祖父がメイデン岩礁のそばのケイマントレーダーの難破船のところまで短い船旅をし、夜になって戻ってきた。祖父はきっとバンバンとたたきつける音や明るい照明灯を見ただろう。きっとそれが他の男たちといっしょにイルカを網に追っている自分の息子だと気づいたことだろう。きっとイルカが網の口から逃れようとしぶきを上げているのを、死んだイルカの子が暗い海の中に流されていくのを目撃しただろう。ロイドが岩壁の下にすわって海を見ていると、祖父が浜に向って一直線に舟で戻ってくるのが見えた。祖父は陸を背に海に入っていき、そこで戻ってくる男たちを待った。 ロイドには、祖父に何か悪いことが起こるなどと思えなかった。使い古して言うことを聞かなくなった舟のエンジンさえ、祖父はなだめて動かすことができたし、岩礁も浅瀬も、海水が深海からわき上がる湧昇も、よく知っていた。海の深さも、海底の山脈や深い谷も熟知していた。祖父は海水がバシャバシャ波うつようなところで、舟に横たわって眠ることができた。魚でいっぱいになったアイスボックスを一人で持ち上げることもできた。水中眼鏡とスノーケルで十メートル近いところまで素潜りし、愛用のうろこ用ナイフで手を切って、指から血を流しても気にもとめなかった。ロイドの父親といえば、その反対、よく文句を言う男だった。祖父と父親が衝突しているのを見ていて、どちらが勝者であるかは疑いようもなかった。 父親は祖父が浜辺で待っているのを見て怖じ気づき、他の男たちの方を向いて何か言い、高速船はイルカを脇に縛ったまま、向きを変えた。浜にいた外国からの商人は手をあげてヘッドライト点滅させたが、声を上げることはなかった。この仕事は秘密裏に知られないように行なう必要があったからだ。男たちが携帯電話で話しているのを、そして高速船が闇の中に消えていくのに続いて、男たちがトラックに乗って走り去るのをロイドは見た。祖父がよたよたと自分の舟の方に走っていき、その中に身を投げ出しすのをロイドは見た。舟は揺れて暗い色の砂にのめり込んだ。ロイドは闇の中から黙って祖父に歩み寄り、祖父と孫は、そこで大きな波が来るのを待った。そしていっしょに、舟を海に押し出した。 「あいつらつかまえんの、イミないさね、じい」 ロイドのくるぶしは、キングストン港のなまぬるい汚れた水にピチャピチャと洗われていた。 「家に帰れや」 そう祖父は言ったが、声は優しかった。「ピクニ(坊ず)、家さ帰れ。明日はガッコがあるだろ。夜は寝なキヤいかん」 祖父はエンジンをかけた。一度でかかった。ロイドは浜に立って、祖父の舟が港を横切っていくのを見ていた(こんな風に高速船を見ようとしたことはなかった)。その夜ことはなされた。次の日、捕まえたイルカは溺れ死に、イルカ商人たちは怒って別の島に行って他の者たちに頼むと脅していった、とロイドは聞いた。 そのことがあった後、父親は母の元を訪ねることをしなくなった。祖父もあまり来なくなった。「どうしてじいは家に来ないの?」 ロイドは母親に訊いた。 「大の男の仕事があんのさ」 「イルカの仕事?」 「イルカのナニしってるんかね?」 「ぼく見たもん。イルカつかまえんの。じいがとめようしてん」 母親は舌を鳴らした。「あん年寄りが、あたま叩いてやらにゃあ。観光客がイルカみたいっちゅうんだからな。でかい魚に金はらうっちゅうんだからな。みんな捕まえろっちゅうこと。おまえの教科書どやて払てる思うん?」 「イルカは魚じゃない」 ロイドは言った。 「いいかい、同じアホちゅうことさ。海に住んでないかて? もしおまえ海ニ住めば、おまえ魚ちゅうことさ。宿題やりにいけ」と言ったと思ったらいつものおまじないが始まった。「神さまミテルかぎり、息子は漁師になったりしません。神さまミテルかぎり」 ロイドは母親に、心配は無用だと言いたかった。祖父も父親も兄弟姉妹がいなかった。だから漁師の家系は、一人息子という一本の線の上の結び目で続いている。その結び目は一世代分、離れている。ロイドも自分の息子をいつかもって、海に出ていく男たちの家系の線を、前と後ろに繋げる可能性はあった。曾祖父、曾々祖父のはるか昔までたどれば、それはアフリカの先祖にまで行き着く漁師の家系だが、それは自分のところで止まるだろうとロイドは思っていた。 ロイドは自分の折りたたみベッドにすわり、教科書をひざに置き、漁師というのは何だろう、海の男とは何だろうと考えてみた。自分の父親は漁師だったのか、それともただ海に行けるときに行って、獲れるものを獲っていただけの男だったのか。父親は祖父がしていたような強い日射しの中での荒々しい日々、孤独な夜また夜、失意に満ちた暮らしを望んでいただろうか。でもロイドは海のもつ自由さ、清らかさ、くっきりと目の前に現われる水平線をよく知ってもいた。祖父といっしょに海にいるとき、自分が海の男だと思うのは難しくなかった。 ペドロ沿岸に行っていた男たちが戻ってきた。実際のところ男たちは、老漁師が遠洋の島々を魚用アイスボックスとともに渡っていくのを目撃していた。老漁師は元気だったし、何も特別なことは聞いてなかった。それにマアス・コンラッドの身に何か起こることなど考えられない、それくらい信頼できる海の男だ、と口を揃えた。天気は快晴、嵐もしばらく起きていなかった。それで水上警察と沿岸警備隊に連絡がとられたが、その部隊は、一人で小舟に乗っていた老いた漁師を熱心に探しはしなかった。ロイドは、以前にロイヤル・ジャマイカ・ヨットクラブの一隻のヨットが、行方不明になったときのことを思い出した。そのとき、軍のヘリコプターはバリバリと音をたてて、白いヨットに乗った肌の白い男たちを探して、上へ下へ右に左に、海上を四角を描くように飛んでいた。捜索隊は、ライフジャケットを着た日に焼かれた男たちの死体が、海を漂流しているのを見つけた。そしてヘルシャー沿岸では、バラバラになったヨットが見つかった。それなのに、ロイドの祖父を捜すヘリコプターは一機も飛ばなかった。 母親は他の漁師から得た魚を売りはじめた。ロイドにはそれが裏切りとウソに満ちた投げ売りだとわかっていた。母親は口を閉ざし、眉にしわを寄せていた。ロイドの父親も行方不明だった。母親は何度も電話をかけていたが、繋がらずすぐに留守電に行ってしまい、父親は電話を返してこなかった。それで父からの収入はなく、他の漁師からの魚はクズばかりだった。ロイドは毎週末になると浜に行って、男たちに話しかけた。「じいを見なかった? じいの舟はいなかった?」 男たちは首ふり、その中の何人かはロイドにこう言った。「オレと魚トリいかんか、わかイの。おまいは漁師のウマレだ。じいはシンダ」 でもロイドには今も、祖父が舟の後尾にすわり、海に出ていったり帰ってきたりするところが見えた。絶対に海はじいを殺したりはしない。おそらくじいの舟に何かあったのかもしれない、けれどじいはどこかの岩礁か浜でしのいでいるはずだ。そこは道がなくて出ていけないのだ。それに釣り糸とナイフがあれば、人は生き延びることができる。ロイドの祖父はそれができる男だった。だからロイドは一週間に一度は、夜になると岩壁に向った。海をじっと見つめ、祖父が戻ってくるのを待っていた。豪雨の中、海を見ていた、あの夜が来るまでは。 「こんなとこで、何シテル?」 ロイドの腕を誰かがつかんだ。祖父が海でいなくなってから父親を見たのは、これが二度目だった。父親は上半身裸で、帽子から雨のしずくが落ちていた。父親はよたついていて、ロイドはラム酒の臭いを感じた。 ロイドが立ち上がると、岩壁のおおいが頭上からなくなり、頭や肩に雨が重く落ちてきた。「ナンも」そうロイドは言うと、地面を見た。父親と目を合わさないために、その目にあるだろう真実を見ないために。 「ここがおまえ、夜にイルところか?」 ロイドには、父親が雨に濡れた浜を見下ろしているのがわかっていた。祖父が戻れなくなった夜、陸を見つけられなくなったあの夜よりもっと前から、息子がいく晩もの雲のない夜に、ここで何を見ていたのか考えるているのがわかった。父親が屈んでロイドの腕を強く握った。父の顔がすぐそばにあった。その息は湿って重く、酸っぱい臭いがした。 「ロイド」 母親の声だった。ロイドが見ると、母親は鮮やかな傘の下に立っていた。そして父親の手には、ナイフが握られていた。うろこ用の祖父のナイフ、巧みな手技で祖父が扱っていたあのナイフ、魚を食べていたナイフ、鋲がとれた象牙の柄のナイフ。母親が傘を高くもちあげ、頭を引いて合図した。「こっちはいって」 父親が母の傘の下に入った。「アンこともう忘れるよう、おまえに話してやろや」 ナイフを指してロイドに言った。「おまえのアタマ、干したココナッツみたい固い」 母親は息子の父親からナイフを取って、ロイドに向き直った。「おいで、ピクニ(坊や)」 そう母親は言い、その声には優しさがあった。「うちに帰してやろね」 傘をロイドの父親に手渡し、母親はマアス・コンラッドのナイフを手にして、砕ける波の方に歩いていった。そして後ろに弾みをつけると、夜の闇の中にそれを投げ込んだ。雨の中、ナイフは弧を描いて落ちていったが、ロイドには落ちた先は見えず、しぶきを上げる音も聞こえなかった。
参考: ダイアナは3冊の本を出版し、好評を得ている。 ダイアナ・マコーレーのウェブサイトは:www.dianamccaulay.com
|
||||