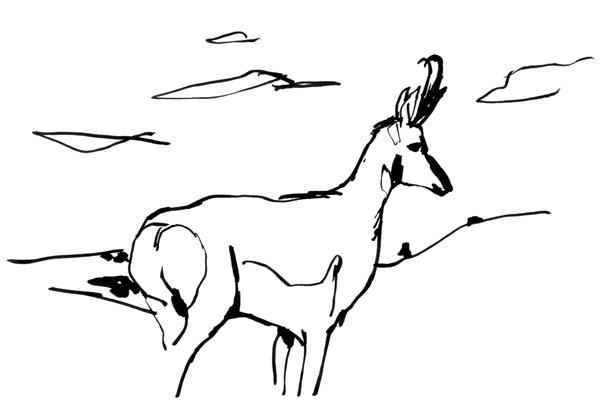羊のあげる砂埃の中、日々ゆうに十キロを超えて歩き、草がなければ十五キロでも歩き、羊に草を与えながら追い、昼になれば休ませる。休憩中ピートは小枝を編んで日除けを作り、頭の上に置いて(頭以外は連れている羊と同じくらい頑丈)、犬たちが羊の面倒を見ている間うたた寝する。夜になれば、どこにいようとそこにキャンプを張り、そんなピートと行き会った疲れた旅人は幸運者。焚き火が燃え、セイバリー香味の肉が鍋で煮立っていて、羊の群れからは寝言が聞こえ、メサのはるか下の方では羊飼いの焚き火がちらちらと瞬き、足元に花の兆しが、峰々に白く神々しい月の光があたり、ユダヤの地とキリスト降誕の情景が我知らず胸に浮かんでいるかもしれない。でも昼の間は、丸裸にされた薮木と喰いちぎられた花の姿を目にして、そんなことは思いもつかない。なんと多くの季節を費やし、なんとたくさんの太陽と雨によって羊毛は生み出されることか。そのせいでメサの草は少ししか種を宿さず、地面に住む鳥たちはその数を減らす。
西の果て、連なるメサや手つかずの名もなき山々のずっと西、そこには世界のどこよりもずっと大きな空がある。地平線の上に平たく広がる空ではなく、宇宙の彼方につづく空、その空間に地球はぽっかり浮んでいて、そのまわりはがらんどう、そしてすがすがしい風が吹き渡っている。血に沁みいるような香気も漂う。それからセージが放つ春の香り、それは命の水など一滴もないように見える地面の下で、樹液が活動し始めたという知らせ。ここを耕すことでどれだけたくさんの実りがもたらされるか想像させる匂い、新芽の始まりの匂い、それは植物の最盛期の匂い、そして野生の牛が残していく草を食んだあとの強い匂い。日暮れ時のセージの匂い、それはインディアンの集落や羊飼いの野営地からやってくる燃えるセージの香り、青白い亡霊みたいな煙に乗って流れてくる。その匂いは髪や服にしみつき、慣れていないと好きになれない匂いだけれど、パイユートや羊飼いはどの人もその匂いを漂わせている。乾期の終わりにアルカリ平地から流れてくる独特の鼻をつく土の匂いがあり、大きく口を開けた峡谷からやってくる雨の匂いもある。最後に、塩性草類の土地の匂いがしてくれば、そこからは別の土地の始まり、メサの小径はここで終わる。
#もくじ